| ■三協アルミ 商品価格改定を発表 サッシ・ドア商品などは4~12%(令和4年1月24日) |
|
三協立山㈱・三協アルミ社は12月20日(月)、商品価格改定を発表した。 サッシ、ドア商品など住宅商品全般については、2022年3月1日受注分からカタログ価格で4%~12%程度の値上げとなる。 同社は、「昨今の原材料、諸資材価格の高騰や物流費の上昇により、生産コストに大きな影響を及ぼしており、コストダウンや合理化などコスト低減に努めてきたものの、自助努力では吸収が困難な状況となったことから、商品価格の改定をさせていただくことになりました」と説明しており、価格改定への理解を求めた。 対象商品と実施時期、価格改定アップ率は、次の通り。 ○エクステリア商品全般(一部商品除く)=2022年2月1日受注分からカタログ価格で10%程度。 ○ビル商品全般=2022年2月1日受注分から10%程度 |
|
■ 令和3年秋の褒章 田村順正氏[前 和歌山県板硝子商工業協同組合理事長(現 和歌山県ガラス・サッシ協同組合)] |
|
全国板硝子商工協同組合連合会(宮代茂会長、以下全硝連)は、2021年11月3日に発表された令和3年秋の褒章において、前 和歌山県板硝子商工業協同組合理事長(現 和歌山県ガラス・サッシ協同組合)で、タムラウインドウ㈱代表取締役の田村順正氏が瑞宝双光章を受章していたことを発表した。 |
|
全国板硝子商工協同組合連合会(宮代茂会長、以下全硝連)は、2021年4月29日に発表された令和3年春の褒章において、元沖縄県板硝子事業協同組合理事長で、トーマ産業㈱代表取締役会長の當眞英男氏(80歳)がガラス施工工として黄綬褒章を受章していたことを発表した。 當眞氏は、平成10年4月~平成20年3月まで沖縄県板硝子事業協同組合理事長を務めていた。 |
■ 板協・複層・安全の3団体 深刻なパレット不足 緊急回収依頼の声明発出(令和3年12月20日)
|
|||
|
板硝子協会、全国安全硝子工業会と全国複層硝子工業会の3団体は12月8日、「リターナブルパレット(鉄製パレット・ラック等)の適正使用に向けた取組み及び緊急回収協力依頼に関して」と題する声明を発出した。東京・高輪の板硝子協会で記者会見し発表した。 声明文によると、団体の会員各社は廃棄物削減や省資源の観点から、製品配送には繰り返し使用できる鉄製パレットなどリターナブルタイプのパレットを採用。社名・登録商標・トレードマークが付された専用パレットは各社が所有権を持つ資産としている。 3団体は今年3月8日、リターナブルパレットの適正使用に向けた連名の共同宣言(別掲)を発表。また、運用ルールを作成して所属会員への周知徹底のほか顧客への啓蒙活動を展開している。 同ルールは、①パレット所有各社製品の配送を終えたパレットは速やかに返却する②各社より返却要請を受けた場合は速やかに返却する③二次配送にパレットを利用した場合、利用者自らが責任をもって回収する。回収困難な配送先の場合、木箱、段ボールなどワンウエー容器を利用する④指定業者以外の業者に空パレットを引き渡したり回収を指示したりしない⑤パレットを破損・紛失した場合、メーカーまたは仕入れ先に速やかに申し出る―と規定している。 他方、足元では製品包装に使う容器不足の状態が深刻さを増し、会員間では生産活動に支障が生じ、顧客に納期調整を要請せざるを得ないケースが頻発しているとしている。声明は「一部のお客様において倉庫の棚板や工程で使用しているケースなど問題となる行為が見受けられる。そうした行為を改善し、早急に容器を回収することが必要。いま一度、業界サプライチェーン全体にご協力いただきたくお願いする次第です」と訴えている。 同協会の伊東弘之専務理事は会見で「ガラスの需要が増える年末にかけてパレットは例年以上に不足し、生産に障害が起きている。出荷できず納期の遅れも出始めている。非常に厳しい状況だ。早く返してもらって出荷がスムーズに進むようにしていきたい」と現状を説明した。 さらに「協会は2018年10月以降、容器の適正使用に向けた取組みを行っており、ポスターやチラシを作成して『早く返してください』と要請している。3年たって理解は少しずつ進んできた。お互いの信用関係の中で意識を高めていきたい」と述べた。 全国安全硝子工業会の増山隆会長(三芝硝材㈱専務取締役)は「日々、パレット回収の問い合わせをしている状況。会員にパレットを自前でつくっていただくよう声掛けしている」と語った。全国複層硝子工業会の片岡靖桂専務理事は「適正使用はだいぶ浸透してきた。7社ほどは自社でパレットを購入した」と話した。 ◇ リターナブルパレットの適正使用に関する3団体の共同宣言(要旨)は次の通り。 一、我々は、パレット所有各社の目的用途以外での流用は行わない 一、我々は不当専有、返却拒絶、第三者への貸与・譲渡、改造・分解・損壊・破棄処分、指定業者以外の業者への引き渡しなどはしない 一、我々は、不適正使用は各社の所有権を害する「違法行為」と認識している 一、万一、不適正な使用が発覚した場合は、直ちにリターナブルパレットを返却する ※ パレットポスターはこちら |
■ 宮代全硝連会長に聞く コロナをチャンスに オンライン活用へ(令和3年12月13日)
|
|||
|
長期化するコロナ禍で板ガラス流通業界はぱっとしない状況が続いている。目標に掲げるエコガラスなど高機能ガラスの浸透もいまひとつ。消費者に一番近い小売店を束ねる全国板硝子商工協同組合連合会の宮代茂会長(神奈川県組合理事長)に現況と展望を聞いた。 —新型コロナウイルス感染症の発生から足かけ2年。仕事、組合活動への影響は。 「業界に直接的な影響はあまりないが、我々の商売は現場施工が原点。変えることができない部分が多い。もちろんリモートワークは成立しません。一般消費者の家に行く際は万全な感染対策を取っている。今はなくなったが、気にするところは、現場でもPCR検査をやらされました…」 「コロナによる一般経済情勢の低迷によるものか、このところメーカーのLow–Eペアが届くのに通常の4~5倍の期間がかかるようになった。シリコンなど副資材も値上がりしている。その一方で、コロナ禍の中、ステイホームや在宅ワークなどによって住まいの環境を再考する機会が消費者の間に増えている」 「また、2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにするという政府のカーボンニュートラル宣言は強い追い風となっている。我々がこれまで行ってきた省エネ、そして健康な暮らしを提供するための活動をバックアップしてくれます」 「令和3年度の総会で提起したように、防災・安全・安心な商品を提供できることは業界としての誇り。幸いコロナの第5波は収まりつつある。今こそ高機能ガラスを普及させるチャンスです。今後も感染対策をきちんととって消費者に安心してもらえるよう努めていきたい」 「全硝連の活動は大きな制約を受けました。令和2年、3年ともに通常総会や理事会はごく限られた人数での開催を余儀なくされた。全国理事長会議も昨年、今年と中止したので、皆さんと顔を合わせて話をする機会を持てませんでした。本年度の理事会は11月12日にリモート併用でやっと1回目を開くことができました」 「この理事会を含めオンラインによるリモート会議はまだ2回。手探り状態だが、うまく使えるようになれば、都合に合わせて気軽にオンラインで意見交換ができるのではないか思っている。慣れないと意見を述べるのも難しいかもしれないが、時間と経費の節約にもなります」 「基本的には対面による会合が望ましいと思うが、リモートは全国組織の全硝連にとって使い方次第では良いツールかも。設備投資をしてリモート環境を改善します。コロナが収束してもオンライン会議を積極的に活用していきたい」 —組合員が年ごとに減少している。対策は。 「組合がまとめた資料によると、令和3年度期首の総組合員数は1319人で前年度から28人減少した。業界の高齢化、後継者不足が主な要因です。若い人が業界に魅力を感じないという実態もある。防止策としては、第一に、若者がガラス業界に魅力を感じるように体制を整備することだろうと思います」 「具体的には、休みを取らせる。週休二日制の徹底です。土日に仕事に出たら代休を取らせる—。私の店(横浜市南区、港南硝子㈱)ではそうしています。次に賃金アップ、そして社会的地位の向上の3点です」 「地位向上の手段としては、全国工事組合連合会と一緒にやっている国交省の登録硝子工事基幹技能者の資格取得者を増やしていくことが肝要。要は、胸を張って仕事に取り組むことができる環境を整えることです」 「小規模のガラス店には、地域に根差した活動を展開して存在をアピールしていただきたい。私は地元の法人会に参加している。そこの機関誌が私の店を紹介する記事を載せた。そうしたらすぐ仕事が飛び込んできた。組合員同士の情報交換は有用です。私の周囲で、『廃業するので顧客を紹介する』といったケースが何件かありました」 「組織としてはユーチューブやSNSを上手に活用できれば良いかもしれないが、今の状況ではなかなか難しい。青年部と連携して何かできればと考えています」 —ガラス製品の値上げについて。 「各地の話を総合すると、今回はしっかりと値上げが実行されているようだ。我々販売店もお客さまにきちんと説明して適正な価格で販売を心がけていきたいと思います」 「値上げとは別に2ミリの型板ガラスが廃盤になり、広島の組合からメーカーへ再販を働きかけてほしいとの要請文書をもらいました。メーカーとしては需要減少や災害時の安全性の問題から樹脂製品に移行してほしいとの要望があるようです」 「その話を聞いた時には樹脂製品かなと思ったが、日々のニュースや新聞でSDGs、脱炭素社会などが取り上げられているのを目にして、樹脂製品はこれにかなっているかと疑問に思いました。ガラスの方が適合しているのではないかと考えています」 —公立小中学校へのガラス寄贈について。 「寄贈は全硝連が単独で行っていると思われているようだが、この事業はガラス業界全体で行動していかないと意味のないもの。今年から寄贈の選別は『ジチタイワークス』からの公募で決定する。実績を積み上げ、公共施設に『防災安全合わせガラス』が採用されるような活動を続けていきます。現在は災害時の避難場所となる学校が中心だが、これからは寄贈先を高齢者福祉施設などに広げていく方針です」 —神奈川の活動は。 |
| ■ YKKAP 堀社長に聞く 来年の2~4月に上代を見直す アルミ地金等の価格上昇が理由 |
| 先日、日本建材新聞協会(軽金属通信ある社、サッシタイムス社、産業新聞社、時報社、ミルト出版会、弊社の6社が加盟)の共同取材で、東京・秋葉原にあるYKK AP㈱(本社=東京都、堀秀充社長)の本社を訪問。そこで、堀社長にインタビューを試み、業界の景気動向や足元の販売状況などを聞いた。堀社長の話では、今期は、増収減益になる見込み。売上高はAP事業として過去最高になる見通し。また、アルミ地金などが急激に上昇しているため、来年の2~4月頃に定価価格の改訂に踏み切る旨を明らかにした。当日の取材内容は次の通り。 (1)コロナ禍での業界景気動向と足元の販売状況について 景気はそこそこの感じで、売上高は半期で前期を上回る状況。海外もいれて112%と好調だった。利益のほうが、アルミ地金とかガラスとかいろいろなものが上昇して非常に厳しい状況。営業利益では、減益を予想している。売上高が4775億円という数字は1996年に事業をはじめて最高の売上高になる。20数年ぶりに売上高のレコードを書き換えられた。利益がよくないのは地金がキロ200円から今は370円、一時は400円までと、ここまで上がるとは予想できなかった。後半はどんどんきつくなっている。 先日は、流通店会をリアルな形で行った。コロナ対策をきちんとやったうえで、何十社と集まっていただいた。その中で価格を上げることをお願いした。今回は掛け率ではなく、上代を変更する。流通店様からの反響としてはありがたいという声が多かった。来年の2~4月に値上げを実施する。今のままではとても無理だということを、はっきりと申し上げ、お願いした。 もう一つは、納期が悪いこと。特にAPWがかなりきつい。これもお詫びした。10月初旬は通常のN(受注日)+7日がN+52日までになり、最近ではN+35日までになった。ということで大変ご迷惑をおかけしている。12月の引き渡しまでにということで、もう少しでN+31日までなってきている。かなりの皆さんに待ってもらっている。5~6%がキャンセルということもあったが、樹脂窓に関しては待ってもらってありがたいと感謝している。流通店の皆さんにはまずお詫びして、そしてお願いした。 前半の売上高は予想以上だと思っている。後半も国内は強いなあという感じ。特に樹脂窓は100万窓というのを目指して期待してやってきたが、今のままだと127万5千窓になりそうだ。 窓サッシのセット数でいうと、アルミ樹脂複合が114%、アルミ窓が87%、全体で112%の数字になる。売上は良いが利益は非常に厳しい状況なので、値上げをお願いしている。 (2)新築市場に対する商品拡販に向けた取り組み、樹脂窓需要急増の要因について 樹脂窓はカーボンニュートラルの影響がある。ビルダー様、工務店様にとって差別化は重要な問題。樹脂窓は断熱性能が良くわかりやすい。もうひとつは、防露性能が良い。防露性能の基準値はないが、非常に良いということで好調だ。 それと、トリプルガラスが出ている。省エネ、防音の効果が大きい。コロナが採択理由の方もいる。防音というのは大きくクローズアップされており、+省エネでトリプルガラスが伸びている。132%ぐらいになる。 樹脂窓のキャパアップを以前に発表したが、それどころでなくなった。4直3交代で何十人という社員を24時間7日間休みなしの体制でなんとかやっている。これでコストも良いだろうと思ったが、逆にいろいろなことをやったことでコスト面では、ボリュームによるメリットよりもきついところがある。なんとか4直3交代フル稼働で対応している。 (3)ビル事業強化に向けた工場建設の進捗状況について 首都圏向けに、埼玉県と栃木県にビルサッシの工場がある。首都圏の需要は大きい。今まで当社は首都圏にあまり強くなかった。東日本統括を作り、首都圏、関東、東北向けにトップを入れ、改装も含め大きな組織を作った。またAPの中に工期事業部を作り、そこで一体となって新しい機械を作りながら25%コストダウンを行う。また、納期を14日から8日しようということで、根本的にコストと納期を見直し、それで首都圏で大きな売上にしていこうとしている。首都圏にもビル事業のキーとなる工場を作ってさらに大きくしていく。 (4)リフォーム市場に対する商品拡販に向けた取り組みについて 当社は新築に比べリフォームは弱い。新築だけならサッシのシェアは1位かもしれないと思っているが、ドアはまだまだ。アライアンスくらいでは弱い。内窓も含め健康を軸にして「ヘルスケア窓」を出し、そういう形で展開している。テレビCMも行っている。今までは、省エネを強調してきたが、これからは、省エネ+健康ということでやっていく。 ビル改装では、窓とドアを分けて考えた方が良い。ドアは窓と比べ、リフォームの対象になりやすい。ドアリフォームは他社に負けている。窓で勝ってもドアでは負けている。ドアは顔認証も出したので。これから力を入れていきたい。 (5)新型コロナに伴う新しい需要、収束後も継続する新しい試みについて 皆さんコロナで初めて在宅勤務をやってみて、住まい方を真剣に考えるようになった。それで、今はバルコニーを押している。グランピング等いろいろな提案ができるのではないか。今後、家を改築しようと思う方がでてくるのではないかと期待している。 (6)その他 ①樹脂窓、アルミ樹脂複合窓、アルミ窓の中で一番利益がでているのは? 「今は、樹脂窓もアルミ樹脂複合窓と肩を並べるまで利益がでるようになった。一番儲からないのはアルミ窓だ」 ②では、アルミ窓は樹脂と比較して性能も良くない。利益もでないのであれば、生産はやめるのか? 「単板ガラス用のアルミ窓の生産はやめる。しかし、複層ガラス用のアルミ窓はまだ一定の需要があるので生産・販売は続ける」 ③樹脂窓のリサイクルについて 「窓として考えるだけではなく、塩ビ業界も巻き込み、日本全体で樹脂部材のリサイクル問題を考えていきたい」 ④その他 「ビル事業において、当社は、高層ビルは強いが、中低層は弱い。中低層にも対応できるよう、完成品、半完成品、ノックダウン、バー材販売などあらゆる場合でも対応できるよう体制を整える」 記者の目 コロナ以降、久しぶりに堀社長とリアルに面談することができた。取材途中、我々に対しても冗談を語るなど余裕すら感じた。AP事業の売上レコードを塗り替えた自信からだろうと思う。樹脂窓だけでなく、首都圏中心にビル事業にも力を入れていく考えを明らかにしている。窓事業に関しては、独り勝ちの感じがしている。 |
■ 全硝連 理事会 コロナ対策実施 会議は必要最小限に ガラス値上げ浸透か(令和3年11月29日)
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(宮代茂会長)は11月12日(金)、東京都中央区の浜町TSKビル2階都硝協会議室で令和3年度第1回理事会を開催し、コロナ対策など当面の課題について協議した。リモートを併用し参加者を抑制した。 午後3時半に開会したリアルの理事会には9人が出席。水野洋太郎専務理事(福井県理事長)司会の下、鈴木和夫副会長(栃木県理事長)が「久しぶりに顔を合わせての会合を開くことができた」と開会の辞を述べた。 宮代会長(神奈川県理事長)は冒頭、「この日は本来なら愛媛県松山市で全国理事長会議を開く予定だったが、コロナ禍でやむなく中止した。理事会も新年度になって本日が1回目。ただ、コロナは第5波で減ってきた。コロナにめげず、これまで通り機能ガラスの普及活動を展開していきたい」とあいさつした。 次いで「ガラス値上げに関して各地域がどのように対応しているか知りたい。私のいる神奈川県では値上げ前の見積りで頭を悩ませている組合員もいる。検討事項はたくさんある。慎重審議をお願いしたい」と述べた。 また、10月30日に逝去した全硝連常務理事の林恭清氏(島根県サッシ・ガラス商工業協同組合理事長)を偲び、「11月2日に島根県太田市の地元で執り行われた葬儀告別式に参列した。林さんはこうした遠いところから本当によく東京などに来てくださった。感謝の念しかありません」と哀悼の意を示した。 報告事項では、令和3年度の機能ガラス普及推進協議会の活動事例を取り上げた。10月10日の「窓ガラスの日」関連では、民放ラジオ番組でのコマーシャルやユーチューブ動画。周知活動の一環として採用した「車用マグネットシート」の普及については、10末時点の販売総数が553枚に上ったとしている。 窓ガラスの日のPR用グッズの候補としては、各会員から他に、ガラス用ダスター、クリアファイル、メモ用紙、消毒剤入りウエットティシュ、ボールペンなどの希望が寄せられている。 恒例の公立小中学校など公共施設への防災安全合わせガラス寄贈事業では、「ジチタイワークス」を活用した募集活動を挙げた。令和3年度の寄贈先は、ジチタイワークスで応募のあった岡山県備前市と山梨県甲府市のうち備前市に内定した。 全国板硝子工事協同組合連合会と進めている登録硝子工事基幹技能者講習については「令和4年度は全硝工連から九州地区で開催したい」との要請があると報告した。 検討事項では、ガラスの値上げに関係して広島県商工業協組が全硝連に提出した「メーカーによる2mm型板ガラスの廃盤について」と題する要望書を紹介。「当組合員は小規模のリフォームやガラス及びサッシのメンテナンスを主な仕事にしている事業者が大半。2mm型板ガラスが無くなるのは大きな痛手」と指摘し、全硝連に対しメーカーに製造継続を陳情するよう求めた。 値上げに関する各地区報告では、「各メーカーとも11月から値上げしている」(和歌山)、「実態は卸がやっている。小売まで伝わってこないのが実情」(大阪)、「詳しい情報はまだ上がっていない」(東京)などとの発言があった。水野氏は「きっちりやっているところと、やっていないところがあるようだが、大体は実施されているか、もしくは実施される、ということだろう」と〝総括〟した。 |
■ 全硝工連 「脱炭素への対応必要」 東京で全国理事会開催(令和3年11月15日)
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連、橋本和明会長)は10月27日(水)、東京都中央区日本橋浜町のTSKビル2階会議室で令和3年度全国理事会を開催し、基幹技能者講習、キャリアアップシステムなど当面の課題について協議した。 理事会には九州、中国、関西、北陸、東海、関東、東北の各地区代表ら13人が出席。冒頭、橋本会長(中国工事理事長)は「本年度はガラスフォーラムが中止、全硝工連の通常総会は書面での開催…皆さんとは今年3月に仙台市で開いた理事会以来なので嬉しく思う」とあいさつした。 続いて業界の動向に触れ「板ガラスメーカー3社が10月1日からの製品値上げを発表した。石油など全てのものが値上がりしている。どのような状況なのか、どう波及していくのか、皆さんと話し合っていきたい。また、国のカーボンニュートラル政策に近づけるためガラス業界として何をなすべきか考えていく必要がある」と述べた。 正午に開会した理事会は山田圭一専務理事(関東副理事長)の司会で進行。最初に、国交省関連の登録硝子工事基幹技能者講習について田中敏也副会長(関東理事長)から講習委員長のポストを引き継いだ山田氏が概況を説明した。 懸案の令和4年度の講習開催地については3月の理事会で久保慎一郎副会長(九州理事長)が九州での開催を要望。この日の会議でもあらためて九州開催を訴え了承された。同事業を連携して進めている全硝連の意向を確認の上、次期講習委員会で決定する。久保氏は福岡市を候補に挙げた。 建設技能者の能力を評価する建設キャリアアップシステム(CCUS)については山田宏理事(関東常務理事)が現状を解説。上位からゴールド、シルバー、ブルー、ホワイトと4段階ある技能レベルのうち、ガラス工事業界では約250人がゴールドカードの保持者と明らかにした。田中副会長は9月の国交省と専門工事団体との意見交換会の模様を話した。 次いで、事務局の前山彰博氏(関東事務局長)が令和3年度の建設マスター並びに建設ジュニアマスター受賞者を紹介した。マスターは、佐山知(中国、石崎本店)、高淵祐治(関西、まねきや硝子)、宮崎清孝(関東、清智工業=遠藤硝子)の三氏。ジュニアマスターは、鶴来豊章(北陸、室野硝子)、宮川啓(東北、ハラダ)の二氏。 業界関係の課題については、橋本会長、原田尚樹副会長(東北理事長)、伊藤覚常務理事(関東副理事長)と事務局が説明。原田氏と伊藤氏は、機能ガラス普及推進協議会の活動計画や10月14日開催の第2回企画運営委員会の内容を紹介した。 橋本会長はガラス製品値上げに関し、9月に田中副会長を中心に作成し各組合に配布した全硝工連の「お願い文書」をあらためて取り上げた。 取引先に向けた同文書は「~今般の値上げは企業努力で吸収できるものではなく、企業の存続そのものが危ぶまれる状況~傘下の組合員がお願いする工事価格の見直しにご理解を賜り適正な価格での発注をお願いする」(要旨)としている。 |
| ■ イチネンHD 新光硝子を子会社化 黒田雅史社長に聞く やり方次第でまだまだ利益は出せる(令和3年11月8日) |
|
「自動車リース事業」「ケミカル事業」「パーキング事業」「機械工具販売事業」「合成樹脂事業」の5事業を傘下会社で運営する株式会社イチネンホールディングス(本社=大阪府大阪市、黒田正史社長)は、このほど新光硝子工業株式会社(本社=富山県礪波市、新海伸治社長)及びその子会社である新生ガラス株式会社(本社=富山県富山市、末永孝光社長)を子会社化したと発表。発表後は弊紙にも多数の問い合わせをいただいた。そこで先日、大阪市内にあるイチネンホールディングス本社に黒田社長を訪ね、新光硝子工業を傘下に収めた経緯などを聞いた。 同社本社は地下鉄と阪急の西中島南方(阪急は南方)駅ほど近くに立派な本社ビルが建っている。建物内部は天井が非常に高く広々とした感じ。万全なセキュリティー体制も施されていた。 ――今までの5事業とは、少し関係性が薄いと思われるこのガラス業界にどうして参入しようと思われたのですか。 「元々はM&A仲介会社の紹介で、新光硝子工業の存在を知りました。ガラス業界は厳しい業界だという話はお聞きしておりましたが、我々が参入した『自動車リース関連事業』にしても『ケミカル事業』のおいても、厳しい業界と言えます。自動車リースにしても将来はEV車にとって変わって大変だという意見もありますが、今事業をやっておれば、その新しい事業にも参入できるかもわかりません。ガラスだって絶対に必要な材料です。なくなることはありません。やり方次第ではまだまだ利益を生み出せる事業だと思います」 「新光硝子工業の決算内容を見ましたが、しっかりと利益を継続してだされています。とても内容の良い会社だと思いました」 ――私たちガラス業界全体に言えることですが、良い製品は持っているもののなかなか世の中に広まらない。営業力が少し弱いのではないかと思われます。その点はいかがですか。 「私たちは、『自動車リース関連事業』では多くの企業様とお付き合いさせていただいています。その企業様を通じてガラス事業も繋げていけないかと期待しています。また『ケミカル事業』では、ガラス事業と共通するところがあるのではないかと思っています」 ――新光硝子工業や新生ガラスには、実際訪問されたのですか。 「両社とも行きました。県民性か、すこしおっとりした印象がありました。工場の方は、コロナ影響とかでそれほど忙しいという印象はありませんでした。弊社のグループ企業と比較して少し管理部門の人間が多いかも知れないと感じました」 ――人事面は今の経営陣はそのままと聞きましたが。 「新海社長、末永専務以下役員はそのままです。新たに、私黒田が代表取締役会長に、また、現イチネンケミカルズの高橋英彦取締役副社長が取締役副会長に就任します」 ※新光硝子工業の退任取締役及び退任監査役では、10月1日付けで鷲山浩一代表取締役会長、大門督幸取締役(非常勤)、山瀬孝監査役(非常勤)が退任し。鷲山氏は新たに同社顧問に就任した。また、新生ガラスは、末永社長以下役員全員そのままで、新たに高橋英彦氏が取締役副会長に就任した。 ――東京や大阪の営業所はどうなりますか。 「私どものグループ企業の事務所と一緒にできないか検討しています」 ――社名については 「グループ企業には頭に『イチネン』と付けています。それも検討中です」 ――今後については。 「とにかく利益を出して欲しいと思います。それとガラス業界の中で、他にM&A先の対象となる企業があれば考えたいと思います」 この後、新光硝子工業の新海社長にお話をお聞きしたところ「経営状況が悪化したからということでM&Aの道を選んだわけではありません。あくまで成長戦略の一環として、1年前から検討していました。次の時代を見据え建築以外の市場にも打ってでたい」と語っていた。 なお、イチネンHDおよび新光硝子工業と新生ガラスの概要は次の通り。 ◎㈱イチネンホールディングス ▽本社所在地=〒532―8567 大阪市淀川区西中島4丁目10番10号 ▽代表者=黒田正史氏 ▽創業=1930年6月1日 ▽連結売上高=1126億18百万円(2021年3月期) ▽資本金=25億29百万円(2021年3月31日現在) ▽従業員数=66名(グループ計1349名)(2021年3月31日現在) ▽その他= 2005年9月 東京証券取引所 市場第一部に上場。 社名の「イチネン」の由来は「第一燃料」からきているという。 ◎新光硝子工業㈱ ▽設立年月日=1953年(昭和28年)8月1日 ▽資本金=5000万円 ▽売上高(単体) ・2021年3月期=9億2580万円 ・2020年3月期=11億3038万円 ・2019年3月期=12億4999万円 ◎新生ガラス㈱ ▽設立年月日=1970年(昭和45年)4月1日 ▽資本金=4500万円 ▽売上高(単体) ・2020年3月期=5億8899万円 ・2019年3月期=6億6653万円 ・2018年3月期=6億1781万円 |
| ■ 日本板硝子 建築ガラス事業部門 大野営業部長に聞く 同じ地域に多数の取引先は得策ではない 価格改定の進捗状況について(令和3年11月1日) |
|
日本板硝子(NSG、本社=東京都、森重樹社長)は、本年7月末に10月1日出荷分より、建築用板ガラス製品の価格改定を発表した。そこで今回はNSGグループの日本国内建築用ガラス事業を担う日本板硝子建築ガラス事業部門 営業部長・大野義之氏にご登場をお願いし、価格改定の進捗状況などについてお話を伺った(2面に関連記事掲載) ――価格改定の進捗具合はいかがですか。 大野 新聞等での発表通り、すべてのお取引先様に対し10月からの価格改定をお願いしています。一部、サッシメーカー各社にも素板を供給しておりますが、当然、サッシメーカーにも価格改定をお願いしています。今回は、新価格の早期適用をお願いしています。 ――しかし、サッシメーカーがペアガラスの価格を改定している話は聞きません。 大野 私たちにとってもなぜサッシメーカー各社がガラス価格の改定に動かないのか不思議です。サッシメーカー各社も含めてすべてのお取引先に対して10月からの価格改定をお願いしております。日本の建築用ガラス事業は、本当に儲かっていません。このままでは、窯の補修も新しい設備投資もできない状況です。日本における建築用ガラス事業の存続をかけて、今回の価格改定を何としても遂行しなければなりません。お客様にご理解をいただき、速やかに転嫁を頂けるよう懇切丁寧に説明するのが、我々の役目だと考えています。流通店や工事店の皆さんにもぜひご理解をいただき、価格改定に動いていただきたいと思いますし、メーカーとしてもサポートさせていただきたいと思います。 ――出荷条件の見直しはどのようになっていますか。 大野 受注出荷条件については、来年の1月出荷分からの改定を各取引店様へご案内しております。 ――これだけガラスの値上げや安定供給が困難という話がでてくると、他社を扱っている流通の方からお取引したいというお問い合わせはありませんか。 |
■ イチネンHD 新光硝子を取得 新海伸治社長は続投 新生ガラスは孫会社に(令和3年10月11日)
|
|||
|
新光硝子工業㈱(富山県砺波市、新海伸治社長、以下、新光硝子)は10月1日、東証一部上場で自動車リース関連事業やケミカル事業を手掛ける㈱イチネンホールディングス(大阪市淀川区、黒田雅史社長、以下イチネンHD)の傘下に入った。なお、新光硝子の子会社である新生ガラス㈱(富山市豊田町、末永孝光社長)は、イチネンHDの孫会社となる。 イチネンHDは、取得額は非公表ながら、新光硝子工業ふたば持株会(社員持ち株会)や伏木海陸運送㈱(富山県高岡市、川西邦夫社長)の保有する全株式を取得した模様で、株式引き渡し日は10月1日。 新光硝子の新海社長は代表取締役社長にとどまり、新たにイチネンHDの黒田社長が代表取締役会長に就任する。また、新生ガラスについても、新海取締役会長、末永代表取締役社長はそのまま留任し、新たにイチネンHD傘下㈱イチネンケミカルズ取締役副社長の髙橋英彦氏が取締役副会長に就任する。 イチネンHDは、今回の株式取得について「このたび、株式を取得した新光硝子工業及び新生ガラスは、ガラス加工製品(曲げガラス、樹脂合わせガラス、その他の二次加工等)の製造・販売を行っている企業であり、当社グループにはない事業領域での製品開発力や技術力に加え、盤石な営業基盤を有する企業。今後、同社の事業を当社グループの新規事業と位置付け、経営資源を投入することにより一層の事業拡大を目指すとともに、同社が保有するガラス製品加工に関する高度な技術と、当社グループのケミカル事業や機械工具販売事業、合成樹脂事業における製品製造のノウハウを融合することで、新たな事業分野への進出を目指す」としている。 なお、新光硝子および新生ガラスの概要は次の通り。 ◎新光硝子工業㈱ 設立年月日=1953年(昭和28年)8月1日 資本金=5000万円 売上高(単体) 2021年3月期=9億2580万円 2019年3月期=12億4999万円 ◎新生ガラス㈱ 設立年月日=1970年(昭和45年)4月1日 資本金=4500万円 売上高(単体) 2020年3月期=5億8899万円 2019年3月期=6億6653万円 2018年3月期=6億1781万円 |
| ■ AGC 日本で建築用ガラスを作り続けたい 価格改定に至った背景や進捗状況は 執行役員建築ガラスアジアカンパニープレジデント 武田雅宏氏に聞く(令和3年10月4日) |
|
AGC(本社=東京都、平井良典社長)は、本年7月15日に国内建築用ガラス関連製品の販売価格を10月1日納品分から引き上げると表明(弊紙7月26日号に掲載)。また、先日放送されたNHKのニュース番組の中でも、国内建築用ガラス関連製品の値上げが取り上げられていた。今回は同社執行役員建築ガラスアジアカンパニーのプレジデント・武田雅宏氏にご登場をお願いし、今回大幅な価格改定に至った背景や現在の進捗状況についてお話を伺った。武田氏は「今回の改定は、日本で建築用ガラスを作り続けるためです。それが必ず業界のためになります」と何度も語っていた。 ――先日放送のNHKの朝のニュースの中で、武田氏自ら価格改定の背景について述べておられました。 武田 今回の改定の発表文をご覧ください。まず引き上げ幅が書いてあります。今回は値上げ幅が大きいのではないかという意見を頂きました。ではなぜそうなったか。次の段落に着目していただきたいと思います。原燃料が上がったため、とは書いていません。最初に書いてあるのは製造関連設備の維持更新費用の上昇と安定供給のために必要な費用負担が増大しているということです。加えて原燃材料費とか物流費が高止まっているので、価格改定が必要ですと書いています。 ―― NHKのニュースでは、原燃材料が先でしたが… 武田 私の思いは逆です。私どもはこれからも日本でガラスを作り続けたい。そのためにはいろいろな設備の維持・更新が必要です。代表的なのは横浜の型板ガラスの窯や、鹿島のフロート窯の冷修です。その他、建築加工もしかり。そういうことをやっていかないといけない。 ――わかります。 武田 単純に発表文に書いている維持更新だけでなく、温室効果ガス(GHG)の排出削減もやらないと、いずれ日本で製造してはいけないということになりかねない。そのためには環境対策や省エネのための技術開発や設備投資も必要です。 繰り返しですが、我々は日本国内で建築用ガラスを作り続けたいのです。そのことは国内のお客様にとって絶対大事なことだと思っています。海外から輸入すればよいのではないか…そういう話ではないでしょう。これまでも我々はいろいろコスト削減もやってきたのですが、今後の設備維持更新に必要な収益を確保するのが大変難しいと判断したので、価格改定をさせて下さいということなのです。 ――日本国内でガラスを作り続けることの意義は? 武田 現在は、ビルでも住宅でも壊すとガラスを含めた多くのの廃材を産業廃棄物として埋め立てしています。ただ、5~10年後にはこのようなことは許されなくなるでしょう。ガラスやサッシなどを分別してできるだけリサイクルしなさいという世の中になると思います。その時に日本で作っていなかったらどうするの?という話になります。循環型社会の中で、日本で出てくるガラスという資源を再利用していくことが大事なのです。このような観点からも、日本でガラスを作り続けることが業界のためになると信じています。そのためには設備投資もしなければならないし、温室効果ガス排出削減対応もしなければならない。そのための技術開発コストも必ず発生します。 ――特約店の中には、いまだに詳しい条件まで聞いておらず、本当に10月から改定となるのかという話も耳にしました。 武田 当社の営業担当から各社様には、既に条件のご説明をさせて頂いています。 ――御社の決算内容をみれば、ここまで大きな値上げをする必要がないのではないかという意見もあります。 武田 業績好調なのは他地域・他事業で、日本国内の建築ガラス事業だけみれば、このままでは事業が続けられなくなります。 ――ガラス業界より先の取引先には、メーカー・流通・工事が一体となってお願いに行ってはどうかという話もあります。 武田 それは法的な問題もありなかなか難しいのです。流通の皆さまには、背景などを丁寧に説明させていただきます。 また今回の改定は、ここだけをやって、こちらはやらないということは絶対にありません。 ――今回は受注出荷条件の見直しも行うのか? 武田 製品本体価格だけでなく、受注出荷条件の見直しも行います。 ――今回の改定について、流通の皆さんは、背景については理解していると思っています。それだけに丁寧な説明が必要なのではないでしょうか。また、実施時期を引き延ばしすると、価格改定の実施自体がなし崩しになってしまう可能性もあると感じています。 |
■ 日本板硝子 英国 水素エネルギー使用(世界初) 「建築用ガラスの製造」成功 「Hynet産業燃料転換」プロジェクト(令和3年9月27日)
|
|||
|
日本板硝子㈱(以下「NSG」)は、英国の事業所で水素エネルギーを使った世界で初めてのガラス製造の実証実験を行い、建築用ガラスを製造することに成功したと発表した。 同実証実験の取り組みは、同社が2020年2月27日に発表(既報2020年3月30日付参照)した、「Hynet産業燃料転換」プロジェクトの一部。実験は8月後半の3週間にわたり、グループ企業であるPilkington United Kingdom Limited社のグリーンゲート事業所(英国・セントへレンズ)で行われた。 実験では、多くの課題を同社が持つ技術の粋を集めて解決し、現在の主燃料である天然ガスと水素という2つの異なる燃料間の切り替えをシームレスに行うことに成功した。これにより、水素でも天然ガスと同様の優れた溶融性能を達成できること、およびガラス溶融窯から排出されるCO2を大幅に削減できる可能性があることを証明した。 同実験の成功はNSGグループにとって脱炭素化を目指すうえで重要なステップで、燃料を天然ガスから水素に切り替えることができれば、グループのCO2排出量の過半を占めるフロート窯を圧倒的に少ない排出量で操業することができるようなる。 世界中の板ガラスの製造に革命をもたらしたフロートガラス製法は、セントヘレンズで1952年に開発されたもので、それから70年後に、同じ地で行われたこの実証実験は、世界のガラス産業にとってもう1つの重要なマイルストーンとなる。 同社では今後、中長期的には、主要な産業拠点をつなぐ水素パイプラインの整備など、安定的な水素供給体制の確立によって、天然ガスから水素への完全な切り替えが可能になると期待している。 |
| ■ セントラル硝子 つくば工場(茨城県)複層ガラスの生産中止 大石製造所(三重県)の強化ガラスも中止(令和3年9月13日) |
|
セントラル硝子㈱は9月1日(水)、6月1日及び8月2日に発表した「国内建築ガラス事業における子会社の一部事業の譲渡と拠点の閉鎖についてのお知らせ」(既報6月7日付及び、8月2日・9日合併号参照)の続報(第3報)として、子会社であるセントラル硝子販売㈱(東京都杉並区、湯浅章社長、以下「CGS」)の一部事業の譲渡と拠点の閉鎖、及びセントラル硝子プラントサービス(三重県松阪市、本山一浩社長、以下「CGPS」)の、一部拠点での生産中止決定を発表した。 同社は現在、国内建築ガラス事業の販売体制を、生産規模に合わせた適正な販売拠点数まで縮小し、建築加工ガラスの生産体制においても、生産性の高い拠点に生産を集約することで生産能力を適正規模にすることを進めている。今回の発表は、その取り組みの一環。 ◎CGS一部事業の譲渡と閉鎖について 9月1日付で、関東地区のCGS直販部門の一部拠点を事業譲渡し、事業譲渡対象外の拠点については、12月末を持って閉鎖する事を決定している。なお、関東地区におけるCGSの特約店への販売業務については、事業を継続する。 ◎CGPS一部拠点での生産中止について 7月末付でつくば工場(茨城県つくば市)における複層ガラスの生産を中止、8月末付けで大石製造所(三重県松阪市)での建築用強化ガラスの生産を中止することを決定した。 同社によると、今回の決定が2022年3月期決算に与える影響は軽微であるとしている。 |
| ■ 全国工事 国内ガラス製品のメーカー出荷価格改正に伴う「ガラス工事価格の見直しについて」 会長・理事長連名で発信(令和3年9月6日) ※ 全国工事が発表した文書はこちら |
|
全国板硝子工事協同組合連合会(橋本和明会長、以下「全硝工連」)は、このほど会長名および各地区板硝子工事組合理事長名の連名で、取引先に向け、「国内ガラス製品のメーカー出荷価格改定に伴うガラス工事価格の見直しについて」の文書を発表、適正価格での発注を呼びかけた。 今回の文書は、国内ガラスメーカー3社(AGC7月15日、日本板硝子7月29日、セントラル硝子8月2日)が発表した出荷価格改定に伴うもので、全硝工連によると、今般のガラス材料の値上げは傘下組合員の企業努力で吸収できるものではなく、企業の存続が危ぶまれる状況にあるとしている。このため、取引先に対しガラス工事価格見直しの理解と、適正価格発注を呼びかけた。 なお、文書の内容(要約)は、次の通り。 既に新聞等の報道によりご承知のことと存じますが、国内ガラスメーカー3社は、国内ガラス事業を維持する為、人員の削減はもとより製造設備の休止、生産並びに販売拠点の閉鎖といった抜本的な構造改革を断行しておりますが、加えて今秋出荷分より板ガラス、加工ガラス材料の価格改定を実施することとなりました。その内容につきましては、各ガラスメーカーの発表をご確認の程お願い申し上げます。 当組合員はこれまでも、建築工事になくてはならない専門工事業者としての自負の下、社会的使命感をもって、お客様の要求にお応えするべくコストの低減に努めてまいりましたが、今般のガラス材料の値上げは企業努力で吸収できるものでなく、企業の存続そのものが危ぶまれる状況と言わざるを得ません。 当組合はこれからも施工技術の向上、工期の遵守、施工品質と安全の確保、施工体制の充実を図っていく所存です。お客様に於かれましては、傘下の組合員がお願いしますガラス工事価格の見直しにご理解を賜り、適正な価格でのご発注を戴きます様衷心よりお願い申し上げる次第です。 令和3年9月 全国板硝子工事協同組合連合会 会長 橋本和明 東北板硝子工事協同組合 理事長 原田尚樹 関東板硝子工事協同組合 理事長 田中敏也 東海板硝子工事協同組合 理事長 木村俊一 関西板硝子工事協同組合 理事長 清水英彦 北陸板硝子工事協同組合 理事長 高村明彦 中国板硝子工事協同組合 理事長 橋本和明 |
| ■ 日本板硝子 第1四半期 板ガラス3メーカー当期好決算を予想 売上高1476億円(前年同期比60.7%増)建築用ガラス事業が増収増益(令和3年8月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日本板硝子㈱は、このほど2022年3月期第1四半期(2021年4月1日~6月30日)の決算を発表した。 同期の連結業績は、売上高1476億7800万円(前年同期比60.7%増)、営業利益71億6100万円、税引前利益55億2900万円、四半期利益28億8000万円、親会社の所有者に帰属する四半期利益25億4100万円となった。 建築用ガラス事業の売上高は645億円(前年同期は449億円)、営業利益は61億円(前年同期は27億円)。売上高・営業利益ともに、新型コロナウイルス感染拡大による影響を大きく受けた前年同期から改善した。売上は好調でしたが、営業利益は、エネルギーコストを中心とする投入コスト上昇の影響を受けた。 日本における売上高は、国内建築需要が低調に推移したことを受け、前年同期を下回りましたが、日本以外の地域で業績が回復したこと、および太陽電池パネル用ガラスの需要が堅調であったことにより、アジア全体の売上高は前年同期並みとなっている。 また、同期の自動車用ガラス事業売上高は709億円(前年同期387億円)、営業利益は13億円(同29億円の損失)。高機能ガラス事業売上高は114億円(同81億円)、営業利益は28億円(同14億円)となっている。 なお、2022年3月期の通期連結業績予想は、売上高5600億円(前年同期比12.2%増)、営業利益240億円(同83.7%)、税引前利益190億円、当期利益120億円、親会社の所有者に帰属する当期利益100億円を見込んでいる。 ◎決算発表会における質疑応答(抜粋)は、次の通り。 Q1 建築用ガラス事業においては、前々期の2020年3月期と比較しても増収増益となっているが、これは価格上昇によるものか、数量増加によるものか? A1 建築ガラス事業においては特に欧州において価格が上昇しており、また同時に、販売数量や構成も改善しており、その両方が寄与した結果、営業利益率の回復につながっている。 Q2 エネルギー価格が上昇しているが、ヘッジによりその影響を緩和することができるか? A2 直近のエネルギー価格上昇による影響については、今回修正した業績予想に織り込んでいるが、エネルギーコスト全てをヘッジしている訳ではない。しかしながら、建築ガラス事業の欧州などでは、エネルギーコストの上昇分を製品価格に転嫁することが一定程度可能であるため、ヘッジと合わせて影響を緩和することができる。 Q3 日本国内での建築用ガラス事業における値上げの効果について教えてほしい。 A3 値上げの対象となるのは、10月以降の出荷分だが、徐々に値上げが浸透することで、エネルギーコストの上昇による影響を吸収することを目指している。 Q4 建築用ガラス事業では南米市場も好調なようだが、アルゼンチンの新フロート窯の建設計画は変わらないとみて
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ セントラル硝子 第1四半期 売上高506億円(前年同期比12.3%増)自動車用ガラスが前年同期を上回る(令和3年8月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
セントラル硝子㈱は、このほど2022年3月期第1四半期(2021年4月1日~6月30日)の連結業績を発表した。 同期の売上高は506億300万円(前年同期比12.3%増)、営業利益19億500万円(同348.6%増)、経常利益23億6600万円(同87.7%増)、親会社に利属する四半期純利益13億8100万円(同126.7%増)で推移した。 ガラス事業では、建築用ガラスは、国内建築需要の減少に加えて、不採算取引を見直したことによる影響により、売上高は前年同期を下回った。 自動車用ガラスは、国内は半導体供給不足による各自動車メーカーの生産抑制の影響を受けたものの、前年同期は新型コロナウイルス感染症による各自動車メーカーの生産一時停止の影響が大きく、前年同期を大幅に上回った。一方で海外の第1四半期は1月から3月を連結対象としており、当期は北米で発生した寒波の影響による各自動車メーカーの生産一時停止の影響を受け、新型コロナウイルス感染症の影響も前年同期ではまだ比較的軽微であったことから、売上高は前年同期を下回った。 ガラス繊維は、電材及び自動車分野の出荷が好調に推移し、売上高は前年同期を大幅に上回った。 このことから、ガラス事業の売上高は279億5800万円(前年同期比4.4%増)となったものの、営業損失は4600万円の(同12億8700万円の改善)となった。 また、化成品事業は売上高226億4500万円(同23.8%増)となり、損益については19億5100万円の営業利益(同1億9300万円の増加)となった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 日本板硝子 10月1日出荷分から引き上げ 板ガラス製品・鏡製品 15~35% 建築用機能ガラス製品 15~20% (令和3年8月9日) |
|
日本板硝子㈱は7月29日(木)に、10月1日出荷分から建築用板ガラス製品の価格改定を実施し、板ガラス製品、鏡製品の価格を15~35%、建築用機能ガラス製品の価格を15~20%引き上げると発表した。 ガラス製品の価格改定は、7月15日に発表したAGCに続くもので、両社とも10月1日出荷分からの価格改定となる。 日本板硝子は、今回の価格改定について「建築用板ガラス製品においては、重油をはじめとする原燃料と各種副資材の高騰、労働力不足による労務費の上昇、物流費のさらなるアップなどが、そのコストに重大な影響を及ぼしている」ことを理由に挙げている。 |
| ■ セントラル硝子 販売価格10%~40%引き上げ 10月1日納入分から(令和3年8月9日) |
|
セントラル硝子㈱は8月2日(月)、10月1日納入分から、フロート板ガラス・鏡製品の販売価格を15~20%、型板ガラス・網入型板ガラスの販売価格を35~40%、網入磨板ガラスの販売価格を30%、加工ガラス製品(建装商品含む)の販売価格を10~30%引き上げると発表した。 この発表により、7月15日に発表のAGC、同月29日に発表の日本板硝子と合わせ、板硝子メーカー3社の10月1日からの価格改定が出揃った。 また、同社は同時に子会社の一部事業譲渡と拠点閉鎖として、セントラル硝子販売㈱(以下CGS)とセントラル硝子プラントサービス㈱(CGPS)の一部事業の譲渡と拠点の閉鎖、東北硝子建材㈱(宮城県宮城郡)の全株式を6月24日付で譲渡したことも発表している。 価格改定について同社は、「今年3月29日付で発表した『国内建築ガラス事業の構造改善について』(既報4月5日付参照)にあるように、型板窯、堺製造所のフロート窯の2021年度中の生産休止、販売体制の縮小、建築加工ガラスの生産体制の集約など構造改善を進めている」と現状を説明。しかしながら、「建築ガラス事業を取り巻く環境が、建築需要の低下に加え原油価格をはじめとする原燃料価格及び資材価格の上昇、設備維持更新コストの上昇により、非常に厳しい状況にあり、自助努力のみでは事業継続に必要な収益を安定的に確保することが困難と判断した」として、今回の販売価格改定を決定した。 さらに同社は、「物流費の高止まりから受注出荷条件の改定についても併せてお願いする」としている。 一方、子会社の一部事業譲渡と拠点閉鎖については、次のように発表している。 ◎一部事業の譲渡 8月1日付で、東北地区のCGS直販部門を事業譲渡した。 また、東北地区のCGPS加工ガラス生産拠点を今年9月末に閉鎖する事を決定している。 なお、東北地区におけるCGSの特約店への販売業務は、事業を継続する。 ◎決算に与える影響について 本事象の2022年3月期に決算に与える影響は軽微。 |
| ■ AGC 国内建築用ガラス関連製品販売価格改定 10月1日納品分から引き上げ 網入り板ガラスおよび型板ガラス30%UP(令和3年7月26日) |
|
AGC㈱は7月15日(木)、国内の建築用ガラス関連製品の販売価格を、10月1日納品分から引き上げると発表した。 引き上げ率は、フロートガラスおよびミラーが15~20%、網入板ガラスおよび型板ガラスが30%、建築用加工ガラス製品については10~20%の予定。 同社の国内建築用ガラス事業は、製造関連設備の維持更新費用の上昇などから、安定供給に必要な費用負担が増大している。また、原燃材料や副資材価格、物流費の高止まりなども加わり、収益性が圧迫される状況が継続していた。 こうした環境下で、投資内容の見直しや生産性の改善、コスト削減、組織のスリム化などの施策を進めることで、今後の設備維持更新に必要な収益の確保を図ってきた。 しかし、このほど自社努力だけで対応することが困難な状況であるとの判断に至ったことから、建築用ガラス関連製品の価格改定に踏み切ったもの。 |
| ■ 日本電気硝子 テーマは「野生のガラス」 10月までデザインコンペ(令和3年7月26日) |
|
日本電気硝子株式会社(大津市)と電気硝子建材株式会社(大阪市)は共済で、10月4日までの期間で「第28回空間デザイン・コンペティション」を開く。課題は「野生のガラス」で、コロナ禍によりコントロールできない状況が起こり、本来コントロールできる素材のガラスと相容れない「野生」を結び付けることで様々な読みが可能なキーワードとして設定した。 賞金は総額で170万円。最優秀賞(1点)には100万円が贈られる。審査委員長は横浜国立大学大学院教授の乾久美子氏。 応募・登録締め切りは2021年10月4日午後4時まで。応募するために特設サイトでの登録が必要。 |
| ■ セントラル硝子 「型板窯とフロートガラス窯」生産休止 松坂工場(2021年10月末)・堺製造所(2022年2月末)(令和3年7月12日) |
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、清水正社長)は、7月6日(火)、松阪工場の型板窯及び堺製造所のフロートガラス窯の生産休止時期について、松阪工場型板窯を2021年10月末に、また、堺製造所フロート窯を2022年2月末で休止すると発表した。 発表内容は次の通り。 当社は、2021年3月29日に「国内建築ガラス事業の構造改善について」にて、松阪工場の型板窯と、堺製造所のフロート窯の生産を2021年度中に休止する旨お知らせしました。 この度、両窯の生産休止時期を決定いたしましたので次のとおりお知らせいたします。 記 1.生産休止時期について (1)松阪工場型板窯 = (2)堺製造所フロート窯 = 2022年2月末 なお、生産休止時期は、現時点での一定の前提に基づいており、今後様々な要因により生産休止の時期を変更する可能性があります。その際は別途お知らせいたします。 2.業績に与える影響について |
■ AGC 北米建築用ガラス事業を譲渡 米国Cardinal社に 譲渡価格は4億5000万US$(令和3年6月28日)
|
||
|
AGC㈱は6月15日、北米建築用ガラス事業を米国Cardinal Glass Industries(以下Cardinal社)に譲渡することを決定し、Cardinal社と合意したと発表した。 AGCの同事業の2020年売上高は281億円、営業利益は11億円。同事業の譲渡価格は4億5000万US$(約495億円/1US$=110円)。 なお、本取引は関係当局への申請を行い、承認を得ることを条件としており、最も早く承認を得られた場合には、2021年7月に譲渡が完了する見込み。 同社の北米建築用ガラス事業は1988年にAFG Industries社(現AGC Flat Glass North America)への資本参加を機に参入。以来、30年以上省エネ性能や意匠性に優れた様々な高機能ガラスを供給していた。 今回の事業譲渡についてAGCは、「今年2月に発表した中期経営計画AGC plus‐2023で、建築用ガラス事業の収益性および資産効率の改善をグループ経営上の重点課題として取り上げている。北米における建築用ガラス事業については、過去に取引実績があり、AGCの資産や人材を有効活用できるCardinal社に事業譲渡することで、更なる事業の発展につながると判断した」としている。 また、今回の事業譲渡に伴い、譲渡益約250億円が発生する見込みで、2021年12月期第3四半期連結決算において、その他収益を計上する見込み。なお2021年12月期の通期連結業績予想に、本件が与える影響などは現在精査中とのことで、判明次第発表するとしている。 事業譲渡の概要は次の通り。 ○北米建築用ガラス事業の経営成績(2020年12月期実績) 売上高=281億円(AGCグループ連携に占める比率=2.0%) 営業利益=11億円(同1.6%) ○同事業の資産、負債の項目及び金額 諸資産=216億円 所負債=8億円 ○譲渡先の概要 ・名称=Cardinal Glass Industries ・所在地=775 Prairie Center Dr ♯200 Eden Prairie, MN 55344 ・代表者の役職・氏名=Roger O‘Shaughnessy |
| ■ 真空断熱ガラス樹脂サッシ「シャノンウインドSPG」発売 開発狙いについてインタビュー パナソニック木村部長・エクセルシャノン橋本本部長(令和3年6月14日) |
|
パナソニック㈱(本社=大阪府門真市、津賀一宏社長)ハウジングシステム事業部と㈱エクセルシャノン(東京都中央区、池田州充社長、以下、エクセルシャノン)は、国内最高クラスの断熱性能の樹脂サッシを共同開発し、6月から「シャノンウインド」の新シリーズ「真空断熱ガラス樹脂サッシ『シャノンウインドSPG』」として全国で発売すると発表。その模様を弊紙(4月26日発刊、第3215号1面)に掲載したところ、読者の方から多くのお問い合わせをいただいた。今回は、記者会見に登壇していたパナソニック㈱ハウジングシステム事業部建築システムBU VIG事業推進部・木村猛部長と㈱エクセルシャノン開発技術本部取締役本部長・橋本幸登志氏に登場していただき、発表当日に聞くことができなかったお話を一問一答形式でお答えいただいた。 ――木村部長にお聞きします。少子高齢化等で国内の新築住宅着工戸数が減少し、板ガラスメーカーも建築事業縮小に向かう中、どうして新たに窓事業に参入されたのですか。 木村 昨年、菅総理が「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロを目指す」と宣言し、脱炭素社会実現に向けた取り組みがさらに推進され、住宅においても高断熱化・省エネ化が今後ますます加速されることが予想されるからです。 ――以前から高断熱住宅について、潜在需要はあると言われていますがなかなか普及しないのが現実です。新築だけでなくガラスのリフォーム市場について、パナソニックとしてどうされるのか。 木村 ガラスのリフォームについては、業界事情に詳しいAGCさんとの協業でと考えています。 ――真空ガラス「グラベニール」が産業用として海外で既に販売されてりいると聞いていますが、建築用としてはいかがですか。 木村 断熱ガラスの市場じゃ圧倒的に海外にあります。産業用だけでなくヨーロッパでは建築用としてAGCさんとライセンス契約を結んでおり、既に製造・販売しています。産業用としてはアメリカでも販売しています。 ――他のサッシメーカとのタイアップは? 木村 考えていません。 ――「シャノンウインドSPG」の販売について、シャノンルート以外にパナソニックルートでの販売は。 木村 6月よりハウジングシステム事業部のグループ内販売会社であるパナソニックリビング株式会社より販売します。既に昨年から同社より、エクセルシャノンの樹脂サッシを販売しています。 ――施主が「シャノンウインドSPG」を見たいと言った場合どこに行けば展示品が見られますか。 橋本 当社の製造工場 ――グラベニールはパナソニックの自社で生産しているとのことだったですが、それを複層にしているのはどこですか。 木村 シャノンさんでお願いしています。 橋本 国内の複層ガラスメーカーで複層にしています。 ――「シャノンウインドSPG」の場合、トータルで3枚のLow―Eガラスを使用しています。断熱効果は高いと思いますが、視界が暗くならないですか。 橋本 そのために高透過ガラスを採用しています。 ――施主の希望で「Low―Eガラスは1枚でもいいです」と言った場合、対応は可能ですか? 橋本 「シャノンウインドSPG」では、対応していません。 ――特寸対応は? 橋本 納期は40日前後で対応しています。 ――反応はどうか? 橋本 発表後、おかげさまで多くの方からお問い合わせをいただいており、採用予定もあります。 ――パナソニックのグループ会社にパナソニックホームズがありますが、そこでの採用予定は 木村 グループ企業ではありますが、別会社ですので、採用については、私どもからは申し上げられません。 ――「シャノンウインドSPG」の防火タイプは。 橋本 ご要望があれば検討しますが、今のところ考えていません。 ――販売目標は? 橋本 前回もお話していますが、シャノンウインド全体で年間約1万棟に採用されています。2030年には製品力強化や協業による販路拡大で年間3万棟まで増やしたいです。 ――これまでガラス業界では、潜在需要を掘り起こすため、展示会、勉強会、セミナー等をやってきていますが、なかなか広まりません。どうも一般施主にまでは情報が伝わっていない感じです。ぜひ、SNS等も活用してアピールをお願いしたく思います。 木村 パナソニックの理念に、「共創」という考えがあります。自前ですべてはやりきれないからです。パートナ企業と一緒になって高断熱窓を広めていきたいと思います。 ★ ★ ★ ☆真空断熱ガラス樹脂サッシ「シャノンウインドSPG」とは パナソニックの真空断熱ガラス「グラベニール」とエクセルシャノンの高断熱フレーム「UF‐H樹脂フレーム」を組み合わせた樹脂サッシ。高透過Low‐Eガラス「ESクリアスーパー」を屋外側(3㎜)と中央(4㎜)配置し、屋内側に6・1㎜の薄さで国内最高クラスの断熱性能を発揮する「グラベニール」を配置したトリプルガラスで、12㎜の空気層にはクリプトンガスを封入し、ガラス面の断熱性能を最大限に高めている。 加えて、高断熱構造の樹脂フレーム内にノンフロンのポリウレタン系断熱材を充填することで、窓全体の熱貫流率が縦すべり出し窓(連窓)で0・52W/(㎡・K)、FIX窓で0・47W/(㎡・K)と国内最高クラスの断熱性能を実現した。 高い断熱性能により住宅のエネルギーロスを抑えられるうえ、結露の発生にも高い抑制効果がある。さらに、3層のうち屋外側2層に高透過ガラスを採用しているため、ガラスを複層化しながらもクリアな視界を確保(可視光透過率55・3%)した。また、住宅性能表示・窓の遮音性の最高等級である等級3と比較して、約3倍の高い遮音性能も確保している。 |
| ■ セントラル硝子 事業譲渡ならびに拠点閉鎖 国内建築ガラス事業構造改善 セントラル硝子販売・プラントサービス(令和3年6月7日) | ||||||
|
セントラル硝子㈱は、6月1日付で子会社のセントラル硝子販売㈱(本社=東京都杉並区、以下、CGS)と、セントラル硝子プラントサービス㈱(本社=三重県松阪市
、 以下、CGPS)の一部事業の譲渡と拠点の閉鎖を発表した。 なお、同社グループの建築ガラス事業については、CGS社は主に特約店への販売業務、ゼネコン、工務店、ハウスビルダー等への販売業務(直販部門)を担っており、CGPS社が建築加工ガラスの生産業務を担っている。 今回の事業譲渡ならびに拠点閉鎖は今年3月29日に発表した「国内建築ガラス事業の構造改善について」(既報4月5日付参照)のとおり、国内建築ガラス事業は、販売体制を生産規模に合わせた適正な販売拠点数まで縮小、また、建築加工ガラスの生産体制も、生産性の高い拠点に生産を集約し生産能力を適正規模にすることを決めており、この一環によるもの。 発表の詳細は次の通り。 ◎一部事業の譲渡と閉鎖について 6月1日付で、 中部地区のCGSの直販部門 および 、静岡のCGPSのガラス切断加工拠点 を事業譲渡した。 また、九州地区においてもCGPSの加工ガラス生産拠点を5月31日に閉鎖、更に同地区の CGSの直販部門の拠点 も、10月末を目処に順次閉鎖する。 なお、中部地区、九州 地区におけるCGSの 特約店への販売業務は、 事業を継続する。 ◎決算に与える影響について 本件について、2022年3月期決算に与える影響は軽微である。 また、セントラル硝子販売㈱九州支社(福岡県粕屋郡、井之口奨支社長)は、今回の発表に関して、すでに取引先に文書で通知を行っている。 これによると、建材営業部の事業終了は9月30日、事業所の閉鎖は10月31日をそれぞれ予定しており、特約店営業部は存続するとのこと。 九州支社の建材営業部の閉鎖に伴う、6月以降の動向は次の通り。 ①10月1日以降は、債権回収や債務支払いの残務処理のみとなり、販売や工事、配送等の通常営業は停止する。 ②新規受注は5月末までの出荷をもって停止する。6月以降は受注済みの継続物件に限り対応する。 |
||||||
| ■ まねきや硝子 CGS中部地区の直販部門 CGPS・静岡の加工拠点を譲り受ける(令和3年6月7日) | ||||||
|
セントラル硝子特約店まねきや硝子㈱(本社=大阪府東大阪市、奥山寛一社長)は、6月1日よりセントラル硝子販売㈱・中部支社(愛知県名古屋市、曽根良得支社長)建材営業部の名古屋支店(愛知県名古屋市)、岐阜支店(岐阜県岐阜市)、静岡支店(静岡県静岡市)、富士支店(静岡県静岡市)および浜松営業所(静岡県浜松市)の事業とセントラル硝子プラントサービス㈱の静岡市にあるガラス加工拠点を譲り受けたと発表した。先日、東大阪市にあるまねきや硝子本社を訪問し、専務取締役・奥山喜茂氏にお話を伺った。 譲り受けた従業員は72名(まねきや硝子は現244名)。投資金額は未発表。特約店の営業業務は引き続きセントラル硝子販売が行うとしている。 統括支店長はまねきや硝子名古屋支店の熊澤部長が担当する。 |
||||||
■ 伊藤硝子 ウイルスクリーンα寄贈 名古屋学院大学に9枚(令和3年6月7日)
|
||||||
|
伊藤硝子株式会社(名古屋市熱田区神戸町)は5月26日、名古屋学院大学名古屋キャンパスたいほうで「ガラス製卓上パーティション」の贈呈式を行った。既にこの春、同キャンパス1階のグループ・ワーク・スペースと2階の学生のカウンターに設置済み。 贈ったのは、日本板硝子の「ウィルスクリーンα(アルファ)」を使ったガラス製卓上パーティションで、1階設置が1000ミリ×600ミリ、2階設置が700ミリ×500ミリ。コーナーR30磨き。4ミリ・中間膜・4ミリ合わせガラスで両面抗菌加工(SIAAマーク取得(ISO21702抗ウイルス加工)。1階に8枚、2階が1枚の合計9枚。 「コロナ禍の影響で学生が学校に行けない状況が続いている。何かガラス業者として出来ないかということから、日本板硝子のウィルスクリーンを寄贈しようということになった」という。更に、「ウィルスクリーンという良い商品を更に広く知ってもらえる機会になれば」と同社では話している。 贈呈式に出席したのは、伊藤硝子株式会社から代表取締役の本田英修氏、営業部の本田幸大氏、同・中春香氏、日本板硝子から硝子建材営業部の新井大智氏。 名古屋学院大学から国際センター長の須川精致氏、国際センター課長の長瀬賢俊氏、事務局長の山田隆氏、総務部長の箕浦太郎氏、広報室室長の小西綾子氏、同・主事の橋之口幸一郎氏。 贈呈者を代表して本田社長があいさつを述べ、「ガラス製卓上パーティションの目録」を贈呈した。名古屋学院大学から須川国際センター長が感謝状が贈られた。 本田社長は「1883年に名古屋学院大学の前身である愛知英語学校が創立されたと聞く。当社も前身の伊藤商店が同時期に創業しており強い縁を感じている。コロナ禍により、大学も授業のやり方を変えるなど大変な状況だ。ガラス業界として何か貢献できないかと考えていたが、飛沫感染防止に日本板硝子のウィルスクリーンが有効と考えた。照明下でも20分で大半のウイルスが消滅するという。毎日の消毒や作業の正確性を考えるとガラスそのものに坑ウイルス機能があり、学生らにも安心・安全を提供できると思う」と話した。 須川国際センター長は「現在、緊急事態宣言により再びオンライン授業を実施しており、学生のいないキャンパスは淋しい限りだ。そのような中、パーティションが寄贈を受けた。学生が安心して勉学に励む環境をいただいたと思っている。1階のグループ・ワーク・スペースは学生に人気がある場所であり、2階のカウンターは学生たちが自ら運営する場所である。学生が再び集まるようになっても対面する環境でも安心と活気を両立できると思っている」と述べた。 |
| ■ 日本板硝子 3月期 売上高4992億円(前年同期比10.2%減)当期損失163億円(令和3年5月31日) |
|
日本板硝子㈱は、2020年3月期(2012年4月1日~2021年3月31日)決算を発表した。 連結の売上高は4992億2400万円(前年同期比10.2%減)、営業利益130億6700万円(同38.3%減)、税引前損失171億7100万円、当期損失163億1600万円、親会社の所有者に帰属する当期損失169億3000万円となった。 なお、2021年3月期の個別業績は、売上高873億2700万円(前年同期比16.9%減)、営業損失56億7400万円、経常損失102億2200万円、当期純損失2億800万円。 セグメント別の概況は次の通り。 ○建築用ガラス事業 建築用ガラス事業の売上高は2155億円(前連結会計年度は2337億円)、営業利益は157億円(同173億円)となった。第1四半期における新型コロナウイルス感染拡大による需要減少の影響を受け、累計では減収減益となったが、第2四半期以降、各四半期の営業利益は前年を上回っている。 欧州の建築用ガラス事業の売上高は、グループ全体における39%を占めている。第1四半期において新型コロナウイルス感染拡大により販売数量が減少し、累計の売上高は減少した。第2四半期には販売数量が大きく改善し、第1四半期に休止していた生産設備も再開、第3、第4四半期にかけて更に改善した。販売価格は需要の増加に合わせて改善し、また安定した操業とコスト管理の強化により、収益性も改善した。 アジアの売上高は、グループ全体の36%を占める。新型コロナウイルス感染拡大により売上高は前年度より減少した。新型コロナウイルス感染拡大の影響は、建築活動において大きかったものの、太陽電池パネル用ガラスの出荷数量への影響は比較的軽微だった。一方、千葉とマレーシアのフロート窯をそれぞれ1基ずつ休止したことによる固定費削減も含めたコスト削減効果等により、利益は改善した。 米州の売上高は25%を占める。累計の売上高と営業利益は、第1四半期における新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、前年度を下回ったが、第2四半期以降、南米の販売数量増加もあり売上は前年度比改善した。建設中だった米国オハイオ州(トロイ地区ラッキー)における太陽電池パネル用ガラス製造用の新フロート窯については、第3四半期に稼働を開始している。 ○自動車用ガラス事業 自動車用ガラス事業の売上高は2452億円(前連結会計年度2810億円)、営業利益は18億円(同61億円の利益)となった。自動車用ガラス事業は、第1四半期に新型コロナウイルス感染拡大により需要が激減した影響を受け、減収減益となった。しかし、新車用ガラスは6月以降徐々に需要が回復し、当第4四半期の3か月間の売上高及び営業利益は、大規模な自動車生産の停止が行われた前年度を大幅に上回った。一方で、多くの地域で自動車生産に必要な半導体部品の供給不足の影響を受けた。補修用ガラスの需要は、ロックダウンの緩和により第2四半期以降に改善した。 欧州における自動車用ガラス事業の売上高は、グループ全体の42%を占めている。累計の売上高と営業利益は、第1四半期において新型コロナウイルス感染拡大により、需要が激減した影響を受け、前年度を下回った。自動車メーカーが第1四半期末にかけて生産を再開し、第2四半期以降、徐々に生産台数を増加させたことに対応して同社の生産も回復。第4四半期の売上高と営業利益は、欧州の多くの地域で実施されたロックダウンや自動車メーカーでの半導体部品不足の影響を受けたものの、前年を上回った。 アジアの売上高は、25%を占める。累計の売上高と営業利益は、新型コロナウイルス感染拡大により前年度を下回った。生産は年度を通じて、概ね継続されていたが、第2四半期以降は自動車生産台数増加の恩恵を受けた。一方、直近では半導体部品不足や、第4四半期に日本で発生した地震に伴う部品の供給不足が、自動車生産台数の回復を押し下げる要因となっている。 米州における自動車用ガラス事業の売上高はグループ全体における当事業売上高の33%を占めている。売上高は、累計では新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、前年度を下回ったが、第4四半期においては、売上高、営業利益は前年を上回った。北米では、自動車の在庫水準の回復や自動車販売台数の増加により、第2四半期以降、自動車生産台数が回復。南米においても、比較的低い水準ではあるものの、自動車生産台数は回復基調にある。直近では北米を中心に、自動車メーカーでの半導体部品不足の影響を受けている。 ○高機能ガラス事業 高機能ガラス事業の売上高は368億円(前連結会計年度は401億円)、営業利益は67億円(同71億円)となった。主に年度前半における新型コロナウイルス感染拡大の影響により、減収減益となっている。 ファインガラス事業は、新型コロナウイルス感染拡大による影響は限定的であり、年度後半にかけて回復基調が続いている。 情報通信デバイス事業では、在宅勤務やオンライン授業の需要増加によりプリンター用レンズの販売数量が続伸した。 エンジンのタイミングベルト用グラスコードの需要は、自動車市場環境の影響を受けて減少したが、年度末にかけて回復した。 化粧品向けに使用されるメタシャインの売上高は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け減少。 電池用セパレーター事業の業績は安定的に推移した。 |
| ■ セントラル硝子 3学期 売上高1906億円(前年比14.3%減) 純利益12億3000万円(令和3年5月31日) |
|
セントラル硝子㈱は、2021年3月期(2020年4月1日~2021年3月31日)の決算を発表した。 連結経営成績は、売上高1906億7300万円で(前期比14.3%減)、営業利益40億6400万円(同49.0%減)、経常利益47億4900万円(同44.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益12億3000万円(同80.8%減)で、減収減益となった。 個別経営成績は、売上高859億1500万円(前期比9.1%減)、営業利益26億2700万円(同38.0%減)、経常利益54億6500万円(同24.2%減)、当期純利益51億6400万円(同1.2%増)となっている。 セグメント別の概況は次の通り。 ○ガラス事業 建築用ガラスは、国内建築需要の減少に加えて、不採算取引を見直したことによる影響、および米国建築用加工ガラス事業からの撤退により、売上高は前期を下回った。 自動車用ガラスは、国内外共に新型コロナウイルス感染症の影響による上半期の大幅な販売減により、国内、海外共に売上高は前期を下回った。 ガラス繊維には、新型コロナウイルス感染症の影響による上半期の自動車分野の販売減が影響し、売上高は前期を下回った。 この結果、ガラス事業の売上高は1123万9800万円(前期比22.1%減)となり、損益は30億2000万円の営業損失(同30億4400万円の悪化)となった。 ○化成品事業 化学品は、主力のハイドロフルオロオレフィン製品が、次世代溶剤の販売は順調に推移したものの、断熱用発泡剤が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、出荷量が減少したことから、売上高は前期を下回った。 ファインケミカルは、医療関連製品の販売は世界的に不急の手術が先送り傾向にあることから低調に推移したものの、堅調な半導体需要により半導体用途の特殊ガス関連製品の出荷が増加し、農薬関連製品、リチウムイオン電池用電解液製品の販売も好調に推移したため、売上高は前期を上回った。 肥料は、一部製品の需要が減少したことにより、売上高は前期を下回った。 この結果、化成品事業の売上高は782億7400百万円(同0.1%増)となり、損益は70億8400万円の営業利益(同8億6700万円の減少)となった。 |
| ■ AGC 第1四半期 売上高3935億円 純利益348億円(令和3年5月31日) |
|
AGC㈱は、2021年12月期第1四半期連結累計期間(2021年1月1日~3月31日)の決算を発表した。 売上高は3935億6500万円(前年同期比10.1%増)、営業利益442億2300万円(同98.0%増)、税引前四半期利益441億5200万円(同176.9%増)、四半期純利益348億9100万円(同161.6%増)となった。 本1四半期のガラスセグメントの売上高は、建築用ガラスが891億円(前年同期比90億円増)、自動車用ガラスは908億円(同19億円増)、その他7億円(同4億円増)の、合計1806億円(同122億円増)となった。 建築用ガラスは、①日本を除く地域で出荷が堅調に推移、②欧州・南米を中心に販売価格が上昇、③欧州建築用ガラス製造設備における稼働率向上により、製造原価が低減、などの要因から増収に転じたとしている。 一方、自働車用ガラスは、中国を除く地域の自動車生産台数は前年同期を下回るものの、中国での自動車生産台数が大幅に増加し、出荷が増加したことから、増収になったと説明している。 なお、2021年12月期の連結業績予想(2021年1月1日~12月31日)は、売上高1兆6500億円(前年同期比16.8%増)、営業利益160億円(同111.1%増)、税引前利益1420憶円(148.6%増)、当期純利益1050億円(155.1%増)を見込んでいる。 |
| ■ AGC 原燃材料の自動管理システム「Smart Inventory System」を開発 |
|
AGC㈱(本社=東京都、平井良典社長)は、4月26日(月)午前11時より同社のDX(デジタルトランスフォーメーション:ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させる意)戦略および購買・物流部門におけるDXの取り組みに関して、オンライン方式で、メディア向け説明会を開催した。 説明会では、経営企画本部DX推進部長・池谷卓氏が、AGCのDX戦略について説明した。池谷部長はAGC推進のポイントについて ・トップダウン+自律・自発のハイブリッド推進体制 経営企画本部内に「DX推進部」を設置(2017年~)→経営トップ主導でDXを推進 各事業部門に推進組織を整備(2020年~)→自律的・自発的な取り組みにより、事業軸で成果 ・取り組み領域 モノづくり、開発の領域からDXに着手→製造業として必要性の高い領域から着手。営業・マーケティング、物流などに拡張 ・二刀流の推進人材 業務知識とデジタルスキルを併せ持つ「二刀流人材」を育成→素材メーカーとしての当社の強みを、デジタル技術でさらに高める、と説明した。 パレットIoTシステムについて、デジタルを活用し、パレットの位置情報、稼働状況を把握。パレットの紛失を防止するとともに、物流を効率化。また、輸送時のCO2排出量を1~5%削減したと述べた。現在、大型パレット1400台に物流トラッカーを取り付け、欧州、アジア地域へも導入を進め、2022年までに対象パレットを3万台にすると述べた。 続いて、購買部門におけるDXの取り組みついて、関西工場尼崎事業所・田中卓弥氏(入社6年目)と同工場高砂事業所事業部業務G・田上直弥氏(入社5年目)が説明。田中氏が「Smart Inventory
System(原料在庫管理システム)」について、また、田上氏が「Smart Inventory System(タンク在庫管理システム)」について説明した。 内容は次の通り。 AGCは、原燃材料の⾃動管理システム「Smart Inventory System」を開発した。本年4⽉より関⻄⼯場⾼砂事業所(兵庫県⾼砂市)および尼崎事業所(兵庫県尼崎市)に本格導⼊し、これまで⼈⼿で⾏っていた在庫確認、調達計画の⽴案、発注などの調達業務にDXを導⼊することで、作業者の技能伝承を進めるとともに、年間1000時間の作業時間の削減を⾒込んでいる。今後は国内ガラス⼯場を中⼼に、他⼯場への展開も検討している。 ガラス⼯場では、ガラスを⽣産するために必要な珪砂などの原料や、排⽔処理で使⽤する苛性ソーダや塩酸などを⽇々調達している。複雑な⽣産計画に対応するため、担当者は毎⽇在庫量の確認を⾏い、調達計画の⾒直し、保管・使⽤計画の変更対応などに多⼤な時間を要していた。
「Smart Inventory System」は、AGCが新たに開発した原燃材料の⾃動管理システム。全ての原料容器に原料データが紐づけられた
RFIDタグを取り付け、建屋出⼊⼝に設置したセンサーによりタグ情報を収集することで、原料データの保管・使⽤履歴をリアルタイムに把握することが可能となる。 また、苛性ソーダなど⽬視で在庫管理をしていたタンクについては、残量をデジタルデータ化し、専⽤の計測装置を設置することでタンク在庫を遠隔監視でき、⾃動で発注できるシステムを開発してた。 |
|
公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は、かねてより令和3年度(第43回)研究助成事業について募集と選考を行ってきたが、このほど助成対象研究を決定し、4月19日(月)午後1時半より、贈呈式を開催した。贈呈式終了後には、特別講演として、イノベーションオフィス田中代表で元東レ㈱代表取締役副社長の田中千秋氏が講師となって「R&Dを通じてサステナブルな社会の実現を」をテーマに講演会が行われた。 昨年の贈呈式は1回目の緊急事態宣言で中止。今年は2年ぶりの開催予定だったが、蔓延防止等重点措置が東京にも拡大適用のためオンラインでの開催となった。 藤本理事長は冒頭に「すばらしい成果を上げるには研究者個人の独創的発想が重要だが、様々な連携、協力、支援が必要だ」とあいさつした。 助成会によると制度の目的は「無機材料分野における科学技術の発展に貢献すること」。財団設立以来、この分野で国内では今回を含め累計5470件の応募があり、そのうち総計1363件を選考した。助成金総額は17億円超に上っている。 令和3年度の国内助成では、54の研究機関から111件の応募があり、その中から36件、3740万円の研究助成をすることになった。 藤本理事長は「助成者の方にはお喜びを申し上げるとともに大きな成果を期待している」と述べた 式典では、選考委員長の平尾一之氏(京都大学名誉教授)が「12月・3月に厳正に審査した。女性4名を含む36名の方に助成することになった。本年度はコロナ禍で研究しにくい状況にあったが、良く練られた研究経過やイノベーティブ研究経過が数多く見受けられた。今回採択された方の平均年齢は39・8歳と40歳以下となり昨年より下がった。35~39歳の方が全体の3割を占め、最も多かった。採択率は30~34歳の方が最も多く50%近くになった。若い方の未来の発展に期待している」と審査経過を報告。 その後、助成者が一人ひとり自己紹介した後、藤本理事長が代表者2名に研究助成金を贈呈した。 続いて、来賓の経済産業省製造産業局素材産業課・小林麻子企画調査官が「本制度は長きにわたり科学技術の発展に寄与されている。本制度は意義があり今後も長く継続されることを願っている」と祝辞を述べた。 最後に、受領者を代表して、大阪大学理学研究科物理学専攻・上田浩平助教が「助成金を有効に活用し最大限努力し引き続き研究に取り組んで行きたい」と謝辞を述べた。 |
■ エクセルシャノン パナソニックハウジングシステム事業部 国内最高クラス 断熱性能の樹脂サッシ共同開発 「シャノンウインドSPG」全国発売 真空断熱ガラス「グラベニール」を建築用に導入(令和3年4月26日)
|
|||
|
㈱エクセルシャノン(東京都中央区、池田州充社長、以下、エクセルシャノン)とパナソニック㈱ハウジングシステム事業部は、国内最高クラスの断熱性能の樹脂サッシを共同開発した。今年6月から、エクセルシャノンより「シャノンウインド」の新シリーズ「真空断熱ガラス樹脂サッシ『シャノンウインドSPG』」として全国で発売する。 なお、シャノンウインドSPGは、2020年度の省エネ大賞で「経済産業大臣賞」を受賞したパナソニックの真空断熱ガラス「Glavenir(グラベニール)」が採用されており、国内の建築物用の樹脂サッシに組み込まれるのは、今回が初めて。 今回共同開発した真空断熱ガラス樹脂サッシ「シャノンウインドSPG」は、パナソニックの真空断熱ガラス「グラベニール」とエクセルシャノンの高断熱フレーム「UF‐H樹脂フレーム」を組み合わせた樹脂サッシ。高透過Low‐Eガラス「ESクリアスーパー」を屋外側(3㎜)と中央(4㎜)配置し、屋内側に6・1㎜の薄さで国内最高クラスの断熱性能を発揮する「グラベニール」を配置したトリプルガラスで、12㎜の空気層にはクリプトンガスを封入し、ガラス面の断熱性能を最大限に高めている。 加えて、高断熱構造の樹脂フレーム内にノンフロンのポリウレタン系断熱材を充填することで、窓全体の熱貫流率が縦すべり出し窓(連窓)で0・52W/(㎡・K)、FIX窓で0・47W/(㎡・K)と国内最高クラスの断熱性能を実現した。 高い断熱性能により住宅のエネルギーロスを抑えられるうえ、結露の発生にも高い抑制効果がある。さらに、3層のうち屋外側2層に高透過ガラスを採用しているため、ガラスを複層化しながらもクリアな視界を確保(可視光透過率55・3%)した。また、住宅性能表示・窓の遮音性の最高等級である等級3と比較して、約3倍の高い遮音性能も確保している。 両社は、シャノンウインドSPGの販売開始にあたり、4月14日(水)午後1時から、オンラインで新製品発表会を開催した。 エクセルシャノンから、池田州充社長と開発技術本部の橋本幸登志本部長が、パナソニックからは、ハウジングシステム事業部 建築システムBU VIG事業推進部の木村猛部長が出席。 初めに、池田社長からエクセルシャノンの会社概要や事業戦略の説明が行われ、同社の樹脂サッシの販売目論見を、現在の年間1万棟から、2030年には製品力強化や協業による販路拡大で年間3万棟まで増やしたい考えを示した。 次に、木村部長が登壇し、真空断熱ガラス「グラベニール」の特長を説明した。グラベニールは、真空断熱ガラスとプラズマディスプレイパネルの構造上の共通点に着目して生まれたもので、信頼性の高い真空封着技術を武器として活用している。①約6㎜の厚さで熱貫流率U=0・7w/㎡・kの断熱性能を持つ、②真空排気孔の封止部レス、③鉛フリーの真空封着材、などの特長を持つことなどを解説した。 続いて、橋本本部長が「シャノンウインドSPG」の製品説明を行い、7窓種(縦すべり出し窓 単窓/連窓/段窓、横すべり出し窓 単窓/連窓、大開口横すべり出し窓、FIX窓)、カラーはホワイトのみで展開し、価格(縦すべり出し窓 サッシサイズ=W640㎜×H1170㎜)で28万5120円(税込)であることを発表。また、外皮性能を高めたい高性能住宅や、窓付近の冷輻射抑制、結露防止が必要な病院・老健施設等の市場も視野に入れた展開も検討しているとし、5月以降全国で内覧会を行う予定と明かした。 最後に質疑応答が行われた。主なQ&Aは次の通り。 Q1 新築用かリフォーム用か?また、海外展開は? A1 新築用。当面は日本国内での販売のみだが、輸出も視野に入れている。 Q2 パナソニックブランドでの窓の販売はあるのか? A2 考えていない。エクセルシャノンのブランドを活かして展開したい。 Q3 グラベニールの生産はどこで行っているのか? |
| ■ AGC平井社長 チャレンジし続ける 入社式をオンライン形式で(令和3年4月12日) |
|
AGC㈱の平井良典社長は4月1日(木)、2021年新入社員の入社(新入社員110名、うち女性16人)にあたり、社長挨拶を行った。 なお、今年は新型コロナウイルスの影響を考慮し、入社式をオンライン形式で開催した。 オリエンテーションでの挨拶(要旨)は次のとおり。 1.歓迎の言葉 本年新たにAGCグループのCEOに就任した平井良典です。世界約30か国、グループ従業員5万6000⼈の仲間とともに皆さんの⼊社を⼼から歓迎します。 2.新⼊社員の皆さんと共有したい3つの思い 2015年、AGCは”2025年のありたい姿”を策定し、以来戦略事業の確⽴と伸⻑、組織・カルチャーの変⾰を⾏ってきました。今年から「コーポレートトランスフォーメーション(企業変革)第2章」と位置付け、⻑期経営戦略”2030年のありたい姿”、経営⽅針
AGC plus2・0、中期経営計画AGC plus‐2023を新たに策定しました。”2030年のありたい姿”の実現に向け、新⼊社員の皆さんと共有したい思いは次の通りです。 1)我々は“One Team“ 2)行動指針は”Challenge“ 3)成長の原動力は”人財“ ブランドステートメント”Your Dreams, Our Challenge”にあるように、お客様を始めとする社会の実現したい夢に対して、私たちの素材とソリューションを通じて貢献していくことに果敢にチャレンジしてください。今⽇からスタートする皆さんの社会⼈⽣活において、時には達成不可能と思われる課題に直⾯することでしょう。そんな時も決してやる前から不可能と思わず、「まず、やってみて」ください。チャレンジし続けることが、必ず皆さんの成⻑に繋がっていきます。 3.最後に |
| ■ 日本板硝子 変化に対応していく気持を 森茂樹社長があいさつ(令和3年4月12日) |
|
日本板硝子㈱は4月1日(木)、新入社員の入社式を開催した。 森茂樹社長のあいさつ(要約)は次の通り。 皆さんは本日から社会人になります。社会人としての要件の一つは経済的自立です。これから毎月会社が皆さんに給与を支払いますが、これは、皆さんが期待される役割を果たしたから支払うものです。会社の期待とは何か、そしてそれにこたえていくためには何をすればいいのかを、常に考えながら仕事に向き合ってほしいと思います。 そしてもう一つ、社会人になるための大切な要件があります。それは社会に貢献することです。社会の構成員として、一人一人が社会を支えて使命を果たしていかなければ社会は成り立ちません。皆さんは、SDGs(エスディージーズ)という言葉を聞いたことがあると思います。SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標です。17の目標が掲げられており、当社もその目標に賛同しています。企業も単に自社の利潤を追求するだけでなく、世界・人類のための貢献を求められています。皆さんにも、一個人として、そして企業人として世の中に貢献していってほしいと思います。 社会人であるためのこれら2つの要件である、経済的な自立と社会への貢献を今後実行していくためには、自分がいったい何者で、どうやって生きていくのかを、考えてほしいと思います。自分の周りを見て、人の気持ちを理解して、その中で自分がどういう役割を果たしていかなければならないかを考えてほしいと思います。客観的にものごとを見る力、そして自分でしっかり考える力を身に付けていくことが重要です。 皆さんは、20世紀の最終盤に生まれ、21世紀に生きていく人たちです。21世紀が今後さらにどうなっていくのか、それには色々な見方があるでしょう。皆さんには、この世紀を生き抜いていくために、「時代を見る目」を養い、そのなかで自己の「アイデンティティを確立するための座標軸」を持ち、そして「どう身を処していくのかということを考える力」を持ってほしいと思います。 私は、21世紀に二つの重要な変化が起きると考えています。 まず一つは、国境の意味が薄れ、グローバルのつながりがよりいっそう強くなるということです。インターネットの発達により情報には国境はなくなりました。また、モノの世界でもサプライチェーンがグローバルにつながった結果、世界は一体となって動いています。最近でも一地域の一工場で起きた火災が、世界の産業活動を止めてしまうというようなことが起こっています。産業界に身を置く以上、グローバルな視点を持ち、常に世界の動きを把握し、そして実際に世界中の人たちと共に働くことが必須になってきます。皆さんも仕事の幅が広がっていくに従い、海外とのコミュニケーションする場が増えてきます。しっかり世界を見て、客観的に考える力を付け、きちんとグローバルにコミュニケーションを行ってください。 次に、デジタル化の進展、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション)です。第4次産業革命と言ってもいいかもしれません。18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化が起こった1次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大量生産が始まった第2次産業革命、そして1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化による第3次産業革命に続いて、IoT・ビックデータ・AI・ロボットなどの技術革新により産業に大きな変革をもたらすと言われています。 シンギュラリティという言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。2045年にはAIが人間の脳を超えるという説です。これが当たっているかどうかは別にして、もうすでに、人間がこなしていた仕事がどんどんコンピュータやロボットに置き換わっています。そして一部ではAIが考えて指示したことを人間が行うということも始まっています。間違いなく定型的な仕事はAIに置き換わっていきます。その時に、皆さんはどう自分の存在感を保っていくか、何で貢献していくか、それは大きな課題です。 グローバル化やデジタル化が進む中で、はっきり言えることは、過去と同じことを繰り返していては企業も生き残っていけないということだと思います。ダーウインは、「生き残る種とは、最も強いものではない。最も知的なものでもない。それは、変化に最もよく適応したものである
」と言っています。 |
| ■ セントラル硝子 国内建築ガラス事業の構造改善 ガラス生産窯を半減 建築需要の低下で(令和3年4月5日) |
|
セントラル硝子㈱は、3月29日(月)開催の取締役会において、国内建築ガラス事業の構造改善を決定した旨発表した。 国内建築ガラス事業の環境は、将来的な人口減少に伴う建築需要の低下が見込まれる中、新型コロナウイルス感染症の影響も加わり、今後の見通しは更に不透明感が強まっている。当事業の将来計画を策定及び実行していく上で市場の縮小を前提に置かざるを得ないと判断。資産の圧縮および効率的な活用を積極的に進めることで、事業収益の改善を目指すことを目的としている。 同社の発表の概要は、次の通り。 ①計画の基本方針 収益性に基づいた事業の選択及び最適な事業規模での運営を基本方針とし、事業収益改善に取り組む。 ②板ガラス生産窯について 稼働率の低下が懸念される松阪工場の型板窯と、堺製造所のフロート窯は2021年度中に休止し、 板ガラスの生産設備を現状の4窯から2窯体制に縮小する。松阪工場のフロート窯と網入磨き板ガラス窯については生産を継続し、2窯の休止後は、型板ガラスは外部調達、フロートガラスは松阪工場のフロート窯に生産を集約、自動車用フロートガラスと併産し対応する。また、休止する2窯の生産に関与している社員は、雇用の維持に努める。 ③販売及び建築加工ガラスの生産について 販売については、すでに電子材料 用及び産業用フロートガラスの販売を2021年度中に中止することを決定しているが、今後も不採算取引を是正するとともに、生産規模に合わせた適正な販売拠点数まで縮小する。また、建築
加工ガラスの生産体制についても、生産性の高い拠点に生産を集約し生産能力を適正規模する。 ④本事業計画における効果について 新たな体制では、事業規模の見直しによる減収が見込まれるものの、損益面では、販売面での採算性の改善と固定費削減による収益改善効果が2022年度より顕在化することで黒字化を見込んでいる。また、向こう5年間での冷修が必要となるガラス生産窯の減少および設備更新投資を抑制し、キャッシュフローを改善する。なお、2022年度以降の計画は、今後策定する中期事業計画で発表する。 ⑤今期の決算に与える影響について 生産を休止する2窯の特別修繕引当金の取り崩しが生じるが、その他の影響も含めて、別途公表する。 なお同社は、同時に特別利益及び特別損失の計上を同時に発表した。 松阪工場の型板窯及び堺製造所のフロート窯を2021年度中に休止することに伴い、両窯の定期的修繕費用の支出に備えるため計上していた特別修繕引当金を取り崩し、特別修繕引当金戻入益として約38億円を特別利益に計上。 一方、構造改善を踏まえた将来事業計画に基づき、当該生産設備の回収可能性を検討した結果、 |
| ■ 令和2年度後期 ガラス施工技能検定合格者 1級95人、2級76人合格 2級に2人の女性合格者(令和3年3月29日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
令和2年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月19日(金)に全国の職業能力開発協会から発表された。 ◇ 1級の受検者が2ケタの所は5都県で、前年の6都府県を下回った。受検者数が最も多かったのは東京の19人(前年22人)で、5年連続の受検者数1位となっている。2級受検者数は、愛知県と鹿児島県の11人(前年は愛知県の29人)が最も多い。 ◇ 1級合格率が100%のところは、茨城県(4人)、石川県(1人)、長野県(2人)、佐賀県(2人)、大分県(1人)の5県(前年は青森県、富山県、石川県、福井県の4県)となった。 ◇ 職業能力開発協会からの回答でガラス施工技能検定試験が未実施との回答があった県は、千葉県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、徳島県、香川県、長崎県、熊本県の12県(前年は千葉県、山梨県、岐阜県、静岡県、三重県、徳島県、香川県、長崎県の8県)で、前年から4県増加した。この中で、岐阜県は8年連続、山梨県は9年連続、香川県は10年連続して、検定試験を実施していない。 ◇ 今回は、3年ぶりに女性の受検者が2人いた。秋田県と東京都で2級を受験しており、いずれも合格している。 ◇ 今回の検定では、前年に比べ、合格率が回復した。昨年は41%にとどまった1級合格率が、今年は53%と12ポイント回復。2級合格率も63%で前年から17ポイント回復している。合格率が向上した背景は現在調査中だが、各単組が開催する訓練校や、講習会の指導が奏功している表れではないだろうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■厚労省 中央職業能力開発協会 全国技能士連合会 「技能グランプリ」開催 和田暁典氏が厚生労働大臣賞金賞 東京都2名、大阪府3名が参加(令和3年3月1日)
|
||||||
|
厚生労働省と中央職業能力開発協会、(一社)全国技能士連合会が主催する、第31回技能グランプリが2月19日(金)~22日(月)の4日間、愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo/愛知県常滑市)ほか3会場で開催した。 |
||||||
■日本板硝子 ウイルスクリーン「SIAA」認証を取得 「ウイルスクリーンα」で販売(令和3年3月1日)
|
||||||
|
日本板硝子㈱は、抗ウイルスガラス「ウイルスクリーン」がSIAA(抗菌製品技術協議会)の認証を取得したと発表した。また、これに伴い、製品名を「ウイルスクリーンα(アルファ)」とし、販売を開始した。 |
| ■ 日本板硝子材料工学助成会 「無機材料に関する最近の研究成果」発表会 「新しい風を」の下、4氏が講演 令和2年度まで総額17億円を贈呈(令和3年2月8日) |
|
公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は1月27日(水)午後1時より「第38回無機材料に関する最近の研究成果発表会」を開催。4人(当初は5人だったが1人は欠席)の研究者が「材料研究に新しい風を」のテーマの下に講演した。今回は緊急事態宣言下での開催のため全オンライン配信での開催となった。 |
| ■ 板硝子協会 |
|
板硝子協会(森重樹会長)は、1月22日(金)午後2時より2021年板硝子協会合同委員会を開催した。今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、Web上での開催となった。来賓は、経済産業省製造産業局素材産業課課長・吉村 一元氏を含む4名。参加者は全員で84名だった。 |
■日本板硝子 マテックス ウイルスクリーン寄贈 抗ウイルスガラス(豊島区役所に) 区長が感謝状を贈呈(令和3年1月25日)
|
||||||
|
板ガラス卸販売のマテックス(東京都豊島区上池袋、松本浩志社長)と日本板硝子ビルディングプロダクツの両社は、日本板硝子が開発した抗ウイルスガラス「ウイルスクリーン」を豊島区役所(高野之夫区長)に寄贈した。 |
||||||
■ 小間久商店 本社ビルをリニューアル 「ストアフロントコンクール」で銅賞受賞(令和3年1月25日)
|
||||||
|
小間久商店(大阪府堺市、小孫雄史社長)は、このほど本社ビルのリニューアル工事を行った。その際に本社ビル前面に取り付けたファサードが、昭和フロント㈱が開催した「第51回ストアフロントコンクール」(既報令和2年12月7日付)において、第3部リニューアル部門の銅賞を受賞した。 |
| ■ AGCとセントラル硝子 |
|
AGC㈱とセントラル硝子㈱は1月14日(木)、2019年12月に基本合意していた国内建築用ガラス事業統合にかかわる協議を中止する旨を発表した。 |
■ 日本電気硝子 空間デザインコンペティション表彰式 第27回 最優秀賞に門田健嗣氏 テーマは「幸せな空間をつくるガラス」(令和2年12月28日)
|
|||
|
日本電気硝子㈱は12月2日(水)午後4時から、東京都港区のTKPガーデンシティ品川で、 第27回空間デザイン・コンペティション表彰式・懇親会を開催した。 ○最優秀賞 |
|||
■ 対談 古いガラスについて語らう 橘硝子工業 橘宏重(会長) 大硝協 大村宗一郎(理事長)(令和2年12月14日)
|
|||
|
このほど、令和2年「秋の褒章」黄綬褒章を受章した、橘硝子工業㈱の橘宏重会長(既報11月9日付2面)は、自社の敷地内で昔の型板ガラスなどを扇状やサッシ枠に固定して、展示を行っている。 ◇ 橘会長 理事長は新聞などで、お顔を知っています。大阪は組合活動が活発なので、よく記事を目にしています。 橘会長 技能士会も活発に活動されている。 大村理事長 今年はなかなか活動できていませんが、先日も鏡貼りの研修(既報11月30日付)をしていました。 橘会長 私と理事長は、何か同じような経歴をたどっている様です。年は私のほうが2つほど上ですが、理事長就任時の記事では2年1期で辞めないと、2期続けると80歳になると話をしていたのを読みました。 大村理事長 若い人に替わらないと、と言っているのに、トップが80歳はおかしい。 橘会長 私も兵硝協は退きましたが、技能士会の方では副会長を続けています。 大村理事長 なかなか放してもらえませんね。 ◇ 橘会長 私は会社の2代目で、初代は大正2年生まれで、大阪の硝子問屋「境英輔商店」で修業をしていました。中学を卒業してすぐに修行に出て、20歳の時に加古川で独立し、取引させていただきました。その後、廃業される時に、残材となっていたガラスをトラック1車いただきました。その後消化したものもありますが、当時の古いガラスがパレットごと多く残っています。最近、コロナ禍の中ロットパレットを開けてみると、合紙が入ったままで、型板の「きらら」や「ており」などが出てきました。大きさも600㎜×1200㎜や8尺×10尺などです。出しても、後片づけまでが仕事と考えると、なかなか手を付けることができずに、ここまで来てしまいました。 大村理事長 (会社の)表に展示してるものを見せてもらいましたが、戦後すぐから昭和30年、40年ごろのガラスが多くありました。 橘会長 柄物が多いのは、昔建具屋さん相手の商売に、新品種を競って仕入れては売り込みに行っていたようです。 大村理事長 私の所も一緒です。建具屋さんに行っていました。今、集めた古いガラスをリストにしていて、手元にないものを探しています。先ほど見せてもらったものの中に4㎜の「いわも」がありました。あれは今まで手に入らなかったので、落としでもあれば分けて貰いたいものです・リストは色物や網入りも作っています。ご存じのものがあったら教えてください。 ◇ 大村理事長 今年の夏に、岩手県の盛岡に行ってきました。インターネットに出ていて、お爺さんのやっていた硝子店を孫娘さんが処分することになって、ガラスが要りませんか?と呼びかけていました。コロナ対策をして、7月末から8月頭にかけて、色々と探してきました。2㎜の型板ばかりでしたが、珍しいものが多く、持っていない物がたくさん見つかりました。 橘会長 私の所は6㎜の型板ガラスが多い。「いしがき」や「からたち」、「はつしも」などです。サッシを売っていたので、雨戸が要らないということで売れていたので、残っていたようです。他にも、網入りが多く出てきました。 大村理事長 昭和39年に日本板硝子が出した「いわも」の6㎜が見つかっていません。 橘理事長 「いわも」に6㎜があったのですか?それは知りませんでした。 大村理事長 「いわも」のような柄で15㎜の「ウォールペン」というものもあったようです。一度も扱ったことが無いのですが……。他にも「亀甲」ワイヤーの網入りガラスなども無いですね。 橘会長 網入りガラスの古いものもありますが、型板のように展示していません。こう言ったものを、いかに飾るかが問題ですね。 大村理事長 まず、入手しないことには……。もうメーカーに資料も現物も残っていないし、そういったものがあったことを知っている人もいなくなりました。私は、入手したガラスをはがき大にして保管しています。大体100種類ほどです。 橘会長 私の所も100種類くらいあります。2㎜・4㎜が90種類くらい、6㎜で12種類くらい。「昔懐かしい昭和の型板ガラス」のタイトルで飾っていますから、網入りを並べていません。 ◇ 橘会長 型板ガラスの展示には、サッシの廃材などを改造して作っています。サッシ屋なので、自分の所で色々と考えて改良しています。最近は型板ガラスを差し替えて、台ごと持ち運びできるものも作りました。 大村理事長 展示方法はいろいろ考えているのですが、まだ決まっていません。展示台も木にするか、アルミにするか、決まっていません。 橘会長 では、展示用の枠なども見てもらいましょう。 大村理事長 ぜひ、お願いします。 ◇ |
|||
■ 機能ガラス普及推進協議会 全硝連 全硝連近畿地区本部 「防災安全合わせガラス」寄贈式 機能ガラスの普及推進に 今市中学校体育館で出張授業(令和2年12月7日)
|
|||
|
機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(宮代茂会長、以下「全硝連」)および全硝連近畿地区本部(大村宗一郎本部長)は、板ガラスメーカー、地元卸店とともに、11月24日(火)午前11時から、大阪市役所5階市長公室(大阪市北区)で開催された「防災安全ガラス」の寄贈式に参加した。 |
■ 光る
|
||||||
|
第54回(令和2年度)日本サインデザイン賞(主催・公益社団法人日本サインデザイン協会)の発表が先日行われ、㈱ミヨシ(本社=広島県、三好清隆社長)が製造・販売するM式LEDサイン防煙垂壁を使用した国際医療福祉大学成田病院「光る防煙垂壁の開発」(応募責任者・株式会社ジェスコ・藤澤光二氏)の作品が関東地区賞を受賞した。 |
■ AGC 平井良典氏が社長就任 島村琢哉社長は会長に 新リーダーのもとでさらなる成長を(令和2年11月9日)
|
|||
|
AGC㈱(本社=東京都)は、10月29日(木)午後5時より、東京にある新丸ビル9Fコンファレンススクエアでの会見及びZoomによる役員人事に関する社長記者会見を開催。その中で、平井良典代表取締役専務執行役員(61歳)が2021年1月1日付けで社長に昇格する人事を発表した。島村琢哉社長(63歳)は、代表取締役会長に就任する。 |
|||
| ■ セントラル硝子 第55回「国際建設設計競技」 最優秀賞はブーン・ハウ・リン、ピャエゾーン・アウンスー両氏の作品(令和2年11月9日) | |||
|
セントラル硝子㈱(本社=東京、清水正社長)主催の「第55回セントラル硝子国際建築設計競技」公開2次審査が開催された。今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年開催していた東京国際フォーラムでの公開形式のプレゼンテーション及び審査は中止し、審査委員のみで行われ、その模様は、10月24日(土)の午後1時からYouTubeでライブ配信された。 |
■ 板硝子協会
|
|||||||||
|
一般財団法人ベターリビング(井上俊之理事長)は10月9日(金)、板硝子協会(森重樹会長)提案の「防災安全合わせガラス」をベターリビングの優良住宅部品「BL-bs部品」と認定し、同日午後、本部がある東京都千代田区富士見のステージビルディング会議室で認定書授与式を開催した。 ◇ 午後1時15分に開会した「窓ガラスの日及びBL-bs認定書」授与式に関する記者会見には、ベターリビングの井上理事長、板硝子協会の森会長(日本板硝子代表執行役社長兼CEO)、AGC執行役員ビルディング・産業ガラスカンパニーアジア事業本部長の武田雅宏氏、セントラル硝子硝子販売部長の玉田保浩氏らが出席した。 |
■ 関東卸 「防災安全合わせガラス」PRを 「全員協議会・講演会」開催 ガラス市場を拡大し、活性化(令和2年10月12日)
|
||||||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)は10月2日(金)午後2時から、東京都港区芝浦のTKPガーデンシティPUREMIUM田町カンファレンスルーム4Eで全員協議会並びに講演会を開催した。約25人が参加し、コロナ禍での当面の課題などについて意見交換した。 |
||||||
■ 機能ガラス普及推進協議会 全硝連 防災安全合わせガラス寄贈工事 大阪市の今市中学校で(令和2年10月12日)
|
||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(宮代茂会長)の近畿地区本部(大村宗一郎本部長)は、10月5日(月)~8日(木)までの4日間、大阪市立立今市中学校体育館(大阪市旭区)で「防災安全ガラス寄贈工事」を行った。 |
■ 機能ガラス普及推進協議会 ぼうさいこくたい2020@HIROSHIMA(10月3日(土)午前10時~午後6時)に参加(令和2年9月23日)
|
|
今年で第5回となる「ぼうさいくこくたい2020@HIROSHIMA」が、10月3日(土)の午前10時~午後6時まで、広島と東京の2か所で同時にオンライン(https://bosai-kokutai.com/)で開催される。 |
| ■ 機能ガラス普及推進協議会 防災安全合わせガラス寄贈工事概要発表 大阪市 今市中学校体育館へ 工事期間は10月5日~8日(令和2年9月14日) |
|
機能ガラス普及推進協議会は、このほど「防災安全合わせガラス寄贈工事」の概要を発表した。 |
■ 板硝子協会 「防災安全合わせガラス」の新呼称に 中間膜の厚み60mil以上 「防災安全ガラス」は廃止(令和2年9月7日)
|
|||
|
板硝子協会(東京都港区高輪、森重樹会長)は、これまで「防災安全ガラス」と呼んでいた特定の合わせガラスの呼称を、中間膜の厚みの違いによって「防災安全合わせガラス」などと変更することになった。8月27日(木)に記者会見し発表した。 |
|
■ 「窓ガラスの日」をとにかく耳になじみのある言葉に! |
|
①ニッポン放送HPへのタイアップ記事掲載 |
■ コロナをチャンスに 新役員に聞く 全硝連新会長 宮代 茂氏 防災安全ガラス寄贈活動に注力(令和2年8月24日)
|
|||
|
6月26日開催の全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)第63回通常総会で新会長に就任して2か月余。神奈川県板硝子商工業協同組合理事長も務める宮代茂氏(横浜市、港南硝子㈱代表取締役)に抱負や今後の業界の在り方を聞いた。 |
| ■ 機能ガラス普及推進協議会 代表者会議 「トレインチャンネル施策」実施 防災安全ガラスの認知度を高める(令和2年8月3日) |
|
機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)は、7月17日(金)に東京の「ホテル ルポール麹町」会議室エメラルドにおいて、コロナ対策を施した上で、22人の会員が集まり、同協議会の代表者会議を開催。昨年度の活動報告や収支報告、今年度の活動計画案と予算案等を審議。議案はすべて原案どおり可決した。会議の中で企画運営委員長の森谷茂明氏(板硝子協会専務理事)は2020年度防災安全ガラスの認知度拡大施策として、特別に板硝子協会の予算より9月・10月に「トレインチャンネル施策」を実施すると発表した。 |
■ 全国複層硝子工業会 本山会長ら留任 難しい時代に入ったと実感(令和2年7月20日)
|
|||
|
全国複層硝子工業会は7月10日(金)午後4時から東京都中央区京橋のAGCスタジオ会議室で、2020年度第49回定時総会を開催し、本山一浩会長ら全役員の留任を決めた。事務局長の池田直輝氏は7月20日付で退任した。 |
|||
■ 機能ガラス普及推進協 「窓ガラスの日」PR 交通広告、ラジオなどで ポスターと幟を一部修正(令和2年7月13日)
|
|||
|
板ガラス関連7団体でつくる機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)は、10月10日の「窓ガラスの日」を広く一般消費者に知ってもらおうと主要駅での交通広告と民間ラジオ放送でPR活動を展開する。7月1日に事務局のある板硝子協会で記者会見し発表した。 |
|||
■ 全硝連 新会長に宮代氏 素晴らしい商材をPRしよう 新副会長に古田氏(令和2年7月6日)
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、辻良明会長)は6月26日(金)午後2時から東京都中央区日本橋浜町の都硝協会議室で令和2年度第63回通常総会を開催し、役員改選で新会長に宮代茂副会長(神奈川県板硝子商工業協同組合理事長)を選出した。 |
| ■ 全国工事 第36回通常総会 書面議決書により採決 議案はすべて可決(令和2年6月29日 |
|
全国板硝子工事協同組合連合会(橋本和明会長)は、例年6月に開催してきた同連合会の通常総会(第36回)は今回に限り中止とし、書面決議書による採決を行った。その結果、令和元年度の事業報告及び決算関係書類承認の件などの議案については賛成者多数で可決した。 |
| ■ 全国卸 松本巌会長は留任 副会長は池田・立木・村島の三氏 書面をもって議決を行う(令和2年6月15日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会は、第34回通常総会を「新型コロナウィルス感染症」感染拡大防止の観点から書面での議決とした。 |
| ■関東甲信越卸 役員全員が留任 議案は原案通り可決決定(令和2年6月15日) |
|
関東甲信越板硝子卸商業組合は、第35回通常総会を「新型コロナウィルス感染症」感染拡大防止の観点から書面での議決とした。 |
■ 都硝協 新理事長に古田氏
|
||||||
|
東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)は5月26日(火)、東京都千代田区平河町のホテルルポール麹町で第72回通常総会を開催し、役員選挙で新理事長に古田昭人副理事長を選出した。専務理事には石川明彦常務理事が就任した。 |
||||||
■ グラステック開催を延期 2021年6月15日~18日 メッセ・デュッセルドルフ社(令和2年6月8日)
|
||||||
|
ドイツ・デュッセルドルフ市のメッセ・デュッセルドルフ社は、5月27日に配信したメールで、今年10月20日(火)~23日(金)まで、同市の国際展示場で開催される「glasstec 2020(グラステック2020 国際ガラス製造・加工機器展)」の開催を延期すると発表した。 |
| ■開業予定の新駅を紹介 日本は世界一の鉄道大国 街の顔として駅舎が注目(令和2年5月25日・6月1日) |
|
日本は世界一の鉄道大国といわれている。経済規模や地理的特性から、鉄道依存度が高く、特に都市部においては鉄道依存度が約30%(首都圏は約58%、京阪神は55%)と言われている。これは、諸外国と比較しても高く(2位のスイスは約15%)、大きな鉄道需要をもたらしている。 |
| ■ 横浜市 全窓リフォームに最大80万円 補助金の公募を開始 住まいのエコリノベ(先着順)(令和2年5月18日) |
|
横浜市(人口約375万人)は5月11日(月)、2020年度「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助事業」(通称、エコリノベ)の一般公募を開始した。補助件数は60戸程度。先着順で予算額に達した時点で申請受付を終了する。 |
■ 経済産業省 防災ガラス窓改修が補助金対象 「次世代建材支援事業」に 1次公募は5月11日~7月17日(令和2年5月4日)
|
|||
|
経済産業省 資源エネルギー庁が公募し、(一社)環境共創イニシアチブ(以下SII)が執行する「令和2年度 次世代建材支援事業」の補助対象製品に、防災ガラス窓(防災安全ガラス)が採用されたことが判明した。必須改修工事である断熱パネルもしくは潜熱蓄熱建材の導入に防災ガラス窓改修工事をプラスすることで補助金の対象となる。 |
| ■ AGC 「人財で勝つ」会社を 新入社員にビデオメッセージ(令和2年4月13日) |
|
AGC㈱の島村琢哉社長は4月1日(月)、2020年新入社員の入社(新入社員109名、うち女性26人)にあたり、社長挨拶を行った。 |
| ■ 国土交通省 2月度「次世代住宅ポイント制度」実施状況 予算消化状況は24.6%(令和2年4月6日) |
|
国土交通省 住宅局住宅生産課は、令和2年2月末時点の『次世代住宅ポイント制度』実施状況を発表した。 |
| 〈 令和2年2月計 〉 | 累計 | ||||||||||||||
| 集計期間(2月1日~29日) | |||||||||||||||
| 戸数 | 件数 | ポイント数 (単位:千ポイント) |
戸数 | 件数 | ポイント数 (単位:千ポイント) |
||||||||||
| 次世代住宅 ポイントの発行 |
54,627 | 100.00% | 7,425,484 | 100.00% | 163,637 | 100.00% | 29,760,981 | 100.00% | |||||||
| 新築 | 16,301 | 29.84% | 5,532,831 | 74.51% | 73,825 | 45.12% | 25,403,384 | 88.96% | |||||||
| リフォーム | 38,326 | 70.16% | 35,406 | 100.00% | 1,892,653 | 25.49% | 89,812 | 54.88% | 79,759 | 100.00% | 4,357,597 | 14.64% | |||
| 開口部の 断熱改修 |
4,468 | 20.14% | 301,089 | 5.28% | 9,582 | 21.60% | 809,258 | 3.26% | |||||||
| ガラス交換 | 652 | 1.84% | 17,450 | 0.24% | 1,432 | 1.80% | 40,316 | 0.14% | |||||||
| 内窓 設置 |
3,846 | 10.86% | 231,441 | 3.12% | 9,296 | 11.66% | 563,418 | 1.89% | |||||||
| 外窓 交換 |
2,580 | 7.29% | 164,119 | 2.21% | 5,826 | 7.30% | 416,526 | 1.40% | |||||||
| ドア 交換 |
1,550 | 4.38% | 109,048 | 1.47% | 3,580 | 4.49% | 311,056 | 1.05% | |||||||
| ○予算消化状況 | |||
| ~2020年2月29日 (単位:ポイント) |
予算枠 (単位:円) |
利用率 | |
| 新築 | 25,403,384,000 | 103,200,000,000 | 24.62% |
| リフォーム | 4,357,597,000 | 26,800,000,000 | 16.26% |
| 合計 | 29,760,981,000 | 130,000,000,000 | 22.89% |
| ■ 元年度後期 ガラス施工技能検定合格者 合格者1級82人、2級70人 合格者は低調で厳しい結果(令和2年3月30日) |
|
令和元年度(平成31年度)後期ガラス施工技能検定結果が、3月13日(金)に全国の職業能力開発協会から、発表された。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 令和元年度(平成31年度)後期 |
|
令和元年度(平成31年度)後期ガラス施工技能検定結果が、3月13日(金)に全国の職業能力開発協会から発表された。 |
■ 東京都 窓、玄関ドア断熱改修に補助金
|
|
東京都(小池百合子知事)は2020年度(令和2年度)から新規に「家庭における熱の有効利用促進事業」を展開する。3カ年計画で、当局は新年度予算案に初年度分として12億4200万円を計上した。主として既存住宅の窓、玄関ドアの断熱改修工事に補助金を交付する。 |
| ■ 東京武蔵野市 窓の断熱改修が急増 |
|
東京都武蔵野市(人口約14万人)が実施している「効率的なエネルギー活用推進助成事業」が好調に推移。2019年度(令和元年度)は年度途中に予算を大幅に増やしたが、3月の年度末にはほぼ満額に達する情勢だ。市当局は2020年度も事業を継続する方針。 |
| ■ マテックス 鳩山センター「樹脂窓生産ライン」新設 2年後に60棟分生産へ 樹脂窓の地産地消が可能(令和2年3月2日) |
|
新ガラス建材商社・マテックス㈱(本社=東京都、松本浩志社長)は、このほど、マスコミ向けに鳩山センター(所在地=埼玉県比企郡鳩山町、門倉幸英センター長)の見学会を開催し、昨年12月より生産を開始した樹脂窓生産ラインを説明した。当日は松本巌会長と松本社長も出席、説明者は門倉センター長と彦坂嘉宏管理部課長が担当した。 |
■東北板硝子3団体 合同賀詞交歓会 働き方改革を推進
|
|
全硝連東北地区本部(袴田恭司本部長)、東北板硝子卸商業組合(大久保章宏理事長)、東北板硝子工事協同組合(原田尚樹理事長)の3団体は2月12日(水)午後5時半から、仙台市青葉区本町のパレスへいあん5階ボヌールホールを会場に、立食形式で令和2年合同賀詞交歓会を開催した。 |
| ■ AGC 売上高1兆5180億円 国内建築用ガラスの出荷は堅調 営業利益は1016億円(令和2年2月17日) |
|
AGC㈱(島村琢哉社長)が2月5日発表した2019年12月期通期(1月1日~12月31日)連結決算は、売上高が前期比0.3%減の1兆5180億円、営業利益は15.7%減の1016億円と減収減益となった。新規連結の効果があったものの、ユーロ安などの為替影響で減収。ディスプレイ用ガラスおよび東南アジアにおけるクロールアルカリ製品の販売下落に加え、一時的な製造原価悪化要因により減益となった。 |
■ 関東卸 都硝協 「合同新年会」開催 どうあるべきかを問われる年 補助金制度を駆使して需要喚起(令和2年1月27日)
|
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)は、1月21日(火)午後5時より、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町2階「ロイヤルクリスタル」において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。令和になって初となる合同新年会には、来賓も併せ約110名が参会した。 |
■ 関西工事 全硝連・関西卸 関西板硝子 業界3組合 新年互礼会 業界の大きな変革の年 キーワードは、防災、省エネ、人手不足(令和2年1月20日)
|
|
令和初となる関西板硝子業界新年互礼会(関西板硝子工事協同組合、全硝連近畿地区本部、関西板硝子卸商業組合の3組合主催)が1月9日(木)午前11時より大阪市北区にある新阪急ホテル2階「花の間」において、業界関係者ら123名が集まる中、盛大に開催され、関西板硝子業界の2020年は華々しくスタートした。今回も全硝連近畿地区本部と関西板硝子工事協同組合の紹介で経産省や国交省からも参加があった。 |
■ 緊急インタビュー AGC セントラル硝子 事業統合 国内建築用ガラス事業 収益性向上、企業基盤の充実を図る(令和元年12月30日)
|
| ■ AGC 素材開発にAR技術使用 開発のスピードアップに貢献 導入前に開発設備が(令和元年12月9日) |
|
AGC㈱(本社=東京都、島村琢哉社長)は、11月27日(水)午前11 時より、東京都中央区にある「AGC Studio」で、開発現場へのAR(AugmentedReality 拡張現実感の意)技術導入に関する記者発表会を開催した。出席者は、同社技術本部材料融合研究所管理チーム設備ユニットマネージャー・山内健氏と「Web AR」の事業を提供するKAKUCHO㈱(本社=東京都、竹本泰輔社長)COO井倉北斗氏のおふたり。当日の発表内容は次の通り。 |
| ■ 山形県 全窓を断熱改修 県サッシ・ガラス協組の運動で 来年度の予算への反映を約束(令和元年12月2日) |
|
山形県(吉村美栄子知事)は本庁舎の全窓をLow―E複層ガラスに順次交換する事業に着手する。初年度の2020年度は知事室など3室で実施する方針。県サッシ・ガラス協同組合(西塚和彦理事長)の地道な陳情活動が実を結んだ。 |
■ 関西卸 関西工事 大硝協 第14回「合同安全大会」開催 日本は災害列島に 小路氏と山田氏が体験談発表(令和元年11月25日)
|
|
関西板硝子卸商業組合(斉藤洋介理事長)と関西板硝子工事協同組合(清水英彦理事長)、大阪府板硝子商工業協同組合(辻良明理事長)の3組合は11月13日(水)午後2時から大阪市中央会館(大阪市中央区)で、「第14回合同安全大会」を開催した。 |
■ 全硝連 「窓ガラスの日」イベント検討 「全国理事長会議」開催 フルハーネス特価で販売(令和元年11月18日)
|
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)は11月8日(金)、長野市のホテルメトロポリタン長野で第35回全国理事長会議を開催し、10月10日の「窓ガラスの日」関連イベントやフルハーネス販売など今後の活動について協議した。 |
| ■ セントラル硝子 第54回国際建設設計競技 最優秀賞はノエル・ピカペール、マリオン・ジャモーの両氏 課題「新しい盛り場を生み出す建築」(令和元年11月11日) |
|
第54回「セントラル硝子国際建築設計競技」(主催・セントラル硝子㈱)の公開審査会が、10月26日(土)午後1時半より、東京国際フォーラムD7ホールで開催された。厳正な審査の結果、栄えある最優秀賞にはノエル・ピカペール(フリーランス)、マリオン・ジャモー(フランス・フリーランス)の両氏の作品に決定し、賞金200万円と記念品及び賞状が、さらに優秀賞には30万円と記念品、入選には10万円と記念品がそれぞれ贈られた。 |
■ 機能ガラス普及推進協議会 全硝連 全硝連近畿地区本部 「防災安全ガラス」寄贈式 白浜市立日置中学校体育館へ 災害拠点での採用義務化を(令和元年10月28日、11月4日)
|
|
機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長、以下「全硝連」)および全硝連近畿地区本部(小村哲也本部長)は、板ガラスメーカー、地元卸店とともに、10月10日(木)午後2時30分から、南紀白浜リヴァージュ・スパひきがわ会議室(和歌山県西牟婁郡白浜町)で開催された「防災安全ガラス」の寄贈式に参加した。 |
■ 機能ガラス普及推進協議会 「窓ガラスの日」登録証授与式 記念日協会代表が出席 全国でキャンペーンを展開(令和元年10月14日)
|
|
板ガラス関連7団体で構成する機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)は10月1日(火)、事務局を置く東京都港区高輪の板硝子協会で、(一社)日本記念日協会代表理事・加瀬清志氏を招き10月10日の「窓ガラスの日」制定に関する記者会見並びに登録証授与式を開催した。 |
| ■ 東京下町の自治体 高断熱窓への改修伸展 最大10~40万円補助 健康・防災意識が高まる(令和元年10月7日) |
| 東京の下町を貫く荒川や隅田川沿いの江東、墨田、台東各区では、省エネ化や台風など自然災害に備え、太陽光発電、蓄電池、エネファーム、高断熱窓などの導入を助成する制度が定着。中でも健康・防災意識の高まりを背景に窓改修の申請が伸びている。 江東区の個人住宅用「地球温暖化防止設備導入助成事業」は、太陽光発電、CO2冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、燃料電池装置(エネファーム)、エネルギー管理システム機器(HEMS)、高反射率塗装、蓄電池、高断熱窓―の7種類が助成の対象だ。 助成額は設備ごとに異なるが、上限額でみると、最高は太陽光発電と高反射率塗装の各20万円。エネファーム、蓄電池と高断熱窓は各10万円。同区温暖化対策課によると、2019年度の当初予算は総額4100万円。9月10日時点の残額は約2500万円という。 高断熱窓(既築のみ)の交付要件は①内窓設置・外窓交換・ガラス交換のいずれか②改修後の熱貫流率が4・65W⁄㎡・K以下③原則1居室以上の全ての窓を改修する―の3点。補助金の申請件数は同時点で21件(計約120万円)に上っている。 同課環境調整係の担当者は「2018年度の交付実績が28件・240万円だったので、本年度は最終的にそれを上回る見込み。ここにきて蓄電池と窓が伸びている」と指摘する。 墨田区は、江東区とほぼ同じ名称の「地球温暖化防止設備導入助成制度」を実施。対象設備の一つである「建築物断熱改修」(既築のみ)の窓ガラスの助成上限額は、戸建て・事業所40万円、分譲集合住宅100万円。 交付要件は①熱貫流率が2・7W⁄㎡・K以下となるもの(複層ガラスの内窓設置・ガラス交換)②一つの部屋の全ての窓を改修すること―の2点。同区環境保全課によると、窓改修の申請は「右肩上がり」(担当者)で、2017年度の11件(交付実績)に対し18年度は22件(同)と倍増。本年度は9月20日現在、申請ベースで14件に上っている。 太陽光発電、エネファーム、LED照明、蓄電池などを含めた予算規模1800万円の半分は上半期で消化したという。 台東区は、エネファーム、雨水タンク、太陽光発電、共同住宅共用部用LED照明改修、高反射率塗装、窓・外壁等の遮熱・断熱改修、屋上・壁面などへのプランター設置―の7種に補助金を交付する事業を展開。 「窓・外壁等」のうち窓の交付要件は①複層ガラスか二重窓に改修すること②一つの部屋の全ての窓の断熱改修③熱貫流率4・65W⁄㎡・K以下に―の3点。補助金は工事費用の20%で上限15万円だ。 同区環境課によると、窓改修の申請は9月24日時点で14件、予算残額は90万円。前年度の交付実績は29件(総額283万円)だった。担当者は「昨年度は予算枠をオーバーした。窓改修は少しずつ増えてきています」と話している。 |
■ 横浜市とマテックス マンション窓断熱改修講座開催 住民の合意形成に努力 管理組合幹部ら経験談(令和元年9月30日)
|
|
横浜市と板ガラス卸のマテックス㈱(東京都豊島区、松本浩志社長)が連携して運営する「よこはま省エネルギー住宅アカデミー特別講座⁄マンション窓断熱改修講座」が9月14日(土)、横浜市の横浜ランドマークタワー・ドックヤードガーデンBUKATSUDOホールで開かれた。 |
■ 全硝連 近畿ブロック 機能ガラス普及推進協議会の寄贈工事 和歌山白浜日置中学校体育館 防災安全ガラス262枚を(令和元年9月9日)
|
| 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)の近畿地区本部(小村哲也本部長)は、8月26日(月)~29日(木)までの4日間、和歌山県白浜町立日置中学校体育館で「防災安全ガラス寄贈工事」を行った。 今回の工事に使用した防災安全ガラスは、機能ガラス普及推進協議会が寄贈したもので、防災安全ガラス262枚(約140平方㍍)。ガラスは日本板硝子㈱が、中間膜をイーストマンケミカルジャパン㈱がそれぞれ提供し、現場配送は㈱コムラ(和歌山市西浜、小村哲也社長)が担当した。施工は全硝連近畿ブロックが中心となって行い、関西板硝子卸商業組合、関西板硝子工事協同組合も協力している。 体育館2階ギャラリー部分の連段窓引違いや、1階段窓突出の窓ガラスの交換が行われ、ガラスの大きさは2階部分がW825~870㍉×H870㍉、1階はW435~461㍉×H495~545㍉のものが主体となっている。 1階の窓は、過去に一度窓交換が行われたのか、カバー工法によるサッシが入っていた。一方、2階の連段窓引違いは、アルミサッシに網入りガラスがパテ止めされていた。このため、工事前には、2階部分のガラス交換作業がスムーズに行えるのかが不安視されていた。 初日の26日は、和歌山県ガラス・サッシ協の8人がガラスの間配りや、工事に向けた養生を行った後、不安視されていた2階の窓の一部について、実際にガラス交換を行った。交換作業を行ってみると、パテの掛かり代が少なく、想像よりも外れやすいことが判明した。サッシのビスを外し、ガラスを取り外してから、サッシに残ったパテのはつりを行うため、多少時間はかかるものの、ガラス交換はスムーズに行われたとのことだった。 翌27日には、近畿ブロック各単組からの応援部隊15名が到着。計23人が午前9時前から工事をスタートし、手際よく交換作業が行われた。 サッシが固く、取り外しにバールを用いることもあったが、2階のギャラリーに幅があったため、足場台を設置してサッシの取り外し作業が行えたことや、当初は1階に下ろして行われる予定だったはつり作業も、ギャラリー内で出来たことなどが、作業時間の短縮につながっていた様子。 また、スカイマスターが2台用意されており、外側からのガラス交換も行われたほか、強化ガラスが入っていた体育館のエントランスドアについては、ガラス交換を行わず、フィルムを貼ることで対応していた。 ㈱コムラの玉置圭常務は、「パテ止めのガラス交換が思っていたよりもスムーズに進んでいるので、期間内に作業を終えることが出来そうです」とした上で、「今回は色々な方にご協力いただきました。近畿ブロックからの応援はもちろん、地元の方の協力も大きい。応援の皆さんが宿泊している民宿が、昼間の食堂の営業を休んで、クーラーの効いたところで食事をとれるように配慮してもらえました。漁協にも話をして頂いただき、飲み物を冷やす氷も提供してくださいました。役場も、駐車場の使用を許可してくれるなど、非常に助かっています」と話していた。 現地入りしていた大硝協の大村宗一郎副理事長は「思っていたよりも速いペースで作業が進んでいる。予定では30日(金)まで工期を取っているが、明日(28日)で作業の目処を付けて、明後日(29日)は片付けにあて、作業を終わらせたい」と話していた。 また、28日には全硝連の辻会長が現場を訪れ、工事の様子などを視察している。 寄贈工事は28日の午前中で目処が付いたため、各地からの応援部隊は午後に撤収し、午後4時頃に工事は終了したとのことだった。 なお、今年から「窓ガラスの日」となった10月10日(木)に、白浜町内(会場未定)で寄贈式が行われ、その後同中学校で防災安全ガラスの出張授業が開催される予定。 |
■ 仙台市 窓の断熱改修が伸展 「Lets熱活!補助金」4か月で予算の約半分を消化(令和元年9月2日)
|
|
宮城県仙台市(人口1 |
| ■板ガラス3メーカー 決算発表(令和元年8月26日) |
|
板ガラスメーカー3社は、それぞれ決算を発表した。各社のガラス事業の概況は次の通り。 〇日本板硝子㈱(2020年3月期第1四半期決算) |
| ガラスメーカー3社 業績 | ||||||||
| AGC㈱ 2019年12月期第2四半期連結業績 | (2019年1月1日~6月30日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 税引前四半期純利益 | 四半期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 2019年12月期第2四半期 | 737,489 | △ 1.1 | 41,487 | △ 31.2 | 42,556 | △ 34.5 | 36,332 | △ 31.6 |
| 2018年12月期第2四半期 | 745,499 | 8.0 | 60,305 | 22.4 | 64,933 | 32.9 | 53,115 | 25.6 |
| (%表示は、対前年同四半期増減率) | ||||||||
| AGC㈱ 2019年12月期連結業績予想 | (2019年1月1日~12月31日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 通期 | 1,540,000 | 1.1 | 105,000 | △ 12.9 | 98,000 | △ 23.7 | 74,000 | △ 27.4 |
| (%表示は、通期は対前期増減率) | ||||||||
| 日本板硝子㈱ 2020年3月期第1四半期連結業績 | (2019年4月1日~6月30日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 四半期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 2020年3月期第1四半期 | 147,066 | △ 7.2 | 8,817 | △ 9.0 | 3,055 | △ 49.2 | 2,891 | △ 46.6 |
| 2019年3月期第1四半期 | 158,414 | 9.1 | 9,690 | 12.6 | 6,017 | 125.2 | 5,416 | 131.2 |
| (%表示は、対前年同四半期増減率) | ||||||||
| 日本板硝子㈱ 2020年3月期連結業績予想 | (2019年4月1日~2020年3月31日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 第2四半期(累計) | 310,000 | 0.6 | 17,000 | △ 4.8 | ― | ― | ― | ― |
| 通期 | 620,000 | 1.2 | 35,000 | △ 5.0 | 19,000 | △ 16.4 | 12,000 | △ 16.5 |
| (%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) | ||||||||
| セントラル硝子㈱ 2020年3月期第1四半期連結業績 | (2019年4月1日~6月30日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 2020年3月期第1四半期 | 54,152 | △ 2.6 | 1,737 | △ 3.2 | 2,065 | △ 19.6 | 1,326 | △ 24.5 |
| 2019年3月期第1四半期 | 55,576 | ― | 1,794 | ― | 2,564 | ― | 1,756 | ― |
| (%表示は、対前年同四半期増減率) | ||||||||
| セントラル硝子㈱ 2020年3月期連結業績予想 | (2019年4月1日~2020年3月31日) | |||||||
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |||||
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
| 第2四半期(累計) | 112,000 | △ 0.3 | 3,500 | △ 26.1 | 3,700 | △ 33.1 | 2,800 | △ 35.1 |
| 通期 | 234,000 | 1.8 | 11,500 | 13.5 | 11,800 | 5.6 | 8,500 | 12.2 |
| (%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) |
||||||||
| ■機能ガラス普及推進協議会 「窓ガラスの日」10月10日決定 機能ガラスの市場を拡大 「防災・安全」「省エネ」「健康」を柱に(令和元年8月5日) |
|
機能ガラス普及推進協議会(森重樹会長)は、7月29日(月)に東京の「ホテル ルポール麹町」会議室ガーネットにおいて、28人の会員が集まり、同協議会の代表者会議を開催。昨年度の活動報告や収支報告、今年度の活動計画案と予算案等を審議。議案はすべて原案どおり可決。「窓ガラスの日」も正式に10月10日に決定した。 (1)災害時の安全・安心に向けて、公共避難所への「防災安全ガラス(合わせガラス)」の採用を働きかける(2)省エネ規準義務化のスケジュールを踏まえ「エコガラス・エコガラスS(LowーE複層ガラス)」の認知向上・普及促進に注力する(3)10月10日「窓ガラスの日」制定を踏まえ、一般ユーザーに安全・安心・健康的な生活を提供する高機能ガラスのPR活動の充実を図る(4)機能ガラスのさらなる認知度をあげるために「防音」「防犯」に優れたガラスの普及促進に注力する(5)加盟団体が連携し、地域での活動を強化する(6)活動促進のための支援体制、ツールの充実を図る(7)情報の共有化、および連携を強化する。 会議の最後には、経済産業省製造産業局素材産業課長・吉村一元氏が「窓ガラスの日に機能ガラスを考えてみませんかということで、ぜひビジネスにつなげて欲しい」とあいさつした。 会議終了後、懇親会も開催され、全硝連の辻会長が乾杯のあいさつ。さらに締めのあいさつは全国複層硝子工業会の本山一浩会長が担当した。 「窓ガラスの日」制定記念施策について ・ガラス業界の経済的発展と高機能ガラスの普及促進活動等のPR活動の充実を図るため「窓ガラスの日」を制定。 |
■ 松本市 好調省エネリフォーム補助事業 交付実績額は1億円に 開口部の改修が倍増(令和元年7月22日)
|
|
長野県松本市(人口約24万人)が実施中の省エネリフォーム補助事業への関心が高まっている。平成30年度の交付実績は当初予算を大きく上回る約1億円に上った。中でも窓中心の開口部は件数、金額ともに前年度の2倍以上となっている。 |
■ 愛硝協 安全衛生協力会 滑落制止器具を学ぶ 2022年から完全施工に 安全衛生・事故防止に不可欠(令和元年7月8日)
|
|
愛知県板硝子商工業協同組合(愛硝協、太田吉則理事長)の愛硝協安全衛生協力会は6月25日、名古屋市千種区の名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)で「フルハーネス型墜落制止器具特別教育」を開いた。同会館第2会議室に満席の37人が受講した。 |
■ AGC キッザニア甲子園 パビリオンの火入れ式 鏡の製造体験を行う(令和元年7月8日)
|
|
AGC㈱と“こどもが主役の街”「キッザニア甲子園」(兵庫県西宮市)の企画・運営を行うKCJ GROUP㈱(東京都千代田区、住谷栄之資社長)は、7月1日午前11時から、「キッザニア甲子園」内のAGCパビリオン前で、オープニングセレモニーとパビリオン内ガラス製造ラインの火入れ式を行った。 |
| ■ 日本板硝子 建築用板ガラス値上げ 10月1日より(令和元年7月8日) |
|
日本板硝子㈱は、2019年10月1日出荷分から建築用板ガラス製品の価格改定を実施すると発表した。板ガラス製品、鏡製品の価格を10~15%、建築用機能ガラス製品の価格を5~10%引き上げる。 |
■ 関西G6 「ビル防火講習会」開催 施工に関する勉強会 個別認定の対応などを説明(令和元年7月1日)
|
|
関西板硝子業界G6(中島富幸代表幹事・大阪鏡)は6月18日(火)午後1時30分から、大阪市中央会館第1・第2会議室(大阪市中央区)で、ビル防火講習会を開催した。当日は、定員70名の所に加盟6団体などから90名が参加、関心の高さが伺えた。 |
■ 板硝子協会 「エコガラスS」の普及促進へ
|
|
板硝子協会は、昨年のJIS(日本工業規格)の改正に合わせて、高性能Low―E複層ガラス「エコガラスS」を商標として制定し普及促進を図ることになった。6月5日(水)に記者会見し発表した。 |
■第21回 板ガラスフォーラム 機能ガラスの認知度UP 保険会社と提携して安全ガラスPR(令和元年6月17日)
|
|
板ガラス業界8団体(全国板硝子商工業協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合連合会、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催の「第21回板ガラスフォーラム」が、6月7日(金)、品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホール(東京都品川区)で、盛大に開催された。毎年恒例となった板ガラスフォーラムも今回で21年目を迎え、今年も全国から業界関係者など約400人が参加し、盛況を見せた。 |
| ■ 板硝子協会 新会長に森重樹氏(令和元年6月17日) |
|
板硝子協会は、6月7日(金)に開催した総会で、会長の交代を決定した。 |
■ 北京市 ChinaGlass2019 28ヵ国から関連企業904社 坂東硝子が出展(30年連続)(令和元年6月10日)
|
|
5月22日(水)~25日(土)の4日間、中国・北京市の中国国際展覧中心(新館)において、「第30回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2019)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 |
■ 宮田硝子 社長 宮田武司氏が表彰 労働・技能功労部門で(令和元年6月10日)
|
|
宮田硝子㈱社長で、兵庫県板硝子商工業協同組合と兵庫県板硝子技能士会の会計理事を務める宮田武司氏は5月3日、兵庫県から兵庫県功労者として表彰された。 |
| ■ AGC、セコム、DeNA、NTTドコモ 世界初バーチャル警備システム 人手不足のニーズに対応 等身大キャラクターが警備 (令和元年5月13日) |
|
AGC㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)とセコム㈱(本社=東京都渋谷区、中山泰男社長)㈱ディー・エヌ・エー(以下「DeNA」本社=東京都、守安功社長)、㈱NTTドコモ(本社=東京都千代田区、吉沢和弘社長)は、4月25日(木)午後1時より、東京都渋谷区にあるセコム本社2階にある「セコムホール」で共同記者発表会を開催し、AIを活用した警戒監視などの警備や受付業務が提供可能な「バーチャル警備システム」の試作機を開発したと発表。今後、2020年の発売に向けて実用化を進めていくとしている。当日はセコムの中山社長が開発の背景等を説明し、続いて同社上田理執行役員企画担当が概要を説明。質疑応答ではAGC・執行役員ビルディング・産業カンパニーアジア事業本部長・武田雅宏氏のほかDeNA、NTTドコモの執行役員らが出席した。当日の発表内容は次の通り。 |
| ■ 関東板硝子工事協同組合 ビル用防火戸個別認定で勉強会 サッシ3社が製品説明(令和元年5月6日) |
|
関東板硝子工事協同組合(遠藤浩吉理事長)は4月19日(金)、東京・日本橋浜町の浜町TSKビル2階大会議室で「ビル用防火戸・サッシ個別認定に関する勉強会」を開催した。約100人が出席し、板硝子協会や業界の対応とサッシメーカーの製品説明を聞いた。 |
| ■国交省防火設備の仕様を改正 断熱性に配慮した窓の位置づけ 木製・樹脂製サッシ一般的仕様を明確化 (平成31年4月22日) |
|
国土交通省は、住宅等の断熱性能の向上を図る上で木製又は樹脂製枠の窓を使用するニーズが高まっていること等を踏まえ、防火設備として必要な性能を有することが確認された仕様について、一般的な基準として定める告示を改正し、2019年3月29日に、公布・施行したと発表した。 |
| ■ 日本電気硝子電気硝子建材 「ファイアライト」販売強化 耐熱結晶化ガラスが防火窓に(平成31年4月22日) |
|
別項の記事のとおり、国交省は「防火設備の構造方法を定める件」を改正し、耐熱結晶化ガラスが透明な防火ガラスとして、告示に定める一般的な仕様として位置づけされたことから、日本電気硝子㈱(本社=滋賀県大津市、松本元春社長)は特定防火設備・防火設備用ガラス「ファイアライト」の販売を強化する。 |
■ 山形 ベトナム人技能実習生導入へ 山形のガラス業者など6社で事業組合設立 年内30人目標(平成31年4月15日)
|
|
慢性的な人手不足を外国人の「技能実習制度」や新たな在留資格「特定技能」で補おうとする機運が産業界で高まっている折、山形県ではガラス工事など建設関連企業が集まってベトナム人の技能実習生を導入する試みが実践段階に入っている。 |
| ■ 東京 第21回「板ガラスフォーラム」 開催は6月7日(金) (平成31年4月15日) |
|
板ガラス業界8団体共催の「第21回板ガラスフォーラム」の開催概要が、このほど板ガラスフォーラム事務局から発表された。 |
| ■ 全硝工連 働き方で方針提示へ (平成31年4月8日)
|
| ■ AGC 「人材で勝つ」会社を 新入社員入社式を行う (平成31年4月8日) |
|
AGC 旭硝子㈱は、4月1日(月)午前9時45分から、如水会館 スターホール(東京都千代田区)で新入社員132名(うち女23人性)が参加して、「2019年度新入社員入社式」を行った。 |
| ■ 平成30年度後期ガラス施工技能検定合格者(平成31年3月25日・4月1日) 合格者1級101人、2級83人 受験者数が昨年より56人減少 |
|
平成30年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月15日(金)に全国の職業能力開発協会から、発表された。 1級の受検者が2ケタの所は4都県で、前年の7都道県を下回った。受検者数が最も多かったのは東京の24人(前年31人)で、3年連続の受検者数1位となっている。 しかし、2級受検者数は愛知県の30人(同25人)が最も多く、総受検者数でも愛知県が全国で最も多い40人となっており、2位の東京(30人)を大きく引き離している。 ◇ ◇ ◇ ◇ |
※1:千葉県は実施公示をしていないとの回答 ※2:山梨県は試験を実施していないとの回答 ※3:静岡県は非公示との回答 ※4:滋賀県は実施公示を行ったが申請がなかったとの回答 ※5:長崎県は公示していないとの回答 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 厚生労働省・中央職業開発協会・全国技能士連合会 第30回技能グランプリ開催 髙田悠介氏(兵庫)が厚労大臣賞金賞1級技能士10名が参加 (平成31年3月11日)
|
厚生労働省と中央職業能力開発協会、(一社)全国技能士連合会が主催する、第30回技能グランプリが3月1日(金)~4日(月)の4日間、神戸国際展示場(神戸市中央区)ほか4会場で開催された。 |
| ■ AGCグラスプロダクツ 付加加工代を設定 個別認定品の複層ガラス製品(平成31年3月11日) |
AGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都、深川祐一社長)は、ビル防火戸個別認定品適合仕様(複層ガラス)に付加加工代を設定すると発表した。 カーテンウォール・防火開口部協会のビル防火戸の通則的運用停止に伴い、サッシメーカー各社では個別に主翼下大臣認定に基づく製品への置き換えの準備を進めている。 大臣認定の防火設備(個別認定品)の仕様は順次公表されており、ガラスについても各商品に適合する仕様が規定されている。 これを受けて、同社では受発注システムの改変を行い、個別認定の内容に沿ったガラスを提供できるよう準備を進めているが、システム準備や整備などが伴うことから、付加加工代を、新たに設定することに決めたもの。「ビル防火戸 大臣認定防火設備(個別認定品)向け複層ガラス製品」全般が付加加工代の加算対象となっており、同社受発注システム発注画面の「個別仕様入力」欄で、ビル防火戸個別認定品の仕様を選択すると、付加加工代が加算されるとしている。 |
| ■ 日本板硝子 創業100周年記念事業 「スペーシア」を寄贈 龍ヶ崎市(茨城県)の施設と図書館へ (平成31年3月4日)
|
■ AGC 「ミラノデザインウィーク」出展 インスタレーションを発表(平成31年3月4日)
|
AGC㈱は、4月9日~14日まで、イタリア・ミラノで開催される「ミラノデザインウィーク2019」において、インスタレーション「Emergence of Form」を発表する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ マテックス 「マンション改修事業」に本気で取り組むマテックス
|
ガラス・サッシ販売店をはじめとした、地域の住まいづくりに関わる全ての事業者をサポートし、パートナーシップを形成し、パートナーとの協働により生活者に「窓」の魅力を伝え、業界に活力を与える活動を展開する新ガラス建材商社・マテックス㈱(本社=東京都、松本浩志社長)。全国板硝子卸商業組合連合会の会長で同社の会長でもある松本巖氏は「現状、ガラス業界全体が、本気になってリフォーム事業を積極的に進めているところが少ない。特にマンションの大規模改修と言えばサッシメーカーの世界と言わんばかりの勢いで、これを何とか打ち破っていかないといけない。立ち位置に応じた仕事をしていく。そのためには意識改革が必要だ」と幾度も述べており、同社としても「マンション改修事業」に積極的に取り組んでいる。そこで、今回は、地域事業者サポート事業の一環として「マンション改修事業」をすすめている、同社ビル統括部の有富史法部長と藤代慶美さんのお二人にご登場をお願いし、同事業の活動内容や現在の進捗状況についてお話を伺った。 ――「マンション改修事業」の現状についてお聞かせ下さい。 現在、マテックスでは、横浜市と連携し、「マンション窓断熱改修講座」を行っており、今年も3月2日(土)午前10時半より横浜市西区みなとみらいにあるBUKATSUDOホールで開催します。今年で4年目になります。 ――今回、横浜市のマンション大規模改修工事を受注したと聞きました。 そういう活動がベースにあります。ご存じのとおり、当社は卸の精神を貫くと言う事で、直販は基本的にはしないということで、窓を通じて地域事業者を育成しながら、CSR活動をやっていくという基本方針があります。その延長線上にマンション改修事業があります。この事業をはじめてもう8年が経過しました。 ――講座に参加される方は。 マンションの管理組合の住民の他、設計事務所等マンション改修ビジネスに携わっておられる方も参加されます。 ――今回、横浜市のマンション大規模改修のスタートは。 横浜市内にある築後約40年を経過した、5棟約600戸の物件です。環境省の補助金を活用したマンションですので、窓はすべて改修しました。工事はカバー工法で、複層ガラス用サッシと高性能複層ガラスで工事をしました。 ――受注に繋がった要因は? 最終的に相見積になりましたが、受注できたのは総合的な評価をいただけたのだと思います。マテックスという会社は、流通では、知られていますが、マンション改修業界ではまだまだです。販売店様やマンション管理組合様との良好な関係もあり、当社を推薦していただきました。 ――最後に。工事を終えて 今回工事を行って自信になったことは、販売店様も工事が進捗するに連れて、当社も住民からの評価がだんだん高くなってきたことです。マンションの住民の方々も非常に協力的でした。 ――ありがとうございました。更なるご活躍を期待しています。 |
■ AGC 売上高1兆5229億円
|
AGC㈱(島村琢哉社長)が2月6日発表した2018年12月期通期(1月1日~12月31日)連結決算は、売上高が前期比4.1%増の1兆5229億円、営業利益は0.8%増の1206億円と増収増益となった。営業利益は4期連続の増益。各事業の出荷数量増などにより増収となったが、原燃材料価格上昇などにより増益幅は縮小だった。 親会社の所有者に属する当期純利益は前期比29.4%増の896億円となった。 セグメント別にみると、ガラスの売上高は7575億円(前期比223億円の増収)。建築用ガラスの出荷は欧州で増加、ユーロ高の影響で円ベースの売上高が増加した。自動車用ガラスは日本・アジアや欧州で出荷増、同じくユーロ高の影響で円ベースの売上高が増加した。営業利益については前期比45億円減の225億円となった。 電子の売上高は2526億円(前期比97億円減)、営業利益は240億円(同33億円減)の減収減益。液晶用ガラス基板の出荷は微増したものの、販売価格が大幅に下落。ディスプレイ用特殊ガラスの出荷は、車載ディスプレイ用カバーガラスの欧州向け出荷が増加した。 化学品の売上高は4844億円(同467億円増)、営業利益は711億円(同75億円増)の大幅な増収増益。クロールアルカリ・ウレタンは2017年3月から連結したビニタイ社がフルに寄与、クロアリ製品の価格改善。フッ素・スペシャリティも半導体関連製品向けをはじめとするフッ素関連製品の出荷が堅調に推移したことなどにより増収となった。 営業利益のセグメント別構成をみると、化学品が711億円、ガラスが225億円、電子が240億円と化学品がけん引した。 2019年通期業績見通しをみると、売上高は1兆6000億円(前期比771億円、5.1%増)、営業利益は1250億円(同44億円、3.7%増)。親会社の所有者に帰属ずる当期純利益は780億円(同116億円、12.9%増)の増収増益を予想。営業利益は5期連続増益を見込んでいる ガラス事業について、建築用ガラスは、各地域での数量が堅調に推移、加えてブラジル新窯が稼働する。日本や欧州で前期に行った値上げがフルに寄与するとし、増収増益を見込んでいる。 決算発表の後、島村社長より「AGC puls―2020」の進捗状況について説明があり、「AGC puls―2020」では、2025年に向けた礎を築くとし①市況変動に強い高付加価値事業を伸ばす②戦略事業の成長戦略を推進する③成長地域・勝てる地域へ経営資源を集中する④戦略的なM&Aにより持続的成長を図ると4つの主要課題を上げ、戦略事業には「モビリティ」「エレクトロニクス」「ライフサイエンス」の3事業をあげていた。2025年には営業利益2292億円以上の過去最高益更新を目指す。 |
| ■ ひのまるチェーン大阪支部関西部会 定時総会を開催 「主婦目線でスペーシアを売る方法」講演 (平成31年2月18日) |
|
定時総会開催に先立ち、関西部会を代表して山下会長が参加者にお礼を述べ「去年関西では災害が多かった。テラス等未だに仕事が間に合わない部分がある。災害で仕事が多かったというのもどうかと思うが、社会貢献と思えば良いことだと思う。またバブルの頃と違って今の人手不足は営業する人間はいるけれど、技術者がいない。AIにはどうしても変われない部分もある」とあいさつした。 続いて日本板硝子の取引店で構成される関西ひのまる会を代表して北橋成夫会長(㈱三供システム代表取締役)が挨拶し「今日は主婦の目線から講演していただく。我々が一番大切にしなければならない方の目線でお話が聞ける。非常に興味深い。楽しみにしている」と述べ、総会に華を添えた。 さらに日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱執行役員大阪支店長・大野義之氏は最近の関西景気動向述べた後「新築の数は年々減少して行く傾向にあるが、建物の質は上がっている。また、ストック住宅の断熱化も遅れている。そういうところに高機能商品を進めていくのが我々の役目だ」とあいさつした。 定時総会では、2018年度の活動報告ならびに会計報告、2019年度の活動計画案や予算案などを審議。賛成多数ですべて可決した。 後半の講演の部では、宮本営業接客コンサルティング・宮本美保氏が講師となって「主婦目線でスペーシアを売る方法」をテーマに約1時間講演した。講演の前に実際にご自身で「スペーシア」を販売してきたそうで、「スペーシアは売れる」と自信いっぱい話していた。今回は関西ひのまる会・村島硝子商事の村島靖基氏の紹介で講師が決まったようだ。 |
■
板硝子協会 合同委員会を開催
島村会長「防災安全ガラスの更なる普及」を訴え(平成31年2月4日)
|
|
板硝子協会(島村琢哉会長)は、1月25日(金)に東京都千代田区一ツ橋にある如水会館において、協会役員や各委員会委員長、さらにその委員・関係者らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。合同委員会終了後には、場所を2階に移動して平成31年ガラス産業連合会(略称GIC =板硝子協会、硝子繊維協会、電気硝子工業会、㈳日本硝子製品工業会、日本ガラスびん協会、㈳ニューガラスフォーラムの6団体が加盟)の新年会も開催、官・学・団体関係者・会員ら約390人が参加する中、盛大に行われた。 合同委員会の冒頭に島村会長は参加者にお礼の言葉を述べた後、「この会が始まる前、景気討論会にパネラーとして出席した。他のパネラーさんの話を聞くなかで、全般的に言えば米中貿易戦争の影響はあるものの、日本の潜在成長率はそこそこあって、東京オリンピック、大阪万博、政府の政策実行にともなって景気は底堅いものではないかと皆さんの意見は一致した」と語り、「板硝子業界においても内需がベースだ。住宅着工件数についても、ここ数年の動きをみても安定している。複層ガラスの普及率も高まり100%に近付いている。LowーEペアについては80%に上昇している。環境・省エネ・居住空間の快適性に対して皆さんが関心を持っている証拠だ。板硝子協会としてもエコガラスの普及にあわせて、防災・防犯の観点からの防災安全ガラスの更なる普及活動を皆さんと一緒になって進めていきたい」と挨拶した。 引き続いて行われた合同委員会の発表では、建築委員会(武田雅宏委員長=旭)、輸送機材委員会(丸山徹委員長=日本板)、規格委員会(湯浅章委員長=セ社)、環境・技術委員会(宮之本昭二委員長=日本板)、税制委員会(岩崎成俊委員長=セ社、当日欠席)等の各委員会の委員長より、今抱えている問題や今後の方針を述べた(それぞれの発表内容については後日紹介予定)。 その中で武田委員長からは、建設省告示 1360 号「防火設備の構造方法を定める件…」の 改正案に耐熱強化ガラスが追記されたと発表があった。これまでの告示使用では、鉄枠+網入りガラスしか認められていなかったが、板協も参画した建築基準整備促進事業F9の結果や、昨年制定された耐熱強化ガラスのJISを基に、告示改正案には、「耐熱強化ガラス」が追加仕様案として記載された。 ◎ガラス仕様 ・耐熱強化ガラス単板 (厚さ6.5㍉以上、エッジ強度250MPa以上)※エッジ強度は、昨年制定された耐熱強化ガラスのJISの値を引用している。 ・耐熱強化ガラス+Low―Eの複層ガラス(Low―E厚さ5㍉以上、垂直放射率0.03~0.07) ◎枠仕様 鉄材又は鋼材(含むステンレス) 最後に来賓を代表して経済産業省製造産業局素材産業課・湯本啓市課長が、「建築関係について、住宅エコポイントについては、国土交通省が中心となって行うが、今回で、4回目で、拡充・改善されてきている。防災安全については国土強靭化ということで総点検した。今年から3年間集中期間として対策を打っている。港湾・インフラ系がメインだが全部で7兆円の予算。公共施設への対応も影響がでるかもと期待している」と述べ、さらに、輸送機材、規格、環境関係、税制にも触れた後、「多くの課題がある。物事の流れが早くなってきている。皆様のご要望・ご意見をキャッチして、政策の方に繋げていきたい」と挨拶した。 |
■東海卸・東海工事・愛硝協 東海3団体が講習会 防火設備が個別認定へ移行(平成31年2月4日)
|
東海板硝子卸商業組合(立木彰一理事長)、東海板硝子工事協同組合(木村俊一理事長)、愛知県板硝子商工業協同組合(太田吉則理事長)は1月24日、名古屋市千種区の名古屋ビール園浩養園スターホールで「防火設備に伴う通則的運用停止に伴う個別認定制度への移行講習会」を開いた。午前と午後の2回開かれ、それぞれ約250人、合計500人近くが参加した。 冒頭、主催者である3団体の立木理事長、木村理事長、太田理事長があいさつを述べ、講習会の意義などについて話した。 はじめに、概論として日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社の機能硝子部 部長で板硝子協会建築委員会技術部会長の久田隆司氏が壇上に立った。 通則の説明と、防火関連法規の歴史や位置づけ、法規や対象地域についても説明した。更に、防火設備の設置が必要な部分、使用部位の例、試験事例などにも言及。また、最新の法改正へのアプローチについても話した。 続いて、サッシ・ガラスメーカーへの積算・発注上の発注上の注意点について宮吉硝子株式会社の国立大介取締役本部長が説明した。 この後、各メーカーからの特徴の説明があり、株式会社LIXILの中部エンジニアリング営業グループの鈴木裕章主任が商品設定と基本仕様の紹介を行いスライドなどで表示しながら説明した。 YKK AP株式会社から、ビル本部開発営業統括部の山口勝中部エリア部長が、大臣認定防火設備・個別認定の取り扱いについて従来の通則認定と現行の住宅個別認定、新規のビルの個別認定について制度から説明し、自社の商品体系について説明した。 三協立山株式会社三協アルミ社の東海ビル建材支店ビル建材一課の穂積宏貴課長はビル基幹商品の「MTG―70R(防火型)」について開発コンセプトと「70」と「70R」についての比較説明。窓種別の特徴についても言及した。 昭和フロント株式会社工務部工務課の梁瀬崇課長は「フロントサッシ防火設備における通則的運用の停止に伴う個別認定制度への移行について」と題し、同社の防火対応の商品体系や防火用フロント(個別認定品)の特徴や4月からの発売商品について説明した。 文化シヤッター株式会社中部設計センターの關岡利明センター長は個別認定製品の提案として、通則品運用停止後の対応として、「エリファイト」「カームスライダー」の提案や、防火設備や特定防火設備の例示しようについて話した。 ナブテスコ株式会社住環境カンパニー商品企画部の構井克典主査は運用停止の対象製品について説明。「アルミニウム合金製引き自動ドア」は停止し、鋼製の「ナブコ防火戸(20)/FEB型」「ナブコ防火戸(20S)/FEC型」とすると説明。 防火窓施工の実演を秀硝子株式会社の倉持秀利社長らが行った。 会場中央にディスプレーし、実際にガラスをはめる作業を行った。来場者全員が施工の参考にしようと注目ししていた。 東海板硝子卸商業組合の立木彰一理事長のあいさつ ガラスは専門知識がないと工事ができない業種だ。各種メーカーからの説明は部分的に聞くとよく分からないことが多い。情報のスムーズさが必要だ。 ガラスとサッシをつなぐところが防火の性能を担保する箇所だが、それを塞いでしまったらもう分からない。もし、不正が見つかったら中を開けての再点検は不可能。防火性能を担保するためには全て取り替えるしかなくなる。防火窓の信用を得るためには正確な知識と施工が必要。高い技術を学んで頂いて火災に関する関心を持ちご協力を願いたい。 東海板硝子工事協同組合の木村俊一理事長のあいさつ この講習会の実現に大きな意味がある。ぜひ学んで欲しい。 昨年、業界を騒がせた防火の話だが、われわれもまだまだ理解できていない。今日だけで完全に理解はできないと思うが、今後も学ばなくてはならない。 建築キャリアシステムも進んでいる。あいまいな業界ではあってはならない。われわれの仕事の仕方も変化しなくてはならない。まず、今日、ルールを把握し、しっかりした対策が必要だ。 愛知県板硝子商工業協同組合の太田吉則理事長のあいさつ |
■関東卸都硝協 合同新年会開催 若い力を業界に-松原氏(平成31年1月28日)
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)は、1月18日、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町2階「ロイヤルクリスタル」において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で10回目となる合同新年会には、来賓を併せ約130名が参会した。 今年は都硝協の当番ということで司会を務めたのは上柿勝宏氏。同氏の開会宣言で新年賀詞交歓会はスタートし、まず主催2団体を代表して都硝協の松原理事長が多くの来賓の方々にあいさつの後「昨年東京でも、大風が吹いてガラスやドアが壊れたりして、改修工事で皆さん忙しく働いていらっしゃることと思います。住宅の快適さ・安全に協力する重大な仕事としてやってきた。これからもしっかり仕事をしていかなければならないと思っている。組合員が減少している中で、社会的責任を果たすということは段々難しくなってきている時代。そういったことで社会の皆様にご不便をおかけしないような状況を我々が協力し合いながらやっていかなければならない。本年も仕事環境をいかに良くしていくかを業界全体で考えていかなければならない。来年にオリンピック開催を控えて皆さん忙しくされていることと思う。まだまだこれから忙しくなるし、人手不足も言われている。我々の仕事に対する状況をいかに良くするか。新しい若い力をいかに業界に入れていくか、我々の課題である。時間の許す限り、皆さんで話し合っていただきたい」と述べた。 引き続き来賓を代表してAGCグラスプロダクツ㈱東日本関東営業部部長・宮石真英氏が「納期面で皆様にご迷惑をおかけしている」とお詫びの挨拶の後「2019年、今年は変化の年。年号が代わり、消費税増税がある。首都圏ではオリンピック開催に向け最終年を迎える。町並も変わってきている。非住宅の防火認定も通則から個別に代わる。業界にとっては大きな話だ。変化に対応するというより、この変化をテコにして会社の構造改革、効率化を進めていきたい。5年後、10年後に振り返ってあの年が転機だったと皆様と笑って過ごせるように、今年1年頑張っていきたい」と力強く挨拶した。 乾杯の音頭は関東卸・松本理事長が担当。「今年4月で平成の時代は終わる。平成はどういう時代だったかを振り返ってみたが、最初の頃はバブルの余韻が残っていて、業界では単板のガラスを扱い、サッシは在庫を倉庫に一杯積んで商売をやってきた。30年も経つと業界はガラッと変わって、単板の商売は無くなり、機能ガラスに変わってきたが、一般の消費者に対して、機能ガラスの認知度が非常に低いと言うのが今の課題。いろいろ機能を持ったガラスがある。 皆さんと一緒になって一般消費者に機能ガラスの啓蒙活動をやっていこう。まだまだガラス業界は捨てたものではない」とあいさつした。 しばし歓談を楽しんだ後、日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱営業本部執行役員東京支店長・齋藤淳氏が中締めのあいさつを行い、終了した。なお、当日の来賓団体・企業は次の通り(敬称略)。 ☆関東甲信越板硝子卸商業組合(敬称略) ▽板硝子協会=専務理事・森谷茂明、調査役・浅沼光一▽AGCグラスプロダクツ㈱=東日本関東営業部部長・宮石真英▽日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱=営業本部執行役員東京支店長・齋藤淳、東京支店硝子建材販売グループ課長・富山真司▽セントラル硝子販売㈱=取締役東日本営業本部長・井上昌久、東日本営業本部特約店営業部長・松本康司 ☆東京都板硝子商工協同組合 ▽東京都職業能力開発協会=能力開発部長・大畑章▽関東板硝子工事協同組合=副理事長・山田圭一▽全硝連関東甲信越地区本部=本部長・宮沢芳宏▽東京都鏡商工業協同組合=理事長・尾崎由雄▽東京板硝子施工組合=理事長・吉岡通匡▽東京板硝子鏡加工組合=会長・岩澤精一▽日本自動車ガラス販売施工事業協同組合=事務局長・森野好洋▽東京建具協同組合=専務理事・佐藤秀明▽東京南部法律事務所=弁護士・芝田佳宣、同・黒澤有紀子▽塚越税務会計事務所=総括リーダー・内山肇▽城東労務管理事務所=主任・常盤瞬 |
■関西板硝子業界国交省と経産省初参加「新年互礼会」開催(平成31年1月21日)
|
|
今回は主催者として、関西板硝子卸商業組合が担当。司会は理事・福利厚生委員長の奥山善茂氏が行った。互礼会の冒頭に、関西板硝子卸商業組合・斎藤洋介理事長が、新年のあいさつ、参加者への御礼、昨年の状況等を振り返って述べた後、次のように語った。 「消費税増税がこの秋に実施されると思うが、増税後の政府の景気対策の一環として、住宅エコポイントの復活の話も出てきている。前回を大幅に上回る予算が計上されており、増税後に落ち込むであろう新築・リフォームの需要を喚起してくれるのではないかと期待している。また、関西における明るい話題として2025年に大阪万博開催が決まった。この経済効果は2兆円とも言われており、息の長い景気拡大が関西を中心に続くものと思われる」と述べた。 さらに「昨今の職人不足、資材高騰、物流コストの上昇と言った懸念材料もある。これらの問題はガラス業界においても重要課題として捉え、今後、機会があるごとに議論していきたい」と語った。 また、関西板ガラス業界の課題として、①ガラスの日の制定について②働き方改革について③G6のあり方などについても触れ、その他の諸問題も含め、情報を共有しながら、取り組んでいきたいと強調していた。特にガラスの日の制定については、「ガラスの日をどのように一般に伝えていくのか、ガラスの日を通じてガラスの魅力をどのようにアピールしていくのか、皆さんと意見交換したい」と述べていた。 この後、来賓を代表して国土交通省近畿整備局建政部建設産業調整官・永富栄三氏が「これまではガラス業界の皆様とあまり接点はなかったということで、今回初めて新年互礼会に参加させていただいた。今後、お願いすることやお知らせすることも多々あるかと思います。皆様のお役に立てられるようにやっていきたい」 また、経済産業省近畿経済産業局産業部産業課長・原田敏行氏が「板ガラス業界は素晴らしいことをおやりになっている。割れても飛び散らない合わせガラスを開発され、それを避難所となる小中学校にお配りになっている。安全・安心というものは、こういうことから成り立っていくものだと感じた」と、それぞれ壇上に立って挨拶。新年互礼会に華を添えた。 さらに、国内板ガラス3メーカーを代表してセントラル硝子販売・取締役西日本営業本部長・瀬古雅裕氏が「今年は元号が変わる節目の年。祝賀ムードも高まってくる。今年後半は来年のオリンピックに向けて盛り上がってくる。首都圏の建設ラッシュも最終段階に入ってくる。消費マインドも上がり、景気も上向くことを期待したい。大阪万博開催も決まり、IR法案も昨年成立した。これらをビジネスチャンスと捉え皆様と共に2019年は頑張っていきたい」と挨拶した。 来賓挨拶のあと、経済産業大臣・世耕弘成氏からの祝電も披露された。 この後、全硝連近畿地区本部長・小村哲也氏の乾杯の音頭で、祝宴はスタート。それぞれ和やかな雰囲気の中で年初のあいさつや情報交換を行い、相互の親睦を深めた。小村氏は挨拶の中で、国交省や経産省の方達に「防災安全ガラスの公共施設への標準仕様」等をお願いしていた。 最後は、関西板硝子工事協同組合・清水英彦氏の中締めで終了した。 なお、当日の来賓出席官庁・団体・企業は次の通り(順不同)。国土交通省近畿整備局建政部、経済産業省近畿経済産業局産業部、AGCグラスプロダクツ、日本板硝子ビルディングプロダクツ、セントラル硝子販売、大阪府鏡工業協同組合、大阪板硝子鏡加工組合、神栄ホームクリエイト、ハードグラス工業、新光硝子工業、藤原工業、中島硝子工業、三芝硝材、エヌビーエス。 |
■日本電気硝子第25回空間デザイン・コンペ(平成30年12月31日)
|
||
|
日本電気硝子㈱(本社=滋賀県大津市、松本元春社長)は12月7日(金)、東京・港区のTKPガーデンシティ品川で恒例の「第25回空間デザイン・コンペティション」の表彰式を華やかに開催。応募登録数301件、応募作品数185点の中から最優秀賞に輝いたのは山本将支氏(I.R.A.)の作品で、表彰状と賞金100万円を授与した。優秀賞1点には中村春菜・岡本隼樹・桑原 萌・山下尚行・山田昭徳(㈱ジェイアール東日本建築設計事務所)の各氏らの作品に、表彰状と賞金30万円が贈られた。 今回の課題は「生きもののようなガラス」。6月に応募を開始し、10月9日に締め切った提案部門の応募登録数は301件、応募作品数は185点に上った。 コンペは古谷誠章氏 (建築家・早稲田大学教授・NASCA主宰)が審査委員長を務め、審査委員は原田真宏(建築家・芝浦工業大学教授・MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO主宰)、羽鳥達也(建築家・日建設計・設計部門設計部部長)、岸本暁(日本電気硝子執行役員コンシューマーガラス事業本部事業本部長)の3氏が担当。また、建築評論家で東北大学教授の五十嵐太郎氏がコーディネーターを務め、最優秀賞1点、優秀賞1点、入賞作品10点を決めた。 表彰式では、主催者を代表して松本社長が壇上に立ち「おかげさまでこのコンペも25回目を迎えた。今回のテーマは生きもののようなガラスということで、それに対して皆さんのアイデアがどのように盛り込まれているのか楽しみにしてきた。弊社は売上で行くと3000億円の規模の会社。作っている主な商品はディスプレイ用。売上の8割を占めている。建材は全体の2%ぐらいだが、ユニークな商品を作っている。特殊ガラスでは、世界で有数なメーカーだ。将来的には世界一のレベルまで持っていきたい。環境にやさしい、自然にやさしい物づくりをやっていき、社会に貢献していきたい」とあいさつ。 表彰状を授与の後、審査委員長や審査委員からの審査の講評があり、古谷誠章氏(懇親会の席で述べた)が「授業を抜け出してきた。2年続けて審査委員長をやらせていただいた。かつては私もこのコンペで何回か入賞させていただいた。今回は考えようのないテーマだったが、すばらしい皆さんの着想をいただいて、大変喜ばしく思っている。最優秀賞の作品はとても美しいドローイング(製図)に印象付けられた」と語り、また審査委員の原田氏が「ガラスの印象が変われば都市の印象も変わる。今回のテーマは今までのガラスのイメージとはまったく反対のイメージ。都市もいきもののように変わるのではないか。とても楽しませてもらった」、羽鳥氏が「どんなアイデアが集まるのか。楽しみに審査させていただいた」、岸本氏が「このテーマで応募がなかったらどうしようかなと心配したが、非常にたくさんの応募をいただいた。似たような作品が非常に少なかった」と講評を述べ、最後に最優秀賞に輝いた山本氏が御礼を述べ表彰式は終了した。この後、部屋を移動し、懇親会も開催された。 審査結果は次の通り。 ◎最優秀賞 1点 賞金100万円 山本将支 ㈱I.R.A. ◎優秀賞 1点 賞金30万円 中村春菜・岡本隼樹・桑原 萌・山下尚行・山田昭徳 ㈱ジェイアール東日本建築設計事務所 ◎入選 8点 賞金各5万円 ①土佐谷勇太(フリーランス) ②渡部高弘(㈱日建設計)、樺浩太(熊本大学大学院) ③廣田竜介(㈱日本設計) ④谷戸星香(フリーランス) ⑤安藤寿孝・石田高義 (㈱竹中工務店) ⑥長谷川将太郎・大野めぐみ(千葉大学) ⑦邱慶涵(創造社デザイン専門学校) ⑧高木潤(タカギカペラン) |
■大阪芸術大学建築家の妹島和代氏が設計 壁面をガラスが占める新校舎(平成30年12月10日)
|
||||||
|
大阪芸術大学(大阪府河南町、塚本邦彦学長)は、このほど建築界のノーベル賞ともいわれるプリツカー賞を受賞するなど、世界的にも活躍する建築家の妹島和代(せじまかずよ)氏が設計した新校舎の竣工を発表した。 2017年に開設したアートサイエンス学科の校舎として使用する。 新校舎は、建築面積2684.2平方㍍、延床面積3137.5平方㍍。地上2階、地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート造。設計・監理は㈱妹島和代建築設計事務所が行い、施工は大成建設㈱関西支店が担当した。 壁面の大半がガラスの壁となっており、1階の中心部は吹き抜け構造の開放的な構造。校舎の内側と外側がつながっており、あらゆる方向から出入りが可能で、内側95㍉~3872㍉、幅1063㍉~3872㍉までのガラス46枚を使用。このほか、合同研究室に17枚、講義室20枚、教員研究室24枚が使用され、回廊からも様々な方向に景色が見えるよう工夫されている。 建物の特長は、壁面の大半を占めるガラスで、1階の共有スペースだけで高さ2で繋がっている2階部には61枚、立ち入りの出来ない3階部分に47枚、計215枚のガラスが使用されている。 これらのガラスの強化および曲げ加工を三芝硝材㈱が行い、ガラス施工は旭ビルウォール㈱が担当している。 なお、三芝硝材によると平強化ガラス146枚(515平方㍍)、ケミカル強化ガラス71枚(280平方㍍)、風冷強化ガラス12枚(74平方㍍)を加工・納入したとのことだった。 同校広報部によると、1階の共用スペースは、アートサイエンス学科の学生だけでなく、一般の学生も自由に出入りできるラウンジや、イベントホールとして使用するとのこと。また、講義に使用する部屋が4部屋、ゼミ室にもなる教員室が8部屋設けられており、教員室の内壁を移動することで、奥の景色が見通せる。2階は半屋外の開けた空間で、オープンテラスとしても利用でき、地下1階は作品の制作室やスタジオとして使用することを想定している。 同新校舎は、あらかじめ連絡があれば見学も可能であるとのことだった。 |
■機能ガラス普及推進協議会添田町勤労者体育施設へ「防災安全ガラス」寄贈式(平成30年12月3日)
|
||||||
|
機能ガラス普及推進協議会(島村琢哉会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長、以下「全硝連」)の九州沖縄地区本部長(三原宏本部長)、板ガラスメーカー、地元卸店とともに、11月22日(木)午前11時から、添田町オークホール研修室(福岡県田川郡添田町)で開催された、添田町勤労者体育施設(そえだドーム)に寄贈した「防災安全ガラス」の寄贈式に参加した。 今回の寄贈式は、同協議会が勤労者体育施設に防災安全ガラス254枚(ガラス提供=日本板硝子㈱、中間膜提供=イーストマンケミカルジャパン㈱、現地配送=山十㈱)を寄贈、全硝連九州沖縄地区本部と福岡県板硝子商工協同組合(山本優一理事長、以下「福岡県協組」)が施工に関わる工事費などを寄贈したもの。なお工事は、今年10月9日(火)から3日間行われた。 寄贈式には、自由民主党副幹事長 大家敏志参議院議員の代理として参加した柴田泰夫氏、福岡県議会の神崎聡議員、福岡県総務部防災危機管理局 消防防災指導課の藤田修司課長と、添田町側から寺西明男町長と藤田季弘副町長、高瀬光一教育長、合戸精一町議会副議長、藤川修司防災管理課長、信國憲文教育委員会教育課長などが出席。機能ガラス普及推進協議会からは、森谷茂明企画運営委員長と浅沼光一事務局長のほか、日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱執行役員 九州支店長の中村哲也氏、山十㈱の池永英喜常務取締役と伊藤広志住宅営業部主任、全硝連から辻会長と三原九州沖縄地区本部長、福岡県協組の山本理事長、立石勝副理事長、横畠勝彦副理事長、宗貞伸繁理事などが出席した。 贈呈式では、初めに森谷委員長が「添田町の皆様には、今回の寄贈プロジェクトの趣旨をご理解くださり、大変お世話になりました、改めてお礼申し上げます。今回寄贈させていただきました防災安全ガラスは一般のガラスよりも強靭で割れても破片が飛ぶことが無く、地震や台風などの災害時に破片による二次災害なども発生しにくく、政府の進める国土強靭化にもマッチしたものです。この防災安全ガラスの寄贈は奈良県生駒市、岡山県和気町、宮城県石巻市に続く4件目となります。公共施設や災害拠点の更新の際には、防災安全ガラスの採用が義務化になるよう、活動を続けていきたいと考えております」と寄贈の趣旨説明と挨拶をした。 続いて、森谷委員長から寺西町長に目録が贈呈され、寄贈に対する感謝状が町長から森谷氏に送られた。 また、寄贈を受けたことについて寺西町長は「寄贈頂いたことを感謝申し上げます。添田町は昨年、今年と2年続きの災害(水害)に見舞われ、大きな被害を受けた所でございます。今、全力で復旧作業を続けております。こうした中、避難所指定している「そえだドーム」に、九州沖縄地区では初めて、防災安全ガラスをご寄贈頂き、設置していただきました。これにより、避難時はもとより、平時でも安心して使用できる施設となりました。皆さんの御支援のもと災害に負けず、頑張っていきたいと思っております」と謝辞を述べた。 最後に、浅沼事務局長が添田町側の参加者に、サンプルを用いて防災安全ガラスの機能を説明し実際にデモ機を使って寺西町長が防災安全ガラスの性能比較実験を行って、贈呈式は終了した。 その後、場所を田川郡添田町立真木小学校に移し、午後2時から、同校の体育館に全校生徒58名を集めて、ガラスの出張授業と機能ガラスの性能比較実験を行った。 授業に先立ち、同校の縄田和之校長が、全校生徒の前で「災害時の避難所になっている「そえだドーム」に防災安全ガラスが取り付けられました。添田地区は、去年も今年も災害が発生しました。また、地震もいつ発生するか判りません。そんなときに役に立つ防災安全ガラスとはどのようなものか、しっかり勉強して、自分の身は自分で守れるようになってください」とあいさつした。 続いて、福岡県協組の横畠副理事長の司会進行で、「ガラスの安全安心エコ講座」(講師=浅沼光一氏)が行われた。講座では、パワーポイントや動画を使用しながら、ガラスの歴史や種類、フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、安全防災ガラスの特性とエコガラスの紹介を行った。 その後、メインイベントとなる、機能ガラスの性能比較実験に移り、デモ器2台を使用して実験を行った。フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、防災安全ガラスの4種類のガラスを、生徒代表がそれぞれハンマーで叩き、その割れ方や、安全ガラスの丈夫さを確認、デモ機を取り囲んでいた生徒たちからは、「(ガラスの)ひびがキレイ」との声も上がるなど、普段見ることのないガラスの割れる様子や、防災安全ガラスの丈夫さに興奮しているようだった。 実験終了後の質疑応答では、生徒から「普通のガラスと強化ガラスの作り方の違いは?」といった質問が行われ、浅沼事務局長が一問一問丁寧に答えていた。 最後に、森谷委員長が、生徒代表に記念品を贈呈し、生徒代表から謝辞を受けて、出張授業は終了した。 |
■新役員に聞く全硝連関東甲信越地区本部長・長野県ガラス・サッシ組合連合会理事長宮沢芳宏氏(平成30年12月3日)
|
||
|
全硝連関東甲信越地区本部長に就任して半年。長野県ガラス・サッシ組合連合会理事長を兼ねる宮沢芳宏氏(上田市、宮沢ガラス店)に会社と業界の動向や組合活動の現状を聞いた。 ―お店はどのような。 「ビル用サッシ工事、ガラス工事、鉄骨組立、壁貼り、建築管理と幅広く展開しています。従業員は4人。先代のころの退職者にも手伝ってもらっている。ガラス担当は私一人。ガラスを切断できる人がいないので」 「会社は父が1969年に創業した。当時は建具がメインでした。私は二代目。高校卒業と同時に入社した。その後1年半ばかり、東京のサッシ店や千葉のガラス販売店に〝修行〟に出ました。もっとも、高層ビルでのサッシの取り付けなんか『俺の方ができる』。もう、みんなわかっているので面白くない、と思って、東京ディズニーランドをオープンさせた次の日の大晦日に、上田に戻りました」 ―小学生でガラスを切っていたとか。 「親父の仕事の手伝いで、小学校高学年のころには2~3㍉程度のカットをマスターした。1987年に技能検定1級の資格を取得しました。当時は職人が多かったせいか検定試験も順番待ち。1~2年待ちました」 「それに比べて今は受検者がかなり減った。カットする機会も減り、板ガラス職人の技術・技能は年々低下している。現場サイドでは1級技能士を再教育しようといった話もある。長野県でも受験生のレベルが著しく落ち込んでいます」 「長野県ガラス・サッシ組合は技能検定講習を重点事業に挙げているが、そうした面で技能グランプリは有効です。幅広い知識を持たないと仕事はできない。ブロック会議では技能グランプリに最低各県1人の選手を派遣してほしいと要請しました」 ―県組合の現状は。 「1987年に県板硝子商工協同組合として発足した。当時の組合員は約180人。2009年に任意組合に転換した。経費節減のためです。現在の組合員は20人。良かったのか悪かったのかどちらとも言えないが、県当局、県議会などに対する『力』という側面ではデメリットになっている」 「どこの職種でも同じだろうが、高齢化と後継者不足は深刻な問題。会合で必ず話題になる。二代目で商売をやめるというパターンが多いようです。働き方改革も懸念材料。若い人は、土日は休みたい、正月・盆休みぐらいは仕事に縛られたくないと主張するが、そのようなことをしていたら我々の仕事は成り立たない」 ―課題は。 「災害時の態勢をつくりたい。地震や大型台風でガラスが割れた時、頼りにするのはガラス販売店。我々自身も緊急時に頼りにされる存在でありたいと思っている。近県、近隣支部などが広域的に連携・協力して対応できるような仕組みを構築できないか思案中です」 「ただ、それにしては人数が少なすぎる。広大で山また山に囲まれた長野県特有の地域性もある。価値観、考え方が違うし、一つにまとめるのは大変。青年部活動は15年前ぐらいから途切れた。ぜひ復活させたい」 ―取り巻く環境は。 「板ガラスメーカー、サッシメーカーとも最近はほとんど回ってこない。もう必要とされていないのかと思うくらいです。インターネットの時代になってメーカーはじめ同業者とのつながりが薄れてきているように感じる」 「私がメーカーの人間だったら、小売店など専門に足繁く戦略的に巡回する人間を配置する。営業マンは商売抜きでいい。カタログも商品説明は不要。顔を合わせ世の中のこと、実例╍╍要は情報を聞かせてほしい。情報が大事なのです。商品そのものでなく、売る側の人の話に心に響くものがあれば、きっと商売につながる」 「人と直接会って五感で感じること。我々の仕事もそう。モノに触れたり、感じたりと五感に頼る面がある。体で覚えて仕事をする。ネットで判断するのではなく、自分で現場に行ってみて感じたことが正解となるはずです」 ―全硝連の活動について。 「課題、問題を共有してどう解決していくかという点でスピード感に欠ける。また、商売は儲からないと駄目。もっと儲けることの質と定義を考えていかないと業界の未来は開けないと思う」 |
■セントラル硝子第53回国際建築設計競技(平成30年11月26日)
|
||||
|
セントラル硝子(本社・東京、清水正社長)は11月10日(土)、東京・丸の内の東京国際フォーラムD7ホールを会場に、恒例の「第53回セントラル硝子国際建築設計競技」の公開2次審査会と表彰式を開催した。 本年度のコンペの課題は、「自動運転が変える、くらし・まち・建築」。公開審査では1次審査を通過した上位7組のプレゼンテーションを実施。審査委員による3回に及ぶ集票の結果、最優勝賞1点には、神谷優梨子氏(早稲田大学大学院)、黒田京佑氏(東京理科大学大学院)の両氏が提案した「車内教室」(仮題、以下同じ)が選ばれた。 優秀賞2点には、クロアチアのソーダ・ロヴレ氏(アルマベトン)による「楽器演奏車」と、朝日啓仁氏(京都工芸繊維大学大学院)、パラモン・モルトン氏(同)の両氏による「水運」が選ばれた。他4点は入選。そのほか佳作10点を選出した。 表彰式では最優秀賞に賞金200万円と記念品、優秀賞に各30万円と記念品、入選には各10万円と記念品を贈呈。佳作10点には5万円が、それぞれ代表者に贈られた。 課題は、「加速、操舵、制動すべてをシステムが行い、システムからの応答も不要な『レベル5』の完全自動運転車が現れた時、われわれのくらし、まち、建築はどのように変わるだろうか」と問いかけ、自動運転が変える未来の形を求めた。 最優秀賞の「車内教室」は、自動運転車を一つの教室に見立て、事前に目標と定めた地域内あるいは郊外にある学習拠点などを自在に回り、実社会に即した教育を実践しようという試み。優秀賞の「楽器演奏車」は、いろいろな楽器を自由に練習できる空間をクルマに求めた。密集地や繁華街を避け他人の迷惑にならない場所を移動しながら楽器演奏を楽しもうという寸法だ。 優秀賞のもう1点「水運」は、自動運転の船舶で新潟・佐渡島と東京の墨田川を海と河川の水路を使って結び、江戸時代の北前船を模した船上では稲穂を育成し、陸揚げして精米にするというユニークな発想だ。 午後1時半から始まった公開2次審査会では、最初にセントラル硝子の清水社長が「今回のコンペには国内63点、海外48点(15カ国)の計111件の応募があった。テーマが難しかったせいか例年より少なかったが、内容はいずれも濃いものばかり。甲乙つけがたかった。若き建築家の皆さんには、これを機会に活動の場を世界に広げるよう頑張っていただきたい」とあいさつした。 7組のプレゼンテーションは、各5分のスピーチと審査委員との質疑応答各8分の範囲で行われた。審査委員長の内藤廣氏(内藤廣建築設計事務所)は講評で「モビリティー革命は確実に社会を変える。ただし、どう対応していいかわからない。提案をみても、シンボリック、デストピア、ロマンチック、身近な所といったように焦点が定まっていなかった。難しい設問に応募していただいて感謝申し上げる」と述べた。 最優秀賞に輝いた神谷さんは「大変光栄です。いかに(社会を)幸せにするかに行き着きたかったが、諦めずに頑張って提案したことが評価につながったと思います」と感想を述べた。同僚の黒田さんは「審査委員との質疑は勉強になった」と語った。参会者は5時半からのパーティーに臨み歓談した。 審査委員は次の通り。(敬称略、順不同) 内藤廣(内藤廣建築設計事務所)▽隈研吾(隈研吾建築都市設計事務所)▽亀井忠夫(日建設計)▽青木淳(青木淳建築計画事務所)▽賀持剛一(大林組)▽塚本由晴(アトリエ・ワン)▽高山聡(セントラル硝子取締役常務執行役員)
|
■AGC・NTTドコモ世界初送受信が可能なガラスアンテナ(平成30年11月26日)
|
||
|
AGC㈱と㈱NTTドコモ(東京都千代田区、吉澤和弘社長、以下ドコモ)は、「AGCとドコモが提携し、世界初の『窓の基地局化』に成功した」と発表し、その共同記者会見を11月7日(水)東京都千代田区内幸町にあるイイノホール4階RoomBにおいて行った。 当日の登壇者は、AGCがビルディング・産業ガラスカンパニーアジア事業本部長・武田雅宏氏と同事業本部日本事業部法人営業グループリーダー岡賢太郎氏、ドコモ側は、無線アクセスネットワーク部長・小林宏氏と同部無線企画・無線技術担当課長勝山幸人氏。 当日の発表内容は次の通り。 AGCとドコモは提携し、景観を損ねずに既存窓ガラスの室内側から貼り付けができる、世界初となる電波送受信が可能なガラスアンテナの共同開発に成功した。 新開発のガラスアンテナは700㍉×210㍉の大きさで、重量は1・9㌔㌘。 両社では、本ガラスアンテナを活用して、2019年上期から携帯電話のサービスエリア拡充を図るとしている。 移動通信のトラヒック量は増大し続けており、安定した高速通信に向けて対策が必要となっている。高トラヒックエリアにおいては、スモールセル基地局を設置し、トラヒックを分散させることが重要で、スモールセル基地局用のアンテナ増設が必要となる。現在、スモールセルアンテナは主に建物の屋上や中低層階の壁面に設置されているが、屋上や壁面は設置できる場所が限定されることや、街の景観を損ねることから、設置が困難なケースが多くある。そのため、建物内にアンテナを設置することで建物内から屋外をエリア化することを検討した。建物内へのアンテナ設置において、室内の意匠性を損ねる、電波が窓ガラスを通過する際に減衰するといった課題があり、これを解決するために、AGCが保有する既存窓の表面にガラスを貼り付けるアトッチ工法を活用することで、室内の窓面に設置可能な新たなアンテナの 開発を進めてきたもの。 今回開発したガラスアンテナは、透明・透視性のある導電材料とガラスを組み合わせており、①透明であるというガラスの特徴により目立ちにくく、景観や室内デザインを損なわない、②新たに開発したGlass Interface Layer(グラス インターフェイス レイヤー)の効果により、窓ガラスを通過した際の電波の減衰・反射を抑える特長を持っている。 両社は2019年上期から、現在主流であるLTEの周波数帯の基地局へ、本ガラスアンテナを展開していく予定で、さらに、5Gに対応したガラスアンテナの開発も検討するとしている。 なお、生産工場は国内を予定(場所は未定)、現状ではLow―Eガラスと網入りガラスにはこのガラスアンテナはつけられないとしている(将来的にLow―Eガラスは可能になる予定)。 AGC・武田アジア事業本部長のあいさつ 今までのガラスと違う形で社会に貢献するということで大変喜んでいる。これまでは、省エネ、安全、防犯、防災といった機能を窓ガラスに付加することによって、世の中のためになるということを進めてきた。しかし、今回の発表のようなガラスの使われ方があるということについて、私も想像できなかった。 AGCは111年前の旭硝子としての創業以来、時代にあった素材を世の中に送り出すことで、皆様方の暮らしを支えていくことをやってきた。今まさにIoT時代が来て、飛躍的に増えていく通信量、それに対応するネットワークを構築するということは、時代が要請していることである。そのことにガラスが貢献できるということで、これは私たちがやらなければならないことである。 ガラスは建物の顔であり、一番良い場所にある。その場所を使った新しい貢献という意味で重要なことだと考えている。 ※記事の画像提供はAGC㈱ |
■長野県松本市省エネリフォーム好調補正予算で対応へ(平成30年11月12日)
|
||
|
国宝・松本城と西に穂高連峰を仰ぎ見る長野県松本市(菅谷昭市長、人口約24万人)が実施中の省エネリフォーム補助金事業が好調だ。本年度は窓改修を中心に上期で予算枠を超える申請が殺到した。当局はオーバー分については補正予算で対応する方針だ。 正式名称「松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金制度」(通称・省エネリフォームの補助金制度)は、平成29年6月1日に正式に発足した。補助金の交付対象は既存住宅の居住者だ。 初年度の29年度は、開口部、LED照明器具、給湯機の3分野で適用。30年度は三分野などを統轄した「省エネ設備」と太陽光発電設備、定置型蓄電設備の新3分野での機器設置に補助金を支給している。 事業の柱に据えている省エネ設備は、窓・ドアの断熱改修、玄関前風除室、LED、高効率給湯機等(エコジョーズ、エコフィール、エコキュート、エネファーム、ハイブリッド給湯機、太陽熱利用設備、地中熱利用設備)―の四つの部門で構成。省エネ設備の補助金額は、設備本体購入費用プラス設置工事費用の20%で、上限20万円。 窓・ドアの断熱改修(ドアの交換、内窓設置、外窓交換、窓ガラス交換)の補助要件は、外気と直接接する開口部(窓・ドア)を改修することと、工事後の開口部の熱貫流率が3.49W⁄㎡・K以下になることの2点。 申請受付期間は31年3月末まで。施工業者は、松本市内に本店、支店、営業所がある事業者に限定している。 事業を所管している松本市環境部環境政策課によると、29年度の支払い実績は当初予算5340万円に対し約4940万円。工事件数の内訳は開口部が244件で約1640万円、LED91件で約670万円、給湯機355件で約2600万円。申請の35%以上が開口部の窓工事を含む。 開口部の内訳は、窓・サッシ201件(846基、1315㎡)、ドア42件(47基)風除室1件(1基)。同課温暖化対策担当の佐々木桃子さんは「窓・サッシは概ね内窓が65%、外窓35%。ガラスはLow―E複層ガラスがほとんどです。寒い地域なので断熱窓を導入する家が増えています」と指摘している。 本年度の当初予算規模は3989万円(補正対応)だが、9月末時点の補助金申請総額は約5500万円。補助金は予算枠に到達した時点で申請を打ち切るケースが多いが、佐々木さんは「申請はまだ続くでしょうが、予算を超えた分については全て補正予算で処理していきたいと思っています」と話している。 窓・サッシの申請が増加している背景に関しては「建設業協会を通して補助金情報を個人の工務店などに流してもらっています。従って業者からの問い合わせが多い。来年度以降も制度を継続していきたい」と説明。 環境政策課が昨年度の補助金利用者を対象にアンケートした結果では、「補助金制度を何で知ったか」との設問に対し、開口部は「住宅会社・工事業者」との回答が79.3%と他の項目と比べ群を抜いてトップだった。 一方、松本市は菅谷市長自ら「健康寿命延伸都市」を宣言。基本施策では、低炭素化社会の推進を前提に、市民の役割として、ライフスタイルの見直しや住宅の高断熱化・省エネ化、そして再生エネルギー機器の導入を挙げた。 佐々木さんは「一般的に温暖化対策としての省エネ化は浸透していないようですが、市民の皆さんには複合的に(補助金にも)いろいろメリットがあるということを知ってほしい」と話している。 |
■2018グラステック50ヵ国から1280社が出展(平成30年11月5日)
|
|||
|
ガラス産業のあらゆる分野を捉え、素材としてのガラスの可能性を様々な視点から紹介する世界最大級の展示会「glasstec 2018(グラステック2018 国際ガラス製造・加工機器展)」(主催=メッセ・デュッセルドルフ)が、10月23日(火)~26日(金)の4日間、ドイツ・デュッセルドルフの見本市会場で盛大に開催された。 今回で25回目となるこの展示会は、9ホール6万4000㎡の展示スペースに、世界50ヵ国から1280社(前回は1235社)が出展し、4日間合計で120ヵ国以上から約4万2000人の来場者が訪れた。 日本からの直接出展社は、AGCセラミック㈱、坂東機工㈱、井原築炉工業㈱、㈱ナカサク、㈱樋口鐵工所、九州ナノテック工学㈱、日本山村硝子㈱などの企業が出展した。 日本からの来場者は、板ガラスメーカーやサッシメーカー、二次加工メーカー、加工・機械・機材関連業者、流通業者など。 メッセ・デュッセルドルフ グラステックディレクター Birgit Hore氏の話によると、今回のグラステックでは、展示内容を決める委員会にダルムシュタット工科大学、ドルトムント工科大学、ドレスデン工科大学(各ドイツ)、デルフト工科大学(オランダ)の4大学が参加した「グラス・テクノロジー ライブ」、ベンチャー企業をサポートする「スタートアップ・ゾーン」などの企画展のほか、各国のメーカーが様々なガラス関連の製品・技術を紹介した。 このほか、AGCヨーロッパ社が真空ガラスを展示したほか、坂東機工は従来型の機械をバージョンアップした製品を、FOREL社は3000㍉×6000㍉の合わせガラスの大板を立てたままま切断する切断機を、それぞれ展示し、来場者の興味を引いていた。 このほかにも、記念講演や、新技術の発表会、プレス向けレセプションなどが行われ、25回目となる同展示会の開催を、盛大に祝った。 なお、弊紙ではグラステックツアーを催行し、関東、東海、関西地区から、多くの方にご参加いただいた。グラステック開催初日の23日には、ツアー参加者を歓迎するウエルカムレセプションが開催され、主催者側から展示会の基本情報や見どころなどの案内が行われている。 (出展各社の詳細等は次号より連載で紹介していく予定です) |
■機能ガラス普及推進協議会石巻市蛇田中学校体育館へ「防災安全ガラス」寄贈式(平成30年10月29日)
|
||||||
|
機能ガラス普及推進協議会(島村琢哉会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長、以下「全硝連」)の東北地区本部(袴田恭司本部長)、板ガラスメーカー、地元卸店とともに、10月9日(火)午後1時から、石巻市役所(宮城県石巻市)で開催された、石巻市立蛇田中学校体育館に寄贈した「防災安全ガラス」の寄贈式に参加した。 今回の寄贈式は、同協議会が、蛇田中学校体育館に、防災安全ガラス140枚(うち約40枚は強化合わせガラス、ガラス提供=AGC㈱、中間膜提供=積水化学工業㈱、ガラス手配=㈱三田商店仙台支店、現地配送=テクノグラスサービス㈱)を寄贈、全硝連東北地区本部と宮城県板硝子商工協同組合(大伴利彦理事長、以下「宮城県協組」)が施工に関わる工事費などを寄贈したもの。なお工事は、今年7月28日および8月1日に行われた。 寄贈式には、石巻市側から亀山紘市長と教育委員会の境直彦教育長、大崎正吾事務局次長、などが出席。機能ガラス普及推進協議会からは、森谷茂明企画運営委員長と浅沼光一事務局長のほか、AGCグラスプロダクツ㈱東日本東北営業部の大利康裕担当部長、㈱三田商店仙台支店の坂井雄司取締役支店長、全硝連から辻良明会長、宮城県協組から大伴理事長、赤岩秀晃副理事と、今回の統括担当責任者でもある山田光彦理事などが出席した。 同市教育委員会副参事で学校管理課の今野順子課長補佐の司会で開会した贈呈式は、初めに森谷氏が「石巻市教育委員会の皆様には、今回の寄贈プロジェクトの趣旨をご理解くださり、大変お世話になりました、改めてお礼申し上げます。今回寄贈させていただきました防災安全ガラスは一般のガラスよりも強靭で割れても破片が飛ぶことが無く、地震や台風などの災害時に破片による二次災害なども発生しにくいものです。この防災安全ガラスの寄贈は奈良県生駒市、岡山県和気郡に続く3件目となります。公共施設や災害拠点の更新の際には、安全安心な防災安全ガラスの採用を、是非ともご検討いただければと思います」と寄贈の趣旨説明と挨拶をした。 続いて、森谷氏から亀山市長に目録が贈呈され、寄贈に対する感謝状が市長から森谷氏に送られた。 また、寄贈を受けたことについて亀山市長は「防災安全ガラスの寄贈を頂き、心から感謝しております。今回、蛇田中学校屋内運動場の窓140枚を防災安全ガラスに交換していただきました。子ども達が授業に使用するだけでなく、地域住民の避難場所としての役割を担う場所です。避難所として使用される場所が、今回の防災安全ガラスでより安全になることに、大変感謝しております」と謝辞を述べた。 最後に、浅沼事務局が亀山市長と境教育長に、サンプルを用いて防災安全ガラスの機能を説明し、贈呈式は終了した。 その後、場所を蛇田中学校移し、午後2時30分から、同校の体育館に全校生徒622名を集めて、ガラスの出張授業を行った。 授業に先立ち、同校の舛田育久校長が、全校生徒の前で「今日は機能ガラス普及推進協議会の方に来ていただきました。この夏に体育館の窓ガラス140枚を、機能ガラスという新しいガラスに変えていただきました。かなり丈夫なガラスという事で、今日は色々な実験も見せていただけます。この体育館は避難所に指定されています。地震やこの前のような台風が来ても、このガラスなら大丈夫と聞いています。蛇田中学校は、全国で3番目に、このガラスを寄贈してもらいました。このガラスの性能を見せて貰って、体育館に避難すれば安全だという事をご家族にも伝えて貰えればと思います」とあいさつした。 続いて、宮城県協組の鈴木裕樹専務理事の司会進行で、「ガラスの安全安心エコ講座」(講師=浅沼光一氏)が行われた。講座では、パワーポイントや動画を使用しながら、ガラスの歴史や種類、フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、安全防災ガラスの特性とエコガラスの紹介を行った。 その後、メインイベントとなる、ガラスの破壊実験に移り、宮城県協組青年部(太田幸宏会長)の部員が中心となり、デモ器4台を使用して、「ガラス破壊デモンストレーション」を行った。フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、防災安全ガラスの4種類のガラスを、生徒代表がそれぞれハンマーで叩き、その割れ方や、安全ガラスの丈夫さを確認、デモ機を取り囲んでいた生徒たちは、割れても貫通しない防災安全ガラスの様子に目を丸くしていた。 実験終了後は、質疑応答が行われ、生徒からは、「防災安全ガラスの値段は?」、「どこで売っているのか?」などの質問が行われ、浅沼事務局長が、一問一問、丁寧に答えていた。 最後に、森谷委員長が、生徒代表に記念品を贈呈、生徒を代表して生徒会長の石崎丈慈君から謝辞を受けて、出張授業は終了した。 |
■AGC「SECOMあんしんうち窓」販売(平成30年10月8日)
|
||
|
AGC㈱とセコム㈱(本社=東京都渋谷区、中山泰男社長)は、既存の窓の内側に設置することで優れた断熱・防音性能などを発揮し、住まいの防犯と快適性を高める高性能ガラス搭載内窓「SECOMあんしんうち窓」の販売を開始する。 AGCとセコムは、2003年6月にセンサー機能を内蔵した防犯合わせガラス「SECOMあんしんガラス」を共同開発し、強盗など在宅時の凶悪犯罪への有効な対策として販売してきた。 今回発売の「SECOMあんしんうち窓」は、新たに共同開発した商品で、既存の窓だけでは実現できなかった防犯と快適性を両立するオリジナルの内窓。既存の窓はそのままに、室内側へ一窓あたり約1時間程度の比較的簡単な設置工事で取り付けることができる。 サッシ部分はアルミと樹脂のハイブリッド構造で、優れた耐久性と堅牢性、気密性を実現。また、ガラスは従来の複層タイプの「SECOMあんしんガラス」に遮熱効果のあるLow‐E膜を追加した、新開発の「SECOMあんしんガラス エコ複層(ペア)ガラス」を標準仕様としている。 「SECOMあんしんうち窓」の特長は次の通り。 ①貫通しにくいガラスで、窓からの侵入を防ぐ、②結露を低減して、健康的な生活、③音による暮らしのストレスを低減、④寒さ厳しい冬でも、窓辺を快適に、⑤暑い夏の西日が気にならない、⑥冷暖房費を抑えて、おトクに暮らせる、⑦窓際の家具が、日焼けするのを防ぐ、など。 参考価格(料金例)は、窓の幅1800㍉×窓の高さ1900㍉のもので23万4500円、同2000㍉×1200㍉で19万2200円。いずれも消費税は含まず、「SECOMあんしんガラス エコ複層(ペア)ガラス」を搭載した金額。なお、設置の際の窓まわりの造作工事やカーテンレール移設工事などが必要な場合は、別途料金がかかる。 |
■キッズデザイン賞YKKに総理大臣賞(平成30年10月8日)
|
||||||
|
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会(山本正巳会長)は9月25日(火)、東京・六本木ヒルズのアカデミーヒルズ49で記者発表会を開催し、本年度の「第12回キッズデザイン賞」受賞作252点の中から最終審査した最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞など計33作品を発表した。 最優秀賞(1点)の内閣総理大臣賞には、ファスナーを改良したYKKの「QuickFree」を選出。また、「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」分野では、キッズデザイン協議会会長賞に、ナブテスコの「ナブコ自動ドアNATRUS(ナトラス)」▽東京都知事賞に、日本自動ドアの「自動ドア装置FJ3」▽審査委員長特別賞に、YKK APの「ルシアス・バルコニー」―がそれぞれ選ばれた。 キッズデザイン賞は、「子どもは社会の宝、私たちの未来」を基本理念に、子どもの安全・安心と健やかな成長に役立つ製品、空間、サービス、研究などを顕彰する制度。2007年創設以降の応募総数は4549点、受賞総数は2705点となった。 今回は新カテゴリーとして増加傾向にあった「アプリケーション・サービス」を独立。共働き家庭や妊娠時期をサポートするサービスなど多数の応募があった。 内閣総理大臣賞を獲得した「QuickFree」は、ファスナーのスライダー部品を改良して操作性を向上させ、子どもが独りで衣服を着脱することを助け、親も着せやすくなる。また、左右に一定の力が加わると、ファスナーが開く機能を持つというのが特長。「滑り台の事故などにみられるように、安全面ではファスナーが外れた方が良い場合もあることに気づいたことで、デザインと機能に新たな方向を示した好例」が受賞理由。 キッズデザイン協議会会長賞のナブコ自動ドアNATRUSは、自動ドアに機器間の相互監視、開閉ごとの安全テスト、センサーエリアの高密度化の三つの機能を搭載し、より安全性の高いエントランスを実現。「大手メーカーのスタンダードモデルで実現された社会的効は大きい」が受賞理由。 東京都知事賞自動ドア装置FJ3は、業界で初めてBluetooth機能を標準搭載し、CAN通信にも対応した装置。機器自身がセンサー故障を監視・通知する仕組みを持つ。受賞理由では「安全対策のIoT化へつながる可能性を持っている」と評価された。 審査委員長特別賞のルシアス・バルコニーは、子どものよじ登りやモノの落下防止、掃除性、階下への採光などに配慮した作品。「ベランダの設計という点からの配慮と同時に、実績と機会を生かし使い方を含めた安全啓発運動が幅広く展開されることを期待する」ことを受賞理由に挙げた。 午前10時に開会した表彰式典では、主催側を代表して山本会長(富士通取締役会長)があいさつ。来賓の経産省、内閣府、東京都の各代表者による祝辞の後、各受賞者に賞状が授与された。参会者は式典後、会場後方に陳列された作品を見て回り担当者の説明に耳を傾けた。また、午後1時半からは受賞記念シンポジウムが開かれた。 益田文和審査委員長(オープンハウス代表取締役)は総評で「時代の流れが見えてきたように思う。これまでは子どもを守ることに気を配り、不備がないよう慮ってきた。しかし、今回、子どもたちが高齢者を見守るという逆転の発想や、子どもの安全を考えると大人にとっての問題解決につながるという可能性に出会うことができた」とコメントした。 |
■埼硝協組合員企業が単独で小学校体育館窓ガラス改修工事受注(平成30年10月1日)
|
|||
|
埼玉県板硝子商工協同組合川口支部のガラス店が、川口市立小学校体育館の窓ガラス改修工事を受注し、8月中にほぼ完工、9月下旬から仕上げに着手した。ゼネコンを介さず市発注のガラス工事を組合員企業が直接単独受注したのは初めて。 埼硝協川口支部(清水辰巳支部長・埼硝協専務理事)による市長、市幹部、市教委、議会関係者などへの長年の陳情活動が実を結んだケースとして注目される。平成30年度は下期にも別の小学校体育館の窓ガラス改修工事があり、支部組合員企業が指名競争入札に参加する構えだ。 川口市大字木曽呂にある市立木曽呂小学校の体育館窓ガラス改修工事を落札したのは、支部組合員の山田硝子店(山田正和社長・埼硝協会計理事)。今年6月20日に行われた指名競争入札に5社で応札し受注に成功した。落札額は347万4000円。他の4社のうち3社も組合員企業。最低制限価格を下回る価格で応札した非組合員の1社は失格となった。 工事内容は、従来スクールテンパ4㍉だった体育館の21カ所・134枚の既存の窓ガラスを全て撤去し、「合わせガラスFL3(一部FL4)・飛散防止フィルム・セッティングブロクなど副資材交換」への新設とガラス回りのシーリング充填。 工事で使用する仮設足場は、同時並行で進められた外壁塗装工事用の足場を利用した。1期工事は7月20日から8月末までの夏休み期間中に終了し、9月20日から2期工事にとりかかった。工期は10月31日まで。 受注獲得に尽力した支部組合員で一級建築士の高橋登美雄氏(リョウサン開発営業部長)によると、期間中、複数の川口支部組合員が工事を支援。「支部挙げて運動してきたので、工事が獲れたら皆で応援しようということです」 もう一件、本年度中に体育館の窓改修工事を実施するのは川口市戸塚南にある戸塚南小学校。年内か年明け早々に指名競争入札で発注先を決め、3月の春休み中に施工する予定。予算は500万円程度とみられる。入札には支部組合員企業が再び複数参加する見通し。高橋氏は「市当局に対し組合の事業者を優先してほしいと要望している」と話している。 川口市には52の小学校と26の中学校があり、埼硝協川口支部と主に支部加盟21店で構成する川口市学校施設営繕協力会は、数年来、教室と体育館の窓に高機能ガラスを導入するよう市教委などに要請してきた。 体育館については「災害時に避難場所となるので、安全性に優れた合わせに改修を」と提言。具体的に見本持参で「FL3+飛散防止フィルム+FL3」の採用を求めた。市教委は要望を受けて昨秋に予算措置し議会の承認を経て執行にこぎつけた。一方、組合自身も電子入札に関する勉強会などを開催し、相応の態勢構築に取り組んできた。 今回の受注獲得と施工方法について高橋氏は「ゼネコンなしの受注は画期的なこと。皆さんの3年間の努力が結実した。今後も小中校の窓改修工事が出てくるだろう。市の職員も危機管理意識を強く持って対応してくれた。高く評価したい」と指摘している。 |
■AGC「DEEP THINKスペース」開設(平成30年9月24日)
|
||
|
AGC(AGC株式会社、本社=東京都、島村琢哉社長)は、東京都千代田区のAGC本社オフィス内に、㈱ジンズ(本社=東京都、田中仁社長)が開発した、集中を科学するワークスペース、「Think Lab」とのコラボレーションによる、従業員向け集中スペースを新たに開設したと発表した。そのお披露目会が9月14日(金)、本社34階スカイテラスで多くの報道関係者が集まり開催した。その中で、同社専務取締役CFO・宮地伸二氏が「AGCの働き方改革」について、同社資材・物流部プロフェッショナル高橋正人氏がAGCの動態分析システムアプリ「スマートロガー」について、また、㈱ジンズ「ThinkLab」プロジェクトリーダー井上一鷹氏が「集中が生み出す価値・可能性について」説明、さらに、同社オフィス内に設けられた「DEEP THINKスペース」を見学、体感した。当日の発表内容は次の通り。 AGCは、2016年2月に発表した長期経営戦略「2025年のありたい姿」を実現するため、戦略事業拡大への取り組み等の成長戦略の実行に加え、個々人の力を最大限に引き出すための様々な働き方改革に取り組んでいる。 これまでに、育児・介護に限定しない在宅勤務制度や、コアタイムを設けないフレックスタイム制を導入。またスマートウォッチ・スマートフォンなどにより従業員の動態を分析するアプリ「スマートロガー」を開発。ジンズの開発した集中度・眠気を計測するメガネ型ウエラブルデバイス「JINS
MEME」とのコラボレーションにより、作業の見える化・効率化を実現している。 今般、ジンズの開発した「Think Lab」とのコラボレーションにより、新たにAGC本社オフィス内に、Think
Labのノウハウを採用した「DEEP THINK スペース」を開設した。 この「DEEP THINK スペース」には、ハイレゾ音源による「集中が続きやすい環境」、ヒノキや柑橘系の香りによる「集中に入りやすい環境」など、利用者の集中力を高める様々な工夫が取り入れられており、最高の集中空間により従業員の生産性・創造性を向上する、としている。 宮地専務は業績回復と再成長に向けて、2015年から変革に着手していると述べ、再成長に向けた風土改革として「自ら考え、自ら動く風土」を取り戻し、再成長を果たすと語り、最後に宮地専務は、スカイテラスに最高の集中空間を実現し、生産性と創造性を高め、成長を加速させると纏めた。 質疑応答の中で、運用ルールの説明があり、①事前予約制②コミュニケーションはしない③飲食はしない④寝るのも禁止など、1回あたり最大二時間まで利用できる。回数は無制限。社員なら誰でも利用可能で、オープン時間は朝7時~夜9時まで。土・日・祝は休み。 「DEEP THINK
スペース」のある、スカイテラスには、同社製品のカラーガラス「マテラック」「ラコベル」、それに、防音ガラス「ラミシャット」などが使われている。 |
■山形県ヒートショック対策導入住宅リフォーム総合支援事業が好調(平成30年9月24日)
|
|||
|
山形県の「住宅リフォーム総合支援事業」が好調だ。平成30年度は新規に「ヒートショック対策」を導入し、開口部の断熱化と浴室、トイレなどへの暖房機器設置を重点項目に据えた。予算規模は7億円。8月中旬までに6割方を執行した。 同事業は、県住生活基本計画に基づき、県土整備部建築住宅課が28年度から運用を開始した。県独自の事業だが、運営主体は県下の全市町村というユニークな制度。 自宅をリフォームしたい人は居住地の役所に補助金を申請する。担当部局が受け付けて審査・決定し、工事完了後に補助金を交付する。その後、県当局が実額を当該市町村に補填する仕組みだ。 対象工事(要件工事)は、耐震改修、減災・部分補強、ヒートショック対策(寒さ対策・断熱化)、克雪化、三世代同居リフォーム、バリアフリー化、県産木材使用―七つの部門で構成。 うちどれか一つの内容で、かつ県の健康住宅認証制度(末尾参照)で定める基準点が10点以上の工事が助成の対象となる。 29年度までの「省エネ化」項目を見直し、一般リフォームタイプのメインに掲げた「ヒートショック対策」は、①健康住宅認証を受けた改修②開口部の断熱性を高める二重建具や複層ガラスを設置する③熱交換システムを設置する④外壁、天井、床に断熱材を使用する⑤浴室・脱衣所・トイレ・廊下に設備工事を伴う暖房機器を設置する―五つの要件工事から成っている。 県の補助金額は、5要件工事のいずれか一つの工事(例えば、内窓設置、外窓交換、カバー工法、ガラス交換など窓のリフォーム工事)で、補助率10%、上限20万円。別部門の耐震改修は25%、40万円に設定している。 市町村によっては同事業の上限に上乗せする自治体もある。また、自治体独自のリフォーム補助金との併用も可能としている。 県住宅建築課によると、平成29年度は6億5000万円の予算枠の9割超が現行のヒートショック対策とバリアフリー化に充てられた。本年度は予算戸数3720戸に対し、8月15日時点で総計2000戸を超える申請が各市町村に寄せられ、うち半分以上がヒートショック対策という。 同課住まいづくり支援主査の上田健一郎さんは「先着順なので酒田市や天童市など大きな自治体は既に受付を終了しました。鶴岡市も7割程度。最大の山形市は抽選方式を採るようです」と話している。 ヒートショック対策強化には、山形県内での住宅内でのヒートショックによる死者が年間200人以上と交通事故死の4倍超に増大したことが背景にあるという。同課建築物耐震化主査の大泉明子さんは「酒田、鶴岡など豪雪地帯を抱える庄内地区では交通事故の9倍にも上ります。断熱化などで室温を10℃以上に保つ必要があります」と指摘している。 新機軸のヒートショック対策については山形県サッシ・ガラス協同組合(西塚和彦理事長)が導入をめぐって陳情活動を展開。こうした努力が奏功した面もあるようだ。 一方、29年3月改訂の県住生活基本計画によると、県は産業振興の視点から住宅リフォーム総合支援事業を来年度以降も継続し、計画最終年度となる37年度までの10年間に、住宅リフォーム市場の規模を28年度の415億円から520億円に拡大する方針だ。 ◇ |
■東京都豊島区エコ住宅普及促進費用助成金交付申請31年1月31日まで(平成30年9月10日)
|
||
|
「窓は断熱効果が大きい」―。東京の繁華街・池袋がある豊島区は、平成29年度から「エコ住宅普及促進費用助成金」の対象機器の中に、新規に「一般住宅・断熱改修窓」を導入。市民の反応は上々で、初年度は予算をほぼ100%消化した。 この助成金は、地球環境の保全を目的とし、CO2削減に配慮した住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器を導入する区民に対し、設置費用の一部を補助する制度。 対象機器は、一般住宅用が、太陽光発電システム、自然循環式太陽熱温水器、強制循環式ソーラーシステム、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、雨水貯水槽、エネルギー管理システム(HEMS)と断熱改修窓。 集合住宅共用部分用が、太陽光発電システムと29年度から新規にLED照明器具を加えた。 助成対象は豊島区に居住する個人だが、施工は区外の業者も認めている。平成30年度の交付申請受付期間は4月2日~31年1月31日まで。先着順で、予算を超えた時点で受付を終了する。 本年度の予算枠は29年度と同じ1146万円。8月2日時点の執行率は43.1%となっている。 窓関係は戸建てと集合住宅個別が対象。内容は内窓設置、ガラス交換、外窓交換のどれでもOKだ。熱貫流率は問わない。 助成金額は、断熱改修窓は設置費の4分の1で上限10万円。太陽光発電システムは出力1kW当たり2万円で上限8万円。LED照明器具は設置費の5分の1で上限20万円。エネファームは一律8万円―など。 事業を所管している豊島区環境政策課によると、29年度の交付実績はエネファームが「飛び抜けて多かった」。次いでLED照明器具。窓は21件の3位で予算ベースでは全体の1割程度だった。 同課環境政策担当係長の冨樫由美さんは窓の申請状況について「当初は周知が行き渡らず伸び悩んだが、結果的には思ったより申請が多かった。本年度は他のアイテムよりぐんと動きがある。昨年度以上になる見通しです」と分析。 断熱改修窓を加えた背景については「例年、対象機器の見直しを行っているが、『断熱性という点では窓の効果が大きい』との結論に達したため」と指摘している。 一方、冨樫さんによると、区の事業担当者は、板ガラス卸・販売のマテックス(本社・東京都豊島区)が主導する「エコ窓普及推進会」と交流し、推進会主催の説明会などに職員を派遣して断熱窓などの情報収集に努めているという。 区環境政策課とエコ窓普及推進会は今年7月29日、豊島区役所1階センタースクエアで開かれた「としまエコライフフェア」に出展。普及推進会は「豊島区にもっとエコ窓を!」と呼びかけ、パンフレットにも「豊島区は窓リフォームの補助金制度を実施しています!」と記載し有効活用を側面からアピールした。 |
■仙台市窓の断熱改修が急増「Let’s 熱活!補助金」(平成30年9月10日)
|
||
|
宮城県仙台市(人口約109万人)では、「市熱エネルギー有効活用支援補助制度」を利用して窓のリフォームに取り組む市民が急増している。平成29年度は年度途中の10月末で申請受付を終了。30年度も年内に予算枠に達する勢いだ。 仙台市環境局環境部環境企画課が事業主体の通称「Lets 熱活!補助金」は、地球温暖化対策推進事業の一環として28年度から始まった。窓断熱改修または熱エネルギーを活用するシステム導入を支援する。 補助金額は、窓断熱改修(内窓設置、外窓交換、ガラス交換)が1カ所または1枚当たり2000円~2万円で1棟当たりの上限額は10万円。エネファームは15万円。太陽熱利用システムは上限3万~12万円。地中熱利用システムは上限50万円。 窓改修の要件は、「同一居室内の全ての窓の断熱改修を推奨する」と緩やかだ。補助額は、外枠やガラスの面積、熱貫流率の値に基づいて9種に分類している。 内窓設置ないし外窓交換で熱貫流率2.33以下、面積2.8㎡以上の場合は1カ所当たり最高の2万円を交付する。1.6㎡以上~2.8㎡未満は1万4000円。熱貫流率3.49以下、面積2.8㎡以上は1万8000円。1.6㎡以上~2.8㎡未満は1万2000円。 窓枠は変えずにガラスを複層ガラスなどに交換するケースでは、熱貫流率3.49以下、面積1.4㎡以上は1枚当たり7000円。熱貫流率は同じで面積が0.2㎡以上~0.8㎡未満の場合は最低の1枚当たり2000円となっている。 補助対象者は、仙台市内に住宅を所有しているか、所有予定の人もしくは建売を購入する人。事業所も対象に含んでいる。募集は先着順で、本年度の募集期限は来年1月31日まで。期限以前に予算額に達した場合は申請受付を打ち切る仕組みだ。 30年度の予算額は前年度比400万円増の3800万円。執行率は7月末時点で30%強に上っている。 29年度の実績をみると、総交付件数366件のうち「窓」が250件と過半数を占め、次いでエネファームの109件。あと太陽熱関係の2件など。窓は28年度もトップで127件だったが、昨年度は倍に急上昇した。窓改修では内窓が大半で、ガラス交換は少ないという。 環境企画課によると、昨年度は10月末で予算残高が約100万円と少なくなったため、その時点で申請を打ち切りにし抽選方式に切り替えた。 |
■新光硝子工業新生ガラスを買収 末永孝光氏(新光硝子工業専務)が社長就任(平成30年9月3日)
|
||
|
曲げ硝子の加工を柱とし、60年以上積み上げてきた確かな技術力で全国的に商業用施設やオフィスビル、美術館など著名建築を手掛け、ビル建材・内装・ケース・車輛用とあらゆる市場において高い評価を受けている新光硝子工業㈱(本社=富山県砺波市、新海伸治社長)は、今年7月に富山市に本社を置く新生ガラス㈱(旧真野ガラス)の株を100%取得し、完全子会社化したと発表した。新生ガラスの栗本三行社長(栗本氏は岐阜に本社を置く栗本建材㈱の社長を兼務)は退任し、新光硝子工業・専務取締役の末永孝光氏が社長に就任した。そこで、今回は新光硝子工業の本社を訪問。新海社長と末永新生ガラス社長のお二人に登場をお願いし、買収の狙いなどを聞いた。新海社長は「両社の強みを活かし、不足する部分を補完し合うことでシナジー効果を高め、お客様により高品質・高付加価値の製品を生産していきます」と話してくれた。 ――買収の話はどちらから? 新海 実質的に。新生ガラスの経営を見てきた方が高齢となり、その代わりとなる人物を岐阜から派遣するのは大変ということで、後継者がいない状況となったようだ。それで栗本氏の方から話が持ち込まれた感じです。 ――新生ガラスは、以前は真野ガラスで住宅用分野が強かったと記憶しています。逆に新光硝子は商業用ビルが強いと思っているのですが。 末永 住宅用とかビル用とかのくくりで考えたことはありません。新光硝子工業として、次の一手として何をやるかということを中期経営計画の中で議論していました。その時に、強化ガラスが伸びているということでそこをターゲットにしていました。新生ガラスが作った強化ガラスに新光硝子工業が強みをもつ合わせガラスに加工していく。より強い強化合わせガラスを生産していきます。 ――自社で強化ガラスのラインを設備投資をするということは? 末永 それも検討しました。しかし、機械だけあっても人がいないと動かせません。どうしようかと考えている時に今回のお話をいただきました。 ――新生ガラスには40人の従業員もいると聞きました。 新海 人手不足の時代にそれも大きいと判断しました。 ――人事の交流は? 新海 私も代表権のない会長として新生ガラスに加わります。監査役には舘良成・新光硝子工業取締役が就きます。 末永 新生ガラスから新光硝子への異動はまだ一緒になったばかりですので、それは考えていません。 ――設備の移動は? 末永 それも今までどおりで、移動は今のところ考えていません。 ――真野ガラス時代の負の遺産は 末永 民事再生法に則り進めていました。今では、何も残っていません。 ――新生ガラスとして関東への進出は 新海 それは考えていません。新生ガラスが作ったものは、新光硝子工業経由で関東へ納品していく予定です。 ――買収金額は。 新海 公表していません。 ――目標は。 新海 売上は両社合わせて20億円。利益率は新光硝子工業からの目標である5%以上をターゲットにしています。 ――大いに期待しています。ありがとうございました。 新光硝子工業は従業員数75人で2018年3月期の売上高は約11億円、新生ガラスの従業員数は約40人で2017年12月期の売上高は約6億5千万円だった。 |
■濱田特殊硝子常務の濱田真輝氏が社長就任
|
||
|
1918年(大正7年)5月に大阪市西区北堀江の地に濱田商店を設立以来、今日に至るまで育まれた伝統と、絶えず新しいことにチャレンジする精神「CHANGE
FOR THE BETTER」をモットーに挑戦してきた濱田特殊硝子㈱(本社=大阪市平野区)は、今年100周年を迎えたのを機に社長を交代。これまで、社長を務めてきた濱田陽右氏が代表取締役会長に、常務の濱田真輝氏が代表取締役社長にそれぞれ就任し、7月より新しい体制でスタートした。今回は、同社本社を訪ね、両氏にお話を伺った。濱田陽右会長は「脱建築から15年かかって、やっと自分の思った形に近づいた」と語り、一方、濱田真輝社長は「これから新しい分野にチャレンジしていきたい」と力強く抱負を語った。 ――このたび100周年を迎えられましておめでとうございます。 会長 ありがとうございます。私が社長に就任したのは1991年(平成3年)6月で、私で3代目になりますので、息子は4代目になります。 ――100年の中でいろんなことがあったと思いますが、陽右会長が社長になってからの一番の思い出は? 会長 今から25年前私が社長に就任したころは、売上構成比を見ると75%がサッシとガラス工事。特殊ガラスは25%ぐらいでした。その時、会社の中で、どういう方向で会社を進めていこうか、今後の生き残り策を話し合った。「本業に立ちかえってやるのが一番ではないか」と私が提案。これからは脱建築(建築用は、売上高は大きいが利益は少ないから)で特殊ガラスに特化していこうということになった。完全に変わるまでには15年を要しました。 会社案内にも書いていますが、「本業を離れるな」「本業を続けるな」「本業の中身を変えろ」を合言葉にしています。 ――真輝社長が入社したのは? 社長 2002年(平成14年)です。将来はこの会社の社長になるつもりで入社しました。 ――会社に入った時の感想は。 社長 こんなものかなと思いましたが、入社するのを辞めておけば良かったとは思いませんでした。 会長 自分が社長になった時はかなりきつかったが、息子が入社したころから会社は上向きになりはじめました。 ――きつかったというのは? 会長 当社が仕事をさせていた下請け企業に引っ掛かってしまい、多額の借金を抱えてしまったことです。そのマイナス分をほとんど返し終えたのも最近のことです。 (建築用の)仕事を辞めるのは簡単ですが、しかし、それでは、お金が回らなくなります。資金繰りを考えながら、徐々に縮小していくことにしました。一番きつかった時は、売上高は一時の半分以下になってしまった時です。 ――特殊ガラスに移行できたのは。 会長 先ほども申し上げましたが、下請けの会社を潰してしまいました。当時は、特殊ガラスの加工はほとんど下請けに任していました。下請けは多い時で80社ほどありました。それで、倒産した下請けの社員や機械を自分で引き受け、ガラスの倉庫に加工工場を作って、内製化をはじめました。 ――技術的な不安は? 会長 当然ありました。知っている人間はほとんどいません。自分は昔修業していたこともあるので、少しは経験がありましたが、一から勉強しました。ここまで、特殊ガラスが伸びたのは下請け企業のおかげだと思っています。 ――今後については 社長 他社ができないこと、やらない分野を増やしていきたいです。社内的には、自動化、省力化を進めたいです。具体的な内容については、できてから発表します。 会長 少量、多品種かつ高品質な分野をターゲットにしています。 とにかく、私どもが売りたいものを売っているのではダメです。お客様が売って欲しいと思っている商品を売らないとダメだと社員には言っています。 ――ありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 ☆濱田真輝社長のプロフィール 1978年(昭和53年)3月生まれ。40歳。大阪府出身。大阪芸術大学卒。奥様とお子様二人の4人家族。趣味はゴルフ。 |
■経産省・S I I 次世代省エネ建材支援事業(平成30年8月27日)
|
||
|
経済産業省は平成30年度当初から新規に始めた「次世代省エネ建材支援事業」の2次公募に当たって申請要件を大幅に緩和した。事業を執行する環境共創イニシアチブ(SII)は8月1日から公募を開始した。先着順で、期間は9月14日(金)まで。予算は1次公募と同じ3億円程度とみられる。 同事業は既存住宅を対象に、短工期で施工可能な「断熱パネル」や「潜熱蓄熱建材」などを導入するリフォームに対し補助金を交付する制度。補助率は対象経費の2分の1以内。補助金額は1住戸当たり戸建てが最大200万円、集合住宅は125万円。 居室に導入必須な製品である断熱パネルまたは潜熱蓄熱建材を施工する場合に限り、任意製品として「玄関ドア」、「窓」、「ガラス」、「調湿建材」の同時改修も補助対象としている。1次公募は5月28日~6月29日の期間で実施した。 SIIによると、2次公募では、補助金の下限額を1住戸当たり20万円(補助対象経費の合計は40万円以上)に下方修正した。1次では40万円(同80万円以上)だった。小規模な改修も補助対象とした格好だ。 対象となる任意製品については、新たに、断熱リノベ事業に登録されている「断熱材」を追加。また、導入必須製品の要件を満たせば、他の居室に導入する任意製品も補助対象に含めるとした。 必須製品についても一部要件を緩和し、「外気に接する一部屋の床・壁・天井のいずれか一面」に導入すればOKとした。施工面では、「既存の床・壁・天井を撤去せずに室内側から施工すること」としていたのを、「下地補強や、耐荷重強度を担保するための内装仕上げ材の解体・撤去でも可能」と改めた。 公募方法については、期間中に応募のあった物件を締め切り後にまとめて審査する「公募採択式」から、順次審査する「先着順」に変更。公募期間も1カ月半と1次の時より長めに設定した。 こうした申請要件の緩和は、1次公募の応募件数が当初の想定を下回ったためとみられる。事業主体の経産省当局は「新規事業なので業界への浸透がいまひとつ」と分析している。 一方、必須・任意ともに製品そのものの要件は据え置いた。 窓については、カバー工法用製品か内窓設置が条件。ガラス交換は「既存の窓・ドアフレームは木製もしくは樹脂製、または木と金属の複合材料製もしくは樹脂と金属の複合材料製」と規定している。 熱貫流率について経産省製造産業局生活製品課住宅産業室は「窓の場合、1.9以下が条件。従って自ずとLow―E複層ガラスの導入となる。ガラス交換のみの場合、フレームが木製ないし樹脂製は1.3、複合材料製では0.93と高く設定しています」(今福幸一係長)と説明している。 事業全般について同住宅産業室の中野亮係長は「リフォームは壁を一回壊したりするので仮住まいが必要。消費者には経済的、心理的負担が大きい。本事業では仮住まいをしなくてもいいように敷居を下げた。窓でいえば内窓かカバー工法に限定した。サッシを取り替えずにすみます。新しい施策で省エネリフォームの裾野を広げていきたい」と積極的な活用を呼びかけている。 |
■新役員に聞く神硝協青年部会長山下裕一氏(平成30年8月27日)
|
||
|
今年6月5日に開催された神奈川県板硝子商工業協同組合(神硝協)・青年部の総会で、新しく青年部会長に就任した山下裕一氏(横浜サンミラー㈱代表取締役社長、横浜市都筑区)。 山下新会長に、抱負や現状の課題などを聞いてみた。 ――新会長就任おめでとうございます。早速ですが、ご就任の経緯からお聞かせください。 山下 35歳で会社を継ぎました。会社は組合に加入していたので、その流れで青年部にも参加することになりました。最近では、副会長を2期4年務めていましたが、今回、会長にとのお話を頂きました。鏡組合にも加入しているので、会長は遠慮したかったのですが、皆さんから推薦していただいたこともあって、受けることにしました。 ――続いて、現在の青年部の状況を教えてください。 山下 現在、青年部員は13名です。部員は減っています。我々の青年部は50歳で卒部するルールがあり、来年1名卒部されます。私自身も47歳なので、卒部が見えてきています。以前、卒部の年齢を55才に引き上げてはどうかとの案もありましたが、問題の先送りでしかないため、廃案になりました。 ――やはり、部員の減少は大きな問題になっているのですね。 山下 そうなります。そこで、今後の青年部の強化に向けて、3つほど考えています。1つ目は、親組合に加入している会員さんの息子さんで、青年部に入られていない所には、必ず青年部に加入してもらうことを考えています。青年部に入ってもらうことで、手が足りない時の助け合いや、技術のやり取りが出来ることはメリットになると思います。2つ目は、ガラスに関連するフィルム屋さんや、工事店さんなどにも、賛助会員のような形になるかもしれませんが入ってもらおうと思っています。3つ目として、神奈川には、神硝協から独立した「川崎市のガラス組合」があります。30~40年前に分かれたらしいと聞いていますが、その川崎にも青年部があるらしいので、8月中にも親睦を兼ねた情報交換会を開催しようと打診しています。一緒になることは難しいかもしれませんが、交流を深めることをやっていきたいと考えています。 ――交流が進むのは良い事ですね。 山下 決してマイナスになることではないと思っています。この3つを柱にやっていけば、人が減ることはないだろうと、ずっと減り続けていたので、今年は絶対に増やしていこうと思っています。「増」と「強」を進めてゆき、みんなで仲良く、他の都道府県とも交流を図りながらやっていけたら良いなと考えています。 ――人が増えれば青年部もより活発になると思います。各地域の青年部との交流も、青年部加入のメリットになりそうですね。最後に、少し会社のお話をうかがいます。社内にも色々と飾られていますが、サッカー・J1リーグの湘南ベルマーレのスポンサーをされていると伺っています。 山下 縁があって、オフィシャルパートナーをしています。今年で3年目になります。ホームスタジアム(Shonan BMW スタジアム平塚)のスタンドにバナーを掲出しています。昨年、ベルマーレがJ2優勝をした際の記念写真にも、バナーが写っています。私のパソコン壁紙にしています。 ――先日の試合(取材日は7月26日)でも、大型補強をしたクラブを相手に勝利されていました。 山下 あの試合は痛快でした。あのような試合を見たいものです。 ――スポンサーをされているチームが活躍すると、楽しみが増えますね。今日は、お忙しいところ、ありがとうございました。 |
■全硝連東北地区本部防災安全ガラス寄贈工事(平成30年8月6日)
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)の東北地区本部(袴田恭司本部長)は、7月28日(土)~29日(日)および8月7日(火)~9日(木)の計5日間、宮城県石巻市の市立蛇田中学校で「防災安全ガラス寄贈工事」を行った。 今回の工事に使用した防災安全ガラスは、機能ガラス普及推進協議会が寄贈したもので、防災安全ガラス140枚。ガラスはAGC㈱が、中間膜を積水化学工業㈱がそれぞれ提供し、現場配送はテクノグラスサービス㈱(仙台市宮城野区、清水典之社長)が行い、副資材はフヨー㈱仙台支店と㈱ダイドー仙台支店が提供している。施工は宮城県板硝子商工協同組合が中心となって行い、東北板硝子卸商業組合、東北板硝子工事協同組合も協力している。 工事初日の28日は、日本列島に台風が近づいている影響からか、雲が多く風の強い天候にもかかわらず、宮城県板硝子商工協同組合(以下、宮城県協組)から30名が参加し、工事を行った。 体育館2階のギャラリー部分と、1階のトイレの窓ガラスの交換が行われ、ガラスの大きさは、W878㍉、Hは560㍉~1160㍉。上下2段の引違い窓に、ボールなどがぶつからないための対策なのか、鉄製の重い格子が取り付けられていた。サッシも体育館開設当初からのもので、ガラスはフロート3㍉が入っていたほか、引違いの片側に木製の枠に網を取り付けた網戸がはめ込まれており、時代を感じさせるものだった。 大友利彦理事長の話では、「青年部が積極的に動いて人を集めてくれた。朝の集合は8時20分だったが、一部の人が7時過ぎから現場に入ってくれ、養生や窓に取り付けられていた格子を外すといった作業を率先して行ってくれたので、スムーズに作業に入れている」とのことだった。 宮城県協組の理事で機能ガラス普及推進協議会にも所属する山田光彦氏(山三建硝㈱社長)の話によると、「今回の寄贈工事の現場となった蛇田中学校体育館は、詳細は分からないとしながらも、おそらく昭和の終わりから平成の初期に建てられてものだろう」とのことで、「ガラスは単板ガラスが多いが、過去に何度もガラスの割れ替えが行われているようで、校庭に面している部分には一部強化ガラスが、校舎に面している部分には網入りガラスなど防火ガラスが約40平米ほど入っている。強化ガラスは、過去の割れ替えの際に、例えば野球のボールが当たっても割れないように、当時の業者が勧めたのではないだろうか。このため、今回交換するガラス140枚のうち、約40枚は強化合わせガラスになっているし、網入りガラスなどの一部は交換を行わないことになった」とのことだった。 大友理事長も「ガラスを交換するかどうかの判断も含めて青年部が行ってくれた。青年部が積極的に動いてくれるので、非常に助かっている」と話す一方、「多くの組合員に動いてもらっている。組合としての持ち出しも大きいので、ガラス運搬などでの協力や、幾らかでも補助的なものがあれば変わってくるが……」と、工事の難しさを話していた。 なお、当日は地元紙の河北新報が取材に入っており、山田氏によると「大伴理事長が、工事の概要を持って地元のマスコミを訪問、説明をしてきてくれた」とのこと。 また、今回の寄贈工事に伴う寄贈式は、10月9日(火)に石巻市役所で行われ、その後蛇田中学校で安全ガラスの授業が行われる。授業には全校生徒約600人が参加する大規模なものになるとのことで、今後授業のやり方や機材などを検討しなければならないとのことだった。 |
■関西卸理事長斉藤洋介氏新役員に聞く(平成30年8月6日)
|
||
|
今年5月に開催された関西板硝子卸商業組合の総会で新しく理事長に就任した斎藤産業㈱代表取締役社長の斉藤洋介氏。今回は、兵庫県姫路市にある斎藤産業㈱の本社を訪問。斉藤理事長に新理事長としての抱負や現状組合として抱えている問題や課題等を聞いてみた。 ――今回の役員改選では、斉藤理事長を始め、新副理事長に村島靖基氏(村島硝子商事)と安藤康隆氏(山田硝子店)が就任されるなど役員が若返りました。これからの組合の運営をどのように図っていきたいと思っておられますか。 斉藤 皆さんと同じ考えだと思いますが、理事長としては、機能ガラスの普及をもっと図りたいと思っています。一般消費者の方に機能ガラスというものをもっと知ってもらいたい。この間の板ガラスフォーラムでも全硝連さんからお話が出ておりました「ガラスの日」の制定についても、一般消費者に機能ガラスの存在を知らせる一つの手段でもありますし、もちろん、我々流通だけでPRすることには限界がありますので、そこは、メーカーさんにも協力していただきたいと思います。 メーカーさんのお仕事は、良い商品を作ること、それをアピールして一般消費者の方に認知していただく。我々流通は、それを刈り取っていくというのが前提だと思っています。 当然、我々流通としてもPR活動はやっていきます。また、やらなければなりません。その手段・方法については、いろいろあり、検討していきたいと思います。 ――学校に業界をあげて、機能ガラスをアピールしているところですが、本当に知らない方が多い。残念ながら、未だに網入りガラスを防犯目的だと思っている先生方がいます。 斉藤 これが悔しいですよね。 ――役員が若返りましたが、組合の事業、運営は? 斉藤 今まで諸先輩方々がおやりになってきたこれまでの事業を急に変えて行くつもりはありません。これまでにやってこられた、景況感アンケートなど継続してやっていく予定です。 ☆ ☆ ☆ 関西板硝子卸商業組合平成30年度の活動計画 (1)総務・教育関係 ①経営課題についての共有化促進 ・景況感アンケートの継続と定着 ・方針アンケートの充実と定着 ・経営課題についての都度議論 ②経営課題についての研修 ・全員協議会での講演会の開催、場合により見学会の実施 ・合同研修の規格 (2)調査委員会 ①3組合(大硝協、関西工事、関西卸)合同安全大会 ②関西板硝子業界G6の活動 ・会議関係、行事計画など (3)福利厚生事業 ・ゴルフ、ボウリング、新年互礼会、永年勤続表彰など ☆ ☆ ☆ ――新築が減少するなかで、リフォームが注目を集めています。確かに水回り関係は効果がでているようですが、窓廻りについては苦戦しているようです。このあたりについては…… 斉藤 我々窓の業界としては、国や多くの地方公共団体が行っている補助金制度の活用ですかね。内窓の取付とか断熱複層ガラスへの取り換えとか、当社では、規模は小さいですが、マンションの個別改修にも取り組んだりしています。 リフォームの場合、今までのルートだけでなく新しい取り組みも必要になってきています。 ――マンションの大規模改修は一企業レベルではハードルが高いかもわかりませんが、組合単位で役所に働きかけることも必要では? 斉藤 エンドユーザーへの働きかけも大事ですが、同時に、行政に働きかけて行くことも必要ですね。いろいろアプローチの方法はあるかと思います。 また、マンションについてはリフォームだけでなく新築についても、建材メーカーさんが窓ごと受注するケースもでてきています。それに対して我々流通がどのように対処していくか、考えなければなりません。 ――後継者の問題については。 斉藤 皆さんのところも同じだと思いますが、取引先の代表者の方の年齢が60歳以上の方が多いかと思います。後10年もしたらどうなるか……ご子息さんがいても、自分から継いで欲しいとよう言わないし、息子は継ぐといっても積極的には勧めない。工務店さんをたくさん抱えている販売店様も少なくなり、後の事業を大きなところが引き継いでやるというのも難しいところがあり、悩ましいところです。個人商店のようなところは、引き継いでくれるところもないような状況です。とにかく業界として利益を出して、人に投資できるようにならないと解決できません。 ――後継者のいない個人企業のようなお店は自然に消えて行くかもわかりませんね。業界ではこの先、人手不足が心配という声も聞かれます。女性の採用などの検討は? 斉藤 そうですね。若い人が3Kのこの業界にはなかなか振り向いてくれません。外国人の採用などその受け入れ体制も含め検討していかなければならないと思います。 ――その他には。 斉藤 業界ですすめているキャリアアップシステムについても積極的に協力していきたいし、先ほどお話した「ガラスの日の制定」についても応援したいと思っています。 斉藤洋介理事長のプロフィール 昭和48年(1973年)7月生まれ。45歳。兵庫県姫路市出身。27歳の時建材メーカーに。3年後斎藤産業に入社。家族は3人。趣味はゴルフ。ハンデ19。 |
■校舎の窓改修を受注墨田区立中の3校(平成30年7月23日)
|
||
|
東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)加盟の板ガラス店3社が墨田区立中学校3校の校舎の窓改修工事を随意契約で受注した。7月中に発注元の区教育委員会と正式契約を交わし、8月の夏休み期間中に工事を完了する見通しだ。 平成30年度上半期の改修工事を請け負ったのは、都硝協本所支部所属の㈲内田ガラス店、㈲鷲尾硝子店と向島支部の㈱ママダ建装の3社。 区教委庶務課によると、工事名称は「ガラス飛散防止対策その他改修工事」で、内容はフィルム貼付、強化ガラスへの置き換えのほかサッシを含む窓交換も含むとしている。 内田ガラス店は本所中学校(墨田区東駒形三丁目)の改修を約1100万円で受注。鷲尾硝子店は錦糸中学校(同区石原四丁目)を約1300万円で、ママダ建装は寺島中学校(同区八広一丁目)を約1900万円でそれぞれ受注した。 学校の窓改修関係では3社とは別に、区内の元組合企業1社が今期、梅若小学校(同区墨田二丁目)の飛散防止工事を請け負っている。 内田ガラス店、鷲尾硝子店、ママダ建装の3社は29年度下半期にも中学3校体育館の窓改修工事を500~700万円で受注し、今年3月の春休みに施工した。 墨田区の公立小全25校と公立中全10校の窓改修事業は26年度からスタート。都硝協本所、向島両支部による区長、区議への陳情活動などが功を奏し、初年度から地元の組合員企業が事業に参入している。 これまでの施工実績を反映し、区教委は下半期以降も地元ガラス店への特命随意契約での発注を継続するとみられる。 |
■愛硝協理事長太田吉則氏 新役員に聞く(平成30年7月23日)
|
||
|
5月に開かれた愛知県板硝子商工業協同組合(愛硝協)総会で第12代理事長に選出された太田吉則氏に現状や今後の展望などを聞いた。 ―既に2カ月が経過した 太田 理事長に就任し、はや2カ月が経過しました。その間、理事会を2度開催し、少しずつペースが分かってきたというところです。 しかし、理事会を開催するにしても資料作りをはじめ、必要な準備が多々あるなど、故・岡田守浩前理事長のご苦労、まだ偉大さを感じている次第です。まだまだ、私は組合員各位への連絡だけでもばたばたとしている状況です。 昨年より機能ガラス推進協では安全ガラスの寄贈などの活動を行っており、このエリアでは名古屋市の教育委員会を訪問するなどの活動を行いました。 名古屋市は建築物の大規模改修を行う際に、安全ガラスを使うよう指針があり、勧めています。近年、地震だけでなく水害など多くの災害が頻繁に発生しており、ガラスの安全・安心は多くの市民に望まれています。災害対策としては、ウインドウ・フィルムを貼るという方法もありますが、耐用年数を過ぎると劣化し、将来の貼り替えが必要な事もあり、ガラスの交換が必要という見解のようです。合わせガラスの高い機能性が少しずつですが知られるようになってきたのではないでしょうか。 ―災害が増加。ガラス小売りのできることとは。 太田 今年に入ってからも北大阪地区での地震、西日本の広い範囲で被害が起こった水害などを思うと、われわれが貢献できる分野は少なくないと思います。災害に遭った方々には心からお見舞い申し上げます。 愛知県には昔ながらの、町のガラス店が多くあります。私どもの会社もその中の1社です。地元に密着し、地域に貢献することが長く続くガラスへの需要を獲得し、施工への信頼を得る道であると思います。愛硝協の多くの会員も同様に、施工技術と地域貢献で今後も長く続けて頂きたい。メーカー、卸、工事がそれぞれの立場でガラス業界に貢献している。小売りもその一員でありたいと願っています。「愛知県の小売りは頑張っている」という声をかけて頂けるよう、理事長として努める決意です。 ―岡田理事長は3期6年近く務められた。 太田 岡田前理事長は3期6年の間、多くの変革を成し遂げられました。コストの削減により組合としての収支も改善しました。 しかし、5年先、10年先を考えますと、組合員の高齢化がさらに進むでしょう。業界を引退される方も出て来るでしょうから、そのための組合としての準備も必要になります。また、入会者を増やすことが必要です。今後はガラス小売りだけでなく、隣接業界でガラスを取り扱う業種にも声をかける必要が出て来るかもしれません。 愛知県は物作りの町です。職業訓練校にはここ数年、10人を超える生徒が入校しています。しかし、技能検定では受験者数に比べ合格率の低下が課題です。卸、工事とも協力して合格率向上に努めます。 また、できるだけ多くの組合員が参加できるイベントを設けたい。組合員の交流を密にして、より良い組合運営を実現したいと思います。 |
■山形市立小学校2校を組合企業2社が受注(平成30年7月9日)
|
||
|
山形県サッシ・ガラス協同組合(西塚和彦理事長)傘下の山形市のガラス店2社が、山形市発注の市立小学校2校のエコ窓改修事業に応札し受注に成功した。6月中に契約を締結。7~8月の夏休み期間中に一部工事に着手する。 組織内に「エコ窓推進事業部」を立ち上げ、市に対し地域住民の避難所ともなる公立学校施設の窓を安全かつ省エネ・断熱効果のある窓に切り替えるよう繰り返し呼びかけてきた県サッシ・ガラス協同組合の陳情活動が実を結んだ形だ。 市教育委員会は学校施設整備計画に基づき、市内の小中高計51校の全校校舎の窓を段階的にエコ窓に改修するプロジェクトを策定。平成24年7月から4カ年で蔵王温泉スキー場の麓にある市立蔵王第三小・第二中併設校校舎の窓に内窓を取り付ける改修工事を実施。27年7月からは6カ年計画で蔵王第二小などのエコ窓改修を始めた。 27年度以降も蔵王併設校、蔵王第二小を含む1級積雪寒冷地(2月の積雪50㌢以上、1月の気温0℃以下)にある小中6校について、Low―E複層ガラスへの交換か内窓への改修工事を順次スタートさせている。 本年度に組合員企業が受注した学校の窓改修は、山形市立みはらしの丘小学校と継続事業である蔵王第二小学校の2件。造成新興住宅団地の一角にある、みはらしの丘小は校舎増築に伴う既存校舎の窓改修。防火窓の設置がメインで受注額は1250万円。蔵王第二小は内窓設置で受注額は440万円。 市当局が寒冷地を中心に学校施設の窓断熱改修に踏み切ったのは、県サッシ・ガラス協同組合によるエコ窓寄贈がきっかけとなった。組合は22年、蔵王併設校の教職員室と教室の2カ所に組合が掲げる「エコ・スクール整備構想」のモデル事業として内窓を寄贈した。 県組合はその年の冬期、施工した部屋の断熱・省エネ効果を独自に計測・検証し、「内と外との温度差は12℃」との実測値を市教委に報告。翌年度以降の全面改修事業につながった。 県組合は昨年8月、山形県本庁舎の総務部長室にも内窓を寄贈。その後冬期、夏期に断熱実証実験を実施。シミュレーション結果を近く県当局に提出する方針だ。前理事長の須藤氏は「県議、市議とも交流を続けている。県全域に安全防災ガラスが浸透するよう努力していきたい」と話している。 こうした県サッシ・ガラス協同組合が行った学校施設などへの内窓寄贈と断熱効果の調査・検証は内外に高く評価され、昨年秋の「ストップ温暖化⁄エコカップやまがた2017」では活動事例団体の一つとして表彰され、組合の布施英夫専務理事とエコ窓推進事業部長の五十嵐慶三副理事長の2氏が壇上で活動内容を報告した。 今年6月5日に山形市で開催された山形県地球温暖化防止県民運動推進大会では、県組合が応募した「エコ窓改修によるCO2削減効果の検証」が県環境保全協議会による環境保全推進賞の選考委員特別賞を受賞した。 |
■グラス・ラップ社「グラス・ラップ」の輸送実験 浜新硝子佐賀工場で実施(平成30年7月9日)
|
||||||||
|
グラス・ラップ社(本社=ドイツ・レンネシュタット、マリオ・リュッテケ社長、http://glass‐wrap.com/jp/)が開発した、板ガラスパッケージングシステム「グラス・ラップ」による、板ガラスの輸送実験が、このほど浜新硝子㈱佐賀工場(佐賀県神埼市)で実施された。 「グラス・ラップ」は、ドイツで開発されたガラスの物流・保管のための梱包材。軽量で弾力のあるEPS(発泡スチロール)やEPP(発泡ポリプロピレン)製の枠材を組み合わせ、枠の固定と衝撃吸収の役割を持つ木材で固定することで、ガラスの周囲を保護するもの。枠内部の支持材を取り換えることで、最大4枚までの単板ガラスを保持できるほか、複層ガラスや曲げガラスにも対応ができる。 ガラス運搬時には、コンテナ内で縦積み、横積みが可能なため、コンテナ内のスペースを有効に活用できるほか、周囲の保護材に直接運搬用のローラーと持ち手を取り付けることで、キャリーバックのようにガラスを運ぶことも可能となっている。 また、枠材のEPSやEPPはリサイクルが可能ため、エコ商品としても評価されており、ドイツをはじめとしたヨーロッパや、アメリカなどでは「グラス・ラップ」の採用は進んでいる。 今回、浜新硝子佐賀工場で行われた実験では、厚さ4㍉、サイズ2000㍉×1000㍉の生板ガラス1枚を「グラス・ラップ」で梱包、ストレッチフィルムで巻いたものを、一般の路線便で同社東京営業所(東京都墨田区)まで往復の搬送を行うというもの。往路と復路で違う路線を通ることで、より厳しい条件下でも、ガラスを割らずに運搬できるかを実験する。 浜新硝子 営業部九州営業課の金納純也課長代理によると、内装用の小ロット品を運搬する際に路線便を使うケースがあったが、途中で割れてしまうケースが多かった。割れにくい運搬方法を探していたところに、インターネットで「グラス・ラップ」の新聞記事を見かけ、実際に試してみることにしたと話している。 実験当日は、「グラス・ラップ」の日本代理店であるラーゴム・ジャパン㈱(名古屋市東区徳川2‐24‐3、電話050‐3772‐7784)の藤井理夫社長と担当スタッフのペレ・スィルィエダール氏が佐賀工場を訪れ、事務所内で「グラス・ラップ」概要を説明。その後、工場内で実物の組み立てを行った。 当初は厚さ6㍉、サイズ864㍉×1930㍉の合わせガラスでの実験を予定していたが、機材の関係から急きょ、厚さ4㍉、サイズ2000㍉×1000㍉の生板ガラスに変更された。 この大きさのガラスの輸送実験が日本で行われるのは初めてとのことで、「グラス・ラップ」の組み立てに時間を要したものの、無事に梱包は完了。 梱包後は、実際にガラスを横向きや縦向きの状態から地面やスロープ状の斜面に倒してみせ、衝撃でガラスが割れないことを確認した。 金納課長代理は、「路線便のトラックの中に立てかけで運送できれば、場所を取らないため、運賃のコストダウンも見込める」として、期待を寄せていた。 その後、テスト配送として佐賀工場から出荷されたガラスは、無事に東京事務所へ到着、東京事務所から佐賀工場への返送においても、破損無く、無事に到着したとのことだった。 今回の輸送実験の結果は良好と見て良い事から、今後は国内においても「グラス・ラップ」の採用が見込まれる。 |
■7月1日より旭硝子は「AGC」に社名変更(平成30年7月2日)
|
||
|
既報の通り、旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、グローバルグループ一体経営を更に進化させるために、本年7月1日付けでAGCグループの中核をなす「旭硝子株式会社」の社名を「AGC株式会社」に変更した。今回は東京都千代田区丸の内にある同社本社ビルを訪問。執行役員ビルディング産業カンパニーアジア事業本部長・武田雅宏氏に今回の社名変更の理由や最近の国内ガラス市場の状況などを含め伺った。 (1)「旭硝子」から「AGC」へ まず、今回の社名変更に至った背景を簡単にご説明させて頂きます。 今回唐突に「AGC」への社名変更を決めたわけではありません。私たちは2002年よりグローバルグループ一体経営を進めました。具体的には、グループビジョンを制定し、グループ企業名を旭硝子グループからAGCグループに変更したのです。石津進也社長の時です。 また、建築用ガラス事業と自動車用ガラス事業の日米欧3極一体運営を開始したのもこの年です。 グラーバーベル社の社長だったルック・ヴィラム氏が板ガラスカンパニーのトップに就任しました。当時、欧州と日本のガラスの流通形態が違うことを理解してもらうのに大変苦労したことを覚えています。とにかく当時は試行錯誤しながら一体運営を始めました。 それから16年経った今は相互理解が進み、欧米と私たち日本の市場が異なるということを理解した上で議論ができるようになりました。それはすごく大きな進歩だと思います。 創立100周年を迎えた2007年にはグローバルグループ一体経営を更に進化させ、グループブランドを「AGC」に統一し、国内外のグループ会社名には原則として「AGC」を冠称することとしました。その結果、「AGC」が社名につかないのは旭硝子本体だけになったのです。 そしていよいよ7月1日から、その残った本体も「AGC」に変わりました。ということで、突然降って沸いたように社名を変更するということではないのです。 社長の島村はよく、「AGC」の「A」はAdvanced(前進した、進歩したという意)、「G」はGlass(ガラス)、「C」はchemecal(化学の)とかceramic(セラミック)の意味、と申しています。先進的なガラスと化学とセラミックスの会社ですということです。ですから、ガラスを忘れたわけではありません。 島村は、当社の創業以来、110年お世話になった流通の皆様にとても感謝しています。昨年の8月に社名変更を発表した時も、「流通の皆様には直ちにお知らせしなさい」と申しておりました。必要だったら自分が皆様のところに説明に伺う、と言っていたぐらいです。 社名変更については、特約店の皆様は「まあそうだよね」という反応が大半でした。「これは困る」という反応は少なかったという印象です。サッシメーカーさんの中にも社名が横文字に変わっているところがあるからかも知れません。ただ、2代目、3代目という次世代の若い経営者の中には、「えっ」という反応をされる方もいらっしゃいました。この世代の経営者の方は2タイプの方がいるようです。すなわち「ガラス以外の商売を中心にする」という人と「ガラスに拘りたい」という人がいて、後者の方達の中には驚いた反応の方がいました。 そのような方にも、「社名が変わるということで、商売を変えるつもりもありませんし、環境を変えるつもりもありません」というお話しをすると、納得頂いています。 6月の板ガラスフォーラムの前日に、当社特約店の皆様をお招きしてお客様懇談会を開催しました。その時にも、社名変更のお話と、皆様をこれからも変わらず大事にしたいという思いをお話させていただきました。 懇談会では、創立111周年ということで記念品などをお渡ししました。皆様にすごく喜んでいただいて、「旭硝子が流通店のことを考えてくれていることがわかった」とお話して下さった方もいらっしゃいました。 この会合は旭硝子として最後の会合だったので、少し心配もあったのですが、逆にとても良い雰囲気でした。社名変更の背景や理由についても、少なくとも特約店様のところまではご理解してもらったと思っています。 (3)今後の流通店との関係について 今から、20年前が転換点だったと思います。日米構造協議等以後、いろんな意味でガラスという商品がスーパースターの時代から変わってしまいました。大手住宅メーカーやサッシメーカー向けの特需の流れもこの頃から始まりました。サッシメーカーがガラスの受注もするようになりましたが、当初ガラスはあくまで流通店さんを経由していました。ところが、複層ガラス化が進むにつれて流通店を経由しない流れに変わっていきました。当時、我々も、そして流通店の皆様はそれに気がついていたのかどうか? マーケティングの4P(プロダクツ=製品、プロモーション=広告など消費者への購買意欲を喚起する活動、販促、プライス=価格、プレイス=流通)という言葉があります。20年前は、商品は単板しかなかったからプロダクツの差はない。だからプロモーションはいらない。プライスもほほ同じだったから4Pのうち3つはあまり関係がなかった。他社に勝つにはプレイス=流通しかなかった。 今は、様々な機能ガラスのバリエーションがあります。断熱や遮熱、防犯や意匠などの価値を買って頂くのだから、販促も必要だし、価格もいろいろ考えないといけない。当然流通も考えないといけないのですが、残りの3つのPが、20年前と比べるとものすごく大事になってきました。 ですから、メーカーと流通の皆さんで、どうやって消費者に様々な機能や付加価値を持つ商品を伝え、販売していくかが大事ではないのかと思っています。 ガラス卸売業という商売の形態が非常に難しくなっているのも事実です。ガラス卸売の機能として、在庫、配送、代金回収、注文のロットを大きくする、そして販促の機能があります。単板の時代は、その中の在庫と配送の機能が大きかったのですが、複層ガラスが主流の今は、在庫の機能がいらなくなった。今思えば、その兆しは90年代半ばからあったと思います。我々もこういう変化がくるから皆さんにもその対応を考えておいて欲しいともっと申し上げれば良かったのかもしれません。 でも20年前とは時代が変化しています。当時を懐かしむことはやめましょう、我々も反省はありますが、新しい時代になったので、一緒に新しい関係を作っていきましょう、ということを流通の皆様にはお話ししています。 数量の大きな拡大が望めない日本の建築市場で私たちがこれから進む方法は、言うまでもなく、ガラスの性能プラス加工・施工など様々な機能をお客様に販売する、ということでしょう。一つの商品を「どうか買ってください」と売るだけではなく、加工や施工なども含めて提案する。とくに、これからは施工が重差別化要因となる商品が増えてくるはずです。これらを全て私たちメーカーが担うことはできません。流通の皆様とどういう風に役割・機能を分担し、マーケットを拡げて行くのか。それが皆様と一緒に取り組むべき大きな課題であると思っています。 |
■昭和フロント「ストアフロントコンクール」受賞作品発表(平成30年7月2日)
|
||
|
三和ホールディングス㈱(本社=東京都新宿区、髙山俊隆会長兼CEO)の連結子会社である昭和フロント㈱(本社=東京都千代田区、笹澤英夫社長)は、このほど「第49回ストアフロントコンクール」受賞作品を発表した。 グランプリは、「KOHホーリーランド 表参道」(東京都渋谷区、設計事務所=㈱和田組 一級建築士事務所、建設会社=㈱和田組、販売店/加工店=別鉄サッシ工業㈱・㈱エム・ファサード)が受賞した。 1970年から始まり、今回で49回目を迎えるストアフロントコンクールは、業界で最も歴史のあるもので、歴代入賞作品は技術性、デザイン性に優れ、業界の注目を集める作品として高い評価を受けている。 特別審査委員長に八木幸二氏(京都女子大学教授、生活デザイン研究所長、東京工業大学名誉教授/工学博士)、特別審査委員に橋本夕紀夫氏(㈲橋本夕紀夫デザインスタジオ)と牛建務氏(㈱インタースペースタイム代表)を迎えた今回、応募総数1639件を数え、全国から数多くの優れた作品が寄せられた。 「店舗建築部門」「一般建築部門」では、デザインや建物全体との融合などを中心に、また「アイディア部門」ではアルミ形材の可能性を拡げる魅力ある作品かどうかをポイントに審査がおこなわれ、グランプリのほか部門ごとに賞が決定した。 審査委員長の八木幸二氏は「フロント材+αによる多様なデザインが定着しているのを確認できました。+αは、建築的な廂、パネル、ルーバー、テラス、商業的な看板、照明、色彩、外構的な緑、ウッドデッキ、水面、などですが、どれが主役というよりも見事に共演している感じで、フロント材は名脇役です。名脇役の最たる例が今回のグランプリ作品で、木目調アルミがあるのですから大理石調が有っても不思議ではありません。アイディア部門の2作品がリノベーション関係であるのも注目に値します。フロントは建築の表面ですから、建築自体の寿命を延ばし、エネルギー、資源の浪費を防ぐのに役立っています」と総評している。 なお、各部門の金賞・優秀賞は次の通り。 第1部 店舗建築部門 金賞 「柏の葉 T‐SITE」(千葉県柏市、設計事務所=㈱日本設計、クライン ダイサム アーキテクツ、建設会社=㈱イチケン 東京支店)。 第2部 一般建築部門 金賞 「アンフィニ㈱ 福島工場」(福島県双葉郡、設計事務所=㈱朝日建装一級建築士事務所、建設会社=㈱朝日建、販売店/加工店=㈲グラスフォース)。 第3部 アイディア部門 優秀賞「東京山手調理師専門学校」(東京都渋谷区、加工店=㈲東美フロント)。 |
■旭硝子財団ブループラネット賞(平成30年6月25日)
|
|||
|
公益財団法人旭硝子財団(石村和彦理事長)は6月13日(水)、2018年(第27回)ブループラネット賞(地球環境国際賞)をブライアン・ウォーカ―教授(オーストラリア)とマリン・ファルケンマーク教授(スウェーデン)の2氏に授与すると発表した。 旭硝子財団によると、オーストラリア連邦科学産業研究機構名誉フェローでオーストラリア国立大学名誉教授のウォーカ―氏は、もともと自然生態系の分野で行われていた「レジリエンス」(回復性・強靭性)の研究を「社会・生態システム」の分野に拡大し、社会と環境の変化に対応できる高度なレジリエンスの必要性を提唱した。 漁業などを例に、資源の利用が限度を超えると生態系は突然別の状態に移り、元に戻らなくなることを見出し、「閾値を意識した生態系のレジリエンスに配慮して自然を管理し、限度内での開発をすべきだ」とのメッセージを発信してきた。 この考え方は、地球システムのレジリエンスに着目した「プラネタリーバウンダリー」(惑星の限界)の概念の基礎の一つとなった。レジリエンスは今日、環境保全、持続可能な開発、環境経済、防災政策などの基本的概念になっている。 著名な国際水門学者でストックホルムレジリエンスセンター上級研究員、ストックホルム国際水問題研究所シニア科学アドバイザーのファルケンマーク教授は、水を生物圏の血流ととらえた斬新な発想と広範な活動で環境問題解決の考え方に大きく貢献した。 利用可能な水を何人でシェアするかによって定量化する「ファルケンマーク指標」を発表。また、地下水・河川水(ブルーウオーター)だけでなく、植物が利用できる土壌中の雨水(グリーンウオーター)が水資源として重要であることを世界で初めて提唱した。 ファルケンマーク指標は水資源の比較に重用され、グリーン⁄ブルーウオーターは農業用水管理に用いる標準的な概念となっている。氏は、1960年代にアフリカの貧困や飢餓と水問題との関連に気づき、水不足とさまざまな環境問題の分析に貢献している。 両氏の表彰式典は10月10日(水)、東京・大手町のパレスホテル東京で挙行。翌11日(木)に東京・渋谷の国連大学で両氏による記念講演会が開催される予定。 ブループラネット賞は地球サミットが始まった1992年に発足。地球環境問題の解決に著しく貢献した個人または組織を毎年2件選定し、各受賞者に賞状、トロフィーと副賞金5000万円を贈呈。財団によると、本年度は国内外のノミネーターから130件の候補者が推薦され、選考委員会の審査を経てウォーカ―教授とファルケンマーク教授に決定した。 |
■日本電気硝子「Lamion」防犯用途向けに展開(平成30年6月25日)
|
|||
|
日本電気硝子㈱は、樹脂を超薄板ガラスで挟み込んだ、「ガラス」と「樹脂」の良いところをあわせ持つハイブリッド・マテリアル「Lamion」を展開、グループの電気硝子建材㈱が販売を行っている。 このほど、「Lamion」の割れにくく、衝撃に強い特性を活かし、防犯用途向けに本格展開を開始する。 従来、「Lamion」は、その割れにくさや傷つきにくさ、軽さなどから、駅のホームに設置されるホームドアや、デジタルサイネージのカバーなどに用いられていた。 しかし、近年店舗のショーケースを破壊して、中の商品を奪っていく類の強盗被害が多発しており、ショーケースなど防犯対策として「Lamion」が貢献できると判断し、この度防犯ショーケースとして展開することにしたもの。 「Lamion」の特長である「耐衝撃」、「耐擦傷性」、従来の強化ガラス比で25倍もの「耐貫通性」(落錘試験による)がショーケースの防犯性を向上させることに加え、従来の強化ガラスに比べ約半分の重さである「軽量性」はケースの移動や施工の容易さに繋がり、さらに「紫外線不透過性」と「ガラスと同等の質感」は、ショーケース内の商品の劣化を防ぐと同時に、商品を鮮やかに展示することが出来る。 実際に、厚さ0.5㍉の薄板ガラスで、厚さ3㍉のポリカーボネートをラミネートした「Lamion」を用いて作られたショーケースサンプルの上面を、記者がハンマーで叩いてみたが、ハンマーの平面の側で叩いた際には、ガラス面にキズ一つ付かず、跳ね返るような衝撃が腕に伝わってきた。ハンマーの尖った側で叩くと、ようやくガラスに細かな傷やひびが入ったものの、粉状のガラスが多少舞うだけで、とても樹脂を貫通できるようなものではなく、従来の防犯ガラスとは全く別の物との感想を持った。 担当者の話によると、衝撃が加わった際に、例えばハンマーの平面側のような、ある程度の面積があれば、「Lamion」が衝撃を吸収するため、ガラスにもほとんど傷が入りにくいし、傷が入っても、防犯ガラスのようにガラスが粉々に砕けず、目立たないことから、すぐにガラス交換が出来なくても、しばらくはそのままで凌ぐことが出来るとのことだった。 また、ポリカーボネートの厚みは、標準で15㍉まで用意されており、さらに耐衝撃性に優れるものも用意できるとのことだった。 ◇ このほか、デジタルサイネージカバーなどに採用される場合では、樹脂部分に着色や印刷を施してから、ガラスでラミネートすることが可能となっている。あらかじめ、サイネージの枠に当たる部分の樹脂を黒く着色しておくことで、ガラスに着色するよりも透明感を維持できる。 重量もW1200㍉×H1800㍉クラスの大きさで15Kg程度と軽量であることから、一般の強化ガラスに比べ、運搬や施工を行いやすくなっていると言う。 |
■第20回板ガラスフォーラム(平成30年6月18日)
|
|||||||
|
板ガラス業界8団体(全国板硝子商工業協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合連合会、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催の「第20回板ガラスフォーラム」が、6月8日(金)、品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホール(東京都品川区)で、盛大に開催された。毎年恒例となった板ガラスフォーラムも今回で20年目を迎え、今年も全国から業界関係者などが410人参加し、盛況を見せた。 午後2時に始まったフォーラムは、初めに司会者から、前日に開催したオプショナルツアーが、好天にも恵まれ、無事に終了したとの報告がなされた。続いて、開会挨拶として、主催者を代表し全国板硝子工事協同組合連合会の橋本和明会長が、参加者へのお礼を述べた後、次のようにあいさつした。 「硝子工事組合のお得意先はゼネコン様です。ゼネコン様ここ数年の利益は史上空前のものと聞いておりますが、私たち工事業界は、その恩恵に預かっているかというと、決してそうではありません。首都圏では2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて繁忙期を迎えていきます。職人不足、配送費の値上げ、材料費の値上げと諸問題はありますが、今こそ工事業界の地位向上に向けて一丸となって取り組むチャンスです。ゼネコンという高い壁を業界が一緒になって乗り越えていきたいと思います。私は広島生まれ、広島育ちなので、カープの大ファンです。ご当地東京はジャイアンツファンが多いと思います。私もジャイアンツの背番号3番の方は大好きです。今日は、彼の引退式の言葉を借りて、結びの言葉にしたいと思います。我が板硝子業界は、永久に不滅です」 次に、記念講演の第1部として、慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授の岸博幸氏が「日本経済のゆくえ」‐世の中の流れ‐と題して、約1時間30分の講演を行った。 講演では、現在の日本や日本経済に対して危機感を持っていると前置きしたうえで、現在の政治状況を解説。音楽業界など他業種を参考に挙げながら、イノベーションを作り出す必要性と、オリンピックを控える今こそイノベーションを作り出しやすいタイミングであると説いた。ガラス業界も同じで、まだまだ、色々なことが出来るのではないかと思っている、とまとめて話を終えた。 その後、15分の休憩をはさみ、記念講演の第2部が行われた。講師に、慶応大学理工学部 システムデザイン工学科教授の伊香保俊治氏が、「快適・健康・省エネの家づくり」をテーマに約1時間の講演を行った。 家の寒さが脳卒中や心筋梗塞に繋がっていると指摘し、断熱住宅の普及が疾病や介護予防に寄与する可能性を断熱住宅の普及率と冬季死亡増加率のグラフを対比しながら解説。高知県梼原町での調査結果で温かい住まいでは発病や死亡確率が低くなるとの結果が出ていることを発表し、温かい住まいに住むことの重要性を説いた。 講演終了後の午後5時15分からは、隣室で合同懇親パーティーが行われ、各団体の代表者が登壇、紹介された。団体を代表して板硝子協会・機能ガラス普及推進協議会の島村琢也会長が、岸氏の講演会におけるイノベーションという言葉を用いながら、「今日の講演では、一つ新しいヒントを頂きました。合わせガラスや強化ガラスという材料は、かなり古くからあります。それが安全、防災、あるいは断熱という所につながります。合わせガラスや強化ガラスは、一つのイノベーションをおこすきっかけになるのかなと思います。目線を変えることで社会に貢献できるよう勧めてまいりたいと思います」と、あいさつした。 次いで、来賓を代表して経済産業省 大臣官房審議官の及川洋氏が、「このフォーラムは今回20回目と聞きました。関連する業界がサプライチェーンの上流から下流まで一堂に会して、情報交換を行う機会を長く継続している例は他にないのではないかと思っております。経済産業省ではコネクテッド・インダストリーズを政策的に推進しております。横のつながりだけではなくサプライチェーンをうまくつないでいく事で新たな付加価値を作り出していく。イノベーションをつながる中でやっていくといった取り組みです。この場をそういった機会に繋げることが出来れば素晴らしい事だと思います」とあいさつし、懇親会に花を添えた。 続いて、乾杯に移り、全国板硝子商工業協同組合連合会の辻良明会長が、「我々は機能ガラスといった、素晴らしい商品を持っていますが、一般の方々の認知度がまだまだです。全硝連では、以前から「ガラスの日」の制定を考えております。7団体が一堂に集まることはなかなかありません。是非とも皆さんに賛同していただき、「ガラスの日」を作りたいのです。どうかご賛同をお願いします。何時にするかといった詳細は、これから詰めるとしても、来年のフォーラムの日には、ガラスの日が出来たねと言えるようにしたいと思っています」とあいさつし、乾杯の発声を行った。 懇親会会場は、各地から集まった関係者は、思い思いのテーブルで旧交を温め、情報交換を行うなど和やかな雰囲気に包まれていた。 最後に、中締めの挨拶を全国板硝子卸商業組合連合会の松本巌会長が行い「機能ガラスは一般の消費者の皆さんまで伝わったと言えません。今後、色々なガラスがあることをアピールしていくことで、有望な市場になっていくと思います。業界8団体で足並みをそろえて、前を向いて、積極的に対応していきたいと思います」と締め、午後6時45分に閉会となった。 |
■本荘小学校体育館に「防災安全ガラス」寄贈式(平成30年6月4/11日)
|
||||||
|
機能ガラス普及推進協議会(島村琢哉会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長、以下「全硝連」)の近畿地区本部(小村哲也本部長)は5月31日(木)午後1時から、岡山県和気郡和気町(草加信義町長)の和気町総合福祉センター2階大会議室において、町立本荘小学校体育館(避難所)に寄贈した「防災安全ガラス」の寄贈式を行った。 今回の寄贈式は、同協議会が、本荘小学校体育館に、防災安全ガラス153枚及び強化ガラス3枚、計156枚(ガラス提供=セントラル硝子㈱、中間膜提供=イーストマンケミカルジャパン㈱、現地配送ほか=㈱ADF・アヤベ)を寄贈、全硝連近畿地区本部と岡山県板硝子商工協同組合(西出隆紀理事長)が施工に関わる工事費などを寄贈したもの。なお工事は、今年3月27日~4月8日にかけて行われた。 寄贈式には、和気町側から草加町長と町教育委員会の徳永昭伸教育長、今田好泰教育次長が出席。機能ガラス普及推進協議会からは、企画運営委員の森谷茂明委員長と浅沼光一事務局長のほか、セントラル硝子販売㈱の瀬古雅裕 取締役西日本営業本部長、㈱ADF・アヤベの綾部欽一社長、全硝連の辻良明会長、岡硝協から西出理事長、溝口茂専務理事、大硝協の大村宗一郎副理事長が出席した。 今田教育次長の司会で開会した贈呈式は、初めに森谷氏が「和気教育委員会の皆様には、回の寄贈プロジェクトの趣旨をご理解くださり、大変お世話になりました、改めてお礼申し上げます。今回寄贈させていただきました防災安全ガラスは一般のガラスよりも強靭で割れても破片が飛ぶことが無く、破片による二次災害なども発生しにくいものです。公共施設や災害拠点の更新の際にはご検討いただければと思います」と挨拶した。 続いて、森谷氏から草加町長に目録が贈呈され、寄贈に対する感謝状が草加町長から森谷氏に送られた。 最後に、浅沼事務局が草加町長と徳永教育長に、サンプルを用いて防災安全ガラスの機能を説明し、贈呈式は終了した。 その後、場所を本荘小学校に移し、午後2時30分から、同校の体育館に4年生から6年生までの3学年、約120名の生徒を集めて、ガラスの出張授業を行った。 授業に先立ち、同校の磯本由美校長が、生徒の前で「ガラス協会の方が、皆さんのため、地域の方々のために防災安全ガラスをプレゼントしてくれました。新しいガラスの事を、しっかり学んで、しっかり感謝しましょう」とあいさつした。 続いて、西出理事長が生徒に身近のガラス製品を問いかけると、窓ガラスやコップ、花瓶といった声が上がった。西出理事長は「ガラスにはいろいろな種類があります。今日は、機能ガラス普及推進協議会の浅沼先生に説明してもらいます」と、浅沼事務局長を紹介した。浅沼氏は、パワーポイントを使用しながら、ガラスの歴史や種類、フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、安全防災ガラスの特性などを動画も交えながら説明を終え、メインイベントとなる、ガラスの破壊実験に移った。 ガラス破壊実験は、デモ器2台を使用し、生徒を4組に分けて行われ、サポートには岡硝協の大倉正裕理事と綾部系一理事が付いて行われた。 フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、防災安全ガラスを、生徒代表の4名が、それぞれのガラスをハンマーで叩き、その割れ方や、安全ガラスの丈夫さを確認、割れても貫通しない防災安全ガラスの様子に目を丸くしていた。 実験終了後は、質疑応答が行われ、生徒からは、「防災安全ガラスの仕組み」や「他にどんなガラスがあるのか?」、「防災安全ガラスの値段は?」といった質問が行われ、西出理事長と浅沼事務局長が、一問一問、丁寧に答えていた。 最後に、森谷委員長が、生徒代表に記念品としてボールペンとクリアファイルを贈呈、生徒の代表から謝辞を受けて、午後3時30分に出張授業は終了した。 |
| ■経産省次世代省エネ建材支援事業(平成30年5月14日) |
|
経済産業省は、既存住宅の断熱・省エネ化を図るため平成30年度より新規に「次世代省エネ建材支援事業」を始めた。断熱パネルや潜熱蓄熱建材を導入するリフォームに対し、戸建て住宅は最大200万円を補助する。 環境省に移管した前年度までの「断熱リノベ」に代わる新事業で、居ながらにしてリフォームできる工期短縮と、支援対象を例えばエコキュートなど高性能で付加価値の高い建材製品に特化したのが特徴だ。 また、必須要件の断熱パネルを貼るか潜熱蓄熱建材を入れた場合に限り、玄関ドア、窓、ガラス、調湿建材の改修も補助金の対象に含めた。窓については、カバー工法か内窓専用の製品に限定している。 補助率は、補助対象費用の2分の1以内。補助上限額は、戸建て住宅が200万円、集合住宅は1住戸当たり125万円。下限金額は双方とも40万円となっている。 執行機関は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)で、5月18日の東京を皮切りに同23日までの間、札幌、福岡、仙台、大阪、名古屋で順次公募説明会を開催する。 補助対象の申請者は、住宅の個人所有者または所有予定者と賃貸住宅の所有者(個人・法人どちらでも可)としている。 一般1次公募は戸建て住宅、集合住宅とも5月28日(月)から申請受付を開始する。期限は6月29日(金)まで。事業主体の経産省製造産業局生活製品課によると、 1次公募の予算規模は3億円程度とみられる。 2次公募は8月初旬から同下旬を予定している。予算規模は未定。いずれも、SIIから交付決定通知を受ける以前に契約ないし工事に着手した場合は補助金の対象とならない。完工後に必要な実績報告書の提出期限は1次、2次ともに今年12月14日を予定している。 次世代省エネ建材支援事業は、経産省・資源エネルギー庁が実施している「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」の一環。支援補助金は①工場・事業所の省エネ設備入れ替え②ZEHの導入・実証③ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の実証④今回の次世代省エネ建材の導入―の四つの事業で構成。30年度は全体で600億4000万円の予算を計上している。 |
■環境省新「断熱リノベ」スタート「一般1次公募」開始(平成30年5月7日)
|
||
|
環境省は、既存住宅の省エネ・低炭素化改修を助成する平成30年度「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」の運用に着手した。補助上限額は戸建て120万円、集合住宅15万円。5月7日(月)から一般1次公募を開始する。 事業概要は前年度まで経産省が実施していた通称「断熱リノベ」をほぼ踏襲した形。執行機関は従来通り一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)で、公募に先立ち4月19日の東京を皮切りに札幌、金沢、仙台、名古屋、福岡、大阪、広島の各都市で順次公募説明会を開催した。 1次公募の総予算規模は約21億円。住宅区分別内訳は、「戸建て住宅」約8000万円、「集合住宅・個別」約4000万円、「集合住宅・全体」約19億7000万円。戸建てと集合・個別の公募期間は5月7日から6月29日(金)まで。集合・全体は5月7日から6月4日(月)まで。 2次公募は戸建てと集合・個別のみを対象に、7月17日(火)から8月10日(金)の期間を予定。事業規模は未定。予算に余裕がある場合、戸建てに限って3次公募を実施する。 交付決定については1次、2次とも戸建てと集合・個別は随時採択(先着順)方式を採用している。1次に限定した集合・全体は公募終了後、SIIの審査会がCO2排出抑制評価点を用いて審査し、点数が高い案件を上位とする。交付決定は7月中旬の予定だ。 集合住宅・全体では、1申請当たり100戸以上の場合、設計または施工業者はSII登録の「断熱リノベ事業者」であることが条件。事業者登録の公募期限は今年6月4日まで。また、各住宅区分の本体工事は、補助金の交付決定通知後に契約・着工することも必須要件の一つだ。 補助対象製品は、SII登録の高性能建材(断熱材、ガラス、窓)。戸建てについて家庭用蓄電池と家庭用蓄熱設備(エコキュートなど)を新たに対象に含めたのが特徴。補助率は高性能建材が対象費用の3分の1以内で、上限額は戸建て1戸当たり120万円、集合住宅は個別、全体ともに1戸当たり15万円。 家庭用蓄電池は、設備費3万円⁄kWhか対象経費の1⁄3、工事費1⁄3以内か5万円⁄台。蓄熱設備は1⁄3以内か5万円⁄台と規定している。 改修内容をみると、戸建ては①天井、外壁、床および窓の四つの部位のうち二つ以上を組み合わせて改修する②窓改修工法は、外窓の交換、内窓の取り付け、ガラスの交換(ガラス交換、カバー工法、建具交換)とする―ことが主な要件だ。 集合住宅は個別、全体ともに「玄関ドア以外のガラスを用いた開口部全てを改修すること」が主たる要件。天井、壁などの改修は不要だ。 申請に際し従来と大きく異なるのは、補助金交付申請予定額の求め方を、「積み上げ方式」に変更した点だ。戸建てで高性能建材に加え蓄電池、蓄熱設備を導入する場合、申請額は断熱材及び窓のグレード別補助単価表にある製品単価と設備費用を単純に合計した額(上限内)か3分の1を掛け合わせて算出するなど簡素化された。 事業を所管する環境省地球環境局地球温暖化対策事業室の西山卓也調整第一係長は「パリ条約に基づき日本は住宅部門のエネルギー消費量を4割削減する必要がある。住宅の高断熱化、高気密化は(環境省の)重要なミッションと考えている。そのツールの一つとして補助事業を展開していきたい。普及啓発の観点から手続きの簡素化にも努めた」と話している。 |
■China Glass2018 AGC・坂東機工などが出展(平成30年5月7日)
|
|||||||||
|
4月19日(木)~22日(木)の4日間、中国・上海市の上海新国際博覧中心において、「第29回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2018)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 今回は会場面積8万㎡のスペースに、中国をはじめドイツ、イタリア、アメリカ、日本、韓国など世界29カ国から、ガラス、機械、部品、建材、道具・工具、サービスなどの関連企業865社が出展、製品展示や商品紹介などを行った。 ガラス産業に関連するテクノロジーやソリューションの現状、最新情報を知ることが出来る同展示会には、ヨーロッパ北中米、アジア、オセアニアなど世界各地からバイヤーや関係者が参加し、関心の高さを伺わせた。 会場は、アジアで2番目の広さとなる上海新国際博覧中心の東側、E1からE7ホールまでを使用している。 E1ホールは、ヨーロッパや中東、アジアなど中国以外の企業や、その中国子会社が出展した。主な出展企業(順不同)は、ピルキントン(NSGグループ)、CMS Brembana(イタリア)、LiSEC(オーストリア)、KOMMERLING(ドイツ)、坂東機工(徳島市)、島津製作所(京都市中京区)、クラレ(東京都中央区)、井原築炉工業(大阪市北区)、積水化学工業(大阪市北区)など。 E2ホールは、ガラスメーカーによる展示が主体で、真空ガラス、Low‐Eガラスや耐熱強化ガラス、自動車ガラス、調光ガラスなどが展示された。同ホールの主な出展企業は、AGC(旭硝子特種玻璃有限公司)、中国建材国際行程集団、中国建築材料科学研究総院、台玻集団、中国南玻集団、上海耀皮玻璃集団など。 E3ホールには、セラミック関連や薬剤関連、製品関連、強化炉や切断機などの大型加工機械類が展示されている。主な出展企業は日本旭硝子工業陶瓷(AGCセラミックス)、北玻、名特、杭州精工など。 E4ホールは、オートクレーブや水平強化炉のほか、切断機、研磨機といった大型機械類が展示されていた。また、レーザー加工機もこのホール内で展示されていた。主に、仏山市南海区博亮玻璃机機、世林玻璃机機、広東奥斯玻璃技術、広東仏山市純徳高力威机機などが出展した。 E5ホールは、複層ガラスのラインを展示する企業が多く集まっていた。実際に機械を稼働させてデモンストレーションを行う様子が目立っていた。 出展企業は、済南威力机器、北京市化華朋建材装飾、江芬旭升など。 E6ホールでは、ウォータージェットやフィルム加工機のほか、EVA膜、金物などを扱う企業が出展。山東方県安全玻璃科技術、南京大地水刀や河源鵬翔智造科技術、広東順徳添百利科技などの企業が出展した。 E7ホールはガラスびん関連や、金物類、鋳物、薬剤、インク、装飾フィルムなど、多様な製品を扱う業者が、200社ほど集まり、実演を行うなど様々な方法で自社製品のアピールを行っていた。 ◇ 全体的な印象として、出展品目に大きな変化は無く、来場者も少ないように感じた。特に、日本人を会場内で見かけることは稀で、外国人についても、欧米より中東からの訪問者が多いように見えた。 展示品で目に付いたのは。真空ガラス、耐熱強化ガラスといった製品と、オートクレーブや水平強化炉などの強化炉、ウォータージェットなど。特に強化炉を展示する企業は、昨年の北京よりも増加していたように感じられた。真空ガラスは、厚さ6ミリのガラスを使用し、スペーサー間の幅も60~80㎜と広く設定されていた。会場ではLow‐Eガラスとのペアにしたものが展示されていたが、パンフレットには真空ガラス2枚でのペアガラスも記載されていた。 詳細な展示内容などは、次号以降で掲載する予定です。 |
■横浜市住宅エコリノベ補助事業(平成30年4月23日)
|
||
|
環境未来都市を標榜する横浜市(林文子市長、人口373万人)は4月2日から、既存住宅の省エネ改修を助成する「横浜市住まいのエコリノベーション補助制度」の平成30年度の運用を開始した。窓の断熱化に最大80万円を交付する。 事業主体の市建築局住宅部住宅政策課によると、本年度の補助件数は50件程度で、予算規模は約1600万円。募集は先着順。予算額に達した時点で申請受付を終了する。窓口は市住宅供給公社街づくり事業課。 「住宅全体の断熱性の確保」につなげることを狙いに26年度に発足した通称エコリノベ事業は、「A・断熱改修工事」と、Aと併せて実施する「B・設備改修工事等」で構成している。 補助金額は、29年度までは工事費用の3分の1以内、もしくは「一般改修住宅」の場合は上限40万円、「特定改修住宅」では80万円と設定。新年度はこのうち「3分の1規定」をなくし、代わりに「建材・設備等ごとに設定した補助金額の合計額」とした。 Aでの補助金額の合計10万円以上が条件だが、住宅内の全ての窓を改修しても10万円に達しない場合は例外的に対象に含めるとしている。 居間、ダイニングなど主たる居室の全窓以上の断熱化と1種類以上の設備改修を中心とした一般改修の40万円と、住宅全ての開口部(窓・ドア)を断熱化する特定改修の80万円は維持した。特定では高効率給湯器の設置といった設備改修は従来通り不要だ。 また、これまで交付要件としていた「1次エネルギー消費量の10%以上の削減」も排除するなど規定を大幅に緩和。必須だったHEMSの設置は「任意」に変更した。仮に設置した場合は3万円を補助する。 対象工事と補助金額をみると、Aの開口部の窓では、外窓交換と内窓設置が1箇所で「大」(2.8㎡以上)5万円、「中」(1.6㎡以上2.8㎡未満)3万円、「小」(0.2㎡以上1.6㎡未満)2万5000円。ガラス交換は「大」(1.4㎡以上)1万2000円、「中」(0.8㎡以上1.4㎡未満)9000円、「小」(0.1㎡以上0.8㎡未満)1000円となっている。 いずれも施工後の熱貫流率が「4.65㎡以下」となることが条件。 玄関ドアの交換は開き戸の場合、「大」(1.8㎡以上)8万円、「小」(1.0㎡以上1・8㎡未満)3万5000円。熱貫流率は窓と同じ4.65㎡以下だ。床の断熱工事の補助額は1㎡当たり1000円。外壁と屋根(天井)は同800円。 Bの設備改修面では、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ給湯器、家庭用コージェネレーション設備、太陽光発電設備(3.0kW以上)など1種類について各10万円を補助するとしている。 住宅政策課によると、26、27両年度の交付実績は総計60件。28年度は14件と伸び悩んだが、29年度は23件と増加に転じた。窓改修の内容では、外窓交換が5割、内窓設置4割、ガラス交換は1割という。 住宅政策課の城向咲さんは「もっと使い勝手を良くしようと、HEMSをやめ、補助金額も(積算が煩雑な)3分の1方式から積み上げ方式に変えた。東京都が昨年度から窓断熱改修に特化した補助金を始めた影響か、横浜市民の間にも窓に関心を寄せる人が増えてきています」と話している。 課長補佐の村上まり子さんは「普及啓発活動を進め、機運の醸成に努めていきたい」と話した。 |
■ドイツフェンスターバウ展 断熱競争から快適性へ(平成30年4月23日)
|
||
|
窓やドア、ファサード、カーテンウォール、天窓等の見本市「fensterbau/frontale」(以下フェンスターバウ展と表示)が3月21日から24日までの4日間、ドイツのニュルンベルグで開催された。今回は実際に当展示会を訪れたガラス業界の複数の方達にお話を伺い、その内容を紹介します。 公式サイトの発表では、1329社(42カ国)、約110000人が来場した。日本からはYKK AP㈱(本社=東京都、堀秀充社長)の1社が前回に引き続いて出展。今回で3回目となる。 今回お話を伺ったのは①目新しいガラスやサッシは?②次世代の窓になるであろうと感じたものは③今、流行りの窓の種類は何か④展示されている複層ガラスはどのタイプが多いかなどの項目。 以前記者が2回ほど取材した感じでは、フェンスターバウ展はどちらかというと樹脂窓の展示会かなと思うぐらい、樹脂窓がたくさん紹介してあった。 お話を伺った内容では、①については、樹脂サッシの外側にアルミやアクリルでラミネートされたものが多く、目的は、樹脂の耐候性の問題よりデザインを重視してラミネートしているようだ。日本より暑さについてはそれほど厳しくないのであろう。木製サッシについては、アルミで外側をカバーしているものもあり、また、木製サッシそのものにカラー塗装を施している窓も展示してあったという。日本では珍しいのではないか。 ②については、IoT(Internet of Things=身の回りのものがインターネットにつながる)の技術を活用。スマホの操作で窓やシャッターが自動で開閉できるようなシステムを紹介している企業もあったそうで、ドイツでは、窓の断熱競争から、より快適性を求める動きに変わっているようだ。 ③の窓種については、圧倒的にドレーキップ窓(内倒し+内開き窓)の展示が多く、次いで、大型の片引き戸。大型でも断熱性能が高く(ドイツではU値1.3W/㎡・K以下でないと採用されない)かつ、採光性が良いという。安全性やバリアフリーにも配慮されていたという。引戸の軽さでは日本の商品が一番軽く感じたと話してくれた。 ④のガラスについては、ほとんどがトリプルガラスで中間スペースは、アルゴンガス入りといい、クワトロガラス(4枚複層)はほとんど展示していなかったそうだ。いろいろなサッシメーカーのカタログを見せてもらったがすべてトリプルガラスで掲載されていた。ドイツの窓ではトリプルガラスのガス入りが7割を超えているようだ。 この他、展示会をみて何か驚いたことはありましたかと聞いたところ、(1)ドイツでは樹脂窓よりアルミ窓のほうが高級品で、アルミサッシでもサーマルブレイク構造で樹脂窓より断熱性能の高い窓があったこと(2)ドイツでは、窓のリフォーム市場が多いこと(3)サッシは新築用とリフォーム用に分かれていないこと。住宅用、ビル用との区別もない。規格サイズも存在しない(4)ガラスでは、断熱性能だけでなく遮熱性能の値(η『イータ』値)が0.6以上でないといけないそうだ。断熱性能は高いレベルが求められる(U値=0.8W/㎡・K)一方で、逆に日射熱はある程度取り入れるという考え方でη値は。6以上という規定になっているという。それだけドイツの気候は北海道の気候に近いのではないかと感じたそうだ。(5)ファブリケータと呼ばれる窓の製造業者が大小合わせて6000以上もドイツ国内にあって、彼らが「窓の性能」を守っているとのことであった。そういう仕組みを国が主導して確立したとのことだった。 日本から唯一出展したYKK AP社のブース内容も聞いてみたが、大型片引き戸の木製サッシを中心に展示、多数の戸車を取付け、軽い力で操作ができるという。戸車の取付けにも工夫がしてあり、気密を高めるため、引戸が閉じている時が、戸車は斜めになって障子を引き寄せる構造になっているという。話を聞くと今回の展示会で、彼らが紹介したい商品は「窓」ではなく、「金物」との。前出のファブリケータに販売する部材メーカーの立場との事だったようだ 開催時期が期末にあたる3月末の忙しい時だけに、参加するにはいろいろな問題がありそうだが、次回開催があれば、今回の展示会内容と比較もできるのでぜひ参加したいとも話してくれた。 なお、次回開催予定は同じ場所で、時期は2020年3月18日から21日までの4日間としている。 将来の日本の窓動向を占う上でも、建築用の窓を生業としている方にはぜひ参加してもらいたい展示会といえる。 |
| ■東京都窓リフォームの補助金申請 半年間で約4000戸(平成30年4月16日) |
|
窓改修に限定した東京都の助成事業が順調に推移している。事業着手から半年間の申請件数は700件・3800戸以上に上っている。当局は都民への周知活動をさらに推し進め、目標の3万3000戸達成に拍車をかける方針だ。 東京都環境局が主導する3カ年計画の「既存住宅における高断熱窓導入促進事業」は2017年8月28日に運用を開始した。家庭部門での消費エネルギー低減を目的に、既存の戸建て住宅と集合住宅の窓リフォームに補助金を交付する制度だ。 ガラス単体か窓(サッシ+ガラス)改修工事が対象。1部屋だけでも交付対象となり、国や区市町村の補助制度との併用も可能だ。助成率は対象経費(材料費と工事費の合計)の6分の1以内、助成金の上限額は1戸当たり50万円。いずれか低い額を交付する。3カ年の予算総額は24億7500万円。 助成要件をみると、戸建ての場合、最低でも一つの居室の外気に接する全ての窓について、内窓設置か外窓ないしガラス交換を実施すること。窓が一つしかなくても対象となる。集合住宅の要件もほぼ同じだ。 改修に際しては環境共創イニシアチブ(Sii)に登録されている断熱性能に優れたガラス製品を使用することが条件となっている。 助成対象者は都内にある既存住宅の所有者(個人・法人)と集合住宅の管理組合。住宅所有者または管理組合と共同で申請するリース事業も対象に含めている。また、個人や法人が所有する社宅、寮、セカンドハウス、別荘も対象となる。施工業者の所在地を問わないのも特長の一つだ。 執行機関は公益財団法人東京都環境公社・都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)で、事前申請の受付期限は2020年(平成32年)3月31日までとなっているが、期間内でも予算がなくなり次第募集を打ち切る。 クール・ネット東京によると、昨年8月末の募集開始から今年2月末までの6カ月間の申請は、件数で700件以上、戸数では3800戸以上に達した。池上佐知センター長は「事業初年度としては順調」と評価している。 全体的な傾向としては集合住宅の区分所有者からの個々の申請が多いとしている。管理組合による全戸改修もあり、「1件で100戸以上の大規模改修も数件ある」(池上氏)。リース業者による申請は目下ゼロ。改修の内容では内窓の取り付けが過半数を占めるという。 3月末まで都環境局地球エネルギー部地球エネルギー課長を務めた倉田京弥氏は「3カ年計画で想定した改修3万3000戸に近い形で伸びている。さらに都民にアピールし実績を伸ばしていければ」と話した。 |
| ■ハードグラス工業「売上目標50億達成できる」(平成30年4月16日) |
|
強化ガラスドアの国内シェアナンバー1を占める安全ガラス(強化・合わせ)製造・販売のハードグラス工業㈱(本社=伊丹市北伊丹七―七九、下岡嵩社長)は、伊丹市内にある伊丹シティーホテルにおいてハードグラス工業及びグループ企業のハーディの社員を含む252名が出席する中、今4月から始まる同社の第49期キックオフセレモニーを開催した。 下岡社長はその中で、前期の業績について説明し、「売上高は目標の95%、経常利益は2%だった。売上高40億円も達成できなかった。東京オリンピック関連の物件を期待していたが、工期遅れの影響で、目標は未達に終わった」と語った。 来期49期については、「新しく本社工場に、本年1月より強化炉を導入した。薄板のものから厚み19㍉の厚物まで、また、3000㍉×5000㍉の大きなガラスサイズものまで、対応可能となった。これまで、試験運転も順調に進んでいる。これで、社内で大きなサイズのガラスも加工処理ができるようになり。大幅に生産能力も増強した。これで目標の売上高50億円、経常利益3%以上の目標は達成できる」と大きく胸を張った。 下岡社長は、①強化炉の設備投資の他にも②関東地区に物流拠点を3カ所設けること(千葉、神奈川、北関東、千葉は稼働中)③関連会社のハーディでステンレスサッシの加工~取付までを行うこと等の方策で50億円の目標は、必ず達成可能だと強調した。 この他にも、既に兵庫県東条町に10000坪の工場用地を取得済み。「本社工場の移転はない」とした上で、「近い将来に今は発表できないが、皆さんがあっと驚くようなことを企画している」とのことだ。 下岡社長は、さらに、運送業界もトラック車輌の不足、人手不足などでガラス業界にも少なからず影響がでていることから、自前で運送ルートの確保も辞さない考えを明らかにした。 将来的には、兵庫県伊丹市と提携し、空港整備からインバウンドの受け入れ、宿泊施設の整備から。さらには、町おこしまで考えているそうで、「最低でも後10年は現役で頑張る」と力強く述べていた。 |
■全硝工連全国理事会値上げ対応の検討を(平成30年4月9日)
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(橋本和明会長)は3月23日、広島市南区のTKPガーデンシティ広島駅前大橋で、「全国理事会」を開いた。 冒頭、橋本会長は「メーカーが値上げを発表しているが、仕方ないことだ。知恵を絞りながら対応したい。ご検討をお願いしたい」とあいさつ。 会議では国交省関連の課題として登録基幹技能者関係で、平成30年度講習実施計画、主任技術者要件の追加、次年度以降の進め方について検討。さらに建設キャリアアップシステム、社会保険加入促進問題、建設マスターへの対応について検討した。 引き続き、ガラスメーカーの動きや各地区の動きについての情報交換、開催地である中国工事組合の活動紹介をおこなった。 理事会終了後、懇親会を開いた。 意見交換では、社会保険の加入状況について、「一人親方の定義があいまい。本当に一人でやっている人は少ない。それを指摘されたら説明のしようがない」「一人親方ではないとされると工事業者に不利なことが出て来る。全員社会保険加入は当たり前でその次の課題に入ったと思う」などが挙がった。 値上げについては、「メーカーが上げたから値上げしましたと、言われても物件単位でやっていると値上げの基準が明確化できない」「過当競争が解消されるのなら、歓迎だが、そうならないのではないかと不安」「値上げをするのは良いが、エンドユーザー、施主が受け入れない限り、現実的ではない」などの意見もあった。 各地域からの報告では「首都圏にオリンピック・パラリンピックで需要が集中している。地方には資材が品薄になっている」「関東で価格が上がらないと地方で価格改善は無理」などと、やはり値上げや工事の一極集中に関することが多かった。 平成30年度登録硝子工事基幹技能者講習の日程・計画は、東京が8月25日と26日、東京都中央区日本橋浜町のプラザマーム(募集人員60人、募集期間は7月2日~13日)、大阪が9月1日と2日、大阪市の新大阪丸ビル別館(募集人員60人、募集期間は7月17日~27日)。 |
■全硝連近畿B機能ガラス推進協岡山県和気郡の本荘小学校へ防災安全ガラス寄贈工事(平成30年4月9日)
|
||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)の近畿地区本部(小村哲也本部長)は、3月27日(火)~28日(水)の2日間、岡山県和気郡の本荘小学校で「防災安全ガラス寄贈工事」を行った。 今回の工事に使用した防災安全ガラスは、機能ガラス普及推進協議会が寄贈したもので、窓ガラス153枚とドア用の強化ガラス3枚。ガラスはセントラル硝子、中間膜はイーストマンケミカルジャパン製、配送は㈱ADF・アヤベが行い、施工を全硝連近畿地区本部が担当している。 工事初日には、岡硝協から西出理事長ほか8名、京硝協から2名、奈硝協から2名、大硝協からは辻理事長と大村副理事長ほか4名、兵硝協から宮城理事長と宮田会計理事の2名、計21人が参加した。午前9時の朝礼の後、体育館のサッシを取り外し、ガラスの交換、コーキング、サッシ取り付けの作業が行われ、午後3時すぎには、体育館2階ギャラリー部分のほぼすべての窓のガラス交換が終了した。 工事の時間中には、土井原康文校長や、同校の教職員、岡山県中小企業団体中央会の北山博幸課長、長木佑磨主事などが見学に訪れ、西出理事長が工事の状況や防災安全ガラスの機能を説明した。 工事を見学した北山課長は、「岡山のガラス組合さんが、寄贈工事という形で地域に協力して下さっている。中央会としても、この活動を支援したいと考え、今回補助金を出すことにしている。これからも地域のために、防災安全ガラスのPRと普及を進めて欲しい」と話していた。 土井原校長も「子供たちに防災意識を根付かせる良い機会となったと思う。子ども達を預かる学校としては、安全に学校に来て、安全に帰ってもらう事も大事な事。予算的に手の回らないこともある中で、寄贈していただけるのはありがたい事」と話し、「地域に開かれた学校として活動する中で、地域の安全のためにもなる」と、コメントしていた。 このほか、工事の様子を地元テレビ局の山陽放送や地方紙の山陽新聞が取材。山陽放送は、西出理事長、土井原校長にインタビューした後、ガラス交換の様子や、サッシを外はめする様子を体育館の内外から撮影するなど、工事の様子を詳細に取材、夕方のニュースで放送するとの事だった。 なお、工事2日目は、岡硝協8名、京硝協2名、和硝協2名、大硝協3名の計15名が参加し、一部残っていたコーキングとサッシのチェック、クリーニング、寄贈シールの貼り付けなどを行っている。 |
| ■平成29年度後期ガラス施工技能検定結果(平成30年3月26・4月2日)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成29年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月16日(金)に全国の職業能力開発協会から、発表された。 弊紙では、47都道府県の職業能力開発協会に取材をし、その回答をまとめている。 今年の結果は、1級受検者が231人(前年310人)で、合格者は113人(同179人)、合格率は49%(同54%)。2級受検者は176人(前年159人)で、合格者は83人(同85人)、合格率は47%(同53%)となっている。なお、本年は1名の2級女性受検者(前年は1級受検者1名)があった。 総受検者数は、前年の469人から62人減少し407人、総合格者数は同264人から196人と68人減少した。 合格率は、1級で49%と前年を5ポイント、2級も47%で前年を6ポイント、それぞれ下回っており、1級・2級とも合格率が50%を下回る厳しい結果となっている。 このような結果となった背景について、検定担当者は「2級で、試験で初めてガラスを切ったという受検者がいた」、「1級受験者でも明らかに練習不足で、ミスが多かった」と指摘しており、「総じて、受検者のレベルが低い」との嘆きの声も聞かれた。 ◇ 1級の受検者が2ケタの所は7都道県で、前年の11都道府県を下回った。受検者数が最も多かったのは東京の31人(前年35人)で、2年連続で受検者数1位となっている。 しかし、2級受験者数は愛知県の25人(同22人)が最も多く、総受検者数でも愛知県が全国で最も多い44人となっており、2位の東京(36人)を大きく引き離している。 ◇ 1級合格率が100%のところは、青森、秋田、福島、石川、滋賀、兵庫、徳島、福岡、佐賀の9県(前年は岩手、石川、福井、長野、兵庫、福岡、大分、宮崎の8県)となっている。このうちこのうち、青森(2人)、石川(3人)、兵庫(3人)と福岡(6人)の4県は複数人の受検者が全員合格をした。 一方、山形(7人)、群馬(4人)、富山(2人)、山口(7人)、愛媛(3人)の5県は、複数の受検者がいたものの、合格者は0人という結果に終わっている。 また、1級2級ともに合格率が100%だったところは、石川(1級3人、2級1人)、滋賀(1級・2級各1人)、佐賀(1級1人、2級4人)の3県だった。 ◇ ガラス施工技能検定そのものが行われなかった県は、千葉、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、長崎、の7県(前年は千葉、山梨、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、香川、長崎、熊本の10県)で、前年から3県減少した。この中で、岐阜は5年連続、山梨は6年連続、香川は7年連続して、技能検定試験がおこなわれていない。 ただし、岐阜、静岡、三重の3県の受検者については、昨年、愛知で受検していることが判明したため、検定が行われていないと推測される。 また、千葉、山梨、長野の3県からは、検定試験の実施なしとの回答があり、静岡、香川、長崎3県においては、検定結果未公示との回答があった。 なお、未公示回答の3県のWebサイト上に公開されている後期検定結果には、ガラス施工の結果が掲載されていないため、検定試験が開催され、合格者が0人であった可能性も否定できないが、集計上、受検者0人の扱いとしている。 試験結果の公表が、受検を志す関係者へのモチベーションの一助となる部分もあるので、未公示の県においては、検定未開催であっても、公表の検討を重ねて望むものである。 ◇ 前回に続き、今回も女性の受検者があった。結果は、残念ながら不合格となったようだが、明るい話題と言える。 国を挙げて、建設業界で働く女性を増やそうと、様々な施策や取組が行われている。マンガ界からは「ドホジョ」、日本建設業連合会からは「けんせつ小町」といった愛称も生まれ、注目されているものの、実情はまだまだ環境面などで難しい部分が多い。 しかし、東京オリンピック・パラリンピックに向けての工事が本格化する中、職人不足は深刻化しており、男性の職人だけでは対応が難しくなっている。業界としても、女性職人の育成に力を注ぎ、ガラス施工技能士を女性に向けて、もっとアピールしていく必要がある。 女性の資格取得への挑戦を期待すると同時に、業界として資格取得を後押しできるような体制づくりを期待したい。 ◇ 今回の検定においては、前年から比べ、受検者数が大幅に減少する結果となった。また、合格率も50%を割り込んでおり、業界として危機感を持たなければならない水準になったと言わざるを得ない。 実際に一部の単組を除き、訓練校の生徒募集にも苦戦する状況で、訓練校の開設も危ぶまれる状況が続いている。業界全体で、ガラス施工技能者を広くPRする必要があるのではないだろうか。 資格を取得することで、今秋から運用が開始される「建築キャリアアップシステム」への登録も可能となり、仕事の幅を広げることができる。業界に新たな人材を呼び込むためにも、外部へのPRに注力するべきではないだろうか。
|
| ■東京都墨田区中学校体育館の改修(平成30年3月12日) |
|
東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)本所支部と向島支部所属の板ガラス店3社が墨田区立中学校3校の体育館の窓改修工事を特命随意契約で受注し、3月の春休み期間に集中工事を実施することになった。区議など関係者への息の長い働きかけや施工実績が奏功した形だ。 計画的に小中学校施設の窓改修工事を進めている墨田区教育委員会は、平成30年度についても中学校5校の体育館の工事を随意契約で地元ガラス店に発注する方針だ。 29年度下半期の「飛散防止事業」を受注したのは、本所支部の内田ガラス店、鷲尾硝子店と向島支部のママダ建装の3社。担当の区教委事務局庶務課によると、工事概要は「ガラス飛散防止フィルムの貼付等」で、内田ガラス店は墨田中学校(墨田区向島)体育館の全窓約200㎡のガラスを交換する工事を施工。 鷲尾硝子店は錦糸中学校(同区石原)体育館窓のフィルム貼付と一部強化ガラスへの改修を、ママダ建装は吾妻第二中学校(同区八広)体育館窓のフィルム貼付を中心に施工する。 受注金額は約500~700万円。それぞれ足場を組み、学校が春休みに入る3月24日から31日の1週間程度の期間での完工を目指す。 墨田区の公立小全25校と公立中全10校の窓改修事業は26年度からスタート。第1期は5カ年で小学校、中学校は第2期として30年度から2カ年で実施する計画だった。 しかし、28年4月の熊本地震の被害に鑑み、地域住民の避難場所に指定している中学校体育館の窓改修は急務と判断。全体計画の一部を見直し、築年数の古い施設について29年度から前倒しで改修工事に踏み切った。 公共施設の工事は指名入札が原則だが、学校関係では工事規模が比較的小さいことや域内中小企業の活性化を図るという墨田区の戦略もあり、区教委は初年度から随意契約方式を採用している。 この間、地域の組合員企業は区長や区議、担当部局へ陳情攻勢をかけ続けた。 内山ガラス店の八田章三社長(都硝協副理事長)によると、地元では区教委の基本設計業務などを無償で支援。そうした活動が実を結び、墨田区では学校の窓改修事業については地元のガラス店が毎年度、直接請負契約での受注に成功している。 |
■AGC新商品開発プロジェクトGIC実施 最優秀賞に「AI多機能ガラスブロック」(平成30年3月12日)
|
||||||
|
AGC旭硝子(本社・東京、島村琢哉社長)は2月28日(水)、東京・京橋のAGCスタジオで新商品開発プロジェクト「GLASS INNOVATION CHALLENGE」(GIC)の最終コンペを実施。最優秀賞など入選4作品を選出し表彰した。 GICは、民間のものづくり共創・オープンイノベーションプラットフォーム「Wemake」(ウィーメイク)を介し、一般人とAGC社員が共同で新商品を開発するプロジェクト。昨年10月にスタートした。 今回のGICは、「期待している提案」として①暮らしの体験からの発想②多くの人のためのもの③ガラスという素材を使う必然性④斬新な視点での提案―の4点を挙げ、昨年10月17日~12月8日の間、コンセプトを一般公募した。 多数の応募作品の中から1次、2次審査に残った九つの作品についてスタジオで最終コンペを開催。7作品は代表者がプレゼンテーションし、2作品は主催者側が概要を紹介した。 審査会は、AGCの平井良典CTO・技術本部長、杉本直樹商品開発研究所長、エグゼクティブフェローの中尾泰昌氏と田村良明氏など技術部門のスペシャリストら11人で構成。質疑の後、最優秀賞、優秀賞各1点、特別賞2点を選んだ。 ▽最優秀賞は、作品名「IoTを取り込んだAI多機能ガラスブロック」(代表・江藤太郎工業デザイナー)。積み木感覚でレゴブロックのようにガラスブロックを組み合わせるのが特徴だ。 大規模商業施設やオフィスビルの外窓、一般住宅のエントランスドアや窓、洋間や和室のインテリア、カフェバーなどのパーティションに展開。光や音をセットにしスマートフォンでコントロールできるとしている。 ▽優秀賞は、「お掃除楽ちん!ガラストップ風呂壁」(藤原真紀マーケティングプランナー)。浴室の壁をラコベルなど1枚のガラスに置き換え、「嫌いな家事のトップ」にあげられる風呂掃除の手間を軽減しようという趣旨。ガラスサイネージのインフォベールミラーを製膜し、タッチパネルで操作することができる。 ▽特別賞は、「空間や素材に溶け込む見えないガラス照明」( 鈴木晴也プロダクトデザイナー)と、「Windo—oh!GLASS」( 徳田周太 プロダクトデザイナー)の2点。 「見えないガラス証明」は、低反射ガラスと透明有機EL照明を組み合わせることで照明器具の存在を感じさせないという作品。「Windo」は、フィックス窓に取り付けた風穴を開閉できる装置。高層ビル内のオフィスの閉塞感を断ち切ろうという発想だ。 入選作品発表後に表彰式が行われ、平井氏が各代表者に表彰状を授与した。受賞者は「実りある経験ができた」などとコメントした。 平井氏は講評で「メーカーとしてはB—to—Bでも、B—to—B—to—Cの考え方を持たないと新しいアイディアは生まれてこない。東京・銀座の一等地に圧倒的にガラスはあるが、存在感がない。皆さんガラスの向こう側を見ている。その状態はガラス屋としては残念だ」と指摘。 その上で「AGCは2011年に東京モーターショーに出展してガラスの新しい機能をアピールし、15年からイタリアのデザインの祭典ミラノサローネに出展することでデザイン性を追求している。機能とデザインが加わるとどのように面白くなるか。(そうした意味で)今回のプロジェクトは大変面白かった。住空間が中心だったが、これもどんどん変わっていく。素材にプラスした新しいソリューションを提供していきたい」と述べた。 AGCは、GLASS INNOVATION CHALLENGEについて「ユーザーの視点からもガラスの可能性を捉え直すことで、生活を革新するような商品を生み出せる」とアピール。今後、入選作品の製品化を順次検討する方針だ。 |
■ひのまるチェーン東京支部定例総会「スペーシア全国セールスマラソン」表彰式(平成30年3月5日)
|
||
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=千葉県、井澤尚社長)と取引のある販売店で構成されるひのまるチェーン東京支部(会長・飯島今朝男氏=飯島アルミ㈱取締役会長)は、2月19日(月)東京・渋谷にあるセルリアンタワー東急ホテルにおいて、会員ら約200名が集まる中、盛大に2018年度ひのまるチェーン東京支部定例総会を開催した。その中で、スペーシア全国セールスマラソンの表彰状贈呈式も開催され、全国1位となった小池啓一商店をはじめ、全国20位までの東京支部会員計14社に表彰状が贈られた。この後、講師に医師の松本光正氏を迎え、「笑いと健康ー君子医者に近寄らず」をテーマにした講演会も併せて行われた。 総会の冒頭に主催者を代表して飯島会長があいさつ。最近の業界の動きを紹介した後「我々の仲間には大きな仕事をしている人、新築をやっている人、助成金を駆使して勉強してリフォームを提案している人等、異業種に仕事を取られないよう頑張っている。この会は35年くらい経過しているが、東京から関東一円になり、会員数も730社強と非常に大きな数字となった。2030年には、職人の数が40%減少するという話もある。こういう時だからこそ歴史を繋いで一致団結していけるような会になれば良いと思っている。そのためにはメーカー、代理店、会員が三位一体となって勝利の方程式ができれば良い」とあいさつした。 さらにひのまる会を代表し、松本巌氏(マテックス㈱代表取締役会長)が「5~6年後には新築需要が50万戸、空き家も将来1400万戸ぐらいになるという話がある一方で、リフォーム市場がますます増えそうだ。国や地方公共団体では、リフォーム市場が重要ということで補助金制度を設けている。リフォーム市場はまだまだ伸びる」とし、積極的に頑張っていこうとあいさつした。 さらに日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱東京支店長の鈴木卓氏は参会者にお礼を述べた後「現在オリンピックが話題になっているが、2020年東京オリンピック選手村には高断熱複層ガラスが入ることになっている。10年後、本年が更なる高級グレードの機能ガラスのスタートであったと振り返られるように、皆様方が持つ施工力、完成品組立力、機能ガラスの提案力全てを活かし、ガラス業界を発展させていただきたい」とあいさつし総会に華を添えた。 総会では、予算・活動計画、会則改訂、会計年度の変更などを審議、議案はすべて賛成多数で可決。役員改選では飯島会長は留任、副会長には、山口正人氏(㈱山口硝子)、芹沢幸明氏(㈱芹沢ガラス)、新役員に霜村文彦氏(霜村硝子㈱)と大畑祐二氏(㈲ワイズ・ワン)が就任した。 引き続き行われた表彰状贈呈式では、日本板硝子BP・井澤尚社長より、スペーシア全国セールスマラソンで上位に入賞した東京支部の会員14社に表彰状を、さらに、東京支店より東京エリア地域賞などが贈られた。 ☆スペーシア全国セールスマラソン(全国賞)上位企業 ▽1位=㈱小池啓一商店▽3位=窓工房▽4位=丸山硝子建材㈱▽5位=㈱あけぼの通商▽6位=㈲石田屋硝子店▽7位=㈱ナックス▽9位=横浜バンダイ㈱▽10位=㈲ワイズ・ワン▽11位=小金澤硝子㈱▽12位=㈱坂田ガラス▽17位=㈱芹沢ガラス▽18位=遠藤硝子㈱▽19位=㈱クボガラス▽20位=㈱マルタマ 表彰式後に行われた講演会では、松本講師が「笑いと健康ー君子医者に近寄らず」をテーマに1時間半以上熱弁を奮った。松本講師は、病気のほとんどはストレスが原因。心の持ち方が病気を作る。マイナス思考で血圧は上がる。クスリ(化学薬品)は危険だから、気軽に飲まない。高血圧は病気ではない。ちょうどよい血圧は年齢+90、下げると詰まる。理想体重(身長×身長×22)にしなさいなど、笑いを誘いながらわかりやすく話していた。参加者らは熱心に松本講師の話に耳を傾けていた。 最後に場所を移して懇親会も行われ、お互いの交流を深めた。 |
■AGCグラスプロダクツ―南孝也氏に聞く 補助金情報を発信(平成30年3月5日)
|
||
|
省エネ基準適合住宅が義務化される中、国、地方自治体は補助金を交付して開口部リフォームなどを推進する施策を展開。AGC旭硝子は、ともすれば煩雑なこうした行政の補助金情報をサイトで適宜発信している。担当のAGCグラスプロダクツ営業本部リグラス事業部プロモーションリーダー、南孝也氏に聞いた。 ―東京都は平成29年度から「既存住宅における高断熱窓導入促進事業」の運用を始めた。それを機に東京都の自治体の補助金情報を一覧表にまとめたとか。 「自治体の従来型のリフォーム補助金制度は省エネ関係ならば窓を含め何でもOKのようなところがあったが、都が始めた事業は窓に特化したもの。23区や市町村の助成制度との併用も可能というので、この際、都内全自治体の情報を調べてみようと。その結果を一覧表にしてまとめサイトに掲載した」 「直近では確定情報ではないが、非住宅を含め経産省や国交省、環境省の支援事業の動向をアップした。非住宅部門では病院、介護施設、学校などにアプローチし、こちら側からいろいろな補助金情報を提案。窓単独かセットで改修―といった辺りの情報をかみくだいて発信している」 「確定情報でないものを拡散するつもりはもちろんないが、確度の高い情報を発信して(一般消費者や流通業者などに)関心を持ってもらい、いざ本決まりという段階になってメールマガジンやホームページを更新していろいろな相談に対応できるようにしていきたい」 ―サイト構築のスタッフは。 「3人ほど。情報収集関係はほぼ私一人でやっている。メーカーとしての役割がどうかはわからないが、補助金に興味を持ってもらうのに情報提供は最低限必要。『皆さん、地元にはこんな補助金がありますよ』とアピールすれば、『だったら、使ってみようか』となり、窓の需要につながる。要はどこでヒットするかわからない。全国自治体の補助金情報を一通り網羅する〝全国版〟の作成に取り組んでいる」 「リフォーム会社やマンション管理会社には補助金を活用して窓改修の優先順位を上げていただきたい。昨夏、京都の大型マンションが間接的に我々の情報で補助金のことを知り、丸々1棟の窓改修を施工した」 「旭硝子系列ではないが、東京の卸販売業者がホームページに補助金情報を掲載し地域でセミナーや研修会を開催。横浜市でも市当局と提携して定期的に説明会を開いている。すごいことだと思う。我々も新年度の最新情報をいち早く提供していきたい」 |
| ■セントラル硝子販売価格を改定 板硝子製品10~15%UP(平成30年2月26日) |
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、清水正社長)は、4月1日納品分より板ガラス製品の販売価格を左記のように改定すると発表した。アップ率は板ガラス製品で10~15%、鏡製品で10~15%、加工ガラス製品で5~10%としている。発表内容は次の通り。 ☆板ガラス製品の価格改定について 拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、昨今の原燃料価格及び諸資材の価格は高騰を続けており、板ガラス及び加工ガラスの生産コストは、一段と上昇し、弊社の事業収益に多大なる影響を与えております。 こうした中、弊社としましては、製造及び販売部門におけるコスト削減及び一般管理費の削減等により収益改善の努力を継続して進めて参りましたが、原燃料及び諸資材価格の高騰によるコストの上昇分は吸収できず、また、事業収益も厳しい状況であることに鑑みて、今回、左記の通り販売価格を改定させて頂くことと致しました。 皆様方には、先般ご案内させて頂きました、受注出荷条件の改定に引き続きのお願いとなり、弊社としましては大変不本意ではありますが、何卒、事情ご賢察の上、ご理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 (1)価格改定内容 ・板ガラス製品=10~15%の価格アップ ・鏡製品=10~15%の価格アップ ・加工ガラス製品=5~10%の価格アップ (2)実施時期 2018年4月1日納入分より 以上 |
■日本板省エネルギー庁長官賞 スーパースペーシアが受賞(平成30年2月26日)
|
|||
|
日本板硝子㈱の超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」は、このほど平成29年度省エネ大賞(主催=(一財)省エネルギーセンター)の製品・ビジネスモデル部門において、省エネルギー庁長官賞を受賞した。 同賞の表彰式が2月14日(水)午前10時15分から、東京ビッグサイト会議棟レセプションホールA(東京都江東区)で開催され、省エネルギーセンターの藤洋作会長や経済産業大臣政務官の大串正樹氏ほかと、受賞企業各社の代表者が出席。 日本板硝子からは、上席執行役員 建築ガラス事業部門アジア事業部の鈴木隆部長と、同事業部日本統括部 営業部営業企画グループの朝香寛担当課長が出席した。 資源エネルギー庁長官賞受賞者として鈴木部長が登壇すると、資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部の吉田健一郎省エネルギー課長から賞状とトロフィーを受け取った。 なお、同社のスペーシアシリーズの受賞は今回で3回目。 過去には、平成10年度の資源エネルギー庁長官賞を「真空断熱ガラス スペーシア」が、25年度の省エネルギーセンター会長賞を「スペーシア21遮熱クリア」がそれぞれ受賞している。 |
■環境省壇蜜さん、省エネ住宅推進大使に(平成30年2月26日)
|
|||
|
環境省から「省エネ住宅推進大使」に任命された女優・タレント・グラビアモデルの壇蜜さんが、同省の「COOL CHOICEエコ住宅キャンペーン」に本格的に参入。開口部の断熱性能の違いを実体験し、リフォームの必要性をアピールした。 環境省は、家庭部門でのCO2排出量を2030年度に約4割削減するため、低炭素型の製品、サービス、ライフスタイルなど地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動・COOL CHOICEを推進している。 「賢い選択」の主要な政策の一つが、省エネ住宅・エコリフォームの普及促進だ。作業グループを設け、エコ住キャンペーン、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)宿泊体験と専門メディアを通した情報発信を展開。エコ住キャンペーン事業の一環として昨秋、秋田県横手市出身で昭和女子大学卒の壇蜜さんを省エネ住宅推進大使に任命した。 同省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室の平沼貴信・環境専門調査員によると、壇蜜さんに〝目を付けた〟のは、その名前。省エネ住宅の特徴である「高断熱」と「高機密」の「断(だん)」と「密(みつ)」に因み、所属事務所を通して拝命を依頼し快諾を得た。 10月2日、環境省で中川環境大臣が壇蜜さんに任命書を交付。その際、壇蜜さんは「芸名でこのような役をいただいて光栄。しっかり〝断〟と〝密〟をくっつけて覚えていただきます」と話した。 キャンペーンについては「省エネ住宅は環境への配慮や居住の快適さだけでなく、室内での熱中症やヒートショックを軽減できるので、『命を守るシステム』だとも思う」とコメントしたという。 任命式に立ち会った地球温暖化対策課の加藤聖・地球温暖化対策事業企画官は「壇蜜さんは大学医学部研究室のアシスタントをやったこともあるとかで、ヒートショックなどの知見があった。コメントも的確でした」と話している。 大使就任後、壇蜜さんは環境省とタイアップ。ビジネストークガイド(冊子)「断熱・省エネリフォーム⁄健康・快適な暮らしへ」や啓発ポスターの表紙などに登場し、エコ住キャンペーンに協力している。 平沼氏によると、断熱・省エネのメリットを簡潔にまとめた冊子は工務店や設計事務所などに好評で、当初の3万冊は昨年中に配布を完了し、年明けに3万冊を増刷した。 壇蜜さんは今年になって実践的な活動にも参画。1月17日、東京・新宿にあるLIXILショールームの快適暮らし体験「住まいStudio」を訪問し、アルミサッシ+単板ガラスの「昔の家」(昭和55年基準)とアルミと樹脂のハイブリッドサッシ+アルゴン入り複層ガラスを使った「これからの家」の各部屋に滞在して断熱効果の相違を実体験した。 LIXIL側によると、数時間に及ぶ体験会を終えた壇蜜さんは「部屋を比較してここまで違うとは思わなかった。大使としてもっと積極的に省エネ住宅・建材をPRしていきたい」と話した。 環境省の加藤氏は「著名人の発信力はやはり違う。平成30年度も壇蜜さんに大使を務めてもらう方針だ。次は、できればZEH体験宿泊事業に参加していただければと思っています」と期待を寄せている。 |
| ■AGC建築用ガラス価格引き上げ(平成30年2月12日) |
|
AGC旭硝子㈱は、4月1日(日)納品分から、国内の建築用ガラス関連製品の販売価格を引き上げると発表した。 引き上げ率は、板ガラスが10~15%、ミラーが10%程度、建築用加工ガラス製品が10%程度となる予定。 国内の建築用ガラス関連製品は、原燃材料および副資材の価格の高騰、人件費や物流費の上昇により、製造コストが大幅に上昇し、採算は悪化している。こうした環境の中、同社では生産性の向上や組織のスリム化等によるコストダウン施策を行ってきたものの、企業努力だけではコストアップを吸収することが大変難しい状況となったことから、板ガラス、ミラーの本体価格ならびに建築用加工ガラスの価格改定の実施を決めたもの。 なお、同社では今後も継続的なコストダウン施策を推進し、国内建築用ガラス事業の収益改善を目指すとしている。 |
■板硝子協会合同委員会を開催(平成30年2月5日)
|
||
|
板硝子協会(島村琢哉会長)は、1月22日(月)に東京都千代田区一ツ橋にある如水会館において、協会役員や各委員会委員長、さらにその委員・関係者らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。合同委員会終了後には、場所を2階に移動して平成30年ガラス産業連合会(略称GIC。板硝子協会、硝子繊維協会、電気硝子工業会、㈳日本硝子製品工業会、日本ガラスびん協会、㈳ニューガラスフォーラムの6団体が加盟)の新年会も開催、約370人の業界関係者が参加する中、盛大に行われた。 合同委員会の冒頭に島村会長は参加者にお礼の言葉を述べた後、次のようにあいさつした。 「昨年を振り返ってみると建築分野においてはエコガラス・防災安全ガラスの普及が期待できるさまざまな施策が経済産業省を始めとして、政府あるいは各行政から打ち出された。いくつか例をあげると建築物の省エネ法義務化が2017年4月からスタートした。2000平方㍍以上の非住宅建築物については適合義務化が実施された。今後この動きが、省エネ基準の適合義務化を含めて段階的に進むと期待している。また本年複層ガラスのJIS規格が改訂される。エコガラスの定義を変更することにともない、従来品に加えてトリプルガラスなど新たな機能ガラス、現在のものより機能の高まったグレードのものが設定される」と述べ、さらに、防災安全ガラスについては、「一般ユーザーに対し広報活動を拡げながら安全ガラスの普及に注力していきたい」と語った。 最後に、「自動車業界においても安全と信頼に基づく製品供給に努めるべく国際基準・整備にむけた活動が展開されている」と挨拶した。 引き続いて行われた合同委員会の発表では、建築委員会(武田雅宏委員長=旭)、輸送機材委員会(安東俊治委員長=日本板)、規格委員会(青木重之委員長=セ社)、環境・技術委員会(宮之本昭二委員長=日本板)、税制委員会(岩崎成俊委員長=セ社)等の各委員会の委員長より、今抱えている問題や今後の方針を述べた(別項参照)。その中で武田委員長は、防災安全ガラスの普及促進活動の成果について説明。全硝連等流通関係者の協力の下で、災害時に避難所となる小学校体育館への「防災安全ガラス」を寄贈することができたと強調した。 最後に来賓を代表して経済産業省製造産業局素材産業課・茂木正課長が、①地球温暖化防止活動や安全・健康について②税制について③自動車について等、3つの項目について講評を述べ、「協会の活動を通じて業界の発展につなげて欲しい。経産省としてもしっかりとバックアップしていく」と締めくくった。 合同委員会に引き続き場所を移動して、GICの新年会が開催され、島村GIO会長が代表のあいさつを行った。 |
■関東卸、都硝協新年賀詞交歓会(平成30年1月29日)
|
|||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(松原嘉一理事長)は、1月19日(金)午後5時より、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で9回目となる合同新年会には、来賓を併せ約130名が参会し開催された。 今年は関東卸の担当ということで司会を務めたのは福利厚生委員・堀口孝利氏。同氏の開会宣言で新年賀詞交歓会はスタート。まず主催2団体を代表して関東卸の松本理事長が多くの来賓の方々にあいさつ。 「2018年は出だしから景気が良く、明るい話題が多い」と述べた後、「業界は人手不足、賃上げ、運送費の問題など気を付けなければならない問題もある。我々とすればしっかりと利益を上げていかないとせっかく仕事があっても儲からないという状況になってしまう。ガラスは重くて非常に扱いにくい商品で施工しないと商品にならない。このあたりが我々にとっての良さで、その部分を十分に発揮して、適正な利益を上げて欲しい。ガラスは決して廃れているものではない。まだまだ可能性の多い商品だ。絶対に必要な商品を扱っているわけだから、伸びる余地は十分にある」と力強くあいさつした。 引き続き来賓を代表してセントラル硝子販売㈱東日本営業本部取締役本部長・川北泰三氏が「ガラス業界において、非住宅分野では、ようやく動き始めて、忙しい年になるのではないか。メーカーとしては納期・品質等で皆様にご迷惑をかけないよう努力する所存です。住宅については、新築の着工戸数は減ると予測されるがZEHの普及、既設においてはリフォーム、中古住宅の流通促進といった動きもあり、家の価値を落とさないという点では、開口部の断熱性を高めるということは、大事な要素ではないかと考える。国等からの支援策もあるのでうまく利用しながら、業界の仕事としてその成果を取り込むということが大事になってくる」とあいさつ。さらに「機能ガラスの普及には地道なPR活動が必要だ」と纏めた。 乾杯の音頭は都硝協・松原理事長が担当。「我々販売店は一番消費者に近いという立場を活かし、卸の協力を得て、新しい年に頑張っていきたい」とあいさつし、賀詞交歓会はスタート。しばし歓談を楽しんだ後、AGCグラスプロダクツ㈱東日本関東営業部部長・宮石真英氏が「駅やホテルなどいろいろな建物がスタートし始めた。ガラス業界が担う内装、外装での役割は非常に大きなものだ。非住宅の高機能化が進んでおり、強化ペアの出荷等、今まで単板だったところに高機能商品が増えてきている。我々業界にとって追い風が吹いてきた。逆に人手不足などコストアップの風もあり、風が舞っている状況かも知れないが、課題が多い時こそいろいろなことが変えられるのではないか」と中締めのあいさつを行い、午後7時前に終了した。 なお、当日の来賓団体・企業は次の通り(敬称略)。 ☆関東甲信越板硝子卸商業組合(敬称略) ▽板硝子協会=専務理事・森谷茂明、調査役・浅沼光一、真鼻幸信▽AGCグラスプロダクツ㈱=東日本関東営業部部長・宮石真英▽日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱=営業本部執行役員東京支店長・鈴木卓、硝子建材販売グループ課長・山崎亨▽セントラル硝子販売㈱=取締役東日本営業本部長・川北泰三、東日本営業本部特約店営業部長・松本康司 ☆東京都板硝子商工協同組合 ▽東京都職業能力開発協会=技能検定部長・杉本久雄▽関東板硝子工事協同組合=理事長・遠藤浩吉▽全硝連関東甲信越地区本部=本部長・鈴木和夫▽東京都鏡商工業協同組合=理事長・尾崎由雄▽東京板硝子施工組合=理事長・吉岡通匡▽東京板硝子鏡加工組合=会長・岩澤精一▽日本自動車ガラス販売施工事業協同組合=事務局長・森野好洋▽東京建具協同組合=副理事長・佐藤秀明▽東京南部法律事務所=弁護士・芝田佳宣、同・黒澤有紀子▽塚越税務会計事務所=監査主任・内山肇▽城東労務管理事務所=主任・常盤瞬 |
| ■日本板硝子国内建築用ガラス製品の価格改定(平成30年1月29日) |
|
日本板硝子㈱(本社=東京都港区、森重樹代表執行役社長兼CEO)は、2018年3月1日出荷分より建築用板ガラス製品の価格改定を実施し、板ガラス製品、鏡製品の価格を10~15%、建築用機能ガラス製品の価格を7~10%引き上げる発表した。その内容は次の通り。 建築用板ガラス製品においては、重油をはじめとする原燃料と各種副資材の高騰および 労働力不足による労務費の上昇が、製造コストに重大な影響を及ぼしている。 同社では、製造拠点の効率化を始めとした固定費の削減、一般管理費の削減などのコストダウン対策を実施してきたが、重油価格の高騰などによるコストアップを全て吸収することはできず販売価格に転嫁せざるを得ない状況となっているとし、このため、原燃料・副資材等のコストアップに伴う販売価格の改定を各取引先に対しお願いさせていただくこととしたと発表している。 |
| ■セントラル硝子受注出荷条件を改定(平成30年1月22日) |
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、清水正社長)硝子販売部は、受注出荷条件の一部を左記のように改定すると発表した。その内容はつぎのとおり。なお、実施時期は本年2月1日より。 受注出荷条件の一部改定について 拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、さて昨今の物流業界においては労働力不足をはじめ、多様化する顧客ニーズによる積載効率低下、長時間に亘るドライバー拘束等の環境変化により、輸送・梱包コストが増加する状況になっております。弊社としても、これまで積載効率向上、輸送形態の合理化等、物流コストダウン対策に努めて参りましたが、このような状況下において配送品質・サービスを維持する事は大変厳しい状況であり、この度、受注出荷条件の一部を改定させて頂くことと致しました。 今後も、更なるサービス向上に努めてまいりますが、お客様に於かれましては、何卒事情ご賢察の上、ご理解賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 敬具 記 1.改定内容 物流チャージの改定および新設(詳細は別紙物流チャージ一覧)をご参照ください。 2.実施時期 平成30年2月1日納入分より 以上 |
| ■AGC島村社長高収益のグローバルなメーカーに(平成30年1月22日) |
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、1月5日、島村社長の年頭あいさつとして、2018年度方針説明(要旨)を発表した。その内容は次の通り。 AGCグループにとって2017年は、2015年からスタートした中期経営計画“AGC
plus―2017”の締めくくりの年でした。業績を回復軌道に乗せることを最重要課題として取り組んだ結果、「営業利益1000億円以上」「ROE5%以上」「ガラス、電子、化学品、セラミックスの主要事業がバランスよく利益を生み出す収益構造への転換」という、中期経営計画で掲げた目標を達成できる見込みです。 2018年は、業績回復という足元目線を新たな成長シナリオを描く将来目線へと転換し、2020年を最終年度とする中期経営計画“AGC
plus―2020”をスタートします。ただし、2020年も私たちの長期ビジョンである”2025年のありたい姿”を実現するための通過点に過ぎません。”2025年のありたい姿”で掲げた、「高収益のグローバルな優良素材メーカーとなる」という目標を見据え、AGCグループは2018年を次のとおり位置付けます。 2018年の位置付け “2025年のありたい姿”を実現させるための重要なスタートの年 “2025年のありたい姿”の実現に向け、グループメンバー一同 One teamとなって解決すべき課題や成長施策へ果敢に挑戦していきます。 また、本年7月には、グローバル・グループ一体経営の総仕上げとして、社名を「旭硝子株式会社」から「AGC株式会社」へ変更します。 今後もAGCらしい素材・ソリューションの提供を通じて、社会から信頼される企業グループとなれるよう、チャレンジを続けていきます。2018年は、そのスタートとなる年でもあるのです。
|
■尾畑長硝子尾畑聡一社長情報集約し商流支援(平成30年1月22日)
|
||
|
2017年12月に尾畑長硝子株式会社の社長に就任した尾畑聡一氏に聞いた ―現在の東海地区の板ガラス業界、特に卸売業についてどうみているか。 尾畑 卸売業は他業界と同様に中抜きが進んでいる。右から左にものを動かすだけの商売は終焉している。卸業者は企業として独自のスタイルを確立しないと生き残れない。 付加価値を付けるのが大事だと思うが、現代の市況に応じた付加価値とは何なのか、それを考え最優先課題としたい。 ガラスの商流はメーカーから卸売業を経て販売店へ。更に工務店、ゼネコン、施主へと続く。こう見ると、実はエンドユーザーから最も遠いのがメーカーだ。しかし、窓業界はメーカーが主導しているのが実情だ。 特にサッシ業界にその傾向を強く感じる。施主と近い方がエンドユーザーのニーズを知っている。現状は最も遠いところで商品作りを行っているのだ。 とはいうものの、メーカーが商品を作らないと市場は回らない。メーカーあっての流通業だ。そこで、市場の声を集約する卸売業の役割が重要になると考える。工務店もゼネコンも情報を個々に持っているが、どこかで集約しないと確実な情報にならない。 販売店が減少傾向にあるが、販売店には高い技術がある。ゼネコンでなくても中低層の建物なら十分販売店が対応できるだろう。ここに仕事がある。販売店と卸売業者が協力すれば、この市場をもっと取り込めるはずだ。販売店は技術で生き残れる 卸売業は販売店と協力し、メーカーには情報を伝える。このような川上、川下双方への支援に力を入れたい。 ―サッシメーカーが完成品に傾注していた。 尾畑 完成品のような大きなものを移動させるのには物流コストがかかる。現場に近いところで組み立てる方が圧倒的に安くできる。 販売店は高い技術と現場対応力でコストを削減し利益も捻りだしてきた。それを考慮せずにメーカーが完成品を作った。低価格こそが正義ということかもしれないが。 完成品以外でも、原寸発注が増加している。しかし、これだと販売店が自らの工夫を凝らして切断することで1枚のガラス板をより効率的に使っていた時代と比べると利益を生み出しにくくなっているのではないか。 ―市場は窓業界にとって追い風が吹いているはずだが。 尾畑 ほとんどの建築資材は高騰しているのにサッシとガラスだけが低迷したままだ。省エネ、ZEHなどフォローの風が吹いているが価格は下落傾向にある。 省エネだけを考えたら窓の無い住宅が最も効率が良い。しかし、生活には窓が必要だ。窓を通じた提案はまだまだできるはず。我々が提案力不足であり、その結果、市場に認知されていないのだ。生活者が窓を視界におさめない日はないのに、窓そのものに注目してもらえない。もっと努力が必要だ。 以前は、これはメーカーの仕事だと思い込んでいた。しかし、前述した通りメーカーはエンドユーザーから遠いところにいる。卸業者こそがメーカーと地域を繋ぐ仕事ができる。 ガラス、窓の価値を理解してもらえれば、低価格に落ち込むことはないはずだ。窓は生活を一変させる可能性を秘めているのだから。 ―2020年に創業100年を迎えると聞くが、5代目社長として守るべき伝統とは。 尾畑 長く続く会社だが、変えてはいけないことがある。それは「ガラス」である。当社はガラスにこだわる。 ガラスは素晴らしい素材だ。ガラスがあってこその尾畑長硝子だ。今後、新たな機能を持つガラスが登場し、用途も広がるだろう。内装やサイネージなど、日々その可能性は拡大している。 社名から「硝子」の文字は外さない。「尾畑長硝子」だから「ガラスを扱っている」のが分かってもらえる。ガラス関連企業としてのプライドを持ち続けたい。
|
| ■旭硝子受注出荷条件を改定(平成29年12月25日) |
|
旭硝子㈱(本社=東京都、島村琢哉社長)・ビルディング・産業ガラスカンパニー・アジア事業本部(日本事業部長・新井太吉氏)は、板ガラス・ミラー(定寸品) 受注出荷条件の一部を次のように改定すると発表した。発表内容は次の通り 拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度弊社では、受注出荷条件の一部を改定させていただくことと致しましたので、次のとおりご案内申し上げます。 各メディアでも報道されておりますとおり、配送業務の現場はかつてない厳しい環境にあり、日本全体の人手不足によって労働力の確保も困難となっております。一方、配送品質の維持、向上はメーカーとしての責務であり、良質なサービスを提供していくには、上記の環境変化からコストの増加を避けられない状況にあります。 弊社と致しましても、配送の集約、製造コストダウン、管理費削減等の対策を講じて参りましたが、この度やむを得ず、お客様に一部のご負担をお願いさせていただくことと致しました。 お客様におかれましては、事情ご賢察の上、ご理解いただけますよう何卒宜しく お願い申し上げます。 1.今回改定対象 2.改定内容 * その他の項目につきましては今回据え置きとしておりますが、今後の物流費の状況等を踏まえ、見直しをしていく予定です。 3.適用開始日 ガラス・建材商品受注出荷条件一部改定のご案内 拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度弊社では、受注出荷条件の一部を改定させていただくことと致しましたので、左記のとおりご案内申し上げます。各メディアでも報道されておりますとおり、配送業務の現場はかつてない厳しい環境にあり、日本全体の人手不足によって労働力の確保も困難となっております。 一方、配送品質の維持、向上はメーカーとしての責務であり、良質なサービスを提供していくには、上記の環境変化からコストの増加を避けられない状況にあります。弊社と致しましても、配送の集約、製造コストダウン、管理費削減等の対策を講じて 参りましたが、この度やむを得ず、お客様に一部のご負担をお願いさせていただくことと 致しました。お客様におかれましては、事情ご賢察の上、ご理解いただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 1.改定内容 2.実施時期 |
| ■全国卸・全硝連 断熱リフォーム支援事業で経産省へ陳情に(平成29年12月25日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会の松本巖会長と全国板硝子商工協同組合連合会の辻良明会長は11月28日(火)経済産業省生活製品課を訪問し、次年度も引き続き予定されている「平成30年度高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」に関して、陳情にあがった。面談したのは同課・住宅産業室係長(技術・新市場担当)今福幸一氏。陳情内容は次の通り。 次年度も引き続き実施を予定しております「高性能建材による住宅の 記 1.補助金額に関して「補助対象費用の3分の1以内か1住戸当たり上限15万円のいずれか低い金額」について 要望→1住戸当たり上限15万円の制約を排除して戴きたい。 ※過去の制度通り「算定上限金額と補助対象費用のどちらか低い方の3分の1以内」であればモチベーションも上がり、地域事業者を含む流通も積極的に営業が出来る。 ※一般的には、多数住戸で集合住宅は成り立っているが、少数住戸で窓数が多いマンションの場合は補助金の恩恵を受けられない。 2.事前契約・事前着工は厳禁。 要望時事業者登録申請済み(住戸数は制限しない)事業者であれば可として戴きたい。 ※工事の全体工程そのものが補助金ありきで進捗し、工事期間が集中してしまう。 ※年内遅く契約した物件は、完工納期に間に合わないケースが出て来る。 3.集合住宅(全体)に関する件。 要望→公募を一次公募で終了ではなく、複数回公募にして戴きたい。 ※改修工事には、管理組合の総会決議議事録が必須であり、総会及び臨時総会の開催が時期的に間に合わないケースが発生する。 4.集合住宅(個別)に関する件。 要望→今集合住宅(個別)の公募期聞は、小刻みでも構わないので継続して公募をして戴きたい。 ※補助金予約者決定通知の結果を早く知ることで地域事業者は営業活動がし易い。 ※補助金予算が突然無くなるというリスク(不安)を背負わないでマンション住民にアブローチ出来る。 以上、私ども板ガラス流通団体がお願いをさせて頂きたい事項でございます。何卒ご配慮の程宜しくお願い申し上げます。 |
■日研硝子「SPEED24MB」導入」(平成29年12月25日)
|
|||
|
日研硝子㈱(本社=東京都台東区根岸、久保信之社長)は、このほど関東事業センター(埼玉県上尾市)にイタリアCMS Brembana社製の多機能型CNC加工機「SPEED(スピード)24MB」を導入した。 同社の保有していた加工機が古くなり、メンテナンス等に時間がかかって稼働率が低下していたことから、2017年に入って機種の選定を進め、3月中旬に導入を決め、代理店のバンドー貿易㈱(徳島市金沢)を経由して発注した。8月の盆休み明けに第1工場内に設置し、そこから約2週間のトレーニングなどを経て、9月中旬から本格稼働を開始している。 現在は、主に厚物の異型加工や、カマボコ磨きなどにフル稼働しているとの事だった。 同社製造部の奥脇肇部長によると、「導入直後は、古い機械との違いから中々作業効率が上がらなかったが、バンドー貿易の担当者がトレーニングの2週間、色々と指導をしてくれたので、効率も上がり、今では以前と同様に動かせている。メンテナンスの面でも、オンラインでチェックが出来るため、不具合が出ても早く対応できるため、安心できる」との事だった。 スピード24MBの加工能力許容範囲は次の通り。 ◎板厚、加工範囲 ◎加工形状 ◎その他加工 〇穴あけ ○切込角 ◇多機能型CNC加工機「SPEED24MB」 3軸(X、Y、Z)を内蔵する数値制御で動く、厚手および薄手の板硝子加工に適した加工センター。基本構成として糸面取り、ミリング、端面、彫刻、文字入れや縦方向の穴明け、端面研磨、ポリッシングが可能となっている。 ◇ また、同社は加工以外にも、様々なガラスの施工を手掛けており、最近では都内の大手商業施設などに、鏡やカラーガラスの取り付けを行っている。複雑な施工も多いため、施主に満足してもらえるよう、丁寧な仕事を心がけているとの事だった。 なお、加工に関する問い合わせは、日研硝子㈱関東事業センター(電話=048‐774‐6111・FAX=048‐773‐6000)まで。日研硝子㈱(本社=東京都台東区根岸、久保信之社長)は、このほど関東事業センター(埼玉県上尾市)にイタリアCMS Brembana社製の多機能型CNC加工機「SPEED(スピード)24MB」を導入した。 同社の保有していた加工機が古くなり、メンテナンス等に時間がかかって稼働率が低下していたことから、2017年に入って機種の選定を進め、3月中旬に導入を決め、代理店のバンドー貿易㈱(徳島市金沢)を経由して発注した。8月の盆休み明けに第1工場内に設置し、そこから約2週間のトレーニングなどを経て、9月中旬から本格稼働を開始している。 現在は、主に厚物の異型加工や、カマボコ磨きなどにフル稼働しているとの事だった。 同社製造部の奥脇肇部長によると、「導入直後は、古い機械との違いから中々作業効率が上がらなかったが、バンドー貿易の担当者がトレーニングの2週間、色々と指導をしてくれたので、効率も上がり、今では以前と同様に動かせている。メンテナンスの面でも、オンラインでチェックが出来るため、不具合が出ても早く対応できるため、安心できる」との事だった。 スピード24MBの加工能力許容範囲は次の通り。 ◎板厚、加工範囲 ・板厚=5㍉~19㍉ ◎加工形状 ・小口磨き=5㍉~19㍉ ◎その他加工 〇穴あけ ○切込角 ◇多機能型CNC加工機「SPEED24MB」 3軸(X、Y、Z)を内蔵する数値制御で動く、厚手および薄手の板硝子加工に適した加工センター。基本構成として糸面取り、ミリング、端面、彫刻、文字入れや縦方向の穴明け、端面研磨、ポリッシングが可能となっている。 ◇ また、同社は加工以外にも、様々なガラスの施工を手掛けており、最近では都内の大手商業施設などに、鏡やカラーガラスの取り付けを行っている。複雑な施工も多いため、施主に満足してもらえるよう、丁寧な仕事を心がけているとの事だった。 なお、加工に関する問い合わせは、日研硝子㈱関東事業センター(電話=048‐774‐6111・FAX=048‐773‐6000)まで。 |
■東海ひのまる会、日本板硝子ビルディングプロダクツ「真空ガラス王座決定戦」表彰式(平成29年12月11日)
|
||||
|
東海ひのまる会(立木彰一会長)と日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社は11月29日、名古屋市千種区千種のサッポロビール名古屋ビール園浩養園で「窓サポート倶楽部名古屋大交流祭」を開いた。250人が参加した。 冒頭、東海ひのまる会を代表して立木彰一会長からあいさつがあった。 講演会では有限会社松尾設計室代表取締役松尾和也氏が「健康で快適な省エネ住宅は窓から始まる」の標題で約1時間半にわたって講演した。 松尾氏は「健康に暮らせる住宅は、エンドユーザーが購入時に支払う金額だけでなく、数十年間に渡るランニングコストも含めて提案すれば購入者の理解も深まる」などと話し、また、「男性中心に部屋の暖かい、寒いではなく、奥さんの視点が必要」などとした。窓の性能に焦点を当てた話も多く、「安窓買いの銭失いではいけない」と結論づけた。 この後、日本板硝子ビルディングプロダクツ名古屋支店硝子建材販売課の浅倉裕喜課長代理から超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」について説明があった。 最後に日本板硝子ビルディングプロダクツ名古屋支店小畑哲支店長からあいさつがあった。 立木彰一会長のあいさつ 東海4県の住宅着工件数は前年並みで、経済は総じて東海4県は好調だ。工作機メーカーが3割増になるなど、多業種で増加傾向にある。半面、人手不足というのは悪い状況だといえる。人件費については、パートが正社員に切り替える企業が多くなっている。 小畑哲支店長のあいさつ 松尾先生から専門的なことを省いて分かりやすく説明して頂いた。今後、営業活動のヒントになればと思う。 【表彰企業】 ・岐阜県 ・三重県 ・静岡県 前年伸び率賞 特別賞 20周年記念品贈呈企業 |
| ■日本板硝子ビルディングプロダクツ受注出荷条件を改定(平成29年12月4日) |
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=千葉県市原市、井澤尚社長)は、12月1日の出荷分より建築用板ガラス製品の受注出荷条件を一部改定すると発表した。 昨今、物流業界では、働き方改革、労働力不足、顧客ニーズの多様化などへの対応を求められており、これらの環境変化によって急激に物流コストが増加する状況となっている。 同社としても、製造拠点の効率化を始めとした製造コスト及び物流コストの削減等コストダウン対策に鋭意取り組んできたが、従来のサービスを維持するために、やむを得ず受注出荷条件の一部を次の通り改定することとした、としている。 (1)改定の概要 一般品(鏡を含む)及び機能ガラスに関する出荷条件の一部を改定する。 ①配送料(工事現場向け含む)の改定 ②到着時間指定料金の改定 ③大板配送チャージの新設 ④その他 (2)改定期日 2017年12月1日出荷分より 同社では、本改定を通じ、本来のメーカーとしてのサービス、品質向上に一層集中して取り組んでいくとしている。 |
■中村ガラス中村勉社長に聞く(平成29年12月4日)
|
|||
|
新潟県でガラスの加工などを手掛ける、㈱中村ガラス(新潟市北区島見町3399番地44)は、今年5月に事業所を移転、東京事務所も設立するなど、順調に事業を拡大している。 ◇ ―よろしくお願いします。早速ですが、まずは、新潟県の現在の状況などを、会長のお立場でお訊ねします― ―エコリフォームなどの仕事はいかがですか?― ―人不足という所が、ここにも影響してくるわけですね ―最後に、新潟の組合としての活動はいかがでしょう― ◇ ―さて、ここからは、中村ガラスさんのお話を聞かせて頂きたく思います。今年の春に現在の場所に移転されました。その経緯から伺いたく思います?― ―改めて、加工の内容を改めて伺います― ―最近のお仕事の状況はいかがですか?― ―東京と言いますと、今年、東京事業所を開設されましたが、その経緯をお訪ねしたく思います― ―東京事業所では、どのような加工をされているのですか?― ―東京事業の体制や中心となっているお仕事は?― ―先程、組合のお話の中で、人手不足が話題に上がりました。中村ガラスさんでは、人員の募集をどの様に行われていますか― ―せっかく就職しても、休みが合わないなどの理由で、すぐにやめていく若い人も多いと聞いています。若い人にガラス業界の方を向いてくれるのは難しいかも知れません― ―今回は、お忙しい所、貴重なお話をありがとうございました。 ◇ ◎㈱中村ガラス 電話=025‐255‐3388 WEB http://www.nng.co.jp |
■セントラル硝子国際建築設計競技(平成29年11月27日)
|
||||||
|
セントラル硝子㈱(清水正社長)は、11月11日(土)午後1時30分から、東京都千代田区の東京国際フォーラムD7ホールにおいて、「第52回セントラル硝子国際建築設計競技」の公開2次審査を開催した。 今回の課題は、「広場のリ・デザイン」で、国内外からの応募総数251点(国内134点、海外117点)の中から、1次審査を通過した7組のプレゼンテーションが行われた後、公開2次審査で最優秀作品1点と、優秀作品2点が選出された。 最優秀賞は、都市の20%を占める道路における、交通標識などの内容を、人間用のデザインに読み替える(リ・デザインする)ことで、道路を車の物ではなく、人間のものとして、広場としての機能を持たせることを提案した、韓国のソヒ・ユン氏、スジ・チェ氏(共にソウル大学校)、インジュン・カン氏(東国大学校)の三名からなるチームが選ばれ、賞金200万円と記念品が授与された。 優秀賞2組には、韓国・ソウル市の光化門(クァンファムン)の歴史的な考察と、周囲の壁の角度を変えることで過去と現在をつなぐ広場とすることを提案した、アメリカのジヒョン・キム氏(ラガーディア・ロウ・アーキテクツ)。山手線を動く歩道化し、スピードの違う歩道を並列することで乗り換えの便をよくすると同時に、同じような心のスピードを持つ人々が集まる広場としても活用する提案を行った、日本の山口杏奈氏(長岡造形大学)と河野裕太氏(長岡造形大学大学院)の「動く広場」、のふたつを選び、それぞれ賞金30万円と記念品を贈呈した。 また、入選4点には各賞金10万円と記念品、佳作10点には賞金各5万円が贈られた。 今回の課題である「広場のリ・デザイン」は、人が集い、市が開かれるなど、市民の日常的なコミュニティの場になっている「広場」は、現代においては駅前に広がる交通の要所であり、集会やイベントが開かれる共有の場であり、憩いや休息のための個人の空間であり、公共や個人、官や民の区別があいまいなパブリック・スペースでもある。しかし、社会状況が変化する中で都市形成の中心的な役割を果たしている「広場」は、このままでよいのだろうか?との問題提起から、人を主役とした「広場」の「リ・デザイン」をテーマとしたもの。 同競技を後援する、㈱新建築社の司方裕取締役編集長の司会で開会した公開審査は、初めにセントラル硝子の清水社長の挨拶に続いて、プレゼンテーションが行われた。 9月12日(火)に行われた一次審査を通過した7作品の代表者がエントリー順に登壇、自作品について5分間のプレゼンテーションと、8分間の審査委員7人からの質疑応答に臨んだ。 その後、壇上に審査委員7人が登壇し、各作品についての感想や講評を述べる公開審査が行われ、審査委員からは「広場というテーマに対して、建築物を作り込みすぎる傾向にある。建築設計競技なので仕方のない部分もあるかもしれない」や、「非常に面白い発想の物が審査に上がってくるのは、セントラル硝子のコンペならでは」といった感想や、各作品に対する辛口の評価が行われた。 賞を決める投票では、1回目でソヒ・ユン氏、スジ・チェ氏、インジュン・カン氏のチームが最多の7票を集め、最優秀賞を獲得した。しかし、優秀賞の2点を選ぶ段階で、1票差で3作品が並んでいたことから、再度投票が行われ、ジヒョン・キム氏の作品が優秀賞の1点目に選ばれた。ところが、今度は優秀賞2点目候補の作品ふたつが同展となってしまったため、協議の末、最優秀作品候補にも挙がっていた日本の山口杏奈氏と河野裕太氏の「動く広場」が優秀賞の2点目に決定した。 審査終了後の午後5時からは表彰式に移り、清水社長が壇上で入賞者に賞状と記念品を授与。最後に審査委員長の内藤廣氏が講評を述べ、審査は終了した。 なお、審査委員は次の通り(敬称略、順不同) ▽審査委員長 内藤廣(内藤廣建築設計事務所)▽審査委員 亀井忠夫(日建設計)▽同 小林輝雄(大林組)▽同 隈研吾(隈研吾建築都市設計事務所)▽同 青木淳(青木淳建築計画事務所)▽同 塚本由春(アトリエ・ワン)▽同 髙山聡(セントラル硝子取締役常務執行役員) ◇ ◎セントラル硝子 清水社長の挨拶(要約) 「おかげさまで、セントラル硝子国際建築設計競技も52回目を迎えることとなりました。半世紀を超えて、これからも建築界に微力ながら貢献できるように努めてまいります。本日ここにお集まりいただいた、厳選された、若き力を持つ皆様は、これを機会に世界で活躍することをお祈り申し上げております。2次審査となる本日は、プレゼンテーターの皆さんの、作品の内に込められているテーマに対する回答や、新しい提案をアピールしていただきたいと思います。プレゼンテーションによって審査委員の先生方の評価や、見方も変わるかもしれません。先生方の厳しい言葉に臆することなく、自分の言葉で素直に伝えていただければと思います」 |
■機能ガラス普及推進協議会・全硝連近畿地区本部「防災安全ガラス」寄贈式(平成29年11月27日)
|
||||||
|
機能ガラス普及推進協議会(島村琢哉会長)と 全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長、以下「全硝連」)の近畿地区本部(小村哲也本部長)は11月13日(月)午後1時から、奈良県生駒市(小紫雅史市長)の生駒市役所において、市立真弓小学校体育館(避難所)に寄贈した「防災安全ガラス」の寄贈式を行った。 今回の寄贈式は、同協議会と全硝連が、真弓小学校の体育館に「防災安全ガラス」156枚と、その設置に関わる工事費など約500万円相当を寄贈、今年8月1日~4日にかけて設置工事を実施したことにたいして行われたもの。 寄贈式には、生駒市側から市教育委員会の仲田好昭教育長、教育振興部教育総務課の辻中伸弘課長と山本英樹課長補佐が参加。機能ガラス普及推進協議会からは、企画運営委員の森谷茂明委員長と浅沼光一事務局長が参加し、ガラスを提供した日本板硝子から日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱執行役員大阪支店長の大野義之氏、現場配送を担当した村島硝子商事㈱の村島靖基社長、工事を担当した全硝連の辻良明会長と小村哲也近畿地区本部長、奈良県板硝子商工業協同組合の尾下一雄理事長、大阪府板硝子商工業協同組合の大村宗一郎副理事長と鳥山幸嗣専務理事、生駒市の小紫市長を辻会長に紹介した㈱阪口文化堂の阪口敏也社長が参加した。 山本課長補佐の司会で開会した贈呈式は、初めに森谷氏が「生駒市教育委員会の皆様には、防災安全ガラスの寄贈の趣旨をご理解くださり、工事などにも多大なご尽力をいただき、ありがとうございました。今回寄贈させていただきました防災安全ガラスは一般のガラスよりも割れにくく、割れても飛散しにくいため、割れた場合の二次災害なども発生しにくいものです。生駒市の真弓小学校が寄贈活動の第1号となります。今後も寄贈活動を継続し、社会のお役に少しでも立てればと考えております」と挨拶した。 続いて、森谷氏から仲田教育長に目録が贈呈され、寄贈に対する感謝状が仲田教育長から森谷氏に送られた。 また、仲田教育長から「災害発生時に、公共団体としては地域の方々の安全、安心を守るために、施設が対応しなければなりません。今までは耐震化を重点的にやってきましたが、今後は避難所の確保が重要になってきます。割れたガラスが床に刺さるなどの危険性が指摘される中、今回寄贈を頂いたことは、現場はもとより市民、保護者もガラスの重要性を認識できたと思います。またこの後、真弓小学校で出前授業をしていただけるとの事で、ありがたく思っております。引き続きこのような活動を続けて頂きたい」と謝辞を述べ、贈呈式は終了した。 その後、場所を真弓小学校に移し、同校の多目的教室に5年生の児童84名を集めて、ガラスの出張授業を行った。 授業は、機能ガラス普及推進協議会の浅沼事務局長が講師となり、パワーポイントを使用しながら、ガラスの歴史や種類、フロートガラス、網入りガラス、強化ガラス、安全防災ガラスの特性などを動画も交えながら説明した。 続いて、大硝協の大村副理事長と鳥山専務理事が、ガラス破壊のデモンストレーションを行った。フロートガラス(3㍉)、磨ヒシワイヤガラス(6・8㍉)、強化ガラス(テンパライト/4㍉)、防災安全ガラス(ラミセーフセキュリティ/3+3㍉・30ミル)をセットしたデモ器2台を教室に設置、生徒の代表男女4名が、それぞれのガラスをハンマーで叩き、その割れ方や、安全ガラスの丈夫さを確認した。 また、ガラスを割った後のデモ器には、見学の生徒が押し寄せ、丈夫な防災安全ガラスの様子に目を見張っていた。 最後に、森谷委員長が、生徒代表に記念品としてボールペンとクリアファイルを贈呈、生徒の代表から謝辞を受けて、出張授業は終了となった。 |
■AGC東京モーターショーに出展自動運転にガラスが活躍(平成29年11月13日)
|
|||
|
AGC旭硝子(本社・東京、島村琢哉社長)は東京モーターショーと同時開催の関連企画「TOKYO CONNECTED LAB 2017」に出展し、自動運転に向けて透明材料のガラスが活躍できる最新技術をモデル車で紹介した。 東京ビッグサイトで開催された第45回東京モーターショー2017(10月27日~11月5日)開幕前日の10月26日(木)、西展示棟4ホールに構えた自社ブースでプレゼンテーションを実施した。 CONNECTED LABは、主催者によると、未来のモビリティ社会がもたらす価値や社会とのつながりを来場者とともに考えようという参加型プログラム。主要自動車メーカー、デンソー、KDDI、環境省、国交省道路局などが専用ブースを設けて出展した。 AGCは、「デジタルプラットフォームとしてのガラス」をテーマに、これからの「人と車のインタラクティブ(相互に作用する)コミュニケーションでのガラスの役割」について可能性の高い〝近未来像〟を提案した。 ブース前面にハンドルがない来るべき「AGCの考える自動運転時代のクルマ」を配置。報道陣へのプレゼンテーションでは、最初に同社執行役員・事業開拓部長の杉本直樹氏が理念をわかりやすく解説した。 モデル車では、フロントガラス、ドアウインドウ、コーナーウインドウ、ルームミラー、リアウインドウなど各部位の透明なガラスの果たす役割を独自に明示した。 フロントガラスはスクリーンの役割を担い、ナビゲーション、建造物情報、後方映像を映し出す。ドアウインドウには「間もなく発車します」などと車外の人にメッセージを発信するデジタルボードを用意。コーナーウインドウにはウインカーの機能を持たせる―といった具合だ。ブースの担当者は「どれも透明なガラスの使い方の一つとして提示しました」と話した。 また、車内前面のボードにはインストルメント・パネルを設置し、運転情報、一般情報、ナビゲーション、エンターテイメントを利用できるように配慮。 いずれもガラスに液晶ディスプレイモニターを貼り付ける「インフォベール」、透明なガラススクリーンにプロジェクターで特定な画像を映し出す「グラシーン」など同社のガラスサイネージ製品を応用。さらに、モバイル機器に適した化学強化ガラス「ドラゴントレイル」やフッ素系摩耗耐久防汚剤「シュレコ」を駆使しているのが特徴だ。 |
■全硝工連橋本会長が強調基幹技能者制度を維持(平成29年11月6日)
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(橋本和明会長)は10月24日(火)、東京・日本橋浜町の浜町TSKビル会議室で全国理事会を開催し、登録基幹技能者講習や社会保険加入問題などを協議。来年3月の次期理事会を広島で開催することを決めた。 会合には九州、中国、関西、北陸、東海、関東、東北の各地区理事長ら14人が出席。山田圭一常務理事(関東)の司会の下、午後1時に開会した。 橋本会長(中国工事理事長)は冒頭、「建設業界におけるガラス工事業界の位置付けはなかなか厳しい。その位置付けをもっと上げてゼネコンに認知され、そして儲けさせていただく。その一環として登録硝子工事基幹技能者講習制度があり、既に確立した。素晴らしいことだ。全硝工連としてずっと続けていく」とあいさつした。 全硝連(辻良明会長)と連携し運営している基幹技能者制度については田中敏也専務理事(関東)が実績や次年度の予定を説明。9月2~3の両日、福岡市で実施した平成29年度講習・修了試験では36人全員が合格したが、田中氏は「佐賀、宮崎、沖縄はゼロ。近畿、四国も少ない。この辺をどう穴埋めしていくかが課題」と指摘した。 事務局によると、10月1日現在の合格者は全国で277人。地区別内訳をみると北海道5、東北59、関東甲信越81、東海北陸67、近畿14、中国四国14、九州沖縄37。九州沖縄以外の「ゼロ県」は山梨、富山、滋賀、和歌山、徳島、高知、愛媛の各県。 田中氏は次年度以降の実施計画について9月下旬の講習委員会での意見交換を基に「次回講習は東京と関西・中国地区の計2カ所で開催したい。年内に決定する。また、第1期5年間の有効期限が切れる32年3月27日の半年前から更新講習ができるよう準備が必要」と報告した。 登録基幹技能者については国交省が建設業法による主任技術者の要件に認定する―との情報もあり、会合ではゼネコンの賃金面での優遇策を含め「募集のインセンティブとなる」といった認識が示された。 「協力会社も含めて100%加入を目指す」としている懸案の社会保険加入促進問題については山田宏理事(関東)が説明。議論では一人親方のあり方や労働時間、地域特性といった課題を抱え「一元管理は難しい」(遠藤浩吉副会長)との見方が大勢を占めた。 国交省顕彰の建設マスター・建設ジュニアマスターについては田中専務が「来年度の推薦者地区別配分表に基づき年内に企業・個人を選定してほしい」と要望。建設キャリアアップシステムについては「基幹技能者をゴールドカードに」とのメリットが強調されたものの、「運用は当初予定より遅れている」と報告した。 |
■AGC「DEJIMA」に協賛(平成29年11月6日)
|
|||
|
AGC旭硝子㈱は、伊藤忠テクノソリューションズ㈱(東京都、菊地哲社長、略称=CTC)が10月16日(月)に開設したオープンイノベーションスペース「DEJIMA」に協賛している。 同社の製品が、コミュニケーションを促進し、新たなインスピレーションやイノベーションを生む場に一役買うことになる。 CTCは、新規ビジネスのアイデア創出から事業化までを総合的に支援するオープンイノベーションプラットフォーム「CTC Future Factory」を2017年6月9日からスタートしている。「DEJIMA」は、このサービスにおいて未来のアイデアを創出するための拠点となる場所で、AGCはイノベーション創出に向けた活動に賛同し、製品を提供することを決めたもの。 「DEJIMA」には、①カラーガラス「ラコベル プリュム」 ガラス特有の質感やカラーがイノベーションスペースを彩るだけでなく、ホワイトボードとして利用可能、②ガラスサイネージシリーズ ガラス一体型デジタルサイネージ「infoverre」(年内導入予定) ガラストップテーブルと一体となったディスプレイにタッチ機能を搭載し、情報を瞬時に映し出す、の2つの製品を提供する。 今後、「DEJIMA」で実際にAGC製品を使用した利用者からのフィードバックや、ワークショップの開催などを通じて、新たな機能開発や商品開発につなげていきたい考え。 ◇ 「DEJIMA」の内部は、大きくグループワークエリアとワークショップエリアに分かれている。グループワークエリアの壁面には、ラコベルが貼り付けられており、ホワイトボードのようにディスカッションの内容などが、自由に書き込めるようになっている。現在、AGCとCTCの間で「インフォベール」の「DEJIMA」での活用方法のディスカッションが行われており、様々な意見を集約し、年内に設置する予定との事だった。 「DEJIMA」は、企業や個人が横のつながりを作る場を提供し、新しい市場や商品開発などを進めることを目的としている。入館はスマートフォンなどのアプリで管理され、入館すると館内のディスプレイに入館者カードが表示される。そのカードに自分のカードをドラック・ドロップすることで、初対面の人にもコンタクトが取りやすく、コミュニケーションを図れるようなシステムも用意されている。 CTC社では、ワークショップやコラボレーションなどを通じてコミュニケーションを活性化する場として、運営していきたいとしている。 ◇ なお、「DEJIMA」の概要は、次のとおり。 住所=東京都品川区東五反田2‐10‐2 五反田スクエア13階 電話番号=03‐5789‐2350 開館時間 平日=午前9時~午後6時(時間外利用は応相談) 定休日=土日・祝日 ホームページ=https://dejima.space/ |
■AGCグラスプロダクツ 代表取締役社長深川祐一氏に聞く(平成29年10月30日)
|
||
|
昨年12月にAGCグラスプロクダツ㈱(本社=東京都)の社長に就任した深川祐一氏。今回は社長に就任して1年近く経過したということで、氏に同社を取り巻く環境や現状、今後の動向などを伺った(時報社との共同取材)。 (1)自社の現況について 国内建築加工ガラス事業を統合する形で、平成19年5月1日からスタートしたが、一時業績不振でかなり苦しい時期もあった。ここ2~3年は安定した業績を維持している。ROS(Rate
of Sales=企業の売上高、経常利益をパーセントで表せたもの)的には未だ改善の余地はあるが、順調な業績が続いている。10年前の弊社の立ち上げから参画していたが、東日本大震災やリーマンショック、LIXILとの業務提携等、大きなイベントが多々あった。昨年に社長として戻ってきたが、当時と比較すると社内のマネジメントレベルがかなり向上してきている。その向上が安定した業績につながっている。 建築加工用の業界というのは「濡れ手で粟」の業界ではない。細かい対応を積み重ねて、薄い利益をいただく業界。重要なことは、需給の波にどれだけフレキシブルに対応できるかということ。それで、マネジメントレベルが問われている。そのレベルが向上してきたことが安定した業績になっている。安定した会社になって、戻ってこられたことはありがたいと思っている。パイが限られた業界なので、売上そのものは横ばいにちかい。その限られた売上の中で、利益を上げられるようになったというのが現状。 住宅、ビル、内装関係に分けて現況を説明すると、住宅用のガラスについては、LIXILとの業務提携をベースに一般流通向けにもガラスを供給し続けている。住宅向けの売上については、西日本の方が調子よく、関東・東北が苦戦している。マンション関係はまだら模様。大手ハウスメーカー向けも良くない。 ビル用については、 住宅に比べてアップダウンが激しい。その需給バランスに合わせてフレキシブルに対応している。ビル向けは東京オリンピック等まだまだ伸びる要素が大きい。伸びに応えられるよう、また、付加価値の高いガラスを世の中に広めていくのが責務だと考える。ビル向けの売上については、市場の伸びとほぼ同じくらいで推移している。 (2)今後の市場動向及びその対応 住宅向けは、徐々に悪くなってきている感じ。一過性という声も聞かれるが、個人的には、住宅着工減少という大きなトレンドの波になってきたのではないかと感じている。体制も切り替えていかなければない。 ビル用は、今年の後半ぐらいから物件物が動くと聞いていたので、それに備えてきたのだが、逃げ水のように遅れている感じがする。でも必ず波は来るので、住宅用からビル用に経営資源をシフトすることも考えなければならない。 内装用については、世の中の需給の動きとは別に、これから新たな市場をどれだけ創造し伸ばして行けるかを考えている。住宅用で浮いてくるであろう経営資源をこちらに充てて行きたいと考える。キッチン廻りとかは、高級感などガラスの特性を活かせる分野だと思っている。キッチンでガラスの良さを実感してもらえれば、他の分野にもガラスに興味をもっていただけるのではないかと期待している。そのためのプロモーション等も考えているので期待していて欲しい。 ヨーロッパでは上手に建物の中にガラスを活用している。「ラコベル」はヨーロッパで成功したカラーガラスで日本でも普及させようと注力している。今までのパターンを考えるとヨーロッパで起こったことは、いずれ日本にもきている。「Low―Eガラス」や「トリプルガラス」もそうだ。ヨーロッパでは「トリプルガラス」は当たり前の時代。意外に日本でも全国的にトリプルガラスが普及しはじめている。良いものが欲しいというニーズはどんなエリアでもあるということを実感している。 (3)最後に 住宅用にしてもビル向けにしても日本の人口問題を考えると既存商品による市場のパイが伸び続けることはない。既存商品については、適正で安定した収益があげられればそれで良しとしなければならない。流通には流通の機能がある。それを我々メーカーがやっても逆にコストがあがってしまう。既存商品のパイは奪い合いをしても意味がないし、競合他社や流通から叩き合いによって奪うという考え方は取らない。 そのような中で重要だと考えているのは、新商品や新事業によってお客様に新たなバリューを提供し、その対価として利益をいただくこと。既存事業でも三層ガラスやガス入りペアなど、より付加価値の高い商品を提供していきたい。ラコベルプリュム(内装ガラス)やヘイリオ(スマート調光ガラス)など新事業のネタもある。新たに市場をクリエイトしてお客様に新たな価値を提供し、より大きな利益をいただく、こういう方向が正しいと考える。 ☆深川祐一氏のプロフィール 昭和38年6月28日千葉県銚子市生まれ。54歳。昭和62年に東京大学経済学部経済学科を昭和63年には、同学部経営学科を、さらに平成8年にはハーバード大学でMBAを取得した。 |
■全硝連理事会被災地への寄贈検討(平成29年10月30日)
|
||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)は10月13日(金)、東京・日本橋浜町の都硝協会議室で平成29年度第1回理事会を開催し、防災安全ガラスを東日本大震災の被災地の学校に寄贈する案件などを了承した。11月の全国理事長会議に提案する。 |
| ■日本板硝子「スーパースペーシア」発売(平成29年10月9日) |
|
日本板硝子㈱は10月2日(月)から、超高断熱真空ガラス「スーパースペーシア」の発売を開始した。 |
■全硝連関東ブロック会議次期本部長に長野・宮沢氏(平成29年10月9日)
|
|||
|
全硝連関東甲信越地区本部(鈴木和夫本部長)は9月28日(木)、東京・日本橋浜町の都硝協会議室で平成29年度ブロック会議を開催し、次期本部長を長野県ガラス・サッシ組合連合会会長の宮沢芳宏氏とする人事案を承認。宮沢氏も了承し、来春の定時総会で正式に就任する。 |
■板硝子協会ガラスシンポジウム2017協会創立70周年を記念(平成29年10月2日)
|
||||
|
板硝子協会(島村琢哉会長)は9月25日、東京都港区芝の建築会館ホールで「ガラスシンポジウム2017」を開き、同協会創立70周年を記念しての講演会を開催した。今回は「最近発生した国内外の火災事例」をテーマに東京理科大学大宮喜文教授が、「平成28(2016)年熊本地震における建築およびガラス被害と課題」をテーマに東京大学大学院清家剛准教授が講演を行った。約100人が参加した。 |
■全国板硝子工事協同組合連合会橋本会長に聞く(平成29年9月25日)
|
||
|
14年間という長きにわたり全国板硝子工事協同組合連合会の会長を務めてきた遠藤浩吉会長に代わり、今期より会長に就任した橋本和明氏(中国工事理事長、株式会社橋本硝子店=広島県広島市安佐南区八木8―6―7、代表取締役社長)。先日、広島市内にある橋本硝子店の事務所に橋本会長を訪ね、会長就任の抱負などを聞いた。 ――早速ですが、連合会の現状は? ――ガラスの業界に、もっと若い人に興味をもってもらうにはどうしたら良いと思いますか。 ――そのようですね。 ――その割には、ゼネコンの協力会の会長をやっている業界の方は多いように感じますが・・・ ――なるほど。 ――制度的には整ってきたと言えますね。後はそれをうまく運営・活用していけるかということですね。 ――ご自身の経営のほうはいかがですか。 ――最後に一言。 ――どうもありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 ▽橋本和明氏のプロフィール |
■神奈川県ZEH補助事業が順調 8月で申請は200件(平成29年9月11日)
|
||
|
神奈川県が実施中の「ZEH導入費補助事業」が順調に推移している。平成29年度は予算規模を330件分の1億円に増額したが、11月には枠いっぱいになる勢い。県当局はスマートエネルギー計画推進に向け、来年度も事業を継続させていきたい意向だ。 |
■横浜市ZEH補助事業が軌道に申請は上期で半数超(平成29年9月11日)
|
||
|
横浜市によるZEH補助事業が軌道に乗り始めた。平成29年度は20件の枠に対し上半期で10件の申請を受け付けた。当局はリフォームを含む住宅の省エネ・断熱化支援と普及啓発活動を〝車の両輪〟とし、来年度も継続する方針だ。 |
■東京都補助金の申請受付開始戸建て、集合とも50万円(平成29年9月4日)
|
||
|
◇ クール・ネット東京の連絡先は次の通り。 |
■仙台市窓断熱改修に10万円(平成29年9月4日)
|
||
|
宮城県仙台市(人口約109万人)が実施中の「Let’s 熱活!補助金」(略称)の利用が順調に推移している。窓断熱改修などに助成金を交付する制度だが、平成29年度は既に予算額の半分以上を消化し、年内には満額に達する勢いだ。 |
■全硝連近畿地区本部「防災安全ガラス寄贈工事」行う(平成29年8月28日)
|
||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)の近畿地区本部(小村哲也本部長)は8月1日(火)から、奈良県生駒市の真弓小学校における「防災安全ガラス寄贈工事」を行った。 |
■AGC旭硝子来年7月1日から「AGC」に社名変更(平成29年8月14日)
|
||
|
AGC旭硝子の島村琢哉社長は8月1日の決算説明会の席上、同社の商号を2018年7月1日に現在の「旭硝子株式会社」から「AGC株式会社」に変更すると発表した。3月の株主総会での承認が条件。英文表記は「Asahi Glass Company、Limited」から「AGC Inc.」となる。 |
| ■HAMAYA小池社長に聞く(平成29年8月14日) |
|
先日、盛大に創業100周年記念式典を開催した㈱HAMAYA(本社=東京都新宿区新宿1―7―1新宿171ビル8階、小池恒平社長)。今回は、同社本社に小池社長を訪ね、社名変更の意味や今後の方向性などを聞いた。 ――「HAMAYA」ロゴも新しくされました ――社長は、式典のあいさつの中で、100年を通過点とするには、今後の活動にかかっているとお話されていました。今後の方向性についてはどのように御考えですか。 ――「住宅資材卸売業」以外のビジネスも検討しているのですか。 ――売上が130億円と発表されていました。 ――住宅と非住宅ではどれくらいの比率ですか。 ――今回、代表取締役を社長と吉楽博専務のお二人の体制にされました。 ――住宅の建設も行っているとか。 あくまでBtoBの関係で建設し、年間で70~100棟ぐらい建てています。 ――これからの100年を担う新入社員については。 ――現在の社員数は。 ――ズバリ、売上目標は。 ――ありがとうございました。 ☆小池恒平社長のプロフィール 取材を終えて |
| ■経産省断熱リノベ事業で申請期間延長を要請全国卸松本会長(平成29年7月24日) |
|
経済産業省が平成29年度当初から始めた「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」(断熱リノベ)は2次公募の段階を迎えたが、運用面で懸念を抱く全国板硝子卸商業組合連合会の松本巌会長(関東卸組合理事長)は7月13日、所管の製造産業局生活製品課を訪問し、公募期間の延長など「とっつきやすい制度」への改善を強く要請した。 |
■HAMAYA100周年記念式典(平成29年7月10日)
|
||
|
既報のとおり、浜屋ガラスは創業100周年の節目に当たり、本年6月1日付けで、社名を株式会社HAMAYA(本社=東京都新宿区新宿1―7―1新宿171ビル8階、小池恒平社長)に変更したが、創業100周年記念行事として、7月1日(土)午後12時より、東京都新宿区にある京王プラザホテルエミネンスホールにおいて、100周年記念式典を開催した。当日は、LIXILや旭硝子など同社の取引関係者ら約300人が集まり盛大に行われた。当日は、LIXILから瀬戸氏や元社長の飛田英一氏、旭硝子からは島村琢哉社長、それに元社長の石津進也氏、YKKAPからは堀秀充社長と、大企業の役員・幹部らが勢ぞろいした。 |
■宮硝協、大友利彦理事長に聞く(平成29年7月10日)
|
||||||
|
東日本大震災から6年が過ぎ、復興が進む宮城県において、青年部も含め積極的に活動を続けている宮城県板硝子商工協同組合。 ―組合の状況はいかがでしょう?― ―仕事が少ないと伺いました、復興関連はいかがですか?― ―震災時の避難所に「防災安全ガラス」を、との活動を全硝連が進めています。震災時の経験を持つ宮城県での「防災安全ガラス」導入の動きなどはいかがでしょうか?― ―ありがとうございました。次に、大善硝子店のお話を伺いたく思います。「ミレールミラー」シリーズとして、色々な鏡製品を開発されていますね。 ―大善硝子店としては、鏡の扱いは多いのでしょうか?― ―貴重なご意見を頂戴しました。お忙しい所、ありがとうございました。新しいミレールミラーシリーズにも期待させていただきます。― |
■横浜市学校全面建て替えに着手(平成29年7月3日)
|
||
|
横浜市(人口373万人)は、30年計画で老朽化した市立小中学校の全面建て替え工事に着手する。総事業費は約1兆円。改正建築基準法以前に建てられた計384校が対象。予備調査を経て2020年度から本体工事を開始し、50年度終了を目標としている。 |
■第19回板ガラスフォーラム(平成29年6月26日)
|
|||
|
恒例の「板ガラスフォーラム」が今年も盛大に開催された。板ガラス業界8団体(全国板硝子商工協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催による「第19回板ガラスフォーラム」が6月9日、東京都港区にある品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホールに於いて盛大に開催された。今回の参加者は前回より20人増の約420人。 記者の目 今回も昨年に続き参加者が増加した。新しくガラス加工機関係者の方達を多く見かけた。営業チャンスの場と捉えているのかもしれない。内容については、前日からメーカー主催の講演会に参加している方が多かったせいか、疲れている感じの参加者が多く、興味ある講演内容にもかかわらず、目を閉じている方を多く見かけた。官庁関係の方の講演では、私だけかも知れないが、話すスピードが速く、ほとんど頭に残らなかった。来年は節目となる20回目。人間でいえば成人式にあたる。若い世代の人達による未来のガラス業界への提言などをテーマにしたパネルディスカッションなど、今までと違った内容の物を期待したい。 |
| ■全硝工連総会新会長に橋本和明氏(広島) 遠藤氏は副会長に就任(平成29年6月26日) |
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連)は6月9日(金)、東京・品川のTKP品川カンファランスセンターで第33回通常総会及び全国合同会議を開催し、任期満了に伴う役員改選で新会長に橋本和明氏(中国工事理事長)を選出。遠藤浩吉会長(関東理事長)は副会長に就任した。 |
■全国ひのまる会業界の奮起促すー松本会長(平成29年6月12日)
|
|||
|
日本板硝子ビルディングプロダクツの取引店で構成する全国ひのまる会(松本巌会長)は6月8日(木)、東京・品川の東京マリオットホテル・ボールルームサウスで平成29年度定時総会を開催し、決算、新年度予算案など全3議案を了承した。 |
| ■旭硝子財団「研究助成金贈呈式」(平成29年6月12日) |
|
公益財団法人旭硝子財団(石村和彦理事長)は、6月8日(木)東京・千代田区にある経団連会館において、助成金受領者をはじめ、官庁、報道。学協会、他財団、旭硝子関係者ら約170人が参加するなか、盛大に2017年度研究助成金贈呈式を開催した。 |
| ■旭硝子AGC Studioで懇談会(平成29年6月12日) |
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都、島村琢哉社長)は、6月6日(火)午前11時半より、東京・中央区にあるガラスの機能体験型ショールーム「AGC studio」において、多くの役員らが出席する中、マスコミとの懇談会を開催した。 |
| ■セントラル硝子「特約店研修会」開催(平成29年6月12日) |
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、社長)は、6月8日(木)午後2時より、東京都渋谷区にあるセルリアンタワー東急ホテルにおいて、「第10回セントラル硝子特約店研修会」を開催した。同会は全国のセントラル会のメンバーが一堂に集まり研修や情報交換を行おうという趣旨の下で開催されるもので、今回で10回目となる。全国の特約店の代表者やその役員、さらには同社社員など100人以上が参集し盛大に行われた。 |
■チャイナグラス2017(平成29年6月5日)
|
|||
|
5月24日(水)~27日(土)の4日間、中国・北京市の中国国際展覧中心(新館)において、「第28回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2017)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 |
■神戸市の新商品デュオこうべガラス導光板(平成29年5月29日)
|
||
|
=写真=は、兵庫県神戸市中央区の神戸駅周辺からハーバーランドの間にある地下ショッピングセンター「デュオこうべ」だ。神戸地下街株式会社が運営・管理する。最近リニューアル工事を進めており、神戸市が「浜の手」改修工事の入札を行い、神戸市大手建築会社「カイト」が受注した。今回のリニューアル工事は街の活性化が目的で、ここに採用されたのが、「神戸市の新商品」に認定された早水電機工業㈱(本社=兵庫県神戸市、門野内幸晴社長)社製のガラス導光板(特許)だ。 |
| ■国土交通省既存建築物省エネ化推進事業 対象事業の提案募集(平成29年5月15日) |
|
国土交通省は、「平成29年度(第1回) 既存建築物省エネ化推進事業(建築物の改修工事)」の提案募集~既存建築物の省エネ改修工事に対する支援~について、6月2日まで、対象事業の提案を募集すると発表した。なお、第2回提案募集の開始は9月頃を予定としている。発表内容は次の通り。 |
■厚生労働省技能検定受検料を減額(平成29年5月15日)
|
||
|
厚生労働省は、技能検定の実技試験の受検料を35歳未満の受検生に限定して最大9000円減額する。適用対象職種はガラス施工を含む100職の2~3級。各都道府県職業能力開発協会が6月以降に実施する試験から導入する。 |
■岡山市「スマートエネルギー導入促進補助事業」説明会(平成29年5月15日)
|
|||
|
岡山市の環境保全課地球温暖化対策室は、4月28日(金)の午前10時から、「平成29年度 岡山市住宅用スマートエネルギー導入促進補助事業」の説明会を開催した。 |
■日本板硝子大阪工業大学OIT梅田タワーに「スペーシア21」が採用(平成29年5月1日)
|
||
|
日本板硝子㈱(本社=東京都、森重樹社長)の複層真空ガラス 「スペーシア21®」が、このたび大阪工業大学OIT梅田タワー(学校法人常翔学園)に採用された。 大阪工業大学OIT梅田タワーは、大阪・梅田の中心地に立つ高層タワーキャンパス(関西では最も高い、地上125㍍、21階建て)で、学校法人常翔学園創立100周年に向け、未来を担う新しい知を大阪から発信する「学園のシンボリック拠点」だ。 「スペーシア21」が採用されている高層階北面の吹き抜け空間「コミュニケーションボイド」部は、自然エネルギー利用や消費エネルギーの最適化を行い、太陽光発電量と年間のエネルギー収支のゼロを目指す空間として設計された。 この吹き抜け空間では、北面カーテンウォールのガラスに採用された複層真空ガラス「スペーシア21」が、透明で超高断熱の特長を活かして空調負荷の低減に寄与するとともに、北面の安定的な自然採光により明るく快適な空間を提供している。 今回採用された「スペーシア21」は、高い断熱性能を持つ真空ガラス「スペーシア」と、Low―E(低放射)ガラスで構成された複層真空ガラス。熱貫流率は0・85W/(㎡・K)で、Low―E複層ガラスと比べて約2倍の極めて高い断熱性を有するガラスだ。 「スペーシア21」は今後ますます普及が見込まれるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の実現に向けた貢献が期待されていつ。同社はこれからも、省エネルギーに貢献する新たな高付加価値品を開発していくとしている。
大阪工業大学などを運営する学校法人常翔学園が、西日本で初めて大阪の中心地・梅田に高さ125メートルの超高層キャンパス棟を建設し、全国ネットのTVニュースで紹介されるなど注目を集めている。前回の高機能特集号での日本板硝子とのインタビューの中で、この超高層キャンパスの窓ガラスに複層真空ガラス「スペーシア21」が採用されたのを聞き、過日、同キャンパスを訪問、常翔学園施設部・長谷川清部長や服部・石本・安井設計監理共同企業体として、このキャンパス棟を設計監理した㈱石本建築事務所大阪オフィス次長・一級建築士・東原理子氏になぜ「スペーシア21」の採用に踏み切ったのか、また、使ってみた現在の感想等を聞いた。 長谷川 当学園は2022年に創立100周年を迎えます。それで創立100周年に向けた基本構想「J―Vision」のもと、「連携」「戦略」をキーワードに、より透明性の高い経営を推し進め、「質」「量」ともにバランスのとれた魅力ある教育の実現に取り組んでいます。低炭素社会への貢献、省CO2技術の採用、地域防災などの環境配慮におけるコンセプトを重視しました。 東原 そこで、このプロジェクトではその取り組みについて、国交省・平成25年度第2回「住宅・建築物省CO2先導事業」の採択を受け、日本初となる非住宅建築物「低炭素建築物認定」を取得しました。 ――認定を取得するにあたっては大変な努力やご苦労があったかと思います。東原先生が「スペーシア21」の採用に辿りついたのは。 ――採用するにあたってガラスにあるマイクロスペーサーは気にならなかったですか? ――何か板ガラスのメーカーさんにご要望があればお聞かせください。 ――ありがとうございました。
|
■AGCリグラスカップ表彰式 あけぼの通商が11連覇(平成29年4月24日)
|
|||
|
AGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都、深川祐一社長)の製品拡販に貢献した販売店や特約店をたたえるAGCリグラスカップ2016表彰式及び2017年度プラチナステータス認定式が4月7日(金)、東京・京橋のAGCスタジオで開かれた。リグラスカップでは、㈱あけぼの通商(本社=長野県上田市古里、近江朋秀社長)が販売店の部・総合部門で11連覇を達成した。 |
■全硝工連東京で全国理事会開催(平成29年4月10日)
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連、遠藤浩吉会長)は3月28日(火)、東京・日本橋浜町の都硝協会議室で全国理事会を開催し、登録硝子工事基幹技能者講習、社会保険加入促進問題や市場動向を中心に協議した。技能者講習は9月初めに福岡市で実施することを正式に決めた。 |
■公民連携アカデミー 横浜市とマテックス マンション窓改修講座開催(平成29年4月3日)
|
||
|
横浜市とガラス・建材卸のマテックス(本社・東京、松本浩志社長)が連携して進めている「よこはまエコリノベーション・アカデミー特別講座~住まい手による、住まい手のためのマンション窓断熱改修講座~」の第2回講座が3月20日(月)、横浜市西区みなとみらい、横浜ランドマークタワー・ドックヤードガーデン地下1階のBUKATSUDOホールで開かれた。 |
■九鏡 志免町の返礼品に採用 トヨペットに「現代の鏡の間」(平成29年4月3日)
|
||||||||
|
株式会社九鏡(福岡県糟屋郡志免町)の志免町のふるさと納税の返礼品として同社の「高品位鏡」が採用された。サンゴバンが製造する鏡で、九鏡が壁面鏡などの商品に加工した。 |
| ■28年度後期ガラス施工技能検定合格者(平成29年3月27日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成28年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月10日(金)に全国の職業能力開発協会から、発表された。 ◇ 1級の受検者が2ケタの所は11都道府県と前年の8都道県を上回っている。受検者数が最も多かったのは東京の35人(前年26人)で、受検者数1位の座を愛知(受検者数31人/前年29人)から奪還した。 ◇ 1級合格率が100%のところは、岩手、石川、福井、長野、兵庫、福岡、大分、宮崎の8県(前年は福島、群馬、石川、滋賀、和歌山、佐賀の6県)となっている。このうち受検者が1名の県は、岩手、福井、大分、宮崎の4県。石川(3人)、長野(4人)、兵庫(6人)福岡(20人)の4県は複数人の受検者が全員合格をしており、中でも福岡は受検した20人が全員合格するという快挙を成し遂げている。 ◇ ガラス施工技能検定そのものが行われなかった県は、千葉、山梨、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、香川、長崎、熊本の10県(前年は千葉、山梨、岐阜、徳島、香川、大分の6県)で、前年から2県増加した。この中で、岐阜は4年連続、山梨は5年連続、香川は6年連続して、技能検定試験がおこなわれていない。 ◇ 今回、3年ぶりに山口県で女性の1級受検者がいた。結果は、残念ながら不合格となったようだが、明るい話題と言える。 ◇ 今回の検定においても、前年同様に受検者、合格者とも増加する結果となった。しかし、先述したとおり、職人不足の状況は、一向に改善を見ない。
|
■国交省住宅ストック循環支援事業(平成29年3月13日)
|
||
|
国土交通省が平成28年度第2次補正予算で実施中の「住宅ストック循環支援事業」への事業者登録と交付申請が年度末を控えて急増している。3月1日時点の事業者登録は約4万3000件、交付申請は2万数千件に上っている。 ◇ 国交省住宅生産課住宅ストック活用・リフォーム推進官の村上慶裕氏に進展状況を聞いた。 ―狙いや特徴を。 ―開始後4カ月。感触は。 ―登録、申請数は。 ―申請が煩雑との声も。 |
■全硝連奈良大和高田市長と面談(平成29年3月13日)
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会の辻良明会長は、防災ガラス(合わせガラス)を避難所に指定されている小中学校の体育館などに広める活動に注力しており、精力的に各自治体の首長などへの面会を行っている。 ◇ また、同日午後3時半から、奈良県生駒市の真弓小学校体育館の視察を行った。昨年末に同市の小紫雅史(こむらさき まさし)市長に面談して以降、3校目の現地調査となった。 |
■AGC旭硝子防災安全ガラスを寄贈(平成29年3月6日)
|
||||||
|
AGC旭硝子(東京都千代田区、島村琢哉社長)は2月16日(木)、高知市に地震や突風、台風などの自然災害発生時に効果のある防災安全ガラス(工事費、部品代を含む約700万円相当)を寄贈した。 |
■村島硝子商事村島靖基社長に聞く(平成29年3月6日)
|
|||
|
村島硝子商事㈱(奈良県橿原市曲川町7‐2‐34)の村島靖基社長は、このほど宅地建物取引士(宅建士)試験に合格した。取材時点(2月23日)では、宅地建物取引士証の交付待ちとの事だったが、この春より、宅地建物取引士としての活動を本格化するという。 ◇ 不動産事業を検討し始めるきっかけとなったのは、2015年の夏に、LIXILが展開する不動産事業ERAの説明会に参加したこと。そこで「ガラスサッシ業界から不動産事業に入って成功した会社が九州にある」と聞き、自社でも出来るかもしれないとの感想を持ったという。その会社を見に行き、話を聞く中で、「工務店との関係が変わる」との話を聞いた。今までは、工務店から発注を受ける、使われる側だったものが、不動産事業を手掛けると、工務店に発注する側になる、という話にも興味を持ったそうだ。 ◇ 宅建士の取得については、従業員さんでは、辞めてしまうリスクがあり、安定した不動産事業が成り立たないとの助言受けたため。そこで、社長自ら宅建士の資格取得を決意し、2016年春から専門学校に入学、毎週日曜日の午後、半日を勉強に費やした。大学受験以来の勉強漬けだったと話している。 ◇ 不動産事業はこれからの成長株として期待がかかるが、一方で、3年半前からスタートしたBtoC事業は、知名度も向上し、ようやく軌道に乗りつつあるとのこと。 ◇ 村島社長は、業界の地盤沈下が続いている中、現在の自社の戦略が正しいのか、窓に特化して極めていく方向が良いのか、今でも悩んでいると話している。 |
■第29回技能グランプリ(平成29年2月27日)
|
||||||
|
厚生労働省と中央職業能力開発協会、(一社)全国技能士連合会が主催する、第29回技能グランプリが2月10日(金)~13日(月)の4日間、ツインメッセ静岡(静岡市駿河区)ほか5会場で開催された。 |
| ■電気電子建材竹内清秀社長に聞く(平成29年2月27日) |
|
既報のとおり本年1月1日より大下純夫氏の後を継いで電気硝子建材㈱(本社=大阪府大阪市)の代表取締役社長に就任した竹内清秀氏。先日大阪市内にある同社の本社ショールームを訪ね、新社長としての抱負などを聞いた。 ――今開発中の新商品とかあるのですか? ――竹内社長はこれまで建材関係の道を歩んでこられたのですか。 ――電気硝子建材の現在の業績は。 ――ガラスブロックについて、何か対策は ――今年の目標は。 ――最後に従業員に期待することは。 竹内清秀氏の略歴 |
■日本板硝子材料工学助成会研究成果発表会を開催(平成29年2月6日)
|
|||
|
公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は1月26日(木)、東京・六本木の住友会館・泉ガーデンタワー42階ホールで「第34回無機材料に関する最近の研究成果発表会」を開催し、平成25年度に助成金を贈呈した40件の研究から5件を選出し、「材料研究に新しい風を」をテーマに各研究者の講演を聞いた。 また、同助成会は研究助成以外に国際会議や海外渡航を含む成果普及面での支援も実施。昨年度は総計14件を助成した。 講演内容と講演者は次の通り。(敬称略) |
■経産省省エネリフォーム補助事業 支給上限額を引下げへ(平成29年2月6日)
|
||
|
住宅の断熱・省エネ改修を支援している経済産業省は、平成29年度当初予算で執行する補助事業の概要を明らかにした。基本的に現制度を踏襲するものの、家庭用設備への補助廃止に伴い事業名称を変更。戸建て、集合住宅ともに150万円の支給上限額を引き下げる。 |
| ■リノベ事業受理状況環境共創イニシアチブ(平成29年2月6日) |
|
環境共創イニシアチブ(Sii)は住宅省エネリノベ事業の補助金交付申請の最終受理状況をまとめた。第5次公募を締め切った直後の平成28年11月1日時点の申請総戸数は約3万3000戸で、昨年度交付実績の約2万4000戸を約9000戸上回っている。 |
■板硝子協会合同委員会を開催(平成29年1月30日)
|
||
|
板硝子協会(皿澤修一会長)は、1月20日に東京都千代田区一ツ橋にある如水会館において、協会役員や各委員会委員長、さらにその委員・関係者らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。合同委員会終了後には、場所を2階に移動して平成29年ガラス産業連合会(板硝子協会、硝子繊維協会、電気硝子工業会、㈳日本硝子製品工業会、日本ガラスびん協会、㈳ニューガラスフォーラムの6団体が加盟)の新年会も開催、約400人の業界関係者が参加する中、盛大に行われた。 |
■全硝連生駒市の担当者と面談 防災ガラスを避難所に(平成29年1月23日)
|
||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会の辻良明会長は、防災ガラス(合わせガラス)を避難所に指定されている小中学校の体育館などに広めるため、積極的に各地自治体の首長などへ面会を行っている。 |
| ■旭硝子2017年方針説明要旨を発表(平成29年1月23日) |
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は1月5日、島村社長の2017年度方針説明要旨を発表した。
|
■新役員に聞く全硝連関東甲信越地区本部長鈴木和夫氏(平成29年1月23日)
|
||
|
「学校の先生とも話し合わないと」。昨春、全硝連関東甲信越地区本部長に就任した鈴木和夫氏(栃木県板硝子商工協同組合理事長、全硝連副会長)にブロックの業界の現状や組合活動の在り方について話を聞いた。 ―略歴と仕事を。 ―ブロックの現況は。 ―千葉、山梨、茨城が脱退しました。 ―活動面では。 ―国の補助事業は。 ―流通変革について。 |
■山形市の小中学校「エコ窓改修」本格化(平成28年12月26日)
|
||
|
山形市の市立小中学校を対象とした校舎の「エコ窓改修事業」が軌道に乗り始めた。本年度から1級積雪寒冷地の6校について、Low―E複層ガラスへの交換か内窓設置に本格着手した。山形県サッシ・ガラス協同組合の陳情が奏功した形だ。 |
■日本電気硝子第23回空間デザイン・コンペ(平成28年12月12日)
|
|||
|
日本電気硝子(本社・滋賀県大津市、松本元春社長)は12月5日(月)、東京・丸の内の東京国際フォーラムガラス棟4階G405で恒例の「第23回空間デザイン・コンペティション」の表彰式を華やかに開催。「A・提案部門」で「ガラスの防潮堤」をデザインし最優秀賞に輝いた原田雄次氏(スミルハン・ラディックアーキテクト)に表彰状と賞金100万円を授与した。 ◇ 表彰式典は午後5時に開会。最初に日本電気硝子の松本社長があいさつに登壇し、作品を見ることなく亡くなった小嶋氏に哀悼の意を捧げた。 |
■新役員に聞く全硝連東北地区本部長須藤 清昭氏(平成28年12月12日)
|
||
|
「融和と協調を図っていきたい」。今年6月、全硝連東北地区本部長に就任した須藤清昭氏(山形県サッシ・ガラス協同組合理事長)に東北地方の業界の動向や組合活動の展望を聞いた。 ―山形市に店舗を構える㈲須藤ケンソーの会長。略歴を簡単に。 「昭和38年、山形の工業高校を卒業し、神奈川県にある繊維メーカーに就職した。技術職です。生産工場への転勤も経験しました。51年に実兄が地元で経営するガラス店に入社し、57年に独立した。昨年、長男(須藤暁氏)に社長の座を譲りました」 ―地区本部長になっての感想は。 「全硝連通常総会で指名を受け、7月に第1回地区本部会議を開催したときのこと。ある人が『組合存続に意味はあるのか』と根本的な問題を提起した。これは大変だと思いましたね。秋に第2回を予定していたが、来年2月に延期しました。一泊してお酒でも飲みながら組合についてじっくり話し合おう、と」 ―東北の業況は。 「宮城は人口もあり悪くない。それに3・11(東日本大震災)のいい意味での経済効果を受けている。隣の山形に震災復興の恩恵はない。青森、秋田も同じ。岩手も含め各県とも極めて疲弊している。公共事業もなくなった。話を聞くと、皆さん『やっと』という感じだ。最近、秋田の前理事長の会社が倒産しました」 ―山形は組合挙げて「エコ窓」をアピールしています。 「山形も財源が厳しい。共同受注しないと補っていけない。では、何をするか。新築の受注にはゼネコンが入る。同じ物件を仙台市の業者と競う場面もあるだろう。新築関係ではいろいろな問題が生じます」 ―ガラスとサッシとの区分については。 「サッシ、ガラスと区分けする時代ではない。我々末端は双方一体で『窓』として事業活動をしている。ところがメーカー側には双方全く接点がない。お互いに手を組まない。ここに価格破壊やちぐはぐな流通形態の根源があるのではないか。協力態勢を構築して欲しいと思っています」 ―全般的な課題は。 「先の住宅エコポイント制度は、大きく言えば、単組の要望から始まり国への全硝連トップの陳情で実った政策。業界として唯一、全国組織として機能しているのが全硝連。アルミサッシ、建材関係には存在しません」 |
■旭硝子財団第25回ブループラネット賞(平成28年12月5日)
|
||
|
公益財団法人旭硝子財団(石村和彦理事長)は11月16日(水)、東京・丸の内のパレスホテル東京で、2016年度(第25回)ブループラネット賞を受賞したパバン・シュクデフ氏(インド)とマルクス・ボルナー教授(スイス)を称える表彰式典を開催した。2氏は翌17日、渋谷区の国連大学で記念講演した。 |
| ■AGC製品発表会を開催(平成28年12月5日) |
|
AGC旭硝子(旭硝子㈱、本社=東京都、島村琢哉社長)は、11月25日(金)、東京都中央区京橋にあるAGCスタジオでプレス向け製品発表会を開催し、その中で軽量内装用カラーガラス「ラコベルプリュム」と遮音・断熱性能で世界最高水準の内窓「まどまどplus(プラス)」の2製品を発表した。当日の登壇者はAGC旭硝子カンパニー・ビルディング産業事業本部日本事業部商品統括グループ主席太田里華氏と同日本事業部・藤城留美氏のお二人。当日の発表内容は次の通り。 |
■全硝連全国理事長会議(平成28年11月28日)
|
||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、辻良明会長)は11月11日(金)、12日(土)の両日、石川県金沢市にある金沢ニューグランドホテル会議室で第32回全国理事長会議を開催した。初日の全体会議には全国の理事長や役員、それに今回は青年部からの出席もあり、合わせて65人が参加、自治体への防災や省エネ等高機能ガラスのPR活動実施などを討議した。 |
■全硝協 近畿ブロック会議(平成28年11月14日)
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(辻良明会長)近畿地区本部(小村哲也本部長)は11月4日(金)午後3時から大阪府板硝子会館(大阪市中央区)5階会議室で、第2回近畿ブロック会議を開催した。 ◇ 続いて、①近畿地区本部規約の件および決算の件②全硝連理事長会議提案事項について③次回開催の日時・場所等についての確認、④その他、の議題について論議がなされた。 |
■全硝工連全国理事長会議開催(平成28年11月7日)
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連、遠藤浩吉会)は、10月26日(水)午後1時30分から、大阪板硝子会館5階会議室において、全国理事長会議を開催した。 ◇ その後、約10分間の休憩を挟んで、清水英彦副会長(関西)から、関工硝の課題と活動報告が報告された。関西での活動としてWGRやG6といった、卸と小売、さらに鏡、加工、技能士会も加えた横のつながりでの活動を報告。例としてイチオシ商品説明会や安全大会の開催などを挙げた。 |
■セントラル硝子国際建築設計競技開催(平成28年10月10日)
|
|||
|
セントラル硝子(皿澤修一社長)は10月22日(土)、東京・丸の内の東京国際フォーラムD7ホールを会場に、「風土と暮らす家」をテーマとした「第51回セントラル硝子国際建築設計競技」の公開2次審査を開催した。1次通過7点の中から、棚田の家「田居中」を最優秀賞に選出し、設計者の糸魚川遼氏に賞金200万円と記念品を授与した。 【皿澤氏の挨拶要旨】 この国際建築設計競技は昨年、おかげさまで記念すべき50周年を無事終了し、今回新たな気持ちで51回目を迎えることができました。過去50回に続き、これからも建築界の発展に少しでも貢献できるよう努めていく所存です。 |
| ■国土交通省住宅ストック循環支援事業(平成28年10月10日) |
|
国土交通省住宅局住宅生産課は10月4日住宅ストック循環事業(平成28年度第2次補正予算にて措置予定=10月4日現在国会にて審議中)概要及び説明会に関する情報を発表した。内容は次の通り。 1.制度概要 |
■横浜市独自にZEHを支援新築に最大50万円補助(平成28年10月10日)
|
||
|
環境未来都市を掲げる横浜市(人口約373万人、約166万世帯)が平成28年度から国の政策目標に沿った「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」補助事業を新規に開始し、ハウスメーカー、地場工務店をはじめ戸建て住宅を夢見る一般市民の関心を集めている。 |
■経済産業省住宅省エネリノベ事業が継続(平成28年10月10日)
|
||
|
既存住宅の断熱・省エネ改修を支援している経済産業省は、現行の「住宅省エネリノベーション促進事業」(平成27年度補正)を29年度も継続して実施する方針を決めた。補助総額は本年度と同じ100億円規模。当初予算で来年4月1日から執行する意向だ。 (関連別稿) 申請総数で8千戸増加 経産省は住宅省エネリノベ事業について1~4次公募までの補助金交付申請状況をまとめた。9月2日時点の申請総戸数は約3万2000戸に上り、昨年度交付実績の約2万4000戸を約8000戸上回っている。 |
■ドイツデュッセルドルフ22回GLASSTEC2016(平成28年10月3日)
|
|||
|
ガラス産業のあらゆる分野を捉え、素材としてのガラスの可能性を様々な視点から紹介する世界最大級の展示会「glasstec 2016(グラステック2016 国際ガラス製造・加工機器展)」が、9月20日(火)~23日(金)の4日間、ドイツ・デュッセルドルフの見本市会場で盛大に開催された。 |
■川崎市の公立小中学校窓改修工事が本格化(平成28年9月26日)
|
||
|
神奈川県川崎市(福田紀彦市長、人口148万人)が、市独自の「学校施設長期保全計画」の一環として掲げた公立学校の窓改修事業が本格化している。本年度は設計費用などを含め全体で106億円の予算を計上。窓関係では計30校で複層ガラスへの交換や内窓設置工事を実施中だ。 |
■AGC旭硝子が考える2025年のまちのリノベーション展(平成28年9月12日)
|
||
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都、島村琢哉社長)は、9月2日~10月29日までの2カ月間、東京都中央区京橋にあるAGCstudioにおいて、企画展示「AGC旭硝子が考える2025年のまちのリノベーション展」を開催し、建物価値を高めるためのリノベーションに貢献する様々な製品・技術を紹介する。建設関係者はもちろん、ビルオーナーやマンション理事会などに、窓ガラスだけでなく、通常あまり触れることのない屋上防水や外装用塗料等の製品に「見て」「触って」「体感して」もらえる展示会になっている。またリノベーションに関する制度、施工事例などを紹介する各種セミナーを開催、リノベーション個別相談会も実施するとしている。同展示会の後援は一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会(石村和彦会長)で、会場構成・展示提案は海法圭建築設計事務所が担当した。 |
■新役員に聞く宮硝協理事長大友利彦氏(平成28年9月12日)
|
||
|
「流通を基本に即した形に戻して欲しい」。今春、宮城県板硝子商工協同組合の理事長に就任した大友利彦氏(仙台市、㈲大善硝子店代表取締役)に東北の業界の動向、組合活動の現状を聞いた。 ―会社を創業して48年とか。 ―東日本大震災から5年半。復興需要は。 ―宮城県板硝子組合の現状は。 ―メーカーへの注文は。 |
■全硝工連・全硝連基幹技能者講習修了試験(平成28年9月5日)
|
||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連)と全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)で組織する登録硝子工事基幹技能者講習委員会(田中敏也委員長)は8月20日(土)~21日(日)の両日、仙台市青葉区中央の仙都会館会議室で「平成28年度基幹技能者講習・修了試験」を実施した。東北地方での開催は初めて。各県から60人が受講した。 |
| ■新役員に聞く都硝協理事長松原嘉一氏(平成28年9月5日) |
|
「仲間で仕事を分け合うことがあっても╍╍」。先の通常総会で東京都板硝子商工協同組合の理事長に就任した松原嘉一氏は「地域や人とのつながりが、お店や組合再生の第一歩」と話す。販売店の現状や展望を聞いた。 ―東京・大井町で松原硝子店を経営しています。業務の中心は。 ―地域の商店街は。 「JR大井町駅に近い歴史ある商店街ですが、昔からあったパン屋、肉屋、魚屋、お茶屋などは全部なくなった。スーパーなど大型店に吸収され、今は居酒屋と歯医者ばかり。建築関係でも、この辺りの大工さんはほとんど姿を消した。地元業者との付き合いはますます希薄になっている」 ―減員対策で何か。 ―販売店、組合のあるべき姿を。 |
■機能ガラス普及推進協議会 安全ガラス37.5%、合わせガラス0.5%(平成28年8月1日)
|
||
|
機能ガラス普及推進協議会(皿澤修一会長)は、7月22日(金)に大阪市内にある「ホテルメルパルク大阪」会議室カナーレにおいて、26人の会員が集まり、同協議会の代表者会議を開催。昨年度の活動報告や収支報告、今年度の活動計画案と予算案等を審議。議案はすべて原案どおり可決した。 |
■埼硝協松村健一郎氏 新役員に聞く(平成28年8月1日)
|
||
|
「活力ある支部をつくれば全体が盛り上がる」。5月の通常総会で埼玉県板硝子商工協同組合の理事長に就任した松村健一郎氏は、低迷する組合活動の打開策として「支部の活性化」を強調した。業界の現状、組合運営上の課題、小売店のあるべき姿を聞いた。 ―組合の現況と活性化対策を。 「最盛期には300店近くあった組合員数は現在51店。昨年より5店減った。減少傾向に歯止めがかからない。支部別では川口の21店が最多。あとは全て一桁で、大宮4、私が属する鴻巣6、川越7、南部6など。浦和、朝霞は各1です」 ―小売店に求められているのは。 「板ガラスの流通業界では販売店が一番遅れている。変革のスピードについていけない。それではいけない。ガラス屋は元来器用で、勉強すればなんでもこなせるはず。多角経営に踏み切る必要がある。カーポート、アルミ門扉、フェンス、外構の植栽╍╍最近では窓の自動シャッターを手がけ売り上げを伸ばしている店も出てきた」 |
■経産省 住宅省エネリノベ事業(平成28年7月25日)
|
||
|
既存住宅の断熱改修を支援する経産省の「住宅省エネリノベーション促進事業」の申請が例年より増加。特に戸建ては1次公募の段階で前年度実績を上回った。2次公募の予算規模は全体で50億円。集合住宅(全体改修)は7月4日に3次公募の受付を開始し、4次まで実施する方針だ。 ―戸建て向けの申請が増えました。それでも、まだ少ない? 「戸建ては集合住宅と同じぐらいのストックがある。もっと使ってもらいたいが、改修には窓、壁などとの組み合わせが必要なので難しいことはよくわかる。集合住宅と違ってハードルが高いのは認めます。現状に満足はしていません」 ―どれか外すとか、集合並みに窓だけでもOKとか?
「単純に件数を増やすだけならそのような道もある。しかし、この事業は長期エネルギー需給見通しにおける省エネ目標達成に寄与することを目的としています。窓改修だけでは省エネ効果は出ません」 「個人的には書類の簡素化などもっと使いやすい制度にしていきたい。しかし、税金を使う以上、不正はあってはならない。歯止めは必要だが、ルールを厳しくすると申請しづらくなる。信頼性を確保しつつ、申請しやすい環境をいかにつくっていくか。来年度以降の課題です。制度は存続させる。やっていかなくてはならない事業だと思います」 |
■新役員に聞く 全硝連会長辻良明氏(平成28年7月28日)
|
||
|
先の全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)総会で、会長に就任した辻良明氏(大阪府板硝子商工業協同組合理事長)。平成24年から全硝連常務理事を2年間、26年からは副会長2年間、それぞれ務められ、このほど永島光男前会長の後を受けて、この度会長に就任された。 ―― 全硝連会長ご就任、おめでとうございます。早速ですが、まずはご就任されたご感想からお聞かせください。 趣味は、強いて言うならゴルフです。座右の銘は、“和を以て貴しとなす”としておきます。人とのつながりだけでやってきましたから、その部分を大切にしたいと思っています。組合だからと、年配者が多いからと身構えずに、若い方にもどんどん入って来て貰いたい。色々な意見を交わして、お互いに切磋琢磨できれば良いなと思っています。 ――長時間にわたりお話をいただき、ありがとうございました。辻会長による、全硝連の一層のご発展を期待させていただきます。 ◇ ◎辻 良明(つじ よしあき)氏。 |
■川口市埼硝協支部など運動 小中学校にエコガラス(平成28年7月11日)
|
||
|
埼玉県川口市(奥ノ木信夫市長)にある公立小中学校全校の教室・体育館の窓ガラスをエコガラスや合わせガラスに交換する事業が具体化しそうだ。関係者によると、市当局は本年度下期に予算の一部を計上し、当面3カ年計画で事業に着手する方針とみられる。 |
| ■タナチョー カケハシグループ化の狙いは・・・・ 田中社長に聞く(平成28年7月11日) |
|
2014年2月に創業120周年を迎えた㈱タナチョー(本社=東京都、田中廣社長)は、「空間に太陽と健康をデザインする」をキャッチコピーに住宅建材の卸売業から六本木ヒルズのような大きなビル工事まで幅広く手掛けている。既報のとおり、同社は長崎市佐世保にある旭硝子の特約店でLIXILの代理店である「カケハシ」をタナチョーのグループ会社とし、4月28日より「カケハシ・タナチョー」(本社=長崎市佐世保、田中廣社長)として、新たにスタートした。そこで今回は、現在日本橋室町の再開発工事で東京都足立区に移転中の同社本社に田中社長を直撃し取材を試み、グループ化の経緯や目的などを聞いた。 ――熊本地震については。 ――本社ビルのある日本橋の再開発については。 ――さて、「カケハシ」のグループ化の経緯・その効果についてもお聞かせください ――佐世保には御社の営業所があったと思うのですが。近い将来に一つにするということはありませんか。 ――「カケハシ・タナチョー」の今後はどのように。 記者の目 今回はタナチョーが「カケハシ」を守るため、ホワイトナイトの役割を担ったようだ。聞いたところによると、ガラス・サッシの流通段階で、社員の引き抜き、M&Aの問題がいくつか発生しているようだ。M&Aで業界全体の市場規模が大きくなり、それで潤うなら歓迎したいと思うが、実際は価格の低下等マイナス面の方を多く耳にする。社員の引き抜きについても、社員がそれで幸せになるのなら本当にそれで良いのだろうか。商道徳上の問題はないのか。一度、業界で話し合ってもらいたい。 |
■東海工事勉強会&登録基幹技能者説明会(平成28年7月4日)
|
|||
|
東海板硝子工事協同組合(木村俊一理事長)主催の硝子工事勉強会&登録基幹技能者講習説明会が、6月28日午後1時より愛知県名古屋市にある吹上ホール4階において開催された。今回は、卸、小売、工事の組合関係者だけでなく、非組合員を含むガラス業界関係者ら100人以上が参加し盛況をみた。 記者の目 普段の組合の総会等ではなかなか人は集まらないが、こういうメリットが感じられる勉強会には確実に人は集まるようだ。100人を超える参加者をみて驚きの声をあげる人もいた。運営される方は大変だろうが、ぜひ、次回も期待したい。板ガラスフォーラムのように愛知県の3団体が同じ時期に総会を行い、協同でこういう勉強会を開催するのもおもしろいかもわからない。そうすれば総会の参加者が増えるかも。 |
■旭硝子財団「研究助成金贈呈式」開催(平成28年6月27日)
|
||
|
公益財団法人旭硝子財団(石村和彦理事長)は、6月9日(木)東京・千代田区にある経団連会館において、助成金受領者ら約170人が参加するなか、盛大に2016年度研究助成贈呈式を開催した。 |
■千代田興業水戸営業所新装オープン(平成28年6月27日)
|
||||||
|
茨城県を拠点に地域に根差しサッシ、板ガラスの卸・施工を中心に「ビルから住宅まで」幅広く事業を展開している㈱千代田興業(本社・茨城県土浦市神立中央、君山毅社長)が改築工事を進めていた水戸営業所(水戸市吉沢町、吉田世志夫所長)がこのほど竣工し、報道陣にお披露目した。 |
■第18回板ガラスフォーラム(平成28年6月20日)
|
||||||||
|
恒例の「板ガラスフォーラム」が今年も盛大に開催された。板ガラス業界8団体(全国板硝子商工協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催による「第18回板ガラスフォーラム」が6月18日、東京都港区にある品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホールに於いて盛大に開催された。今回の参加者は約400人。 |
||||||||
■AGCグラスプロダクツリグラスカップ2015(平成28年6月6日)
|
||||||||
|
AGCグラスプロダクツの製品拡販に貢献した販売店や特約店をたたえるAGCリグラスカップ2015表彰式及び2016年度プラチナステータス認定式が5月26日(木)、東京・京橋のAGCスタジオで開かれた。リグラスカップでは、あけぼの通商(本社・長野県上田市古里、近江朋秀社長)が販売店の部・総合部門で10連覇を達成した。 |
■宮吉硝子 盛大に創立90周年記念式典(平成28年6月6日)
|
||||
|
ガラス建材の総合商社・宮吉硝子㈱(本社=愛知県名古屋市昭和区福江3丁目7番2号、立木彰一社長)は、来る8月15日をもって、創立90周年を迎えることから、5月28日(土)午後5時より、三重県桑名市にあるホテル花水木(長島リゾート内)において、同社の仕入先、取引先、従業員とその家族ら約300人が集まる中、盛大に創立90周年記念式典を開催した。 |
| ■AGCグラスプロダクツ新社長に新井太吉氏(平成28年5月30日) |
|
AGCグラスプロダクツ㈱(東京都台東区)は、5月11日に開催された同社取締役会において、伊東弘之社長が退任し、後任に新井太吉氏が就任することを決定し、このほど発表した。 |
■全硝連青年部臨時総会会長に山田忠之氏が就任(平成28年5月16日)
|
|||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)青年部会は4月24日(日)午後3時から大阪市立中央会館(大阪市中央区)で、臨時総会を開催した。 |
■AGCキリン横浜ビアビレッジの試飲室太陽光発電機能「アトッチ」採用(平成28年5月16日)
|
||
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、キリン横浜ビアビレッジ(神奈川県横浜市)の試飲室に、同社の省エネ窓改修用Low‐Eガラスに太陽光発電機能を持たせた「アトッチ(太陽光発電仕様)」が、採用されたと発表した。 |
| ■春の「褒章」受章 藍綬褒章川名硝子店川名吉治氏・黄綬褒章オプトガラス工業澤田勝明氏(平成28年5月16日) |
|
平成28年の「春の褒章」の受章者が発表され、各界で功労のあった704人(26団体)が受章した。 |
| ■日本板硝子複層真空ガラススペーシア21が採用(平成28年5月2日) |
|
日本板硝子㈱(本社=東京都、森重樹社長)は、先日、真空ガラス「スペーシアクール」が福岡市庁舎の窓ガラス改修工事に採用された(弊紙4月25日号1面に掲載)と発表したのに続き、今回は、大手住宅メーカーのネット・ゼロ・エネルギーハウスで複層真空ガラス「スペーシア21」の採用が拡大していると発表した。 ――スペーシアの販売量が増加していると聞いています。 ――それは、省エネポイントや高性能建材等の補助金効果ですか。 ――これまで、「スペーシア」はリフォーム専用と思っていました。 ――ビルでの採用が増えると大きなサイズが必要となってきます。 ――まだまだトリプルガラスが入るサッシ枠は少ないですから、大いに期待できそうですね。 ――生産は間に合うのですか。 ――今後については。 |
■2016チャイナグラス 企業の出展内容(平成28年5月2日)
|
||||||
|
4月11日(月)~14日(木)の4日間、中国・上海市の上海新国際博覧中心で開催された、「第27回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2016)」(主催=中国セラミックス協会)には、世界31カ国から、ガラス、機械、部品、建材、道具・工具、サービスなどの関連企業885社(うち、中国外企業は180社)が出展し、多くの来場者を集めた。 |
■セントラル硝子国際建築設計競技50周年(平成28年4月25日)
|
|||
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、皿澤修一社長)は、4月15日(金)午後1時より東京・千代田区永田町にあるザ・キャピトルホテル東急で、200名以上の参加者が集まる中、盛大にセントラル硝子国際建築設計競技50周年記念の記念講演会と記念パーティーを開催した。昨年50回を迎えたことを記念し記念行事を開催、同社の社会貢献事業である設計競技をより多くの建設業界関係者・学生に周知し、知名度を上げるとともに、同社のPRを図ることを目的に開催された。 |
■2016チャイナグラス(平成28年4月25日)
|
||||
|
4月11日(月)~14日(木)の4日間、中国・上海市の上海新国際博覧中心において、「第27回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2016)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 |
■全硝工連全国理事会仙台・名古屋で開催(平成28年4月11日)
|
||||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(遠藤浩吉会長)は3月29日(火)、仙台市若林区の情報・産業プラザ情報化研修室で全国理事会を開催し、登録硝子工事基幹技能者講習、社会保険加入問題や市場動向を中心に協議した。板硝子協会の杉浦公成調査役が省エネ適合義務化について講演した。 |
| ■第68回AGC STUDIO デザインフォーラム(平成28年4月4日) | |||
|
|
AGC旭硝子とAGCスタジオ主催の「Glass on Details」に連動した「第68回AGCstudioデザインフォーラム」が3月24日(木)午後5時から東京・京橋の同スタジオ2階会議室で開かれた。インテリア、内装を主とする設計事務所、工務店関係者ら約80人が参加した。 |
■フェンスターバウ レポート2 コストが安い樹脂窓(平成28年4月4日)
|
||
|
フェンスターバウ展視察の2日目はドイツ系大手素材メーカー・RENOLIT社の営業担当者から、ドイツの窓事情を聞くことができた。 |
■ドイツフェンスターバウ展盛大に開催(平成28年3月28日)
|
||
|
窓やドア、ファサード、カーテンウォール、天窓等の見本市「fensterbau/frontale」(以下フェンスターバウ展と表示)が3月16日から19日までの4日間、ドイツのニュルンベルグで開催され、弊紙も単独で取材活動を行った。 |
■日本板硝子BP営業本部長沼田哲氏に聞く(平成28年3月14日)
|
||
|
既報のとおり、青山尚明氏の後任としてこの1月より日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=千葉県、井澤尚社長)の代表取締役兼営業本部長に就任した沼田哲氏。今回は東京都港区にある同社東京支店に沼田氏を訪ね、抱負などを聞いた。 ――早速ですが、先日、セントラル硝子販売さんが加工部門と営業部門をわけられたと発表しました。同様の形態を取られる御社はいかがですか。 ――今まで流通のお立場で業界を見てこられたわけですが、今回営業の責任者となられての抱負をお聞かせください。 ――リフォームについて、潜在需要は大きいと思いますが、どのようにして掘り起こしていくお考えですか。 ――最近気になっているのですが、「窓」の断熱性能ばかりを追求しすぎて、「防火」「防犯」「防災」など安心・安全面でのアピールが欠けているように感じています。 ――たくさんの機能をもったガラスはあると思いますが、ユーザーにそれがうまく伝わっていない。 ――大手ハウスメーカーついては。 ――サッシメーカーに対しては。 ――ビルについては。 ――価格改訂については。 沼田哲(ぬまたさとる)氏のプロフィール 昭和36年東京生まれ54歳。早稲田大学政経学部卒。昭和59年に日本板硝子に入社。主に営業畑を経験。モットーとしていることは「継続は力」。趣味はゴルフ。家族は奥さまと二人。現在は日本板硝子で建築ガラス事業部門アジア事業部日本統括部営業部長も兼務している。 記者の目 つねにおだやかな雰囲気の中でインタビューに応じていただいた。氏は流通にいた経験が長かったからか、なんども流通という言葉がでてきて、特にリフォーム事業については流通店の力がなくては、うまくなし得ない感じで話していた。メーカーと流通が一致協力して同じベクトルで進めば、リフォームの潜在需要もうまく掘り起こせるのではないだろうか。そうなれば業界全体も潤う。 |
| ■平成27年度後期ガラス施工技能検定合格者数発表(平成28年3月14日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成27年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月11日(金)に全国の職業能力開発協会から、発表された。
|
■東北板硝子3団体 賀詞交歓会を開催(平成28年3月7日)
|
|||
|
東北板硝子卸商業組合(大久保章宏理事長)、東北板硝子工事協同組合(原田尚樹理事長)と全硝連東北地区本部(山田一善本部長)の3団体は2月16日(火)、仙台市青葉区のパレスへいあん・ソレイユホールで2回目となる平成28年合同賀詞交歓会を開催した。約80人が参集し立食形式で和やかに歓談した。 ◇ 交歓会に先立ち3団体は午後4時からパレスへいあんコーラルホールで合同講演会を開催。冒頭、工事組合の原田氏が「今回のテーマである省エネ適合義務化は業界にとって追い風。しっかり勉強し、エンドユーザーや工務店に話ができるようにしたい」とあいさつ。来賓で講師の板硝子協会調査役杉浦公成氏が「建築物省エネ適合義務化におけるガラスの扱いについて」と題し約1時間講演した。 ▽東北シーリング工事業協同組合理事長高橋保、同理事久光康裕▽日本ガラスフィルム工事業協会東北・北海道支部長石原直人▽宮城県中小企業団体中央会連携推進部主査高野豊▽宮城県職業能力開発協会統括次長川村幸雄 |
■三芝硝材 高岡西工場を設立(平成28年2月22日)
|
||
|
「創意無限」を会社理念とし、建築・インテリア・産業用の広い分野で新しいデザイン ガラスを製造し続ける、三芝硝材㈱(本社=富山県、西英夫社長)は、高岡市内に高岡西工場を設立、このほど本格稼働に入ったと発表した。 |
■日本板硝子材料工学助成金 研究者5氏が講演(平成28年2月8日)
|
|||
|
公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は1月28日(火)、東京・六本木の住友会館・泉ガーデンタワー42階のホールで「第33回無機材料に関する最近の研究成果発表会」を開催し、平成24年度に助成金を贈呈した42件の研究から5件を選び、「材料研究に新しい風を」を共通テーマに各研究者の講演を聞いた。 |
■再開発事業起工祝賀会でタナチョー田中氏があいさつ 日本橋室町3丁目地区(平成28年2月8日)
|
||||||
|
〝お江戸日本橋〟周辺大規模再開発の一環である「日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業A地区」の起工祝賀会が1月29日(金)に開催され、再開発組合理事長を務める板ガラス販売加工・工事施工の㈱タナチョー代表取締役社長田中廣氏が事業主を代表し「この計画が日本橋の魅力を一層高めることに寄与すると確信している」と厳かにあいさつした。 |
■板硝子協会 合同委員会を開催(平成28年2月1日)
|
||
|
板硝子協会(皿澤修一会長)は、1月22日に東京・丸の内にある銀行倶楽部において、協会役員や各委員会委員長、さらにその委員・関係者らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。 また、合同委員会終了後、場所を3階に移動して平成28年ガラス産業連合会(板硝子協会、硝子繊維協会、電気硝子工業会、㈳日本硝子製品工業会、日本ガラスびん協会、㈳ニューガラスフォーラムの6団体が加盟)の新年会も開催、盛大に行われた。 |
■関東甲信越卸・都硝協 新年賀詞交歓会(平成28年1月25日)
|
||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(永島光男理事長)は、1月15日、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で7回目となる合同新年会には、来賓を併せ約120名が参会し開催された。 ☆東京都板硝子商工協同組合 ▽東京都職業能力開発協会=事務局長・間瀬和子▽関東板硝子工事協同組合=理事長・遠藤浩吉▽全硝連関東甲信越地区本部=本部長・小峰梅男▽東京都鏡商工業協同組合=理事長・尾崎由雄▽東京板硝子施工組合=理事長・吉岡通匡▽東京板硝子鏡加工組合=会長・岩澤精一▽日本自動車ガラス販売施工事業協同組合=事務局長・渡辺紳一▽東京建具協同組合=副理事長・岡田弘一▽東京南部法律事務所=弁護士・黒澤有紀子▽城東労務管理事務所=常盤瞬 |
■関西板硝子業界が互礼会(平成28年1月18日)
|
||
|
恒例となった平成28年関西板硝子業界新年互礼会(関西板硝子卸商業組合、関西板硝子工事協同組合、全硝連近畿地区本部の3組合主催)が1月8日(金)午前11時より大阪市北区にある新阪急ホテル2階「紫の間」において、業界関係者ら119名が集まる中、盛大に開催、関西板硝子業界の2016年は華々しくスタートした。 |
| ■AGCグラスプロダクツ「ペアスマート」本格販売(平成27年12月28日) |
|
AGCグラスプロダクツ(本社=東京、伊東弘之社長)はマンション改修用薄型・Low─E複層ガラス「ペアスマート」を開発、2016年1月から本格販売を開始する。ペアスマートはワイヤレスの防火ガラスである耐熱強化ガラスを使用した複層ガラス。網目がないためすっきりとした意匠性を持つ。透明タイプと不透視タイプの2種類をラインアップ。既存のサッシはそのままにガラスだけの取り替えが可能だ。 《商品に絶対の自信有り》 最後にあらためて中坂執行役員営業本部長より、新商品ペアスマート本格販売に対する意気込みを聞いた。 |
■LIXILグループ 「変革が完成」藤森氏が緊急記者会見(平成27年12月28日)
|
||||
|
株式会社LIXILグループは12月21日(月)緊急記者会見し、藤森義明代表執行役社長兼CEOが2016年6月開催予定の定時株主総会で退任すると発表した。後任には建設資材通販大手MonotaRO(モノタロウ)の瀬戸欣哉会長が就任。藤森氏は相談役に退く。 |
||||
■第6回ものづくり日本大賞 優秀賞に坂東機工(平成27年12月14日)
|
||
|
既報のとおり、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省は、このほど第6回「ものづくり日本大賞」の受賞者を発表した。この中で経済産業省関係から優秀賞(経済産業大臣名)として、製品技術開発部門で坂東機工㈱(本社=徳島県徳島市、坂東和明社長)の7人が選ばれた(中田寛美、阿部建弘、島田雅史、武知徹、濵田邦雄、下原利広、遠藤仁の各氏)が、その伝達式が12月2日(水)午後1時半より香川県高松市にある高松サンポート合同庁舎 低層棟2Fアイホールで開催され、坂東機工からは技術センター長・中田寛美氏と技術センター技術開発部・阿部建弘氏の2人が出席し、四国経済産業・成瀬茂夫局長より優秀賞が手渡された。 ※ ※ ※ 優秀賞を受賞した坂東機工の「世界最高速度で高精度な自動車用窓ガラスの全自動連続製造装置」の概要 ※ ※ ※ 中田センター長と阿部氏の説明によると坂東茂会長の発案で昭和61年に最初のマシンを開発、当初は1枚のガラスを加工するのに30秒ほどかかっていた。それが、改良を重ねることにそのスピードは速くなり、今では9・6秒で加工できるといい、将来的には7秒も夢ではないということだった。 |
■横浜市 エコリノベ事業好評 住宅の省エネ改修工事 最大80万円を補助(平成27年12月7日)
|
||
|
環境未来都市を標榜する横浜市が一般市民向けに導入した「エコリノベーション(省エネ改修)補助事業」が好評だ。住宅の開口部を全て断熱改修すると最大80万円を助成。簡易リフォームでも40万円。本年度は30件程度の予算枠が全て消化される見通しだ。 ◇ 横浜市は平成23年12月、国から「環境未来都市」に選定された。市はこれを受け環境未来都市推進プロジェクトを推進し、エコリノベをその一つに位置づけた。住宅政策課の加藤忠義さんと関川陽介さんに話を聞いた。(敬称略) 加藤「主眼は横浜市の温暖化対策。いろいろな切り口がある中で、とかく見過ごされがちな家庭部門でのCO2とエネルギー消費量の削減に取り組もうと考えました。既存住宅の価値向上と中古住宅市場の流通を促進させる意味合いも持ち合わせています」 関川「昨年度はライフスタイル改修工事も補助対象としたが、家族構成の変化を見越したものか、あるいは単なるリフォームか。理想と現実の部分の判断が難しかった。そこで、本年度は補助を省エネ改修に特化し、健康というキーワードを前面に打ち出しました」 加藤「ヒートショック問題を考慮し、特に開口部の断熱対策に力を入れてくれる人に80万円のコースを用意しました。家の中、どこに行っても温度環境は同じにしようということです」 ─HEMS設置は。 関川「エネルギーの消費量を『見える化』することが大事。要件の一つとしましたが、そうした意識を持つ人が増えているのか、割とすんなり受け入れてくれています。ただ、継続的に使っているかどうか。そこが課題です」 ─他との併用は。 加藤「横浜市としては国の省エネ住宅ポイントや高性能建材導入補助事業を含めどのようなものと組み合わせてもOKです。相手側が駄目というケースは多いようですが╍╍エコリノベは来年度以降もぜひ継続したいと思っています」 |
■東京都墨田区 小学校6校の窓改修(平成27年12月7日)
|
||
|
学校施設の窓改修に取り組んでいる東京都墨田区(山本亨区長)は、平成27年度分として公立小学校6校についてフィルム貼り中心のガラス飛散防止対策事業を実施。26年度同様、随意契約で地元ガラス店に順次工事を発注する作業を開始した。 |
| ■3メーカー・板硝子協会に陳情(平成27年11月30日) |
|
「板ガラスメーカーは、サッシメーカーと比べてまだまだ機能ガラスのアピール度が低すぎる」と語るのは全国板硝子卸商業組合連合会の松本巖会長。10月20~29日にかけて国内板ガラス3メーカーと板硝子協会を単独で訪問し、もっとメーカーとしてPRしてもらえるよう陳情に行ったという。 |
■関西卸・関西工事・大硝協の三組合 第10回「合同安全大会」開催(平成27年11月30日)
|
||
|
関西板硝子卸商業組合(小山保和理事長)と関西板硝子工事協同組合(清水英彦理事長)、大阪府板硝子商工業協同組合(辻良明理事長)の3組合は合同で、11月17日(火)に大阪市立中央会館(大阪市中央区)で、「第10回合同安全大会」を開催した。 |
■第31回全硝連全国理事長会議(平成27年11月16日)
|
||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、永島光男会長)は11月6日(金)、7日(土)の両日、愛知県名古屋市にあるキャッスルプラザで第31回全国理事長会議を開催した。初日の全体会議には53人が参加して、賛助会員の件と住宅リフォーム事業者団体登録制度の件を討議した。 |
| ■日本板硝子 ラミシェードペア試験発売 スペーシア21認証取得(平成27年11月9日) |
|
日本板硝子㈱(本社=東京都港区、森重樹社長)は、今年6月に試験販売を始めたサーモクロミック調光ガラス「ラミシェード」に、断熱性能を付加した「ラミシェードペア」の試験発売を決定した。 |
■第50回セントラル硝子 国際建築設計競技(平成27年10月26日・11月2日)
|
||
|
第5回「セントラル硝子国際建築設計競技」(主催・セントラル硝子㈱)の公開審査会が、10月17日(土)午後1時半より、東京国際フォーラムD7ホールで開催された。厳正な審査の結果、栄えある最優秀賞にはヴァッレ・メディナ、ベンヤミン・レイノルズの両氏(スイス)の作品(作品名=PARIS HERMITAGE《パリの隠れ家の意》)に決定し、賞金二百万円と記念品及び賞状が贈られた。 |
| ■全国卸・全硝連が経済産業省・資源エネルギー庁に陳情(平成27年10月26日・11月2日) |
|
既報のとおり、経済産業省は来年度も戸建て住宅とマンションなど集合住宅の省エネ改修を助成する「高性能建材導入促進事業」を来年度も継続する方針を決めた。その発表を受け、全国板硝子卸商業組合連合会の松本巖会長は全国板硝子商工協同組合連合会の永島光男会長と共に10月8日(木)に経済産業省資源エネルギー庁・省エネルギー対策課の中村幹課長補佐を訪問し、「既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業」に関して陳情した。陳情内容は次の通り。 |
■全硝連関東甲信越地区本部価格動向現状を協議(平成27年10月5日)
|
|||
|
全硝連関東甲信越地区本部(小峰梅男本部長)は9月25日(金)、東京・日本橋浜町の都硝協会議室で平成27年度第2回地区会議を開催し、ガラス・サッシの価格動向など各地域の現状を協議。その結果、窓直販に象徴される流通短絡化に伴い小売事業が縮小している実態が浮き彫りとなった。 |
■叙勲の山口信茂さんに聞く(平成27年10月5日)
|
||
|
ガラス工事一筋に43年―。今年春の叙勲受章後もなお第一線に立ち続ける。今夏には登録硝子工事基幹技能者の講習・修了試験に挑戦し、このほど見事に合格証を手にした。㈱田中ガラス(東京都練馬区大泉学園町、田中敏也社長)に勤務する山口信茂さん、64歳。「安全が第一」という山口さんに来し方を振り返ってもらった。 ―遅ればせながら叙勲(瑞宝単光章=専門工事業務功労)受章おめでとうございます。 ―今の仕事を。 ―吸盤器の開発に携わったとか。 ―独房に鉄格子がない! ―功績調書に「施工の精度は当然のこと、安全を最優先にしてきた仕事ぶりは、発注者からも高く評価されている」とあります。事故やケガをしたことは。 ―後進の指導・育成にも力を入れている。 【略歴】東京都中野区出身。昭和45年3月、中央大学付属高校普通科卒業。同年4月、カガトフ硝子(当時)入社。63年4月、クレーン・建設用リフト・巻上機の各運転業務特別教育修了。平成元年9月、安全衛生推進者養成講習修了。4年2月、高所作業車運転技能特例講習修了 |
| ■経産省高性能建材導入事業来年度も(平成27年9月28日) |
|
経済産業省は戸建て住宅とマンションなど集合住宅の省エネ改修を助成する「高性能建材導入促進事業」を平成28年度も継続する方針を決めた。8月末に締め切った来年度政府予算の概算要求に本年度と同規模の70億円余を計上した。 |
| ■旭硝子財団第24回地球環境問題調査「極めて不安」な領域(平成27年9月28日) | ||
回答者が危機時刻を決める上で念頭に置いた環境問題(全11項目、第1~3位選択)をみると、世界全体では昨年同様「気候変動」が最多で25%を占めた。次いで「環境汚染」12%、「水資源」と「生物多様性」11%、「土地利用」9%、「人口」と「環境と経済」7%、「ライフスタイル」5%、「温暖化対策」と「環境と社会」4%、「食糧」3%の順。 選択傾向を地域別にみると、中国は「環境汚染」、南米は「土地利用」(耕作地の増大、乱開発による森林破壊の拡大など)、インドと中東は「水資源」、オーストラリアを除くオセアニアが「気候変動」と「生物多様性」(絶滅する種の増加)―をそれぞれ第1位に挙げた。 念頭に置いた項目を危機時刻の順に見ると、「生物多様性」と「人口」がともに9時36分を示し、危機意識が際立っている。他の項目は9時04分から9時30分の間に分布している。 本年度は2011年から15年までの危機時刻の推移を世代別に分析。それによると、60歳代以上は全世代で最も針が進んだ9時28分~9時35分の間で安定して推移。40~60歳未満は8時56分~9時30分。20~40歳未満は8時34分~9時17分までで概ね上昇傾向にある。 「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」は世界各国の政府・自治体、NGO?NPO、大学・研究機関、企業、マスメディアなどで環境問題に携わる有識者を対象に実施。本年度は4月に世界212カ国に調査票を送付し、6月までに152カ国・2018人から回答を得た。 |
| ■全国卸の松本会長に聞く ガラス業界に奮起促す(平成27年9月14日) |
|
ここのところ全国的に広がりをみせる住宅の窓の改修に対する補助金制度。国だけでなく、地方公共団体にまでその制度は及んでいる。しかし、ガラス業界がその制度を追風としてうまく活用できているかどうかは、大いに疑問のあるところだ。そこで今回は全国板硝子卸商業組合連合会の松本巖会長になぜできないのか、また、制度をうまく活用するにはどうしたらよいのかを聞いてみた。 ――弊紙でも幾度となく紹介してきていますが、住宅の窓改修に対する補助金制度が国だけでなく地方公共団体にまで広く伝わってきています。 ――しかし、いろいろ補助金制度がでてきている割には、われわれの業界ではあまり利用されていない。異業種のほうが頑張っているのではないか、というような声を良く耳にしますし、事実そのようです。 ――板橋区や京都市にも取材に行きましたが、ガラス組合があり、そこには立派な名簿もあるということを言っても「ガラス店さんの組合があるのですか?」と言うのです。もしかしたら、違った部署に訪問しているのかもわかりませんが。 ――確かにサッシメーカーはいろんな新商品を出しては記者会見を行っていますが、ガラスメーカーではなかなか新商品の発表がありません。 ――今だったら防災ガラスをアピールすれば、テレビ局も注目すると思いますがね。 ――このままでは、窓リフォームの仕事が異業種ばかりに盗られ、ガラス店の存在意義が無くなるのではないかと危惧しています。何か対策はないのでしょうか。 ――私は、それにもっと若い人に業界にはいってもらわないといけないと思っています。 ――どうもありがとうございました。 |
| ■高性能建材補助金 3次分は全体で1億円(平成27年9月14日) |
|
高性能建材導入促進事業の本年度(26年度補正)第3次公募分の補助申請が予算枠15億円に対しわずか1億円だったことがわかった。14億円が手元に残った勘定だ。資源エネルギー庁が明らかにした。 |
■都硝協理事長 永島氏が辞意表明(平成27年9月14日)
|
||
|
東京都板硝子商工協同組合の永島光男理事長(全硝連会長)は9月6日開催の9月度合同会の席上、「今期いっぱいで理事長を降ろさせていただく」と辞意を表明した。来年5月の通常総会で正式に引退する運びとなる。 |
■韓国の組合が表敬訪問 九州で全日鏡と面談
|
||
|
9月3日に九州で、全日本鏡連合会(尾崎由雄会長)と韓国ガラス加工組合(Korea Glass Proccesing Asosiation Jun―WOO,Lee会長)との交流会が行われ、日本側からは全日鏡の尾崎会長、辻本豊三郎副会長、福岡鏡工業会から面家隆寿会長、宮副俊浩幹事、上杉隆二氏、それに今回、韓国と日本の橋渡し役のひとりとなった南里製作所㈱の田中本部長らが出席した。韓国側からは、Jun会長以下29人が訪日、福岡にあるガラスと鏡の加工と販売を行う宝鏡㈱(本社=福岡県福岡市博多区東那珂3丁目7?68 宮副俊浩社長)と㈱丸八ガラス(本社=大川市大字大橋15番地の1 面家隆寿社長)の両社工場を見学、その後、場所を佐賀市内にあるホテルに移動し、全日本鏡連合会と韓国ガラス加工組合・役員とのミーティングも行われた。 ▽Lee会長の協会設立の挨拶文より 記者の目 |
■小平市などの公立の小中学校体育館の窓改修が活発化(平成27年9月7日)
|
||
|
東京地方の自治体の間で、公立小中学校の体育館の改修工事に取り組む動きが活発化している。窓の強化、吊り天井の撤去、外壁や床の断熱化が中心。児童生徒の安全はもとより災害時に地域住民の緊急避難場所ともなる公共施設のこうした改修に対し、国や都は補助金交付など支援体制を整えている。 |
■佐藤工務店 超高気密・高断熱住宅が完成 省エネ住宅への取り組みは(平成27年9月7日)
|
|||
|
㈲佐藤工務店(埼玉県上尾市東町1‐2‐13、電話048‐771‐780、佐藤喜夫社長)は、このほど熊谷市の船木台団地で手掛けたST邸において、断熱性能(計算値)がUA値(外皮平均熱貫流率)0.3、気密測定におけるC値(隙間相当面積)0.096という超高気密・高断熱住宅を完成させた。 ―― 早速ですが、省エネ住宅には、いつ頃から、どのようなきっかけで取り組まれるようになったのでしょうか? ―― 現在、何軒くらいの省エネ住宅を手掛けていらっしゃいますか? ―― エリアは埼玉県が中心ですか? ―― 今回、非常に高気密な住宅を手掛けられたわけですが、この部分へのこだわりは? ―― そのあたりがK‐Windowを採用された理由でしょうか? ―― 今回の物件は、全てK‐Windowがしようされているのでしょうか? ――次に、今回の物件現場である船木台団地について教えてください。 ――最後に、今後のお考えについて、お聞かせください。 ―― 本日はお忙しい所、お時間を頂き、ありがとうございました。 ◇ インタビュー後、実際の物件がある熊谷市船木台のST様邸を見学させて頂いた。平屋建ての物件は、全ての窓に防犯ガラスを入れたK‐Windowを採用しており、寝室や浴室などに多くのドレーキップ窓が使用されていた。佐藤社長によると、特に浴室の横長ドレーキップが気に入っているとのこと。 ◇ また、今回の現場である埼玉県熊谷市は、2007年8月16日に岐阜県多治見市とともに当時の日本国内における観測史上最高気温となる40.9℃を観測するなど夏の気温の高さで全国的に知られている。 |
| ■板橋区窓の補助金制度始まる(平成27年8月31日) |
|
ここ数年、東京の自治体の間で、住宅の「窓」断熱改修に補助金を支給する制度が広がりを見せている。本年度はこの4月より板橋区でもスタートした。先日、板橋区資源環境部環境戦略担当課を訪ね、同課環境政策グループの遠藤宏環境戦略担当係長、宮川良治氏、久保田恵美子氏の3人に制度についてお話を伺った。 ――今回の板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度(平成27年度版)ですが、元々の制度はいつからあったのですか。 ――これまで、予算的には使い切ってきた感じですか。 ――今期の予算はどのような感じですか。 ――省エネ住宅ポイント制度の併用は。 ――工事業者は板橋区にお店を構えたところだけ? ――板橋区で「窓の断熱化」の補助制度を導入するにあたってどこか参考にされた自治体の制度とかありましたか。 ――いろいろ自治体を廻ったりしましたが、住民の皆さんにはなかなか制度自体の情報が伝わらないようです。板橋区として特にされていることは。 ――次年度については。 ――なにか困ったことは。 ――どうもありがとうございました。 記者の目 今回「窓の断熱改修」を初めて予算化したと聞いたが、わりとスムーズに流れているように感じた。16件の申し込みがあったと聞いたが、そのうちガラス店が請け負ったと見られる物件は2件で、他はリフォーム工事業者のようだった。せっかくガラス業界で種を蒔いても刈り取りが他の業者では、なんのためにPRしているのかわからない。窓口によくこられるのもガラス業界以外のところが多いようだ。ガラス業界に奮起を促したい。 ☆板橋区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度の概要(平成27年度版) |
■神奈川県茅ヶ崎市室内プールで窓ガラス破損(平成27年8月31日)
|
||||
|
6月下旬、神奈川県茅ヶ崎市の市屋内温水プールで大型のガラス窓1枚が割れて落下し、破片で小学生5人が軽傷を負う事故が発生した。市はプール周囲上部のガラスを全て交換するなど修繕工事を施し1カ月後に営業を再開したが、原因はいまだ不明。建築面積に占めるガラス部分の比率が高い公共施設での安全対策が改めて問われている。 |
| ■エヌビーエス 千葉に新ガラス加工工場建設(平成27年8月24日) |
|
㈱エヌビーエス(本社=東京都台東区、加藤俊明社長)は、8月5日同社本社において、関東工場建設の記者会見を行った。それによると新工場は千葉県千葉市緑区にある土気工業団地内に建設され、敷地面積は約4万平方㍍。完成は来年の秋を予定。従業員は80名程度を計画。売上目標はグループ全体で57億円(現在は約30億円)。投資金額は30億円強とされ、関東地区に巨大なガラス加工工場が登場する。以下は加藤社長の説明。 |
■奈良県橿原市木造住宅の省エネルギー改修等補助事業(平成27年7月27日)
|
|||
|
奈良県橿原市(森下豊市長)は、平成25年6月から「既存木造住宅の省エネルギー改修補助事業」制度の運用を行っている。今年6月から従来の制度を見直し、新たに「既存木造住宅の省エネルギー改修“等”補助事業」として、改めてスタートした。 |
|||
| ■国土交通省住宅ポイント申請状況(平成27年7月27日) |
|
国土交通省住宅局住宅生産課は7月10日(金)、平成27年6月末時点の省エネ住宅ポイントの申請状況を発表した。 |
■大硝協「防犯ガラス教室」(平成27年7月27日)
|
||
|
大阪府板硝子商工業協同組合(辻良明理事長)第10支部(藤野修二支部長)は、7月15日(水)午後7時から福田地域会館(堺市中区)で防犯ガラス教室を開催した。 |
■関西卸「魅力ある業界づくり」提案(平成27年7月13日)
|
||
|
関西板硝子卸商業組合(小山保和理事長)は、このほど、会員からの意見を「魅力ある業界づくりに向けての提言・提案事項2015」としてまとめ、国内板ガラス3メーカーとサッシメーカー3社の関西の拠点を訪問。それぞれの責任者と面談し、組合活動の現状を説明、組合活動への協力と理解を求めた(詳細については弊紙夏季特集号に掲載する予定)。 |
| ■全国板硝子商厚生年金基金企業年金基金に加盟を(平成27年7月13日) |
|
平成25年6月19日、厚生年金基金制度の見直しを柱とした年金制度改正法(「公的年金制度の健全性及び信頼性確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」)が可決成立し、同年6月26日付で改正厚生年金保険法が公布され、平成26年4月1日より施行された。これにより、昭和41年にスタートした企業年金制度のひとつである「厚生年金基金」が、一部の基金を除き、実質廃止に向かって動き出した。 ――厚生年金基金の解散が決議され1年が経過しようとしています。 ――解散となるとこれまでの積立金は? ――各事業主のところには、厚生年金基金が解散されるなら、銀行や保険会社から「当方のシステムを利用して下さい」と説明に来ているようですが、企業年金基金のほうではどのようなメリットがあるのですか。 ※ ※ ※ ☆全国板硝子商企業年金基金の制度概要 ※ ※ ※ ――現在、全国板硝子商企業年金基金にはどれくらいの方が加盟されていますか。 ――業界でも、新しい基金の存在を知らない方がたくさんいらっしゃるかと思いますので、板ガラス業界のためにも、もっとアピールされたほうが良いかと思います。ありがとうございました。 全国板硝子商企業年金基金の問い合わせ先は、Tel 03-3451-2040まで。 |
| ■キッズデザイン協議会「キッズデザイン賞」選出(平成27年7月13日) |
|
特定非営利活動法人キッズデザイン協議会(和田勇会長)は、製品・施設・サービス・研究活動などを対象に、子どもの安全・安心、健やかな成長発達に役立つデザインを顕彰する「第9回キッズデザイン賞」受賞作品308点を選出した。 |
■資源エネルギー庁高性能建材導入事業好調(平成27年7月6日)
|
||
|
経産省資源エネルギー庁が4次に分けて実施している既存住宅対象の高性能建材導入促進事業の利用状況がここにきて好調だ。第2次申請分は集合住宅と戸建て住宅の計23億円の予算をほぼ消化した。執行機関の環境共創イニシアチブ(SII)は予算15億円で第3次分の申請を公募中。 ◇ ◇ 資源エネルギー庁省エネルギー対策課課長補佐の中村幹氏に話を聞いた。 ―応募方式変更で状況に変化は。 ―業界の関心は高い。来年度も継続する? |
| ■日本板硝子環境アメニティ「トロポス NEO」開発(平成27年7月6日) |
|
日本板硝子環境アメニティ㈱(本社=東京都、袴田正人社長)は、トヨタ自動車㈱と共同開発した、自動車ショールーム等の大面積ガラス&視認性が必要な空間の省エネに適したダブルスキンを構築するインナーガラススキン「トロポス
NEO」(試作品)を開発。7月8日から7月10日まで東京ビッグサイトで開催される展示会「省エネ・節電EXPO」に出展すると発表した。 |
| ■経済産業省が調査板ガラス需要ギャップ拡大(平成27年7月6日) |
|
経済産業省は産業競争力法第50条に基づいて、板ガラス産業の市場構造に関する調査を行い、6月26日、調査報告をまとめ公表した。 |
■旭硝子財団第24回ブループラネット賞(平成27年6月29日)
|
|||
|
公益財団法人旭硝子財団(石村和彦理事長)は6月18日(木)、2015年(第24回)ブループラネット賞(地球環境国際賞)をパーサ・ダスグプタ教授(英国)とジェフリー・D・サックス教授(米国)の2氏に授与すると発表した。 |
| ■全硝工連・全硝連 登録硝子工事基幹技術者講習・試験の募集要領(平成27年6月29日) |
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連)と全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)でつくる登録硝子工事基幹技能者講習委員会は、今夏に東京と大阪で実施する「平成27年度登録硝子工事基幹技能者講習・修了試験」の正式な日程と募集要領をまとめ、全硝連などのホームページ(HP)で公開した。 ▼郵送先=〒103?0007、東京都中央区日本橋浜町2?38?9?601又は602、登録硝子工事基幹技能者講習委員会事務局 申し込み受付期間は―、 講習・修了試験の日程は―、 合格発表は9月25日(金)の予定。問い合わせは、03-5649-8577(全硝連)又は03-6413-6222(全硝工連)まで。 |
■第17回板ガラスフォーラム(平成27年6月22日)
|
||
|
恒例の「板ガラスフォーラム」が今年も盛大に開催された。板ガラス業界8団体(全国板硝子商工協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催による「第17回板ガラスフォーラム」が6月12日、東京都港区にある品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホールに於いて盛大に開催された。今回の参加者は約400人。 |
■AGCリグラスカップ2014(平成27年6月8日)
|
||||
|
AGCグラスプロダクツの製品拡販に貢献した上位企業をたたえるAGCリグラスカップ2014表彰式及び2015年度プラチナステータス店認定式が5月21日(木)、東京・京橋のAGCスタジオで行われた。リグラスカップでは㈱あけぼの通商(本社・長野県上田市古里、近江朋秀社長)が全国総合部門で9連覇を飾った。 |
■全国卸 通常総会(平成27年6月8日)
|
||
|
全国板硝子卸商業組合連合会(松本巌会長)は、5月28日(木)に東京都港区にあるメルパルク東京にて、第29回通常総会を開催。今期の事業計画案や収支予算案、などを審議、原案通り承認した。 |
■2015 第26回China Glass(平成27年5月25・6月1日)
|
|||||||||
|
5月20日(水)~23日(土)の4日間、中国・北京市の中国国際展覧中心において、「第26回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2015)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 主な出展企業 |
■第37回日本板硝子材料工学助成金研究助成金贈呈式(平成27年5月11日)
|
||
|
公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は4月23日(木)、東京・六本木の住友会館・泉ガーデンタワー42階で平成27年度(第37回)研究助成金贈呈式を開催し、無機材料分野を中心とした40件の研究に対し総額4131万円を贈った。 |
| ■全国卸・全硝連松本・永島会長が資源エネルギー庁へ陳情(平成27年5月11日) |
|
既報のとおり、経産省資源エネルギー庁は、現在補正予算で実施している高性能建材導入促進事業の公募受付方法を5月から始まる2次申請分から、集合住宅向けについては「先着順」を廃止し、期間中の申し込みについてその全てを受け入れ、締め切った後で、審査委員会において選考する方式に切り替えた。 |
| ■資源エネルギー庁高性能建材導入事業の受付(平成27年4月27日/5月4日) |
|
経産省資源エネルギー庁は平成26年度補正で実施している高性能建材導入促進補助事業の公募受け付け方法について5月の2次申請分から「先着順」を廃止することを決めた。執行機関の一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が4月22日、公募要領の修正をホームページで公表した。 |
| ■AGC LowーE膜コーティングガラス タイ 生産能力を50%増強(平成27年4月20日) |
|
AGC 旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、タイの関連会社、AGCフラットガラス・タイランド(以下、AFT)のサムットプラカン工場で生産するLow‐E膜コーティングガラスの生産能力を50%増強、2016年第1四半期に生産を開始する予定。 |
| ■AGC インドネシアに発電所(平成27年4月20日) |
|
AGC 旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、インドネシアの社子会社アサヒマス・ケミカル社(所在地=インドネシア・ジャカルタ、宮崎淳社長、苛性ソーダ、二塩化エチレン(EDC)、塩ビモノマー(VCM)、塩ビ樹脂(PVC)等化学品の製造販売、以下ASC)に、約4億ドルを投じて、発電所を建設すると発表した。 |
■日本板硝子サーモクロミック調光ガラス試験発売(平成27年4月13日)
|
||
|
日本板硝子㈱(本社=東京都港区、森重樹社長)は、建築用ガラス向けにサーモクロミック調光ガラスを今年夏ごろから試験発売すると発表した。 |
| ■第17回板ガラスフォーラム6月12日(金)開催(平成27年4月13日) |
|
板ガラス業界8団体共催の「第17回板ガラスフォーラム」の開催概要が、このほど板ガラスフォーラム事務局から発表された。 ◎第17回板ガラスフォーラム オプショナルツアー「東京駅周辺 著名物件見学会」 |
| ■AGC入社式 島村社長「何をすべきか考え、行動」(平成27年4月13日) |
|
AGC 旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、4月1日(水)午前10時から、本社会議室で新入社員48名全員が参加して、「2015年度新入社員入社式」を行った。 |
■武蔵野硝子会長 伊藤巌氏をしのぶ「お別れ会」(平成27年4月13日)
|
||
|
2月25日にお亡くなりになった武蔵野硝子㈱(本社=東京都、伊藤隆子社長)の創業者で代表取締役会長・伊藤巌氏をしのぶ「お別れ会」(実行委員長・白井春雄氏=LIXILジャパンカンパニー社長)が4月6日(月)武蔵野市内にある吉祥寺第一ホテルで開かれた。伊藤会長と親交が深かったLIXILや旭硝子などのメーカー、流通店など各分野の関係者ら約900人が参列し、惜別の献花をささげた。 |
■AGC旭硝子武田氏に聞く(平成27年4月6日)
|
||
|
前期に引き続いて体質強化や構造改革に取り組むAGC旭硝子㈱(本社=東京都、島村琢哉社長)の建築用ガラス事業。自動車用ガラス事業を含むガラス事業全体では、2017年の売上高営業利益率を5%以上(現状=0・8%)に目標を定める。そこで今年1月に執行役員ガラスカンパニービルディング・産業事業本部副本部長兼同事業本部日本・アジア事業部長・武田雅宏氏に日本における建築用ガラス事業の話題を中心にお話を伺った。武田氏は「当たり前の話だが、儲からない事業は罪悪である」と強調。前期で通年の黒字化を達成したガラス事業を今後も軌道に乗せていきたい旨を語った。 ――アメリカで学んでこられたことは。 ――日本のガラス事業を儲かるようにするには。 ――直接、流通の方々とお話をなされる? ――売上を伸ばすということですが、具体的な方策は。 ――薄板ガラスを使用したトリプルガラスは。 ――どうもありがとうございました。 ☆武田雅宏氏のプロフィール |
■永島光男氏を祝う会(平成27年4月6日)
|
||||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(略称=全硝連)会長・東京都板硝子商工協同組合(略称=都硝協)理事長の永島光男氏の旭日小綬章受章(昨年秋の受章)を祝う会(発起人会代表=全硝連副会長・施向昌之氏、同副会長・辻良明氏、同専務理事・宮代茂氏、同常務理事・山田一善氏、都硝協副理事長・松原嘉一氏、公益社団法人練馬西法人会会長・阿部財智氏)が3月27日(金)午後4時より、東京都千代田区にあるホテルポール麹町において、国会議員や板ガラス・サッシ業界のメーカー、卸、小売、工事関係者、さらに地元練馬区の住民ら約160名が集まり盛大に行われた。板ガラス業界からは、板硝子協会専務理事・森谷茂明氏、AGC執行役員・武田雅宏氏、日本板硝子上席執行役員・今西実氏、セントラル硝子取締役常務執行役員・高山聡氏ら団体・メーカーのそれぞれのトップクラスが顔を揃えるなど終始華やいだ雰囲気の中で、盛大に行われた。 |
| ■LIXIL「組織変更・人事異動について」のお詫びと訂正(平成27年4月1日) |
|
■訂正箇所(2点) 念のため、訂正したリリースをお送りさせていただきます。何卒宜しくお願い申し上げます。 https://lixil.firestorage.jp/download/cadc9a8c613c7bf4e30363bea717fea2be4f7c 52 ◆この件に関するお問合せ先 株式会社LIXIL 広報部 布施木 TEL 03-6273-3607
|
■経産省資源エネルギー庁高性能建材補助事業スタート(平成27年3月23/30日)
|
||
|
省エネ住宅ポイントとともに板ガラス業界で関心の高い新年度(平成26年度補正)の高性能建材導入補助事業が事実上スタートした。前年度と異なり補助金申請の一般公募を4次に切り分け、それぞれに予算を配分して実施。1次分は約30億円を計上した。 ◇ 事業を所管する資源エネルギー庁省エネルギー対策課課長補佐の中村幹氏に話を聞いた。 ―幾つか修正を。 ―戸建ても窓だけで? ―申請が煩雑とも。 |
| ■平成26年度後期ガラス施工技能検定合格者(平成27年3月23/30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成26年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月13日(金)に全国都道府県職業能力開発協会から、発表された。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■全小学校に飛散防止フィルム東京都墨田区(平成27年3月9日)
|
||
|
災害時に緊急避難場所に指定されるケースが多い公共施設の耐震・防災改修が全国的に叫ばれている折、東京都墨田区が地元のガラス店を使って区立小学校の校舎や体育館の窓に飛散防止フィルムを貼る事業を開始した。東日本大震災後、都内では初めて。板ガラス業界の関心を集めそうだ。 |
| ■ひのまるチェーン東京支店スペーシア全国セールスマラソン表彰(平成27年3月9日) |
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=東京都、鈴木隆社長)と取引のある販売店で構成されるひのまるチェーン東京支部(会長・飯島今朝男氏=飯島アルミ㈱取締役会長)は、2月24日(火)東京・新宿にある京王プラザホテルにおいて、会員ら約200名が集まる中、盛大に2015年度ひのまるチェーン東京支部定例総会を開催した。その中で、スペーシア全国セールスマラソンの表彰状贈呈式も開催され、全国賞1位には古田ガラス㈱(東京都)が表彰された。また、東京エリア地域賞では、住宅部門1位・㈲サンヨーアルミ(東京都)、マンション部門1位㈲石田屋硝子店(東京都)非居住部門1位・古田ガラス㈱、新人賞・光硝子㈱(千葉県)らが表彰。特別賞は、㈲創進(栃木県)・㈱あけぼの通商(長野県)が表彰された。 |
■第28回技能グランプリ 今村氏が厚生労働大臣賞(平成27年3月2日)
|
|||
|
厚生労働省と中央職業能力開発協会、(一社)全国技能士連合会が主催する、第28回技能グランプリが2月20日(金)~23日(月)の4日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)ほかで開催された。 |
| ■ひのまるチェーン大阪支部関西部会定時総会(平成27年3月2日) |
|
日本板硝子の販売店会・ひのまるチェーン大阪支部関西部会(会長・山下義一氏=山下硝子建材㈱会長)は、2月17日(火)に大阪市内にある大阪倶楽部4階大ホールにおいて、会員ら約120名が集まる中、盛大に「ひのまるチェーン大阪支部関西部会定時総会」を開催した。その中で「2014年・下期(7月から12月)スペーシア・コンテスト」の表彰式も行われ、丸一板硝子工業㈱(本社=大阪府茨木市)が見事金賞を受賞、日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=東京都、鈴木隆社長)の最上茂樹取締役大阪支店長より、賞状などが手渡された。 |
| ■セントラル硝子 販売会社7社を統合 セントラル硝子販売㈱を設立(平成27年2月23日) |
|
セントラル硝子㈱(実質本社=東京都千代田区、皿澤修一社長)は2月5日、国内販売会社7社の統合を発表した。 |
■省エネ大賞2社〈YKK AP ・ LIXIL〉が受賞(平成27年2月9日)
|
||
|
省エネルギーセンター(藤洋作会長)では、国内の企業・工場・事業場等に対して優れた省エネ推進の事例や省エネ性に優れた製品及びビジネスモデルを、「省エネ大賞」として表彰している。今回は、1月28日に東京ビッグサイトで、「平成26年度省エネ大賞」(主催=省エネルギーセンター、後援=経済産業省)の表彰式が行われ、YKK
AP㈱が資源エネルギー庁長官賞と省エネルギーセンター会長賞とダブルで受賞、また、㈱LIXILが省エネルギーセンター会長賞を受賞し表彰された。この他窓関係では㈱一条工務店の防犯ツインLow―Eトリプルガラス樹脂サッシが資源エネルギー庁長官賞を受賞し表彰された。 |
■板硝子協会 合同委員会を開催(平成27年2月2日)
|
||
|
板硝子協会(吉川恵治会長)は、1月22日に東京・丸の内にある東京会館において、協会役員や各委員会委員長やその委員らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。 |
■関東卸・都硝協 合同賀詞交歓会(平成27年1月26日)
|
||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(永島光男理事長)は、1月16日、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で6回目となる合同新年会には、来賓を併せ約120名が参会し開催された。 |
| ■永島全硝連会長に聞く(平成27年1月26日) |
|
板ガラス小売業界は住宅市場の低迷や流通慣行の変化を背景に苦境に立たされている。全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)の永島光男会長に打開の方策を聞いた。 ―全硝連の動向は。 ―小売側の問題は。 ―直販問題は。 |
| ■国交省省エネ住宅ポイント 制度概要発表(平成27年1月12/19日) |
|
国土交通省は1月9日、住宅市場のてこ入れを狙って復活させる住宅エコポイントの制度概要を発表した。新しい名称は「省エネ住宅ポイント」。省エネ性能が高い住宅の新築やリフォームで30万円分のポイント(耐震改修を行う場合は最大45万ポイント)を与え、地域の特産品や商品券と交換できるようにする。2014年12月27日以降に工事契約を結び、2016年3月末までに着工することが条件。必要経費として14年度補正予算案に805億円を盛り込んだ。あわせて省エネ性能が高い住宅を対象とした長期固定型の住宅ローン「フラット35S」の金利優遇幅を現在の0・3%から0・6%に拡大する。関連経費として1150億円計上した。 なお、1月19日の東京会場を皮切りに全国50カ所で「省エネ住宅ポイント」の説明会が開催される。詳細は国土交通省のHP(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000047.html)に掲載されている。 |
■関西板硝子業界が新年会(平成27年12/19日)
|
||
|
恒例となった平成27年関西板硝子業界新年互礼会(全硝連近畿地区本部、関西板硝子卸商業組合、関西板硝子工事協同組合の3団体主催)が1月9日(木)午前11時より大阪市北区にある新阪急ホテル2階「紫の間」において、業界関係者ら約110名が集まる中、盛大に開催、関西板硝子業界の2015年は華々しくスタートした。 |
| ■AGC島村社長 本年度の方針発表(平成27年12/19日) |
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、島村琢哉社長)は、1月5日、島村社長の年頭あいさつとして、2015年度方針説明(要旨)を発表した。その内容は次の通り。 |
| ■全国卸・全硝連が国交省に陳情「住宅エコポイント復活へ」(平成26年12月22/29日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会(松本巌会長)・松本会長は、全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)・永島会長らとともに12月5日(金)午後4時半に国土交通省を住宅局住宅生産課 企画専門官(法規担当)倉石誠司氏と同建築環境企画室課長補佐萩原崇氏を訪問した。 国土交通省住宅局住宅生産課課長林田康孝 殿 全国板硝子卸商業組合連合会・会長松本巖 全国板硝子商工協同組合連合会・会長永島光 男 「住宅エコポイント制度」再開に関するお願い 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 さて、平成26年度の補正予算で再開を検討されている「住宅エコポイント制度」に関しまして、当板ガラス流通団体(板ガラス卸売り並びに小売りの団体)としまして下記の各事項についてお願いをさせて頂きます。 記 1.早期に「住宅エコポイント制度」を再開実施して頂きたい。 冬季は窓改修の需要期であり、今回の「住宅エコポイント制度」再開の報道後、既築住宅改修工事の発注が先送りされる物件が増えております。 また、再開された「住宅エコポイント制度」が混乱なく実施されるために、前回の申請方法を踏襲して頂きたい。 2.既築住宅改修に多くの予算が消化されるような制度内容にして頂きたい。前回実施の「住宅エコポイント制度」では、新築住宅と既築住宅改修での申請件数はほぼ同数でありましたが、消化された予算金額では、新築が約85%強と多くを占めました。新築住宅は、既に省エネ効果の高い建材の使用は当たり前となっており、今後の国の省エネ事業推進の観点からも、既築住宅をいかに省エネ効果の高い住宅に改修して行くのかが重要ではないでしょうか。 3.省エネ効果の高い基準での制度内容にして頂きたい。 前回実施の「住宅エコポイント制度」では、例えば旧Ⅳ地域での硝子交換工事の場合は一般の複層硝子、内窓取り付けの場合はガラスが単板仕様の内窓を取り付けるといった省エネ効果の低いものも対象になっていたので、今回の「住宅エコポイント制度」では、さらに省エネ効果の高い基準での制度内容を検討頂きたい。出来ましたら「長期優良化リフォーム推進事業」の基準を取り入れて頂き、省エネ効果の高い基準で改修工事をした場合には、獲得ポイント数を多くして頂きたい。 4.旧Ⅲ地域での硝子交換工事も「住宅エコポイント制度」の対象にして頂きたい。 前回実施の「住宅エコポイント制度」では、旧Ⅲ地域で既存のアルミサッシに省エネ効果の高い硝子を使用した場合、当制度の対象外とされていましたが、平成25年度に改訂された「省エネ基準」の仕様例として追加されておりますので是非当制度の対象として頂きたい。 5.「住宅エコポイント制度」で交換できる商品を汎用性の有る商品にして頂きたい。 以上、私ども板ガラス流通団体がお願いをさせて頂きたい事項でございます、何卒ご配慮の程宜しくお願い申し上げます。 敬具 |
■電気硝子建材大下社長に聞く(平成26年12月22/29日)
|
||
|
本年4月に日本電気硝子のグループ会社・電気硝子建材㈱(本社=大阪府大阪市)の社長に就任した大下純夫氏。同社にとってこの1年はどのような年だったか、2014年を振り返ってもらった。大下社長は「個人的には、満足はしていないが、合格点を上げられるのではないか」と語ってくれた。 ――この1年は大下社長にとってどのような年でしたか。 ――どういう点が良かったか。 ――どこの国からですか。 ――逆に、満足できなかった点はどういうところか。 ――いつごろ市場にでてくる予定? ――消費税増税の延長が決まり、来年度は駆け込み需要がなくなるという話もありますが。 ――来年度に期待することは。 ――お忙しいところ、どうもありがとうございました。今後のさらなるご活躍を期待しています。 |
■長野県自治体住宅リフォーム補助事業 広範囲に普及(平成26年12月8日)
|
||
|
寒冷地が広がる長野県では住宅リフォームに補助金を交付する市町村が増えている。利用度は高く、年度上期で予算を消化するケースが目立つ。省エネ意識の高まりを背景に、窓を中心とした断熱改修に特化した制度を設けている自治体もある。 |
| ■全硝連鹿児島で全国理事長会議(平成26年12月8日) |
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、永島光男会長)は11月28(金)、29(土)の両日、鹿児島市内にある鹿児島サンロイヤルホテル「エトワールの間」で第30回全国理事長会議を開催した。初日の全体会議には58名が参加して、ガラスメーカー・サッシメーカーの値上げに係る業界動向などを討議した。 |
| ■関西卸 全員協議会(平成26年12月1日) |
|
関西板硝子卸商業組合(小山保和理事長=大阪板硝子販売)は、11月21日(金)午後1時より20人以上の会員らが集まる中、「2014全員協議会」を開催した。今回は「業界の抱えている議題2014」を一歩でも前進させることを目的に、第一部では討論会を第二部では講演会も行われた。 |
| ■LIXIL 坂口治司常務に聞く(平成26年12月1日) |
|
㈱LIXIL(本社=東京都、藤森義明社長)では、10月1日よりサッシルートの責任者が大坪一彦常務執行役員より坂口治司常務執行役員にバトンタッチした。今回も10月27日号の特集に引き続き、坂口氏にお話を伺った。 ――現状の動きは ――値上げの進捗状況は? ――来年の読みは。 ――アルミ地金の高騰や円安の流れでアルミ商品の利益が圧迫されてきています。アルミサッシ本体の値上げはいかがですか。 ――「パートナーグロース統括部」を新設され初代責任者に就任されました。 ――これからも、大いに期待しています。どうもありがとうございました。 |
■グラステック リポート2 極薄のガラスに注目(平成26年12月1日)
|
||||
|
前回、前々回と弊紙で紹介したように、10月21日(火)~24日(金)の4日間、ドイツ・デュッセルドルフの見本市会場で「グラステック2014」が開催され、4日間で約4万3000人が訪れた。 今回は、そのリポートの1回目。 ――地域的に増えた所は? ――前回は「省エネ」をテーマとして掲げていましたが、今回は「技術革新」の部分に重点を置いている? ――お忙しいところ、色々なお話を聞かせて頂き、ありがとうございました。今回のグラステックの成功と、次回のグラステック更なる発展をお祈りしています。 |
■第23回ブループラネット賞デイリー教授とジャンゼン教授(平成26年11月24日)
|
||
|
公益財団法人旭硝子財団による2014年度(第23回)ブループラネット賞(地球環境国際賞)を受賞した米国の2氏と1機関の表彰式典が11月12日(水)、秋篠宮ご夫妻をお迎えし、皇居を望むパレスホテル東京2階の葵で開催された。 |
■勲章伝達式に列席 旭日小綬章の永島ご夫妻(平成26年11月24日)
|
|||
|
平成26年秋の叙勲で旭日小綬章を受章した全国板硝子商工協同組合連合会会長の永島光男氏(都硝協理事長)は11月11日(火)、妻の妙子さんを伴って東京・芝公園の東京プリンスホテル2階「鳳凰の間」で執り行なわれた受章者伝達式(経済産業省推薦分)に列席し、晴れて勲章を胸にした。 |
| ■AGC 新社長に島村琢哉氏(平成26年11月10日) |
|
旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)では、指名委員会の推薦及び10月31日に開催された取締役会の決議により、次の通り代表取締役の異動を内定した。 10月31日(金)午後4時より、東京都内で社長交代に関する緊急の記者会見が行われた。会見の中で石村氏は「2008年に社長に就任してから7年目になった。就任当初から液晶の事業はいずれピークを迎えることを予想し、それに変わるビジネスを模索してきた。しかし、予想を上回るスピードで液晶事業が悪化した。それに東日本大震災が発生し、欧州も経済環境が悪化し、建築用ガラスが不振に陥った。本年も含め四期連続で減益となってしまった。 ――社長就任を伝えられたのはいつ。また、その時の気持ちは。 ――今の課題は。 |
| ■グラステック 2014 ガラス新聞社ツアー開催(平成26年11月10日) | ||||||||||||
|
ガラス産業のあらゆる分野を捉え、素材としてのガラスの可能性を様々な視点から紹介する世界最大級の展示会「glasstec 2014(グラステック2014 国際ガラス製造・加工機器展)」が、10月1日(火)~24日(金)の4日間、ドイツ・デュッセルドルフの見本市会場で盛大に開催された。
|
■第49回セントラル硝子国際建築設計競技(平成26年11月3日)
|
||
|
第49回「セントラル硝子国際建築設計競技」(主催・セントラル硝子㈱)の公開審査会が、10月25日(土)午後1時半より、東京国際フォーラムD7ホールで開催された。厳正な審査の結果、栄えある最優秀賞にはリ・スチ(天津大学大学院《中国》)・チェン・シャオティン(SVESMI《オランダ》)の両氏の作品が選ばれ、賞金二百万円と記念品及び賞状が贈られた。 |
■広がり見せる補助制度(東京・台東区、練馬区)(平成26年10月27日)
|
||
|
東京の自治体の間で住宅の窓断熱改修に補助金を支給する制度が広がっている。本年度は台東区や練馬区がスタートさせた。機能ガラスの普及活動に取り組む都硝協や関東卸の成果とみられる半面、組合員の事業に直接結びつくケースはまだ少ないようだ。 |
■スーパーハウジングフェア(広島)(平成26年10月27日)
|
||
|
毎年10月は住(じゅう)とかけて住生活月間。「住生活基本法」(平成18年法律第61号)の目的とする「国民の豊かな住生活の実現」のために関係機関・団体等が広報活動や各種イベントを行って、普及・啓発を図るキャンペーンを行っている。当時の建設省(現・国土交通省)の提唱により、平成元年から毎年10月を「住宅月間」と定め、関係団体が参加した「住宅月間実行委員会」を中心に、各種行事を実施してきている。平成19年度に、「住生活基本法」の成立を受けキャンペーン月間の名称を「住宅月間」から「住生活月間」に改め、「住生活」に関する幅広い分野を対象とする総合的な普及・啓発活動を実施している。 |
|
||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)は10月2日(木)、東京の中央区立総合スポーツセンター会議室で全員協議会を開催し、諸報告を了承した後、機能ガラス普及推進事業の活動状況を中心に板硝子協会・浅沼光一調査役の説明を聞いた。 |
|
||
|
この7月に、矢野廣文前社長からバトンを渡され、新しく坂義臣体制となった㈱アルテジャパン(本社=東京都新宿区納戸町7 ?03―3235―6211)。これまで42年間の長きにわたって社長を務めていた創業者の矢野氏に代わって「アルテジャパン」をどのような色に変えて行くのか。今回は、新宿にある同社本社に坂社長を訪ね、社長就任の抱負などを聞いた。 ――今の目標は。 ――これまでの「矢野カラー」をどのように変えていくおつもりか。 ――具体的には ――特に力を入れる地域は。 ――それでは、社員に期待していることは営業力ですか。 ――現在の業績のほうはいかがですが。 現在はカラーガラスを用いた壁面素材「ディ・コローレ」の販売に注力しています。店舗・店装の内装関係だけでなく、住空間にも注目されています。 ――社長になられて今の感想は ――ありがとうございました。業界の新しいリーダー・顔として頑張ってください。 ☆坂義臣氏の経歴 |
| ■トップランナー基準案 複層ガラスU値2.19に設定(平成26年10月6日) |
|
窓を構成するガラスとサッシのトップランナー基準案が明らかになった。ガラス関係は複層ガラスを対象に、目標年度である2022年度の熱貫流率(U値)を加重平均で「2・19」に設定。サッシは引き違い、FIXなど開閉形式5区分とアルミ、樹脂など材質4種を併せ通過熱流量の目標基準値を設けた。 |
|
|||
|
全硝連関東甲信越地区本部(小峰梅男本部長)は9月20日(土)、東京・日本橋浜町の都硝協会議室で第2回ブロック会議を開催し、「組合間の情報共有にはインターネットの積極的な活用が不可欠」との認識で一致、今秋の全国理事長会議に提言することになった。 |
|
||
|
「窓全部をLow―Eペアに交換」―。住宅リフォーム補助制度を利用し、窓の断熱改修に踏み切る動きが徐々に広まっている。省エネ関連の事業予算を倍増した自治体もある。群馬県内の事例を紹介する。 |
|
||
|
国や地方自治体による既存住宅のリフォーム補助事業が広がりを見せている。栃木県宇都宮市では、市の制度を利用し省エネの一環として窓ガラスをLOW―Eペアに改修するケースも出始めた。同県内の事例を紹介する。 |
| ■全国卸・全硝連が陳情(平成26年9月8日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会・松本巌会長と全国板硝子商工協同組合連合会・永島光男会長は、先月21日(木)左記の文章を携え、経済産業省・資源エネルギー庁を訪問。高性能建材導入促進事業に関し、中小企業の集まりである板ガラスの流通団体が不利にならないよう陳情した。陳情内容は次の通り(全文をそのまま掲載)。 平成26年8月21日 経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 御中 全国板硝子卸商業組合連合会 会長 松本巌 既築住宅・建築物における高性能建材導入促進事業に関するお願い 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 以上私ども板ガラス流通団体がお願いをさせて頂きたい事項でございます、何卒ご配慮の程宜しくお願い申し上げます。 敬具 |
| ■全国卸・松本会長、全硝連・永島会長、全硝工連・遠藤会長 国内板硝子3メーカーに陳情(平成26年9月1日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会・松本巌会長、全国板硝子商工協同組合連合会・永島光男会長、全国板硝子工事協同組合連合会・遠藤浩吉会長の3氏は、8月20日(水)に国内板ガラス3メーカー(旭硝子、日本板硝子、セントラル硝子)の営業責任者とそれぞれ面談し、9月から国内建築用板ガラスの価格が値上がりすることを受け、中小企業の集まりである流通3団体が不利にならないよう、特に大口需要家から値上げを認めてもらえるよう、文章を持って陳情した。 |
|
||
|
「ガラススペースの未来をひらく」を理念に、イタリアやベルギーなど世界各国のガラス・ミラーメーカーとパートナーシップを組み、幅広いデザインテイストのインテリア製品の製造・輸入・販売・施工を手掛けるアルテジャパン㈱(本社=東京都、坂義臣社長)の新社長・相談役就任披露パーティーが8月23日(土)、東京都千代田区飯田橋にあるホテルメトロポリタンエドモントにおいて、旭硝子など取引先関係者ら約50名が集まる中、盛大に開催された。 |
| ■AGC AFLIC(エーフリック)を開発(平成26年9月1日) | ||
現在、日本の多くの新築住宅では、冷暖房エネルギー削減に貢献するLow‐E複層ガラスが採用されているが、国土交通省が2020年の標準的新築住宅の目標としている「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」を実現するためには、さらに遮熱・断熱性能を高めることが必要となっている。 |
|
||
|
既存住宅の省エネリフォームに補助金や助成金を交付する地方自治体が増えてきた。板ガラス業界最大の関心事である「窓の断熱化」を制度の対象に含む所も多い。環境対策に力を入れている埼玉県内の自治体の事例の幾つかを紹介する。 |
| ■セントラル硝子 板ガラス製品の価格を改定(平成26年8月25日) |
|
セントラル硝子㈱(実質本社=東京都千代田区、皿澤修一社長)は8月5日(火)、型板ガラス、フロート板ガラス、網入線入板ガラス、鏡および加工ガラス全般の価格を、9月16日納入分から10~20%引き上げると発表した。 |
|
||
|
北九州市建築都市局住まい向上支援課はエコ工事、安全・安心工事、高齢化対応工事を対象に補助金事業「平成26年度住まい向上リフォーム促進事業」を行っている。予算は2億円で、1期、2期に分けて受け付けている。今年度が3年目の事業で過去2年間はいずれも予算を達成できた。 平成25年6月から「既存木造住宅の省エネルギー改修補助事業」制度を設けた、奈良県橿原市(森下豊市長)。 |
| ■ガラス産業連合会 吉川会長は続投(平成26年7月28日) |
|
ガラス産業連合会(GIC、吉川恵治会長)は、7月11日(金)、東京・丸の内の東京會舘で、2014年度通常総会兼理事会を開催。その中で役員改選も行われ、吉川氏の会長留任が決まった。また、副会長には石塚久継氏(理事・日本ガラスびん協会会長)の就任が決定した。その他新理事にGIC運営・技術委員長の加藤之啓氏の就任が決まった。また吉川氏は(一社)ニューガラスフォーラム会長も就任する。 |
|
||
|
吉本製鏡㈱(大阪市東住吉区、宇田博社長)は、7月1日付で宇田博常務が代表取締役社長に就任することを発表した。 |
| ■セントラル硝子 受注出荷条件を改訂(平成26年7月28日) |
|
セントラル硝子㈱(本社=東京都、皿澤修一社長)は、8月1日より受注出荷条件の一部を改訂すると発表した。 |
|
|||
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は6月18日(水)、2014年(第23回)ブループラネット賞(地球環境国際賞)をハーマン・デイリー教授(米国)とダニエル・H・ジャンゼン教授(米国)及びコスタリカ生物多様性研究所(コスタリカ共和国)に贈ると発表した。 |
| ■セントラル硝子 高遮熱型のLow-E複層ガラス ルミナスブルー新登場(平成26年7月7日) |
|
セントラル硝子㈱(本社= |
| ■日本板硝子BP 受注出荷条件を改定(平成26年7月7日) |
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=東京都港区、鈴木隆社長)は、7月14日より建築用板ガラス製品の受注出荷条件の一部を改定すると発表した。 |
|
||
|
毎年この時期に開催される恒例の「板ガラスフォーラム」が今年も盛大に開催された。板ガラス業界8団体(全国板硝子商工協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、機能ガラス普及推進協議会、板硝子協会)共催による「第16回板ガラスフォーラム」が6月13日、東京都港区にある品川プリンスホテル アネックスタワー プリンスホールに於いて盛大に開催された。今回の参加者は320名。記念講演では講師に旭山動物園・園長の坂東元氏を講師に迎え、「伝えるのは命の輝きについて」をテーマに約1時間半講演。動物たちの純粋に生きる姿から感じる、命の素晴らしさを熱くかつユーモラスに語り、
|
■AGC主催 化学強化ガラス題材 初のデザインコンペ(平成26年6月16日)
|
||||
|
「薄く、強く、傷つきにくい」という化学強化特殊ガラスを題材としたAGC旭硝子(本社・東京、石村和彦社長)主催の「デザインコンペ2014~ガラスに夢を見る~」の受賞作品が決まり、5月28日(水)に東京・京橋のAGCスタジオで表彰式が行われた。 他の受賞作品と受賞者は次の通り。(敬称略) |
■吉本製鏡 創業130周年記念感謝の集い(平成26年6月9日)
|
||||
|
吉本製鏡㈱(大阪市東住吉区、渕田博彦社長)は、創業130周年を迎えたことから、5月14日(水)午後4時より天王寺都ホテル(大阪市天王寺区)6階吉野の間において、「吉本製鏡株式会社(SINCE 1883)創業130周年記念感謝の集い」を開催した。 ○創業130周年金式典における渕田博彦社長の挨拶(要約) ○仕入先代表のAGCグラスプロダクツ㈱伊東弘之社長の挨拶(要約) ○鏡業界代表の全日本鏡連合会尾崎由雄会長の挨拶(要約) |
| ■ガラス新聞がテレビに出ます(平成26年6月6日) |
|
2012年の年末にも放送したがっちりマンデーの特別大人気企画「業界新聞の記者が選ぶ!2014年上半期・儲かるトップニュース」! さらに6月15日(日)午前7時半からのレギュラー版にも放送されます。こちらの内容は日本電気硝子のG-Leafです。お時間のある方はぜひご覧ください。 (放送内容に変更があるかもわかりません) |
|
||
|
店舗やオフィス等の内装壁面にカラーガラスを提案するAGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)。これからの空間デザインの可能性を切り開く素材として、更にカラーガラス「ラコベル」の認知度を上げ市場拡大を狙っている。そこで、今回はAGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都台東区、伊東弘之社長)の特需・市場開拓部内装担当部長・太田里華氏にご登場していただき、内装市場とカラーガラスの現状を伺った。
――そんな中でカラーガラスの動きは ――どのようなところに使われているのですか。 ――目的はやはり奥行き感を持たせるためですか。 ――カラーガラスの量的な動きはいかがでしょうか ――昨年末に「ラコベル」のお話を伺った時、設計・デザイナーの皆様と直接コミュニケーションを取ることを大切に考え、様々なイベント・セミナーを実施していると伺いました。「ラコベル」の新色発表会も渋谷「DIESEL」にて開催したとお聞きしましたが、このような取組は現在でも継続中ですか。 ☆ ☆ ☆ 「ラコベル」は、色彩先進国ヨーロッパで選び抜かれたカラーセレクトと日本が誇る品質管理技術を融合したカラーガラスで①空間に彩りと深みを与える内装材②ヴィヴィットな発色③信頼の日本品質④選べるテクスチャ&マテリアルなどの特徴を持つ。ガラス厚は5㍉。 ☆ ☆ ☆ 太田 今年は、AGCスタジオはもちろん、目先を変えた場所でのイベントも検討しています。更に充実したプロモーションを通じ、「ラコベル」や「AGC」をより身近に感じていただければと考えています。 ――カラーガラスの決定権はエンドユーザーさんにあり、そちらのほうに働きかけをしたほうが良いのでは…。という意見もあります。 ――学校や幼稚園、それに老人ホームなどにも癒し系の建材として、広がっていけばいいですね。 |
|
||
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)は、ブラジルで開催される2014
FIFAワールドカップの12会場全てに、競技者用ベンチ向けガラスルーフを提供する旨発表した。 |
| ■春の「叙勲」受章 宮城硝協(㈲三井サッシ硝子工業代表取締役)三井 国夫氏(平成26年5月12日) |
|
全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)の発表によると、平成26年春の叙勲受章者として、宮城県板硝子商工協同組合の三井国夫氏(㈲三井サッシ硝子工業代表取締役)が、厚生労働省関係(技能検定功労)からの申請分として瑞宝単光章を受章したと発表した。 おめでとうございます。 |
| ■省エネ住宅、補助金制度スタート 京都市、柏市(平成26年5月5日) |
|
機能ガラス普及推進協議会の活動が効を奏し始めたのかどうかわからないが、地方自治体レベルで、省エネ住宅に対する補助金制度がいくつか見られるようになってきた。今回は京都市と柏市の両市役所を訪問し、それぞれの担当者に話を聞いた。 既報のとおり京都市では4月14日より「既存住宅の省エネリフォーム支援事業」をスタートさせた。予算的には1200件程度、最大で50万円助成されるということで、地方自治体レベルでは、かなりの規模の事業と言える。そこで今回は京都市都市計画局住宅室住宅政策課を訪問し、平成の京町家担当係長の青木巌氏に今回の助成制度を始めた契機についてインタビューした。 「平成25年の12月に、環境政策局で『京都市エネルギー政策推進のための戦略』というのを策定しており、家庭部門のCO2削減のため省エネ対策を進めていく方針が示されました。 ――住宅の中でも特に窓を対象としたのは。 「一つは以前行われた住宅エコポイント制度でも省エネ対策で窓に投資をする方が多かったこと。それと、調べた結果で、窓に対策を施すことが、一番効果があるというのがわかったからです」 ――制度を設計するとき何か参考にされたものは。 「『既存住宅の省エネリフォーム支援事業』だけの予算は公開しておりません。京都市の既存住宅の省エネ化・再エネ化の推進としては、4億2100万円あり、そこから配分される予定です」 ――1200件程度ということですが、これで京都市内の何パーセントぐらいカバーできる計算になるのですか。 「人口は147万人。約68万世帯ありますから、まだまだです」 「450名ほどお越しただき、業界の方の関心度が高いことがわかりました。チラシを1万枚、市民しんぶんやHPにも掲載しましたが、エンドユーザーの方にどれくらい伝わっているか気になるところです」 ――工事指定業者を市内に本社のあるところに限定したのは。 「ほぼ住宅エコポイントの時と同程度です」 「サッシメーカーなどにチラシをお持ち帰りいただいています」 「もちろん、担当としてはこの事業を成功させて次年度も継続したいと考えています」 ※平成26年度既存住宅の省エネリフォーム支援事業について 公募期間は4月14日から来年の3月30日まで(但し予算がなくなり次第終了)。補助対象となる住宅は京都市内にある住宅で一戸建てまたは共同住宅。対象の工事は外窓交換、ガラス交換、内窓の設置、壁や屋根に断熱材を入れる、窓の遮熱フィルムの施工もOK。施工業者は京都市内に本店または主たる事務所を置く事業者。基本工事として内窓や外窓設置には1か所につき大=1万8千円、中=1万2千円、小=7千円。ガラス交換には1枚につき大=7千円、中=4千円小=2千円補助される。外壁、屋根、天井、床の断熱も補助の対象となっている。製品については熱貫流率の値など要件に示される性能をクリアしていればメーカーは問わない。
|
■第25回チャイナグラス展 2014上海(平成26年4月28日)
|
||||||
|
4月14日(月)~17日(木)の4日間、中国・上海市の上海新国際博覧中心において、「第25回 中国国際玻璃工業技術展覧会(China Glass 2014)」(主催=中国セラミックス協会)が開催された。 |
| ■日本板硝子 青山氏に今期の見通しを聞く(平成26年4月14日) |
|
第3四半期において、日本国内における建築用ガラスの売上高を前年の547億円から560億円と伸ばした日本板硝子㈱(本社=東京都、吉川恵治社長)。今回は建築ガラス事業部門アジア事業部日本統括部営業部長の青山尚昭氏に昨年度の結果と本年度の見通しについて聞いた。 ――昨年1年間は国内の建築用ガラス事業は堅調に推移したと聞いています。 ――まだ集計中だと思いますが、最終的にはどのように。 ――ビル物件については。 ――それで、今期はどれくらいを見込んでおられますか。 ――需要を掘り起こすための対策、新商品については。 ――トリプルガラスについては。 ――健康も注目を集めています。 ――生産体制については。 ――今後は「窓」だけでなく、「内装」や「外壁」関係にまでもっとガラスの需要が広がればと期待しています。ありがとうございました。 |
| ■大阪板硝子販売 「補助金制度」活用で断熱窓改修工事を獲得(平成26年4月14日) |
|
平成25年度の「既築住宅における高性能建材導入促進事業」の補助金制度をうまく活用し、マンション全40戸(管理人室を含めると41戸)の「断熱窓改修工事」の獲得に成功した企業がある。日本板硝子の取引店である大阪板硝子販売㈱(本社=大阪府大阪市、小山保和社長)は、昨年、日本板硝子大阪支店と共同で国からの補助金事業を活用した「断熱窓改修工事」の獲得に動いていたが、マンション管理会社を通じて、兵庫県芦屋市内にあるマンションに対し、スペーシアよる「断熱窓改修工事」を紹介。制度を利用すれば国から3分の1の補助金を得られる旨を説明。結果として、そのマンションの管理組合が約800万円の補助金を得ることができたという。今回はその現場を担当した大阪板硝子販売㈱迫村洋一取締役にお話しを伺った。 ――この補助金制度を利用するのは難しくて予算も余ってしまったという話を聞きました。 ――時期的には。 ――工事をしていて何か問題は。 ――気をつけたことは。 ――サッシの方の戸車とかクレセントとか何か不具合は。 ――過去に改修工事をされていた施主さんは。 ――住民の方の反応は。 ――今後については。 |
| ■板硝子協会 生産性向上設備投資促進税制始まる(平成26年4月14日) |
|
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、質の高い設備投資に対しての優遇税制の適用が始まった。この制度(「生産性向上設備投資促進税制」)は、生産性の向上につながる設備(建物、機械装置、工具、器具備品等)への投資に対して、即時償却又は税額控除が適用されるもの。新築ビル建設や省エネ改修を検討しているオーナーにとっては、税制の支援措置を受ける絶好のチャンスだ。板硝子協会では、パンフレットを作成し、ガラス業界に今月配布する予定。ガラス流通店を通して、この制度の利用を幅広く呼び掛ける。 |
| ■京都市 省エネリフォーム助成制度 4月14日から(最大50万円)(平成26年4月14日) |
|
京都市主催による「すまいの助成制度に関する事業者説明会」が4月8・9日の2日間、京都市内で開催された。8日は午後6時半から京都駅前にあるキャンパスプラザ京都にガラス・サッシ関係を含む事業者ら約250名が集まる中、開催された。 |
|
||
|
AGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都、伊東弘之社長)主催による「2013年度リグラスカップ」の表彰式が3月27日(木)東京都内で行われ、販売店様総合部門で㈱あけぼの通商(本社=長野県、近江朋秀代表)が8連覇の偉業を達成、伊東社長より表彰状並びに賞金が贈られた。 ――8連覇達成おめでとうございます。単年度だけでも1番になるのは大変なのに、それを8年間続けられたのには、何か秘けつがあるのでしょうか。 ――8連覇されてお客様の反応、また、社内での反応は? ――やはり営業面でも効果があったということですね。今後の目標については。 ――最後にメーカーさんへの要望は。 |
| ■全硝工連 全硝連と合同会議(平成26年4月7日) |
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連、遠藤浩吉会長)は3月28日(金)午後、東京の浜町TSKビル会議室で全国理事会を開催し、登録基幹技能者制度と社会保険未加入対策を中心に協議。技能者問題では全硝連との合同会議とした。 |
| ■AGCグラスプロダクツ渥美部長に聞く 増収増益、黒字化を達成(平成26年3月31日) |
|
世界NO1の建築用ガラスメーカーであるAGCグループの、国内建築用加工ガラス事業を担うAGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都、伊東弘之社長)。昨年度は新設住宅着工戸数が堅調に推移したことを背景に売上を拡大、さらに地道な生産性向上活動の成果によりコスト削減も併せて実施し、増収増益を達成した。今期もさらなる飛躍を目指すとしている。今回は、本社に東日本関東営業部・渥美俊夫部長に同社の近況などを伺った。 ――そういう意味で値上げは。 ――昨春に伊東社長とインタビューした時、昨年後半から末にかけて大きな波が予測されるとおっしゃっておりまして、その通りになりました。 ――現状はどうなのですか。 ――個別認定品の出荷が進めばLow―Eガラスの出荷が増えるのではないかと言われています。 ――今年の見通しは。 ――需要を喚起するために、新商品の発売予定とかは。 ――ありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 |
| ■平成25年度後期ガラス施工技能検定合格者(平成26年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成25年度後期ガラス施工技能検定結果が、3月14日に全国都道府県職業能力開発協会から、発表された。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=東京都、鈴木隆社長)と取引のある販売店で構成されるひのまるチェーン東京支部(会長・飯島今朝男氏=飯島アルミ㈱取締役会長)は、3月3日(月)東京・新宿にある京王プラザホテルにおいて、会員ら約200名が集まる中、盛大に2014年度ひのまるチェーン東京支部定例総会を開催した。その中で、スペーシア全国セールスマラソンの表彰状贈呈式も開催され、全国で2位となったあけぼの通商をはじめ東京支部会員の計9社に表彰状が贈られた。この後、近畿大学建築学部学部長・岩前篤氏が講師となって「住宅と窓」をテーマに約1時間半の講演会も行われた。 |
|
||||||
|
日本板硝子株式会社名古屋支店は2月20日、名古屋市中村区名駅のウインクあいち(愛知県産業労働センター)で「日本板硝子ガラス展示会・講演会 NSGガラスアカデミー2014」を開いた。初めての開催。来場は約150人。 |
■札硝協 創立50周年記念式典と記念祝賀会(平成26年3月3日)
|
||||
|
札幌板硝子商協同組合(札幌市豊平区、吉村國義理事長)は、このほど創立50周年を迎えたことから、2月21日(金)午後6時から、札幌東急イン(札幌市中央区)において、記念式典と記念祝賀会を開催、併せて永年勤続優良従業員の表彰式を行った。 ○札幌板硝子商協同組合 |
|
||
|
省エネルギーセンター(藤洋作会長)では、国内の企業・自治体・教育機関等に対して優れた省エネ推進の事例や省エネ性に優れた製品及びビジネスモデルを、「省エネ大賞」として表彰している。今回は、1月29日に東京ビッグサイトで、「平成25年度省エネ大賞」(主催=省エネルギーセンター、後援=経済産業省)の表彰式が行われ、業界からAGCグラスプロダクツ㈱、日本板硝子㈱、㈱LIXILの3社が栄えある省エネ大賞《製品・ビジネス部門》省エネルギー会長賞を受賞し表彰された。 |
|
|||
|
板硝子協会(吉川恵治会長)は、1月23日に東京・丸の内にある東京会館において、協会役員や各委員会委員長やその委員らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。吉川会長は合同委員会の冒頭に、「昨年は改正省エネルギー基準の施行にともない建築物に対する省エネルギーの考え方が大きく変わった一年。エコガラスを中心として高性能な窓ガラスの販売が促進された。さらに消費税の駆け込み需要などもあり年末にはかなり大きな需要があった。12月には産業競争力強化法も成立した。今年はアベノミクスの第三の矢が放たれる。それによって民間の力を引き出して全員参加の総力戦で我々の産業の新陳代謝を行っていく重要な年だ。さらに防災の課題にも対処していかなければならない」とあいさつした。 |
|
||
|
YKK AP㈱(本社=東京都、堀秀充社長)は、1月24日、同社本社のある秋葉原ダイビル2階にある秋葉原コンベンションホールで新商品の発表会を開催、その中で熱貫流率(U値)0・91W/㎡・K、世界クラスの断熱性能を実現したトリプルガラス樹脂窓「APW430」を発売すると発表した。 記者の目 やっと世界に通用する「窓」がでてきた。価格も機能のわりにはそれほど高い設定になっておらず、比較的手の届きやすい範囲に抑えられている感じがする。躯体の壁厚も変えることなく、現在の納まりとほとんどそのままにサッシを納められるということで、大工・工務店のほうも扱いやすいサッシだと考える。大手ハウスメーカーが差別化目的に樹脂サッシを標準装備すれば、複層ガラス同様、一気に樹脂窓の比率は高まる予感がする。 |
|
||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(永島光男理事長)は、1月17日、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で5回目となる合同新年会には、来賓を併せ約120名が参会し開催された。 |
| ■旭硝子 石村社長が挨拶 2014年度方針(平成26年1月20日) |
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)は1月6日、石村社長の年頭挨拶として、2014年度方針説明要旨を発表した。 |
|
||
|
恒例となった平成26年関西板硝子業界新年互礼会(関西板硝子工事協同組合、全硝連近畿地区本部、関西板硝子卸商業組合の3組合主催)が1月9日(木)午前11時より大阪市北区にある新阪急ホテル2階「紫の間」において、業界関係者ら114名が集まる中、盛大に開催、関西板硝子業界の2014年は華々しくスタートした。 |
■全硝連第29回全国理事長会議を開催(平成25年12月30日)
|
||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長、以下全硝連)は、2013年12月8日(日)午後2時から、ホテル日航奈良(奈良市三条本町)「飛天1/4(C)」で、第29回全国理事長会議を開催、各都道府県理事長など48名が参加した。 ◇ ここから、挙手による意見交換がなされた。 ◇ 会議再開後、辻理事長から、宮沢会長への回答として、ガラス組合の定款(大阪府板硝子商工業協同組合のもの)が読み上げられ、設立時の理念が改めて説明された。 ◇ 会も終盤に入り、今後の対応策の論議に移った。事前のアンケートを元に、パンフレットを使ってのPR、青年部活動の後押し、行政と連携し環境イベントなどに参加して組合でエコ窓の受注などを行う、メーカーや卸が一体となって強くアピールする、全国共通の看板やネームプレートなどの作成、組合活動に尽力された方への表彰制度、インターネットを使い、在庫情報を掲載して小口の取引を活性化するなど様々な提案がなされた。 ◇ その後5時30分から、同所「飛天1/4(D)」で懇親会が行われた。 |
|
||
|
先日、関西でも樹脂窓の採用が増えつつあるという話を耳にし、京都・城陽市にある133区画の府内最大級の大型分譲地「プログレスガーデン城陽」を訪問した。この133区画のうち100区画を担当、そのすべての住宅の窓に樹脂窓(YKK AP社のAPW330)を採用した企業がここにあると聞いたからだ。それは、㈱大上住宅不動産(本社=京都府城陽市、大上真司社長)といい、昭和63年に設立された企業だ。今回は同社で営業を担当する大上修明氏にご登場していただき、なぜ、関西で樹脂窓の採用に踏み切ったのかを聞いてみた。また、YKK AP㈱関西支社住宅建材部企画室・今川陽一室長にも同行していただき、一緒にお話を聞いていただいた。 ――100区画すべての販売区画に樹脂窓が採用されたと聞いて正直驚きました。関西の地で、樹脂窓は一般消費者にも、まだ馴染みが薄い。もっと言えばオーバースペックになるのではないかとも思いました。以前から樹脂窓を採用されていたのですか。 ――購入されるとき、樹脂窓にユーザー様は抵抗がなかったですか。 ――売れゆきはどんな状況ですか。 ――次の住宅地を分譲するとしたらやはり樹脂窓を採用されますか。 ――今後の参考にご意見をお願いしたいのですが、樹脂窓に要望はありますか。 記者の目 お話を伺ったがはっきりと目的意識をもって自信を持ってお話していただいた。松尾先生やこの間の住宅特集でご登場していただいたエネルギーパス協会の今泉太爾氏とお知り合いだと聞いて皆さん繋がりがあるのだと思いびっくりした。このように次の世代の方達ががんばると必ず新しい動きに繋がる。防火窓等では値段があがり樹脂窓や木製窓とあまり変わらなくなったという話も聞く。このままいけば、樹脂窓が標準仕様になるのもそれほど遠くないのかもわからない。 |
|
||
|
弊紙9月9日号の1面で報じているように、AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)では、欧州カラーガラスナンバー1ブランド「ラコベル」の生産を鹿島工場(茨城県神栖市)で開始、日本へ本格導入している。今回はAGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都台東区、伊東弘之社長)の特需・市場開拓部内装担当部長・太田里華氏にご登場していただき、国内生産に切り替えた理由などを聞いた。 ――それだけ国内でもカラーガラスの出荷が増えてきたのですか。 ――例えばどういうところに用いられているのですか。 ――さらなる用途拡大のためにどのような活動をされていますか。 ――ありがとうございました。新たな需要を創造していただき、業界を明るくして欲しいです。 |
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連)の永島光男会長は11月21日(木)午後、衆議院第2議員会館に公明党幹事長の井上義久衆議院議員(比例東北)を訪ね、住宅用防火サッシの個別認定に伴う値上げ問題について大手サッシメーカーへの行政指導を求める陳情書を手渡した。 |
■積水化学工業 建築向け合わせガラス乳白グラデーション中間膜「シエロラ」販売開始(平成25年11月25日)
|
|||
|
積水化学工業㈱(本社=大阪市北区、根岸修史社長)高機能プラスチックスカンパニー(松永隆善プレジデント)は、2014年3月から、デザイン性と安全性を併せもった建築向け合わせガラス用乳白グラデーション中間膜「Cielora
(シエロラ)」の販売を開始する。 |
■第22回 ブループラネット賞(平成25年11月11日)
|
||||
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は10月30日(水)、皇居を望む東京のパレスホテルを会場に、2013年度(第22回)の地球環境国際賞「ブループラネット賞」を受賞した松野太郎博士(日本)とダニエル・スパーリング博士(米国)の表彰式典を開催した。 |
|
|||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連、遠藤浩吉会長)は10月29日(水)、浜町TSKビルの都硝協会議室に国土交通省の担当官を招き、社会保険未加入対策の進捗状況に関する説明会を開催。終了後に開いた全国理事会で、標準見積書運用などこの問題への対応について協議した。 |
|
|||
|
セントラル硝子㈱は、10月26日(土)、27日(日)の二日間の日程で、福井県産業会館1・2号館を会場に開催された「住まいの情報展2013」(主催=(一財)福井県建築住宅センター)初日の26日(日)午前11時より、会場内のプレゼンテーションコーナーで、機能ガラス普及推進協議会の一員(当番幹事)として、『安全・安心ガラス設計施工指針』の手引きを資料に、セントラル硝子関西㈱特約店第1営業部秋村一夫、大熊雄一両課長が設計・施工のポイントについて説明をおこなった。 |
|
||
|
第48回「セントラル硝子国際建築設計競技」(主催・セントラル硝子㈱)の公開審査会が、10月19日(土)午後1時半より、東京国際フォーラムD7ホールで開催された。厳正な審査の結果、栄えある最優秀賞には赤塚健・井上岳(いずれも慶應義塾大学大学院所属)の両氏の作品が選ばれ、賞金200万円と記念品及び賞状が贈られた。 |
|
||
|
エネルギーパスとは、EU全土で義務化されている「家の燃費」を表示する証明書。そのエネルギーパスを広く一般に普及し、持続可能なまちづくりを目指すことを目的に活動しているのが一般社団法人日本エネルギーパス協会(所在地=東京都港区、マンフレッド・ランシエン会長)である。過日、東京・新橋にある同協会の事務所を訪問。代表理事でドイツの環境政策に精通している今泉太爾氏(㈱明和地所・代表取締役)にドイツのエネルギー戦略やそこから日本が学ぶべきことは何かを聞いた。今泉氏は現在㈱マテックス(本社=東京都、松本浩志社長)が運営する「窓のコンシェルジュ」(http://www.madocon.jp/)でコラムを連載中だ。 ――なぜドイツに学ぶことになるのですか。 ――住宅に関するところをお話下さい。 ――エネルギーパスとは? ――先ほどの話でドイツの新築住宅着工戸数が15万戸というお話がありました。日本とは相当違いますね。 |
|
|||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)は10月3日(木)、東京の中央区立総合スポーツセンター会議室を会場に全員協議会を開催し、板硝子協会の浅沼光一調査役から北関東を襲った竜巻の被災状況とリフォーム補助事業の応募状況について話を聞いた。 |
|
|||
|
日本電気硝子㈱(本社=滋賀県大津市、有岡雅行社長)は、10月1日(火)~5日(土)まで幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催された、アジア最大級の最先端IT・エレクトロニクス総合展“CEATEC JAPAN 2013”に出展した。 |
|
|||
|
千葉最大の環境活動見本市「エコメッセ2013inちば」(主催=エコメッセちば実行委員会)が9月28日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で開催、行政やNPO法人、大学などのほか、AGC硝子建材㈱や旭硝子㈱千葉工場が出展、ソーケングループとエコ窓普及促進会もコラボ出展した。 |
|
|||||||
|
東海ひのまる会(立木彰一会長、宮吉硝子社長)と日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社(名古屋市中区)は9月26日、「窓サポート倶楽部 名古屋大交流祭」を開いた。講師に日本レストランエンタプライズの齋藤泉氏、共立総合研究所経営コンサルティング部の水野浩里氏を講師に迎えた。 水野浩里氏の講演(要旨) |
|
|||
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は9月5日(木)、東京の経団連会館で記者会見し、第22回「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の調査結果を発表。指標となる環境危機時計の2013年度の平均時刻は、依然「極めて不安」の領域に入る9時19分を示し、回答者の大多数は時刻を決める際に「気候変動」を一番に選択した。 |
| ■森嶌昭夫氏の解説 気候変動政策先送り(平成25年9月23日) |
|
森嶌昭夫氏の解説の要旨は次の通り。 |
|
|||
|
AGC旭硝子㈱(本社=東京都千代田区、石村和彦社長)は、欧州カラーガラスシェアNo.1のブランド「ラコベル」の生産を鹿島工場(茨城県神栖市)で開始し、10月より販売を開始する旨発表した。 |
| ■国土交通省 住宅リフォーム支援状況 HPで検索可能(平成25年9月9日) |
|
国土交通省住宅局住宅生産課は、同省のホームページにおいて、「【平成25年度】地方公共団体における住宅リフォームに係る支援状況調査の結果」を発表している。 |
|
|||
|
既報の通り、千葉県柏市の「柏市エコハウス促進補助金」や東京都世田谷区の「世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業」、新潟県長岡市の「長岡市省エネルギー・新エネルギー設備等導入補助事業」など、市区町村レベルにおける省エネ改修補助金制度が整備されつつある。5月に開催された「機能ガラス普及推進協議会」においても、柏市の補助金を成功事例として、業界側から各自治体へ安全・安心をPRする旨の採択がなされている。 ――よろしくお願いします。さっそくですが、どういった部署にアプローチされたのでしょうか? ――機能ガラスのどのような内容をご説明されたのでしょうか? ――今後、他の市町村を回るご予定は? |
|
|||||||
|
LIXILグループの㈱LIXIL(本社=東京都、藤森義明社長)は、大阪・うめきたの注目スポット「グランフロント大阪」(大阪市北区)に旗艦ショールームとなる「LIXILショールーム大阪」(タワーA11階、延べ床面積約2330㎡)を新設した。また、同グループの㈱川島織物セルコン(本社=京都市、中西正夫社長)も、大阪市北区中之島に開設していた「大阪ショールーム」を同所12階(同約600㎡)に移転・リニューアルし、共に8月25日にオープンするこれに先掛け、21日午前10時30分から内覧会を開催した。 ㈱川島織物セルコン中西正夫社長の挨拶の要旨。 |
|
||
|
「Human Harmony」を企業理念に掲げる㈱石崎本店(本社=広島市安芸区矢野新町1丁目2番15号、石崎信三社長)のグループ企業で、中国地方の複層ガラス製造やガラス切断部門を併設した板ガラスの供給基地の役割を果たす㈱ウインドウシステム(本社の所在地は石崎本店と同じ、井上純一社長)。同社は石﨑本店との連携活動によりユーザー直結型の窓ガラス製造会社として活動している。今回は、新たなガラス加工機を導入したと聞き、同社を訪問。設備投資の目的と今後の動向について井上社長にお話を伺った。 ――まず、御社の事業内容についてお聞かせ下さい。 ――地域的にはどのあたりまでカバーしているのですか。 ――今回新たな加工機を導入したというお話を業界で耳にしました。どのような加工機を導入されたのですか。 ――導入の目的は。 ――いつごろからご検討されていたのですか。 ――これで加工の内製化率はどれくらいになるのですか。 ――今回の投資はどれくらいで回収ができる見込みですか。 ――今後の展開については。 ――お忙しいところどうもありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 記者の目 井上社長とのインンタビューを終えてから、工場の中を見させていただいた。サッシの組立ラインといい、板ガラスを粉砕する機械といいこれまであまり目にすることのない機械がたくさん並んでいた。工場の天井には省エネ塗料が塗られており、また、大型扇風機も導入され、工場内は比較的涼しい感じがした。さらに石崎本店の工場の屋根には太陽光発電パネルが1344枚敷き詰められ、今年の3月より売電事業も始めているという。日本の地方都市において、今後同社のような企業がガラス製造・加工の拠点となり、地域ブロックごとに登場するようになるのではないかと思いながら、工場を後にした。 |
|
|||
|
板ガラス及び建材の卸売、さらには合わせガラスや強化ガラスの加工や施工まで一気通貫で行うセントラル硝子の特約店・まねきや硝子㈱(本社=大阪府東大阪市吉原2―1―13、?072―963―6061、奥山寛一社長)。同社が生産する強化、合わせ、さらには防火ガラスの販売を強化するため、三重県伊賀市にある伊賀工場を増設、新たに複層ガラスのラインを導入、2020年省エネ基準の義務化に対応するため、着実にその準備を進めている。今回は同工場を訪問し、まねきや硝子・奥山喜茂専務取締役に導入目的などを伺った。 ――複層ガラスの設備は過剰ぎみという声がある中で、今、なぜ、新たに設備投資されたのですか。 ――今回導入した機械の特徴を教えてください。 ――投資金額はどれくらいですか。 ――生産量の目標は ――やはり東京方面が多いのですか。 ――JISは。 ――第一号はどちらに納品されましたか。 ――新たな切断機もあるようですが。 ――お忙しいところありがとうございました。 ▼増設した工場の概要 記者の目 同社の強みは自社製品の販売ルートが確立されていること。作ったものは自販できる能力がある。既存の設備もみさせてもらったが、機能ガラスを生産するという点では『卸店が機能ガラスの生産もやっている』というレベルではない、どちらかと言えば『二次加工メーカーが卸もやっている』という感じで、ここに他の二次加工メーカーや卸店との違いを感じる。 |
|
||
|
5月、杉村商事株式会社の新社長に就任した杉村亨氏。杉村茂樹会長から引き継いだ。1969(昭和44)年2月生まれ、44歳。趣味はゴルフ、釣り、フットサルだという。景況感、商品への見方、会社の将来像などについて聞いた。 ‐アベノミクスの効果が一部で出ているというが、景況をどうみているか。 ‐多能工が増えたことで、専門職人が減少している。影響があるのか。 ‐杉村商事は全国的に知られており、歴史と実績のある企業に成長したが、どう発展させるのか。 ‐品質を維持する「杉村の基準」とは何か。 ‐将来的にはどう発展させていくのか。 |
|
|||
|
機能ガラス普及推進協議会(吉川恵治会長)は7月23日(火)、東京・日本橋浜町の都硝協本部会議室で平成25年度代表者会議を開催し、「防犯・防災・省エネを3本柱に、特に省エネ基準義務化に向けての活動に注力する」ことを基本方針とする新年度活動計画案を承認した。 東日本大震災以降、電力問題を機に新エネルギー技術の促進や断熱性の向上などさまざまな取り組みが官民挙げて行われている。こうした中で、ガラスが果たせる役割は非常に大きい。特に省エネ性能の高いエコガラスの普及促進が重要な役割を持っていると考えている。 これまでの活動により新築戸建て住宅ではエコガラスの普及率は高いものになっている。制度面においても改正省エネ基準が今年より施行され、断熱基準は上がっていく。 一方、5000万戸といわれる既存住宅の大半は断熱性能に関しては低い水準のままだ。結露によるカビの発生、寒さによる体力の消耗や病気の誘発など住環境は健康にも大きく関係している。最近では住宅と健康に関する研究も多く行われ、その内容が学会やシンポジウムで発表されている。 地域の行政においては、省エネ改修に関する補助金制度が見受けられる。国レベルでも「既築住宅における高性能建材導入促進事業」が八月から公募を開始した。このようなインセンティブを活用し、より良い商品の提供とエコガラスの普及促進を一層進めていきたいと思う。 また、7月から日本建築防災協会発行の「安全・安心ガラス設計施工指針」を基に、各地区の行政へ機能ガラスのPR活動を開始した。併せて学校へのゼロエネルギー化のPRも行っている。 当協議会として取り組む内容は多岐にわたるが、見方を変えればビジネスチャンスに恵まれていると思う。 |
|
||
|
㈱LIXIL(本社=東京都、藤森義明社長)は、本年4月に組織変更を行い、新たにプロダクツカンパニーを設置し、その中に9つのBU(ビジネスユニット)を新設した。今回は、LIXIL資料館(旧トステム本社)で川本隆一プロダクツカンパニー社長以下9つのBUの責任者の出席の下、記者懇談会を開催。BUの設立目的や事業戦略について説明した。川本氏は「LIXILにしかできないお客様価値の追究を行う」と力強く述べた。当日説明のあったプロダクツカンパニーの経営方針は次の通り。 |
|
||
|
尾畑長硝子株式会社(名古屋市中区栄)の尾畑雄二郎社長。東海地区の状況や今後の見通しなどについて話を聞いた。 ‐重要の増加とは裏腹に課題も多く存在するが。 ‐業績は順調のようだが。今後、要点と考えるのはどのような点か。 |
|
||
|
旭硝子(AGC、本社=東京都、石村和彦社長)は、6月28日(金)午後12時より東京會舘11階ゴールドルームにおいて、石村社長、西見有二副社長、田村良明専務、藤野隆取締役常務ら役員らの出席の下、恒例の記者懇談会を開催した。今回はガラスカンパニーから現在開発中の軽量で高断熱な新3層LowーEペアガラス、また、電子カンパニーからはこのほど発売となった超低熱収縮ディスプレイ用ガラス基板「AN Wizus(エイエヌ ウィザス)」など「各事業における最近の取り組み~成長基盤の強化・定着に向けて~」をテーマに石村社長が説明した。 |
|
||||
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は6月18日(火)、東京の経団連会館で記者会見し、地球環境問題の解決に寄与した個人や組織に贈る「ブループラネット賞」2013年度(第22回)受賞者に、日本人の松野太郎博士と米国人のダニエル・スパーリング博士の2氏を選出したと発表した。 |
| ■「第15回板ガラスフォーラム」を開催(平成25年6月24日) |
|
安倍政権による成長戦略に期待が寄せられる中、板ガラス業界8団体による恒例の板ガラスフォーラムが6月14日(金)、東京・高輪の品川プリンスホテルで盛大に開かれた。15回目となるフォーラムには約350人が参加。今回は1日のみの開催だったが、記念講演や合同懇親会パーティーを通して相互に交流し、高機能ガラスの普及・促進や窓リフォーム需要の開拓など業界の総意結集に努めた。 |
|
||
|
全国板硝子工事協同組合連合会(全硝工連)は6月14日(金)、東京のTKP品川カンファレンスセンターで第29回通常総会を開催し、「財政逼迫の折、的を絞った効率の良い活動を目指す」とした平成25年度事業計画案を承認。役員改選では遠藤浩吉会長の続投を決めた。 |
|
|||
|
|||
|
AGC旭硝子株式会社はサッカースタジアムで使うベンチ向けガラスルーフをFIFA(国際サッカー連盟)の依頼を受けて製作した。6月15日からブラジルで開催されている「FIFAコンフェデレーションズカップ2013」の6会場すべてで使われる。一つの会場につき5台ずつ計30台を提供。更に、高機能フッ素樹脂フィルムを外装に使ったスタジアムが完成した。6月6日、東京都千代田区丸の内のJPタワー、アトリウムで元日本代表サッカー選手のラモス瑠偉さんを招き、発表会を開いた。 アフレックス使用のスタジアムで日本が試合 発表会でラモス瑠偉さんとトークショー |
| ■全国板硝子3団体 メーカー6社に要望書(平成25年6月10日) |
|
全国板硝子卸商業組合連合会(松本巖会長)、全国板硝子工事協同組合連合会(遠藤浩吉会長)、全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)の業界3団体は、5月30日(木)と31日(金)の2日間、国内板ガラス3メーカー(旭硝子、日本板硝子、セントラル硝子)と国内サッシメーカー3社(LIXIL,YKK AP、三協立山)を訪問し、板ガラス(窓)及び防火戸の完成品について、業界の総意としてつぎのようなお願いの文章を直接それぞれの責任者に手渡した。申し入れをした流通側は、メーカー側の反応を踏まえて今後の対応策を検討したいとしている。今回それぞれのメーカー側に提出した文章の内容は次の通り(全文を掲載)。 板ガラス(窓)及び防火戸の完成品出荷について(お願い) 拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 なおメーカー側の出席者は次の通り(敬称略)。 |
|
||
|
「円安」「株高」が進む中で、安倍政権の経済政策「アベノミクス」への期待から企業心理が改善し、輸出も回復の傾向をしめしている。これらの要因を背景に「建設」「製造」などの業種の景気動向も大幅に改善し、明るい動きが顕著になってきた。このような中、昨年の10月1日付けで、日本板硝子㈱(本社=東京都、吉川恵冶社長)の建築ガラス事業部門アジア事業部日本統括部営業部長に就任した青山尚明氏。今回は、東京都港区浜松町の同社に青山氏を訪ね、日本統括部の営業部長として、業界をどのような方向性に進めていくか、足元の数字からこれからの需要期に対する動きも含め、同氏にお話を伺った。 ――まず、足元の動きからお話をお聞かせください。 ――他の建材メーカーでもお話がでたのですが、国が発表している新築の着工戸数を見るともっと出荷があってもおかしくないのに、どういうわけかそういう指標の数字と連動していない感じがするということを幾度が耳にしています。 ――現状は指標とのギャップを感じている。その要因が人手不足だったらいつまでたっても終わらないから、危機感を感じているということですね。夏以降それが積みあがった段階で出荷が増えたら、加工ガラスの生産のほうの対応はどうなりますか。 ――他のガラスメーカーさんの話ではある程度製造設備に余力を持って走るつもりでいるということを聞いています。 ――その、夏以降に増える状態の期間ですが、どれくらい続くと見ておられますか。すぐに終わると見ておられますか。 ――2014年度まで続くと見ている方もいらっしゃいます。 ――地域的な差は出てきていますか。 ――値上げはどうですか。 ――このように業界としても明るい方向にあるわけですが、営業部長として、ガラス業界をどういう方向に向けていきたいと考えておられますか。 ――お忙しいところありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 ******* ******* ******* ******* *******青山尚昭(あおやまなおあき)氏の経歴。 1960年兵庫県生まれ。53歳。神戸大 学経営学部卒。1983年日本板硝子に入社。名古屋、東京、大阪の各支店・特需部等の営業畑を中心に担当。2012年6月より日本地区の営業を統括し同年10月に営業部長となり現在に至る。2男1女の5人家族で現在は単身赴任中。趣味は読書。「誠実」という言葉を大事にしているという。 |
|
||
|
建築用ガラスの加工・販売で旭硝子グループの一翼を担うAGCグラスプロダクツ㈱(本社=東京都、伊東弘之社長)。今回は昨年12月に前任の武田社長の後、同社社長に就任した伊東弘之社長に社長就任の抱負や今後の同社の方向性などを聞いた。 ――私たちから見ると突然に武田社長からバトンを引き継がれた感じがします。 ――社長としての思いは。 ――社員に期待することは。 ――お客様には。 ――現状の動きは。 ――武田前社長はエリア単位で製販一体事業運営を進めるという方針がありました。 ――東北の方は。 ――LIXILとの統合後は。 ――拠点数は。 ――さらにこれを集約する予定は。 ――需要の波が一気に来た場合の対応も考えて様子を見ようということですね。 ――このままいけば、黒字化という目標は達成しそうですか。 ――どういうことですか。 ――今年の建築業界の動きはどのように見ていますか。 ――値上げは。 ――今後の動きは。 ――流通の皆さんからは今年後半に大きな波がきても「間に合わない」ということがないようにお願いしたいと聞いています。 伊東社長の略歴 1957年千葉県に生まれる。現在55歳。慶応大学法学部卒。1981年旭硝子入社。入社後船橋工場の総務を経て、営業として大阪支店~関東支店~福岡支店に赴任。その後本社に戻って営業部門の構造改革を担当。2000年に営業センターの初代リーダーに就任。2006年から2010年までタイで海外勤務も経験。帰国後AGC硝子建材の社長を2年間担当し現在に至る。好きな言葉は「一期一会」趣味は旅行と写真。現在家族3人で、東京で暮す。 |
| ■春の叙勲 青森協組前理事長大杉氏、新潟硝連・田代氏に瑞宝単光章(平成25年5月13日) |
| 全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)の発表によると、平成25年春の叙勲受章者として、青森県板硝子商工協同組合の前理事長・大杉眞一氏(㈲野辺地ガラス)が厚生労働省関係(技能検定功労)からの申請分として瑞宝単光章を、また、新潟県板硝子商工組合連合会・田代明雄氏(資田代建硝)が同じく厚生労働省関係(技能検定功労)からの申請分として瑞宝単光章を受章したと発表した。本当におめでとうございます。 |
| ■タナチョー田中社長に聞く 年後半、建材の需給ひっ迫?(平成25年5月6日) |
|
快適な都市づくりと住まいづくりに取り組む総合建材商社・タナチョーグループ(本社=東京都中央区、田中廣代表)。今年開催された同グループ企業の㈱タナチョー兵庫(本社=兵庫県、田中廣社長)の新春例会のあいさつの中で、田中社長は今年後半に建材の需給がひっ迫する可能性を示唆した。そこで今回は東京にある㈱タナチョーの本社ビルを訪ね、田中社長に発言の真意のほどを聞いてみた。 ――今年2月初めにあったタナチョー会冒頭のあいさつで今年後半に需給がひっ迫するかもわからないので、決まった物件があれば早めに手当てをしておいて欲しい旨をお話されました。関西では実感がわかないという声をたくさん聞いております。この間の発言には何か理由があるのでしょうか。 ※ ※ ※ 結局バブル期間中もそういう建物はそのままになってしまった。逆に郊外にビルを造るとか新しい工場を造るとかそういうことをやってしまった。 ――そういう話がかさなると一気に大きな波が押し寄せるかも知れませんね。 ――ガラスやサッシが不足している感じはあるのですか。少数ですが、ガラスの供給に遅れがあるという話も耳にしました。 ――今、鉄骨や材木などいろんなものが値上げとなってきています。私が聞いた話では他の資材の値上げ分をガラス・サッシのほうに押しつけて逆に値下げを要請されているお店の話も耳にします。このような中でガラスやサッシの値段が上がると間に挟まった流通は非常に困るという話も耳にしました。 |
|
||
|
YKK AP(本社=東京都、堀秀充社長)はTOTO、DAIKENの両社と出展協賛企業によるグリーンリモデルフェアを4月から全国4会場(東京・名古屋・大阪・福岡)で共同開催している。今回は4月19日と20日に東京ビッグサイトで開催された同フェアの模様を取材した。 |
| ■柏市「エコ窓補助」出足好調(平成25年4月22日) |
|
既報のとおり、4月よりエコ窓改修工事費用としてその4分の1を補助する「柏市エコハウス促進補助金」制度を設けた千葉県柏市役所(秋山浩保市長)。4月1日にこの制度がスタートしたばかりだが、先日の取材(15日)時点ですでに15件の申請が届いているというほどの人気ぶりだ。そこで今回はこの制度設計から携わった同市環境部環境保全課環境保全担当・原田圭介主査を訪問、「柏市エコハウス促進制度」を設けることになった経緯から今後の動きまでお話をうかがった。 ――先日この制度の記事を掲載したところ、読者の方から他の市町村でもやってもらえないか。また、どこに行けば役所の方に耳を傾けてもらえるのかという問い合わせもいただいております。まず「柏市エコハウス促進制度」を設けるきっかけをお聞かせください。 ――「窓」に注目されたのは、どなたか「窓」に詳しい方がご担当の中にいたのですか ――ということは、制度を設計するにあたって業界団体から何か働き掛けがあったということではなかったのですね。 ※ ※ ※ ☆柏市エコハウス促進補助金制度とは ※ ※ ※ ――パンフレットなどを見るとかなり詳しく書かれています。 ――総予算額は。 ――現状ではどんな進捗具合ですか。 ――どちらかというとこの閑散期にそれだけの申請があるのはすごいと思います。今後については。 ――ありがとうございました。全国の地方自治体からも問い合わせがあるかも知れません。その時はよろしくお願いいたします。 |
| ■省エネ補助金活用 全国卸・松本会長に聞く 「流通自ら自治体へ働きかけを」(平成25年4月15日) |
|
既報のとおり、省エネ建築に向けた支援制度が経産省で検討されており「住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業補助金」(110億円)、「スマートマンション導入加速化推進事業」(130億円)などを予算要求。住宅の耐震改修などリフォーム工事では、所得税や固定資産税の減免措置など特例措置を拡充するとしている。さらに地方自治体レベルでも省エネに対してさまざまな助成制度を講じる動きがあり、例えば東京都墨田区の地球温暖化防止設備導入助成や千葉県柏市のエコハウス促進補助金制度などで、我々ガラス業界にはフォローの風が吹いている。そこで今回は流通を代表して、全国板硝子卸商業組合連合会の松本巌会長(マテックス会長)にご登場をお願いし、流通としてこの追風をいかに活用していくか、お話を伺った。 ――ところで、そういう自治体への働き掛けは、流通の仕事ではなく、メーカーの仕事ではないかという声も流通の中で聞こえてきます。 ――自治体に行っても窓口や担当者がだれかはっきりわからず、結局、名刺やチラシを置いてくるだけに終わって効果が少ないように思うという話も耳にします。 ――ただ単に地方自治体に訪問し、おねがいだけして帰ってくるようではダメだということですね。地元が開催するイベントに積極的に参加・協力しアピールすることも必要だということですね。 ――今後については。 |
| ■ハードグラス工業 空港第2工場を建設(平成25年4月8日) |
|
強化ガラスドアの国内シェアナンバー1を占める安全ガラス(強化・合わせ)製造・販売のハードグラス工業㈱(本社=伊丹市北伊丹7―79、下岡嵩社長)は、伊丹市内にある伊丹シティーホテルにおいて社員ら約200名が出席する中、今4月から始まる同社の第44期キックオフセレモニーを開催した。下岡社長はその中で、今期の業績について説明、「売上高は前年度の105%、経常利益は3・5%だった。売上のほうは大阪北ヤードの仕事が貢献した」と説明した。さらに、昨年完成した空港第1工場前の220坪の倉庫を取得、今秋にはさらに800坪、合計約1000坪の土地取得計画も明らかにし、空港第1工場に続く、第2工場の建設を表明した。 |
| ■24年度後期ガラス施工技能検定合格者(平成24年3月25日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成24年度後期ガラス施工の技能検定結果が全国都道府県職業能力開発協会から3月15日に発表された。 今年の結果は1級受検者が319人(昨年は249人)で、合格者が141人(同130人)合格率は44%(同52%)となっている。また、2級の受検者は104人(昨年度は109人)で、合格者が56人(同75名)、合格率は54%(同69%)となっている。なお女性の合格者は1級・2級とも今回はゼロだった。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
ガラス関連八団体で組織する機能ガラス普及推進協議会(石村和彦会長)は3月1日(金)、事務局を置く東京・高輪の板硝子協会会議室で平成25年度活動計画を協議する打ち合わせ会合を開催し、建築分野における省エネ基準義務化の流れを「追い風」と捉え、地方公共団体への働きかけなどLow─E複層ガラス(エコガラス)を核とする機能ガラスの普及に業界一体となって取り組んでいく方針を確認した。 |
| ■「HOUSE VISION 2013 TOKYO EXHIBITION」 LIXILとYKK AP出展(平成25年3月11日) |
|
㈱LIXIL(本社=東京都、藤森義明社長)、YKK AP㈱(本社=東京都、堀秀充社長)の両社は、東京・江東区青海で3月2日(土)から24日(日)まで開催される、「HOUSE VISION2013 TOKYO EXHIBITION」に出展した。 |
|
||
|
厚生労働省や中央職業能力開発協会、(社)全国技能士会連合会が主催する第27回技能グランプリ競技が2月23日(土)~24日(日)までの2日間、千葉県にある幕張メッセ国際展示場9・10ホールで盛大に開催された。競技には全部で28職種が参加。今回は4年振りにガラス施工もその職種の一つとして参加した。 |
| ■AGC 新中期経営計画を策定(平成25年2月25日) |
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京都、石村和彦社長)は、2月7日(木)午後3時より東京都千代田区にある大手町サンケイプラザ4Fホールにおいて、2012年12月期決算説明会を開催した。当日の登壇者は石村社長と取締役兼常務執行役員社長室長・藤野隆氏の二人。発表によると、売上高は前期比2・0%減の1兆1899億円。営業利益は同43・9%減の929億円。経常利益は48・0%減・866億円。当期純利益は54・0%減の437億円の減収減益だった。 |
| ■恒例「タナチョー会」盛大に(平成25年2月25日) |
|
㈱タナチョー兵庫(本社=兵庫県加古郡、田中廣社長)は、2月8日、神戸市内にあるチサンホテル神戸にて、同社との取引店など約40名が集まる中、恒例の2012年タナチョー会(新春例会)を盛大に開催した。 |
|
||
|
関東板硝子工事協同組合(遠藤浩吉理事長)は2月13日(水)午後3時半から、東京・日本橋浜町のTSKビル会議室で全員懇談会を開催し、全国的に導入を進めている登録硝子工事基幹技能者制度と社会保険未加入問題について協議した。 |
|
|||
|
公益財団法人(公財)日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長)は1月28日(月)午後、東京・霞が関ビルの東海大学校友会で「第30回無機材料に関する最近の研究成果発表会」を開催した。「材料研究に新しい風を」をテーマに、平成21年度に同助成会が助成金を贈呈した40件の研究の中から5件を選び、講演を聴いた。 |
| ■国交省 住宅・建築物の省エネ・バリアフリー改修支援 補正予算に50億円盛り込む(平成25年2月11日) |
|
国土交通省は平成24年度の補正予算の中に盛り込まれた「住宅・建築物省エネ改修等緊急推進事業」(国費50億円)について2月5日に次の通り公募内容について情報を提供した。なお、本事業については、平成24年度補正予算成立後に内容を確定し、公募を行う予定としている。事業説明会については、東京は2月8日、大阪については、2月14日(木)午後3時より4時半まで大阪府豊中市にある「千里サイエンスセンター」において開催された。 |
|
||
|
板硝子協会(石村和彦会長)は、1月24日に東京・丸の内にある東京会館において、協会役員や各委員会委員長やその委員らの出席の下、板硝子協会合同委員会を開催した。石村会長は冒頭に、「住宅・建築物の省エネを進めるための、改正省エネ基準の普及、安心安全ガラスの普及などに取り組んでいく」(要旨別項)と力強くあいさつした。 |
|
||
|
米国のガラスメーカー、ガーディアン・インダストリーズ・コーポレーションの日本法人、ガーディアン・ジャパン・リミテッドの社長に昨年12月、就任した岡戸志門氏。就任に際しての抱負と今後の日本市場に向けてどう取り組むのか。話を聞いた。 ‐‐外資企業として、日本市場をどうみているのか。 ‐‐社長として目指すところは何か。 |
|
||
|
関東甲信越板硝子卸商業組合(松本巌理事長)と東京都板硝子商工協同組合(永島光男理事長)は、1月18日、東京・千代田区にあるホテルルポール麹町において、合同の新年賀詞交歓会を開催した。今年で4回目となる合同新年会には、来賓を併せ約130名が参会し、華やかなムードの中で進められた。 |
| ■旭硝子 石村社長が ’13方針 業績を上昇トレンドに(平成25年1月21日) |
|
旭硝子㈱(本社=東京都)の石村和彦社長は、年頭のあいさつの中で、2013年度方針説明(要旨)を次のように述べた。 |
|
||
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京、石村和彦社長)は、昨年5月に竜巻による甚大な被害を受けた栃木県真岡市への支援活動として、地震や突風、台風などの自然災害発生時に効果のある防災ガラスを寄贈した。寄贈先である同市指定避難場所の真岡市立真岡小学校(大関馨校長)体育館では、窓ガラス約150㎡(材料費及び工事費は設計価格で約1,018万円)がすべて防災ガラスに交換され、自然災害時の安全性が高まった。 |
|
||
|
新年にふさわしい明るい話題をひとつ紹介しよう。合わせガラスや強化ガラスなど機能ガラスの製造・販売を行う三芝硝材㈱(本社=高岡市岩坪2312、西英夫社長)は、このほど新規加工設備としてイタリア・ブゼッティ社のダブルエッジャーとフォルベット社の四軸同時加工機・キアラを導入したと発表した。 |
| ■弊社からの提言 「もったいない」「技能者を大事に」の文化を育てよう(平成25年1月21日) |
|
今年はスタートから、安倍内閣ができて株高、円安ドル高となり、消費税の駆け込み需要も見込めることから、好景気になると予想する人が多く明るい話題も多い。建材メーカーの決算数字を見ても前年同期比でプラスになってきているところも多い。この状態が末端の我々の段階までおりてくるのかどうか、今後はその動向を注視していくことが必要だ。 |
| ■旭硝子 自動車ドア用強化ガラス発売(平成24年12月24日) |
| 旭硝子株式会社(東京都)は2012年12月から、紫外線を約99%カットしながら、日射しによる暑さや「ジリジリ感」の原因となる赤外線をカットする自動車ドア用強化ガラス「UVベール Premium Cool on」の販売を始めた。「紫外線を99%カットしながら赤外線をカットするのは世界初」だという。 女性ドライバーにとって、自動車の窓回りの最大の悩みは日焼けやしみ。その原因となるのは紫外線である。同社は2010年に紫外線を約99%以上カットする「UVベール Premium」を発売し、すでに十五車種に広がっている。しかし、「車内が暑い」「運転中に腕がジリジリする」などの赤外線が原因の不快感の解消も求められるようになっている。今回の新商品は赤外線カットの要望にも応えた。 この高機能ガラスは「快適なドライブ環境を実現し、暑さを和らげることで弱めのエアコン設定を可能にする」という。環境負荷低減にも貢献する商品となっている。 同社のガラス材料技術、コーティング技術、化学技術を融合したもの。紫外線、赤外線をともにカットするだけでなく、ドアガラスの昇降時に傷が付きにくい新材料や、高品質コーティング技術により製品化に成功した。 この製品は12月5日に発売されたトヨタ自動車の「ヴィッツ 特別仕様車」に「IRカット機能付きスーパーUVカットガラス」として採用されている。 |
| ■10月の新設住宅着工戸数 8万戸を突破 前年同月比25.2%増(平成24年12月10日) |
|
国土交通省が11月30日に発表した本年10月の新設住宅着工戸数は、 持家、貸家、分譲住宅ともに増加したため、前年比25.2%増の84251戸となり、2カ月連続の増加となった。季節調整済み年率換算は97万8000戸だった。持家は前年比13.0%増で2カ月連続の増加、貸家は同48.2%増2カ月連続の増加、分譲住宅は同14.2%増で2カ月連続の増加となった。近畿圏の分譲の数値以外はすべての分野において前年度を上回る結果となっている。消費税増税の影響がでてきているかもしれない。 |
|
||
|
強化ガラス・強化ガラスドア・合わせガラスの加工・製造・販売を行う藤原工業㈱(本社=大阪府大阪市、松井均社長)は、8月29日に前社長で父親の故松井清氏の死去に伴い、代表取締役社長に松井均氏が就任した。今回は、この業界の荒波の中をどのように航海していくのか、松井社長ご自身にご登場をお願いし、お話を伺った。松井社長は「藤原工業は昭和2年に電熱処理で曲げガラス加工をもって創業してもうすぐ90年を迎えます。独自の技術で零戦の風防やミゼットのフロントガラスをダイハツに納入していた長い歴史があります。機能ガラスの二次メーカーの老舗としてのプライドを強く持って、前社長の方針と基盤を守りながらも時代に合った新製品を開発し供給していきたい」とその抱負を語った。 ――社長のこれまで歩んでこられた道程を教えてください。 ――現在の社員数は ――住まいは ――社長がモットーとされていることは。 ――今後の動きについては。 |
| ■12月12日(水)夜7時~8時54分 TBS “特大がっちりマンデー”にガラス新聞社が登場(平成24年12月12日) |
|
業界新聞No.1ニュース大賞2012 この番組にガラス新聞が登場します。 予定では1番目に登場します。ぜひご覧ください。 |
|
||
| 板硝子協会が、ジャパンホーム&ビルディングショー最終日の11月16日、東京ビッグサイト会議棟605号室で「ガラスシンポジウム2012」を開き、業界関係者など約130人が集まった。宇都宮大学の郡公子准教授と株式会社日建設計主管の水出喜太郎氏が「最近のガラスファサードの設計法とその性能」の表題で、独立行政法人建築研究所主任研究員の喜々津仁密氏が「竜巻による建築物被害とその軽減に資する取り組み」の表題で講演を行った。 シンポジウムの冒頭、板硝子協会建築委員長の市川公一氏は「ガラスシンポジウムは設計、施工に携わっている板硝子に関するさまざまな情報に出会える。今回は10回目の節目である。近年、ガラスに社会的要求が増えた。複層化、遮熱・断熱、防犯、防災など高度なガラスへの要望が増えている。今後も開発、普及・促進しなくてはならない」などと、主催者を代表してあいさつした。 【高機能ファサードの最新性能を考える】 郡博士は「地球環境時代となり、ガラス建築は環境的に高性能でなければ存在が許されなくなっている。ガラスファサードを熱的に高性能化する手法にエアフローウインドウ、エアバリア窓、ダブルスキンなどの高性能窓システムがある」とし、それぞれの仕組みを説明。竣工年による高性能窓システムの採用件数などを示した。更に、ダブルスキン、AFWの熱性能算定式や実用計算法なども示した。すべて屋外排気するAFW、窓排気の一部を空調機に戻すAFW、自然換気を行うダブルスキンの熱性能など、図を交えながら説明した。 水出主管は「ファサードは外部環境と内部空間との境界を形成し、サスティナビリティ、コミュニケーション、快適性などの今日的テーマと関わりが深く建築空間を豊かにするための重要な要素だ」と話し、「高性能ファサードの設計法と具体例」として、「福山市まなびの館ローズコム」「スーパーコンピュータ 京(けい)」を例に挙げて説明した。 福山市まなびの館ローズコムは、旧福山藩校「誠之館」の跡地に市民学習と交流の拠点として計画された。図書閲覧室などの建築物の回りに道三川を利用した水盤を広げ、外気との温度差で館内の空気を冷却し循環できる。自然換気併用の空調システムとなっている。 スーパーコンピュータ 京の施設である研究棟は日射遮蔽と海風の影響を防ぐ断熱性強化のダブルスキン外装。研究棟と計算機棟の間にアトリウムを設置し、これを利用した自然換気システムを構築している。 【竜巻による建築物被害とその軽減に資する取り組み】 喜々津博士は「建築物の竜巻被害の概要」「竜巻再現実験の展開」「竜巻被害の軽減に向けできること」の3点に分けて話した。今年5月6日に発生した竜巻被害について、木造建築物の転倒、倒壊、飛散、移動について現地の写真を示しながら解説。木造小屋組の破壊、鉄骨造の残留変形、転倒、RC造建築物の開口部などの損壊などについても説明した。 更に、「飛来物による被害が大きかった」ことに言及し、中には鋼板製屋根材が電線に引っ掛かった例もあった。 竜巻発生を再現することで風力や方向などについても検証している。つくば市の被害状況と実験結果の対応関係についても言及した。 竜巻被害の軽減について、①建築基準法では竜巻によって生ずる荷重・外力は想定されていない②人命・財産・機能保護の観点で被災後の影響が大きい建築物については竜巻に脆弱な部位に対する設計の考え方の整備が求められる――などと指摘。通常の耐風設計の延長線上で竜巻に対して脆弱な部位(屋根・開口部)に、合わせガラスの採用など、プラスアルファの性能を持つ仕様を採用する。米国の重要施設を対象にした対竜巻設計の考え方を参考にする――などと提言している。 |
|
|||
|
強化ガラスドアの国内シェアナンバー1を占める安全ガラス(強化・合わせ)製造・販売のハードグラス工業㈱(本社=伊丹市北伊丹7―79、下岡嵩社長)は、既報の通りかねてより建設中だった同社空港第一工場(所在地・兵庫県伊丹市口酒井3丁目3番30号)がこのほど竣工し、その披露宴が11月21日(水)の大安の日に、旭硝子など取引関係者ら約100名が集まる中、盛大に行われた。 |
|
|||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、永島光男会長)は11月12日(月)、羽田雄一郎国土交通大臣に対し、住宅エコポイント制度復活、省エネ基準の明確化とサッシ問題の改善を求める陳情書を提出した。板ガラス業界では流通短絡化や異業種参入を背景に、近年、特に末端の小売部門が苦況に立たされている。
|
|
|||
|
建設産業における雇用・医療・年金保険の未加入問題に取り組む「社会保険未加入対策推進協議会」の第2回会合が10月31日午後2時より、東京・霞が関の国土交通省中央合同庁舎3号館の共用会議室で開かれた。 |
|
||
|
ガラス産業のあらゆる分野を捉え、素材としてのガラスの可能性をさまざまな視点から紹介するユニークな展示会「グラステック2012(国際ガラス製造・加工機器展)」が10月23日から10月26日までの4日間、ドイツ・デュッセルドルフの見本市会場で盛大に開催された。今回で22回目を迎えたこの展示会には、世界53カ国(前回は51カ国)・1162社(同1275社)の企業が出展。4.3万人以上(同4.5万人)の来場者が訪れた。 |
|
||
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は10月31日(水)午後3時より、東京・丸の内の東京会館ローズルームで、2012年度(第21回)「ブループラネット賞」表彰式展を厳かに開催した。 |
| ■真空ガラス「スペーシア」のTVCMの放送を開始(平成24年11月12日) |
|
【放映予定期間】 TVCMの内容はつぎのURLからご覧ください。 http://glass-wonderland.jp/movie/spacia.html |
|
||
|
第47回「セントラル硝子国際建築設計競技」(主催・セントラル硝子㈱)の公開審査会が、9月28日(水)午後1時半より、東京国際フォーラムD7ホールで開催された。厳正な審査の結果、栄えある最優秀賞には韓国のジョーフィ・ソンさんの作品が選ばれ、賞金200万円と記念品及び賞状を獲得した。 |
| ■AGC 銀三層コーティング 省エネ性能最高(同社比)エコガラス開発(平成24年11月5日) |
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京、社長=石村和彦氏)は、国内生産として初めてとなる銀三層コーティングを施した、同社製品の中で最も省エネ性能が高いエコガラス「サンバランス トリプルクール」を開発した。 |
|
||
|
「省エネ基準の義務化」について、政府は2020年に新築住宅・建築物の省エネ基準の適合義務化を目指しており、それを踏まえて国交省と経産省が省エネ基準を見直す合同会議が開催されている。会議の内容では、現行基準(平成11年基準、次世代省エネ基準と呼ばれているもの)では、外壁や開口部といった外皮のみが対象だった住宅の省エネ基準を、空調・換気・給湯・照明・昇降機など設備機器の基準も合わせた「一次エネルギー消費量」に変更するとしている。それに伴い今後日本の「窓(ガラス・サッシ)」というものがどのように変化していくのか大いに関心のあるところだ。今回の住宅特集では板硝子メーカー3社と設計事務所の先生にご登場をお願いし、それぞれの立場からご意見を伺った。さらにサッシメーカー3社には今後のリフォーム市場への対応についてお話を聞いた。 ――この間の板ガラスフォーラムで先生の講演を聞きました。かなり開口部に興味を持たれている設計士の先生だなと思いましたが。 ――先生が思っておられる日本の窓のあるべき姿とはどのような窓になりますか。 ――そこから先はどうなりますか。 ――これで良いわけがない。 ――窓の見込みが大きくなるのでは。 ――日本の住宅は狭いので枠見込みが大きくなるとさらに居住空間が狭くなるのでないかと思ったものですから。 ――樹脂サッシは防火についての対応はどうなんでしょうか。 ――お忙しいところどうもありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 |
| ■NEDO・東大 新光触媒材料を開発(平成24年10月22日) | ||
|
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と東京大学先端科学技術研究センターは10月11日(木)、東京・霞が関のNEDO分室で記者会見し、「新しい可視光応答型光触媒材料を開発した」と発表した。
日本板硝子(吉川恵治代表執行役社長兼CEO)は10月11日、ガラス表面についた細菌やウイルスの増殖を抑制する抗菌・抗ウイルス性光触媒ガラスの開発に成功したと発表した。NEDOのプロジェクトの一環として取り組んでいた。 |
| ■AGC高砂工場の屋根にメガソーラー重量半分、超軽量パネル(平成24年10月8日) |
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京、石村和彦社長)は、高砂工場の屋根を活用して発電容量約5メガワットのメガソーラーを建設し、来年3 月に稼働開始すると発表した。このメガソーラーでは、同社の薄くて強いガラス“Leoflex(注)”を搭載した超軽量ソーラーパネルを一部に採用することで、従来型のソーラーパネルでは設置が難しいスペースも有効活用し、屋根に設置する発電システムとしては国内最大規模を実現している。 |
|
||
|
「曲げガラス」加工で来年60年を迎える実績を持ち、「樹脂合わせガラス」とともにオンリーワンの企業を目指す新光硝子工業㈱(本社=富山県砺波市、新海伸治社長)は、今年の6月22日に行われた株主総会で新海伸治社長が新しく就任した。交代目的は前社長の稲船幸夫氏が定年を迎えたことから若返りを図った。そこで今回は砺波市にある同社本社工場を訪ね、新海社長の人となりに迫ってみた。 ――社長がここまで歩んでこられた道程を簡単に紹介して下さい。 ――現在の会社に入社されたのは。 ――平成2年といえば大変忙しかったのでは。 ――一サラリーマンから今度社長になられたわけですが。 ――ご自身でどうして社長になることができたと思われますか。 ――社員は。 ――お住まいは。 ――ご家族は。 ――趣味は。 ――社長のモットーしていることは。 ――社長になられた抱負・基本理念は。 ――今後の動きについては。 ――ありがとうございました。 |
| ■全硝連宮城・松島で第28回全国理事長会議(平成24年10月1日) | ||||||
|
||||||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(全硝連、永島光男会長)は9月23(日)、24(月)の両日、宮城県・松島温泉のホテル「松島一の坊」で第28回全国理事長会議を開催した。初日の全体会議には45名が参加して減少著しい組合の活性化について活発な議論を交わし、翌日は東日本大震災の被災地を視察、復興に向けた支援態勢の在り方について現場サイドで意見交換した。 |
|
||
|
全国理事長会議は全体会議終了後、「東日本大震災当日から現在までの道のり」と題した松島一の坊・畠山光夫支配人の講演を聴いた。 |
| ■旭硝子財団アンケート 環境危機時計昨年比平均22分進む(平成24年9月24日) |
|
公益財団法人旭硝子財団(田中鐵二理事長)は9月10日、韓国・済州島で記者会見し、2012年版(第21回)「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の結果を発表。全回答者の平均環境危機時刻は「9時23分」と昨年比22分進んだ。 |
■上原成商事・守山エネルギーセンター セントラル硝子製「ペアレックスソネス ネオ」採用(平成24年9月24日)
|
|||
|
エネルギー関連をはじめとして、建築資材、住宅設備、リフォームなど人の暮らしに必要な資源・資材・技術を提供する総合商社・上原成商事㈱(本社=京都府京都市中京区御池通烏丸東入仲保利町191番地、?075-212-6000、上原大作社長)は、産業サポート事業において物流の効率化で拠点の統合を推し進めている。その一環として老朽化が目立つ湖南のガス充填工場(滋賀県)を守山油槽所(滋賀県)に集約し、このほど守山エネルギーセンターとしてスタートした。これによりエネルギー物流システムの効率化と更なる保安強化を推進できるとしている。なお、今回の投資額は約4億8000万円としている。今回は同社取締役物流部長・福井善徳氏にご登場をお願いし、投資の目的などを聞いた。なお、同社はセントラル硝子の特約店・上原硝子㈱(本社=京都府京都市、太田邦男社長)の親会社にあたる。 ――今回の投資目的は。 |
| ■旭硝子財団意識調査「政策見直し」32% 「反原発」世界レベル(平成24年9月24日) |
|
旭硝子財団は2012年版「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」で「原子力発電と環境」に焦点を当てた意識調査も実施。その結果、世界レベルで原発に反対する市民が多くなり、政策面では「なんらかの見直しを望む」とする意見が大勢を占めた。 |
| ■社会保険未加入問題 建設業 国・業界で加入推進協 国交省 山野氏に聞く(平成24年9月10日) |
|
弊紙夏季特集号の中で、全国板硝子工事協同組合連合会・遠藤浩吉会長のあいさつや前々号の三面鏡などでも紹介したが、建設業を営む会社の「社会保険未加入問題」に国交省がついにメスを入れはじめた。この件については、ガラス工事業界を中心に少しずつ話題にのぼりつつあるものの、まだ、大きな問題として捉えている企業も少ないのではないだろうか。しかしこのまま何も手を打たないでいるといずれは仕事が回ってこなくなる可能性を含んでいる。そこで今回はこの問題の窓口である国土交通省 土地・建設産業局建設市場整備課労働資材対策室担当・山野美鈴課長補佐になぜ今「社会保険未加入問題」なのか、その背景から対策、さらにはあるべき姿までを聞いてみた。 「バブル崩壊以降、建設投資額は減少し、平成23年度見込みでは約42兆円です。これは平成4年のピーク時の50%にまで減少しています。このため、競争参加者が増加し、受注競争が激化しています。 ――背景はわかりましたが、実際どれくらいの方が未加入なのですか。実態はどのような感じですか。 ――では、具体的にどのような対策をとられるおつもりですか。 「対策としては、(1)行政・元請・下請等の関係者が一体となった保険加入の促進(2)行政による制度的チェック・指導(3)建設企業の取組(4)法定福利費の確保などがあります。 ――行政として最終的にはどのような形を目指すおつもりですか。 「5年後の平成29年度を目途に、企業単位では、許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指します。これにより、技能労働者の処遇の向上や人材の確保、公平な競争環境の構築を図ります」。 ――背景や目的、その対策などはわかりました。ところで、もし、この3保険とも今現在入ってなくて、新たに入ろうとすると1人あたりどれくらいの額になるのですか。 「こちらの試算では、事業主負担額の合計は賃金の約15%程度となります。表を見て下さい。例えば日当たり賃金で15,000円、標準月額報酬が34万円とすると、法定福利費の月当たりの事業主負担額は約5万円となり、年間で約60万円の負担となります。」 ――これだけの負担が新たにでてくるとなると、今の経済状況では、頭の中でわかっていても、実際には行動できないのではないでしょうか。 「保険加入は、現在の建設業の現状を見れば、非常に困難な取組だと思います。しかし、もう避けては通れませんし、苦しい中でも、きちんと保険に入っている企業が馬鹿を見ない業界にしなければいけません。保険未加入問題は、行政だけでなく業界全体の問題というということで、社会保険未加入対策推進協議会というものをスタートしました。これには建設業関係登録団体の73団体が参加しており、代表的な発注者団体もオブザーバーとして参加しています。 ――地方や全国協議会の日程などを教えてください。 「地方協議会は全国10ブロックで、7月から9月まで順次開催しています。また第2回目の全国推進協議会は10月ごろ開催する予定です。そこで、社会保険加入促進計画や法定福利費の標準見積書のとりまとめなどを行う予定です。 記者の目 ガラス業界の現場担当の方の話も伺えたが、理屈ではわかっていても、これを本気でやったら工事現場には誰もいなくなるのではという声を聞いた。物件が少なくなる中で、激しい見積競争の結果、元請提示額より金額を下げて物件を取りにいく下請業者もあるという。今回の件でそういう業者だけを排除することができれば良いのだが…。とにかく安ければ良いという風潮を変えていかなければならない。 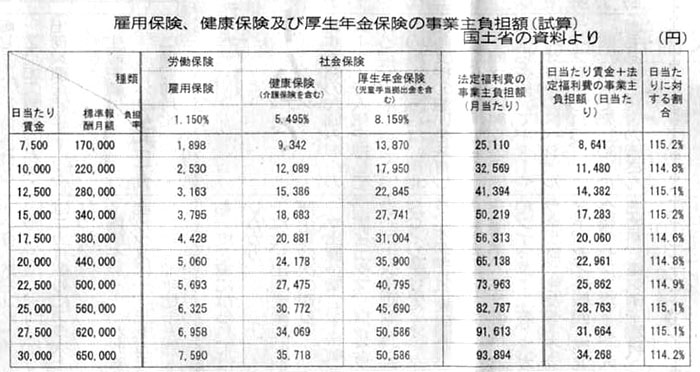 |
■中島硝子工業関東・東圧工場 素板を自動で切断機投入(平成24年9月3日)
|
||||||
|
ガラスに、機能、満足を求め、新時代に挑戦する中島硝子工業㈱(本社=岡山県井原市、勇木健社長)は、かねてより増設中だった関東・東庄工場の第5期建築工場が今年2月に完成、さらに同建屋内にガントリーシステムの導入も完了、8月より本格稼働に入ったと発表した。そこで今回は、同社東庄工場を訪問、勇木社長に今回の投資目的や今後の展開について聞いた。勇木社長は「関東・東庄の工場はこれまで首都圏を近くにし、より早く、より安く、より良く、をモットーにして、お客様のニーズに応えてきた工場です。今回は、さらにその能力を増強しました。これからも、お客様の要望に応えていきたいです」と力強く語っていた。これにより、切断能力は従来の倍近くのスピードになる模様だ。なお、同工場は昭和フロント㈱が主催する第43回ストアフロントコンクールの第2部で金賞を受賞している。 ※ ※ ※ ▽関東・東庄工場の概要 ※ ※ ※ 最後に勇木社長は「この関東・東庄工場には地震警報(アナウンス)装置が設置されており、昨年の3月11日に発生した東日本大震災では、地震で揺れる前に作動しアナウンスがあったため、ガラスは倒壊したものの、従業員にはケガもなく全員無事に屋外に避難できました。また幸いにも建屋、設備も無事でした。東海や西日本にも大きな地震がくると言われています。皆さんもぜひこの地震警報装置の設置をお薦めします」と語っていた。 記者の目 コンクールで金賞を受賞したように大変、明るくて立派な工場だった。省エネにも気を使っており、増設した工場にはLED照明が使われていた。設備はまるでグラステックのショーを見学しているようで、大きなガラスが次から次へとコンピューター制御で自動的に切断機のところまで搬入され、また、その切断機のスピードも速かった。同社の今後の動きに注目が集まる。 |
| ■日本板硝子BP溝型ガラスプロフィット波型の「ウェーブ」発売(平成24年8月27日) |
|
ビル・住宅などの建築用ガラスの製造・販売を行うNSGグループ・日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=東京都、鈴木隆社長)は、このほど独特な質感と透明感をもつ溝型形状の細長いガラスプロフィリットに新しい仲間「プロフィリット・ウェーブ」が加わり、今月より発売となった。「プロフィリット・ウェーブ」は、波型のフェイスフォルムが連続感のあるデザインと光の演出を実現する。 |
| ■日本電気硝子高性能反射防止膜を成膜「見えないガラス」開発(平成24年8月27日) |
|
日本電気硝子㈱(本社=滋賀県、有岡雅行社長)は、ナノメートルレベルの優れた膜厚制御によって生まれるユニークなガラス「見えないガラス」を開発、販売を開始したと発表した。 |
| ■全硝連 復興支援エコポイント制度 業界挙げ協力(平成24年8月6日) |
|
機能ガラス普及推進協議会(石村和彦会長)では、全国板硝子商工協同組合連合会(永島光男会長)の協力の下、全国の工務店に対し、復興支援エコポイント制度(新築)に関するアンケートを纏めた。これは今後住宅については2020年までに省エネ基準への適合義務化をすることが決まっているが、地域に根ざした工務店にとっては省エネ基準が義務化された場合、営業・設計・施工について容易に対応ができないのではないかという懸念があり、実際のところどうなのか、また、その懸念があった場合にはガラス業界としてどのような解決手段を提供できるのかについて考えたいということで、アンケートを纏めた。今回はそのアンケート提出に協力した全硝連の永島会長にお話を伺った(アンケートの結果は別項参照)。 ――この間、機能ガラス普及推進協議会の代表者会議の中で、アンケートに協力した話題がでていました。 ――今後も機能ガラス普及推進協議会から依頼があれば協力していく御考えですか。 アンケート内容の結果については次の通り。 |
| ■浜屋ガラス小池社長 エコポイント効果と今後の動向を聞く(平成24年8月6日) |
|
サッシやガラスの窓回りだけではなく、キッチン・バス・トイレなどの住宅設備機器、カーポートやベランダなどのエクステリア、室内建材やサイディングなどトータルでサービスを行う浜屋ガラス(本社=東京都、小池恒平社長)。今回は、予定よりも早く復興支援・住宅エコポイントが終了したことで、これまでの効果やその影響、また2014年の4月から消費税が8%にさらには2015年の10月からは10%に上がることから、業界にどのような影響がでてくるかなどを聞いた。 ――ということは、効果はあったということですね。 ――エコポイントが終わりました。では今後どのような動きになると思いますか。数量は下がると思いますか。 ――安いところには無理して良いものを提案しないし、良いものが欲しいところにはさらに良いものを提案していく。要は二極化していくということですね。ところで、住宅エコポイントは「窓リフォーム」の概念は広まりましたが、その反面異業種の参入を招いたと言われています。このことについてどのように思われますか。 ――消費税が上がった後は一説には50万戸時代が来るかもという話もあります。 ――今後の動きとしては。 ――お忙しいところどうもありがとうございました。今後のご活躍を期待しています。 |
| ■機能ガラス普及推進協代表者会議 省エネ体験デモ機を作成(平成24年7月23日) |
|
機能ガラス普及推進協議会(石村和彦会長)は、7月11日(水)、東京・丸の内にある旭硝子本社会議室で経済産業省や業界8団体の代表者など約30名が集まる中、平成24年度代表者会議を開催した。その中で今年度の活動計画を纏め、基本方針として「防犯」「防災」「省エネ」の三本の柱とし、特に省エネ基準の義務化にむけての活動に注力して業界の活性化を図る①省エネ基準義務化の早期化および省エネ基準の引き上げに向けての活動②地方行政組織への訪問とPR活動③会員間の情報共有化および連携活動の推進の三つに取り組んでいくことで合意した。また、同協議会として省エネ体験デモ機を10セット作成し、各団体に貸与、各地で実施される省エネイベントへの参加を支援することも併せて決定した。 |
| ■ガラス産業連合会総会総会・理事会 新会長に岡本氏就任(平成24年7月23日) |
|
ガラス産業連合会(GIC、山中衛会長)は、7月6日(金)、東京・丸の内の東京會舘で、平成24年度通常総会兼理事会を開催した。その中で役員改選も行われ、新会長には岡本毅氏(《一社》日本硝子製品工業会会長)が、また、副会長には井筒雄三氏(電気硝子工業会会長)の就任が決定した。その他新理事には硝子繊維協会会長の狐塚章氏と日本ガラスびん協会次期会長(7月24日の総会で正式に就任する予定)の清水泰行氏がさらにガラス産業連合会技術・運営委員長の新井敦氏の就任が決定した。 |
| ■日本板硝子ビルディングプロダクツ スペーシア全国セールスコンテスト開催(平成24年7月23日) |
|
日本板硝子ビルディングプロダクツ㈱(本社=千葉県、鈴木隆社長)は、このほどスペーシア取扱店を対象に、窓リフォーム需要の更なる取り込みのため、「スペーシア全国セールスコンテスト」を開催すると発表した。 |
| ■記者懇談会 旭硝子「ありたい姿」(平成24年7月9日) |
|
旭硝子(AGC、本社=東京都、石村和彦社長)は、6月28日(火)千代田区丸の内にある丸ビルコンファレンススクエア8階において、石村社長、西見有二副社長、加藤勝久専務、藤野隆常務らの役員の出席の下、記者懇談会を開催した。今回は「新しいガラスで新市場を開拓~あらゆるところにガラスのソリューションを~」テーマに石村社長が説明した。 |
| ■旭硝子 鹿島工場見学会 フロートガラスライン、新コーティング設備(平成24年7月9日) |
|
旭硝子は7月2日(月)マスコミ向けに、同社鹿島工場(所在地=茨城県神栖市東和田25)の見学会を開催した。午前11時に東京駅前をマイクロバスで出発した一行は、午後2時に鹿島工場に到着した。平岡正司工場長より同工場の概要説明を受けた後、早速フロートガラスラインと新コーティング設備を見学した。 |
|
||
|
日本板硝子の取引店で構成される全国ひのまる会の定時総会(平成24年度)が、6月16日に、東京・品川にあるホテルラフォーレ東京で約100名の会員が集まる中、盛大に開催された。来賓として日本板硝子の吉川恵治社長やクレメンス・ミラー副社長も出席し、総会に華を添えた。その後は記念講演も行われ、慶応義塾大学経済学部教授・金子勝氏を講師に迎え、「日本経済のゆくえ」をテーマに約1時間半行われた。 |
| ■AGC 日本初銅使用量ゼロの鏡開発(平成24年7月2日)) |
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京、石村和彦社長)は、鏡の新製品「サンミラーG」を、今月より販売したと発表した。 |
|
|||
|
昨年の東日本大震災で中止になった「板ガラスフォーラム」が今年再開した。板ガラス業界7団体(全国板硝子商工協同組合連合会、全国板硝子工事協同組合連合会、全国板硝子卸商業組合、全日本鏡連合会、全国安全硝子工業会、全国複層硝子工業会、板硝子協会)共催による「第14回板ガラスフォーラム」が6月15・16日の2日間、東京都港区にある品川プリンスホテルに於いて盛大に開催された。今回の参加者は約三百名。初日の記念講演では三菱総合研究所の理事長であり、プラチナ構想ネットワークの会長でもある小宮山宏氏を講師に招き「日本『再創造』―プラチナ社会の実現に向けて」をテーマに約1時間を講演、さらには「経産省講演」として同省製造産業局住宅産業窯業建材課の土橋秀義企画官が「住宅・建築物省エネ化に向けて」をテーマに説明した。また2日目は、同会場で「省エネ(高断熱)住宅はガラス・開口部の進化に期待する」(講師・松尾設計室代表取締役・松尾和也氏)と板硝子協会より先月発生した「茨城県つくば市の竜巻被害によるガラス被害の状況報告」(講師・板硝子協会調査役・俵田忠明氏)、「安全・安心ガラス設計施工指針について」(講師板硝子協会調査役・岡野敏彦氏)の講演も併せて行われた。 |
|
||
|
全国板硝子商工協同組合連合会(略称・全硝連、永島光男会長)は、6月15日午後12時より東京都港区にあるTKPガーデンシティ品川「アネモネ」において、会員ら約50名が集まる中、第55回通常総会を開催した。その中で役員改選も行われ、永島会長(東京)の留任が決定した。その他の役員は別項参照のこと。 |
| ■グラステック2012視察ツアー紹介 2012年10月24日(水)~31日(月)までの8日間 ドイツ・イタリア【PDF】 (平成24年6月13日) |
| ■「平成24年度(第二回)家庭の省エネエキスパート検定の手引き」を発表【PDF】(平成24年6月12日) |
| ■AGC 超薄板ガラス積層技術を開発(平成24年6月11日) |
|
AGC(旭硝子㈱、本社=東京、社長=石村和彦氏)は、超薄板ガラスを顧客の製造工程で搬送するためのキャリアガラスへ貼り合わせる積層技術の開発に成功したと発表した。この技術により、顧客の設備を変更することなく超薄板ガラスを取り扱うことが可能となるため、超薄板ガラスの利用が期待される次世代ディスプレイなどの様々なアプリケーションの実用化に大きく近づくとしている。 |
|
|||
|
FPD・板ガラス・太陽電池・LED・セラミック他の製造装置および切断・加工工具の開発・製造・販売を行う三星ダイヤモンド工業㈱(本社=大阪府、三宅泰明社長)は、既報のとおり、本年5月7日に、現在数ヵ所に点在している本社等の拠点を一ヵ所に集約統合し、お客様への対応力向上と業務効率化を図るため新社屋に移転した。新社屋は、大阪府摂津市香露園にあり、以前同社の本社のあった場所のすぐ近くに完成、また昨年できたばかりの阪急京都線・摂津市駅が徒歩4分圏内にあり、交通の便利なところに位置する。今回はその完成したばかりの新社屋に三宅社長を訪ね、新社屋建設の狙い、今後の目標などを聞いた。 ※ ※ ※ 新社屋は地下1階地上4階からなり、地下は駐車場、4階部分には社員専用の食堂を有する。食堂のメニューをみるとカロリー表示もしてあり、社員の健康にも気をつけているのがわかる。4階部分にはウッドデッキや専用庭もあり社員の憩いの場となっている。1から3階部分は、事務所、会議室、実験室等からなり、会議室にはプロジェクターやテレビ会議用のモニターなど最新の設備が施されている。セキュリティーも万全でエレベータに乗るのもカードキーが必要となる。 ※ ※ ※ ――要は効率化とスピード化が目的ですね。 |
|
||
|
全国板硝子卸商業組合連合会(松本巌会長)は、5月25日(金)に東京都港区にあるメルパルク東京にて、第27回通常総会を開催。今期の事業計画案や収支予算案、などを審議、原案通り承認した。また役員改選も行われ、会長に松本巌氏(関信越)の留任が決定した(その他の役員については別項参照のこと)。 なお来賓出席者は次の通り(敬称略)。 ☆平成24年度新役員の顔触れ(敬称略)
|
| ■日本板硝子 遮熱タイプ「スペーシア クール」発売(平成24年5月28日) |
|
日本板硝子(本社=東京都、吉川恵治社長)は、本年6月1日より、遮熱タイプの真空ガラス「スペーシア クール」を発売し、製品ラインアップの拡充を図るとともに製品最大寸法の拡大を行うと発表した。今回新製品の説明を行っていただいたのは、日本板硝子ビルディングプロダクツ(本社=千葉県、鈴木隆社長)事業統括本部商品企画グループグループリーダー・一級建築士、坪田敏氏。 ※ ※ ※ 真空ガラス「スペーシア」は、同社が世界で初めて実用化した高断熱窓ガラスだ。2枚のガラスの間に0・2㍉の真空層を閉じ込めることによって、1枚ガラスの約4倍、一般的な複層ガラスの約2倍の断熱性能を実現した製品で、1997年10月発売以来、好評の商品だ。 ※ ※ ※ 以下は坪田氏との一問一答。 ※ ※ ※ 期間中に窓ガラスをスペーシアに交換すると、抽選で「おうち快適グッズ」が当たる。 ※ ※ ※ ――名称の変更は。 |
|
||
|
セントラル硝子(本社=東京都、皿澤修一社長)は、5月18日(金)午後2時より、東京都文京区にある椿山荘において、「セントラル硝子特約店研修会」を開催した。同会は全国のセントラル会のメンバーが一堂に集まり研修や情報交換を行おうという趣旨の下で開催されるもの。今回で5回目となる。全国の特約店の代表者やその役員、さらには同社社員など約120名が参集し盛大に行われた。 |
■日本板硝子材料工学助成会第34回助成金贈呈式 今年度は43件、4490万円(平成24年5月14日)
|
|||
| 公益財団法人日本板硝子材料工学助成会(藤本勝司理事長、東京都港区三田)は4月26日、東京都港区六本木の泉ガーデンタワー住友会館で「平成24年度研究助成金贈呈式(第34回)」を開いた。 冒頭、藤本理事長は「当助成会は無機材料の基礎研究、応用研究をうたい設立34年。公益財団法人となって4年。国内での無機材料への助成は当会の柱である。これまでに998件の応募があり、13億円余の助成金の実績となった。84の研究機関から211件の応募があった。うち8つが初めての応募だった。今年度は、昨年12月から時間を費やし厳正な審査を行い、43件で、4490万円の研究助成となった。経済情勢の影響で財団の財政も厳しいが、我が国において経済克服は技術開発以外にないと思う。新しい成果を研究者各位にお願いしたい。政府のファーストプログラムは研究助成である。世界のトップ研究者としてのまい進を期待したい」とあいさつで述べた。 |
■全硝連関信越地区本部総会 新本部長に中村氏(平成24年5月14日)
|
||||
|
全硝連関東甲信越地区本部は4月26日(木)午後、東京・浜町TSKビル会議室で平成24年度通常総会を開催し、新本部長に中村勉氏(新潟県板硝子商工組合連合会会長)を、副本部長に小峰梅男氏(埼玉県板硝子商工協同組合専務理事)をそれぞれ選出した。 |